問い合わせ対応向けのチャットボットとは?導入のメリットやサービスの選び方を解説
公開日 2025/04/28
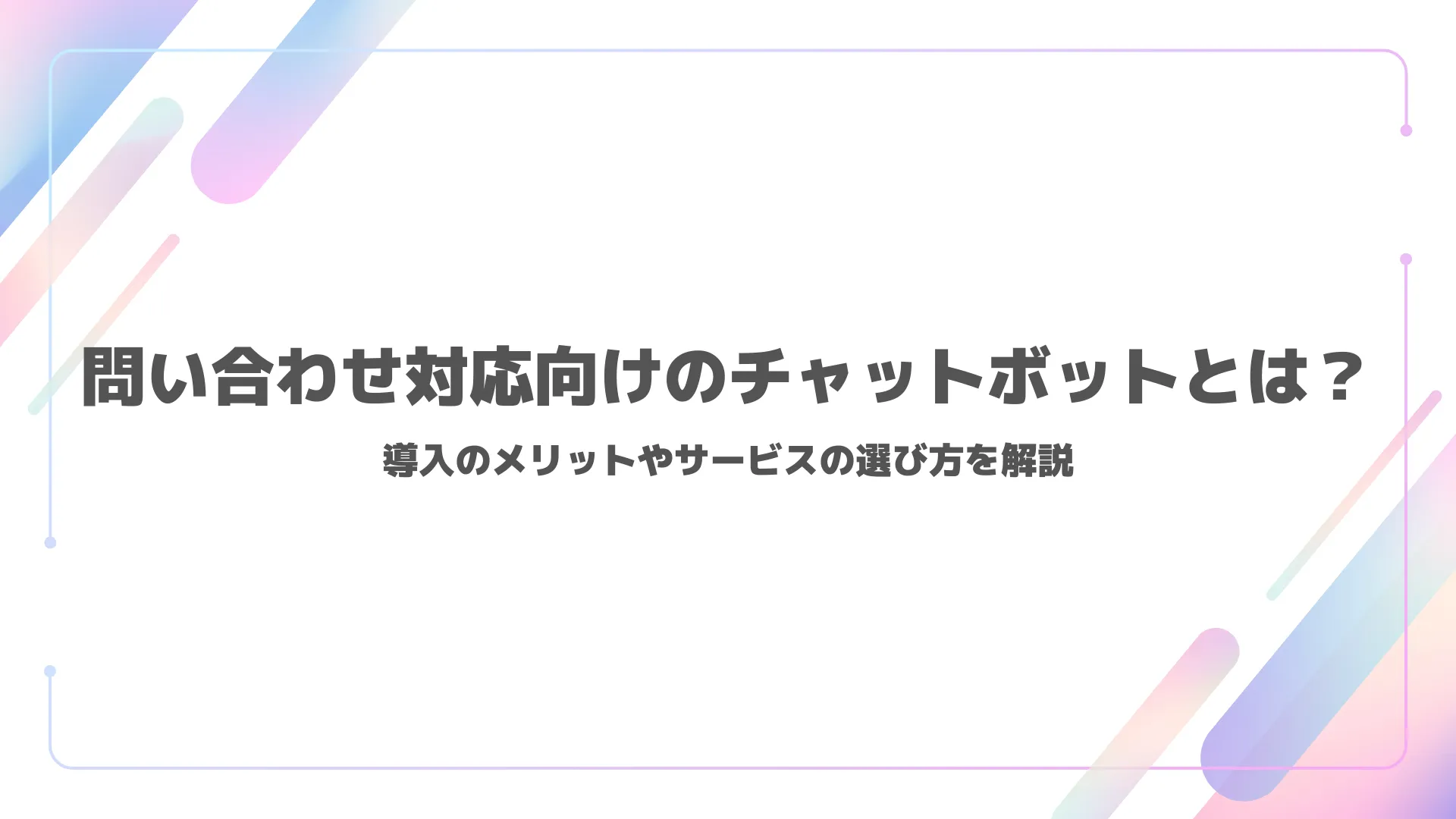
問い合わせ対応は、企業にとって欠かせない業務ですが、対応の遅れや担当者の負担増加など、さまざまな課題が発生しがちです。特に、対応の属人化や問い合わせの増加は、業務の効率を下げる要因にもなります。
そこで注目されているのが、チャットボットの活用です。適切に導入すれば、問い合わせ対応の負担を軽減し、業務の効率化につなげることができます。本記事では、問い合わせ対応で起こりやすい問題点や、チャットボットの活用方法、導入の手順について詳しく解説します。
目次
問い合わせ対応で発生しやすい問題
企業の問い合わせ対応では、さまざまな課題が発生します。特に人が対応する場合、品質のばらつきや対応の遅れなどの問題が起こりやすく、業務効率にも影響を与えます。
以下で、主な問題点を解説します。
担当者によって回答内容・品質にバラつきが出る
問い合わせ担当者によって、回答の内容や品質に差が出ることはよくあります。たとえば、経験豊富な担当者と新人では、同じ質問に対する回答の内容や質が異なります。対応に違いが出ると、ユーザーが「前回はこうだったのに」と不満を感じる原因になります。
また、担当者ごとに解釈が異なることで、「以前の説明と違う」と混乱を招くこともあります。企業として統一した対応が求められますが、業務の忙しさや教育の時間不足により、なかなか実現できないケースが多いです。
質問した人が返答待ちになる
問い合わせが集中すると、対応が間に合わずに回答待ちの状態が発生します。とくに、複数のシステムを切り替えて情報を確認する必要があると待ち時間が長くなりやすく、「返答が遅い」「コールセンターにつながらない」といった不満が生まれやすくなります。
また、問い合わせ対応が営業時間内に限られている場合、営業時間外に質問した人は翌営業日まで待たなければなりません。迅速な回答を期待している人にとって、長い待ち時間は大きなストレスとなる可能性があります。
特定の人物がいなくなったら業務が滞る
問い合わせ対応が特定の担当者に依存していると、その担当者が休暇や退職などで不在になった場合、業務が滞るリスクがあります。
たとえば、従業員が「何かあったらあの人に聞けばいい」と考えていると、知識や情報が特定の人に集中してしまい、その人が不在の場合対応が難しくなります。これはとくに社内のお問い合わせ対応で発生しやすい問題です。
問い合わせ担当者の業務が滞る
問い合わせ対応を担当する人が、他の業務も兼任している場合、対応に追われて本来の業務が進まなくなることがあります。たとえば、総務や経理の担当者が社内からの問い合わせ対応も行っていると、他の仕事に手が回らず、結果として残業が増える原因になり得ます。
問い合わせ対応向きのチャットボットでできること
企業の問い合わせ対応において、チャットボットは大きな役割を果たします。人手不足の解消や、業務効率化に貢献するだけでなく、顧客満足度の向上にもつながります。ここでは、問い合わせ対応向けのチャットボットができることについて解説します。
事前に登録された質問への返答
チャットボットは、あらかじめ登録された質問と回答のデータをもとに自動で返答を行います。
特に役立つのが、よくある質問への対応です。サービスの利用方法や料金に関する質問など、定型的な質問に対しての回答を設定しておけば、チャットボットだけで問い合わせ対応を完結できます。
オペレーターの負担を軽減し、対応品質を均一化できるメリットがあります。
問い合わせに24時間365日対応する
チャットボットは、メンテナンス時間を除いて24時間365日稼働できます。そのため、深夜や休日など、オペレーターが対応できない時間帯でも問い合わせ対応が可能です。
本社が休みでも営業中の店舗がある企業は多いでしょう。そのようなケースでも問い合わせに対応でき、店舗の業務をスムーズに進められます。
素早い返答
事前に登録された情報がある場合、即座に回答を生成できます。利用者は、問い合わせに対する返答を待つ必要がなくなります。
とくに社内問い合わせでは、スムーズに回答が得られることで、業務の進行を妨げることがなくなります。回答待ちの時間が短縮されるぶん、業務効率の向上も期待できます。
問い合わせ内容のデータ化と蓄積
チャットボットのなかには、問い合わせ内容やユーザーの属性情報を蓄積できるものがあります。こうした機能があれば、問い合わせの傾向を分析し、サービスの改善に活用できます。
たとえば、問い合わせの多い項目を把握し、FAQの改善や業務プロセスの見直しを行うことが可能です。AIを活用したチャットボットでは、過去のデータをもとにより適切な回答を生成する機能を持つものもあります。
問い合わせ対応にチャットボットを導入するメリット
問い合わせ対応にチャットボットを導入することで、業務の効率化や利用者の満足度向上など、多くの利点が期待できます。以下に、具体的なメリットを紹介します。
問い合わせ業務の効率化
チャットボットを活用することで、よくある質問への対応を自動化できます。担当者は複雑な問い合わせや高度なサポートに集中できるのがメリットです。問い合わせ業務の効率化が行えます。さらに、問い合わせ対応の負担軽減にもつながります。
利用者の満足度の向上
チャットボットは24時間365日対応が可能です。利用者はいつでも迅速に回答を得ることができます。これにより、回答の待ち時間が減少し、利用者の満足度が向上します。
さらに、社内での問い合わせ対応でも即座に回答が得られるため、社員の業務効率や満足度の向上にも寄与します。
蓄積したデータを会社の方針決定や会議に活かせる
チャットボットを通じて収集された問い合わせデータを分析することで、頻ぱんに寄せられる質問や課題を特定できます。これらの情報は、新しい製品やサービスの開発、既存サービスの改善、さらにはチャットボットの回答精度向上に活用できます。
このように、チャットボットの活用により得られるデータの蓄積と分析は、企業の戦略的な意思決定をサポートします。
問い合わせ対応に向いているチャットボットの選び方
チャットボットを導入する際、適切なものを選ばなければ業務の効率化は実現しません。特に問い合わせ対応を目的とする場合、必要な機能や運用のしやすさが重要です。本記事では、チャットボットを選ぶ際に押さえておくべきポイントを解説します。
「AI搭載型」か「シナリオ型」かを決める
チャットボットには大きく分けて「AI搭載型」と「シナリオ型」の2種類があります。
- AI搭載型:機械学習を活用し、ユーザーの入力内容を解析して最適な回答を提供します。問い合わせの種類が多い場合でも柔軟に対応でき、運用負担が少ないのが特徴です。
- シナリオ型:あらかじめ設定されたシナリオに沿って対応します。シンプルな問い合わせには向いていますが、想定外の質問には対応しにくい点に注意が必要です。
問い合わせの種類が多く、複雑な対応が求められる場合は「AI搭載型」、決まったフローで対応できる場合は「シナリオ型」が適しています。
自社に必要な機能が付いているかを調べる
チャットボットにはさまざまな機能が搭載されており、用途によって必要な機能が異なります。
- データ蓄積機能:過去の問い合わせ内容を分析し、回答の精度向上に活用できる
- 社内ヘルプデスク向け機能:FAQ対応、システムトラブル対応、社内ツールとの連携や人事・総務サポートなど社内問い合わせをサポート
- 多言語対応:海外ユーザーとのコミュニケーションに役立つ
- 外部ツールとの連携:ビジネスチャットやCRMと連携して活用できる
導入前に、自社の業務で必要な機能を整理し、それに適したサービスを選びましょう。
トライアル期間・サポートの有無を確認する
いきなり本格導入するのではなく、トライアル期間を活用して実際の運用を試すことが大切です。実際に使ってみて機能や使い勝手を確認しておきます。
チャットボットによってはサポートを受けられるものもあります。運用に不安がある場合は、サポート体制の充実度を確認し、導入後に不明点をすぐに解決できるかをチェックすることも欠かせません。サポートが充実しているチャットボットなら、運用開始後にトラブルがあった場合も安心できます。
問い合わせ対応のチャットボットを導入する方法・手順
問い合わせ対応のチャットボットを導入する際の手順を、5つのステップに分けてご紹介します。
ステップ1:社内でチャットボットについて話し合う
まず、社内でチャットボット導入に関する話し合いを行い、以下の項目について方針を固めます。
- 導入目的:問い合わせ対応の効率化や顧客満足度の向上など、チャットボットを導入する目的を明確にする
- 必要な機能:自動応答、有人対応への切り替え、データ分析機能など、チャットボットに求める機能を検討
- 設置場所:自社のウェブサイト、SNS、社内ポータルなど、チャットボットを設置する場所を決定
- 候補の選定:上記の要件を満たすチャットボットサービスを2〜3つ選ぶ
これらの検討を通じて、チャットボット導入の方向性を明確にします。
ステップ2:いくつかのチャットボットサービスを試す
選定したチャットボットサービスの無料トライアルやデモ版を利用し、実際の操作感や機能を確認します。長期利用できそうかといった利用のしやすさのほか、自社の目的を達成できそうかも確認してください。
可能であれば、サービス提供者と直接話し、サポート体制やカスタマイズの可否についても確認すると良いでしょう。詳しく話を聞くことで、自社のニーズに最適なチャットボットを見極めることができます。
ステップ3:チャットボットの導入に向けて開発者とやり取りする
導入するチャットボットを決定したら、開発を担当するベンダーと詳細を話し合います。設置場所の確認、既存システムとの連携、導入側でやること、支払い条件など、具体的な事項を話し合っておくとスムーズに導入できます。トラブルを最小限にするためにも、細部まで確認をしてください。
ある程度話がまとまったら、この段階で契約を結ぶベンダーが多いです。契約を結んだあと、詳細なシナリオ構築へと進みます。
ステップ4:想定される質問と回答のシナリオを準備する
チャットボットに登録するための、「想定される質問」と「その回答」を準備します。たとえば、以下のような内容を考えて、シナリオを準備します。
- よくある質問(FAQ)をリストアップする
- 異なる言い回しに対応するために質問のバリエーションを予測
- 質問に対して、明確でわかりやすい回答を準備
- 場合により択肢を提供し、具体的な質問・回答へと導く
問い合わせ対応のチャットボットは、シナリオ作成数が多くなりやすいため、早めの準備が大切です。一部のチャットボットサービスでは、質問と回答のテンプレートが提供されている場合もあります。
ステップ5:仮導入を行って改善点や問題点を修正する
仮導入を行うことで、より効果的にチャットボットを運用できます。
まず、本格的な運用を開始する前に、限定的な範囲でチャットボットを試験運用し、改善点や問題点を洗い出しておきましょう。そして問題点を修正し、準備が整った段階で全体運用を開始します。
問い合わせ対応のチャットボットの導入を成功させるポイント
チャットボットを導入する際には、使い勝手や効果を最大化するために、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。この記事では、問い合わせ対応におけるチャットボット導入を成功させるための4つのポイントを解説します。
チャットボットの存在を広く知らせる
チャットボット導入後の悩みのひとつに、「使ってもらえない」というものがあります。利用者は、導入したことを知らない、もしくは、その利便性を理解しないと利用しません。
導入したら、まずは存在を多くの人に知らせることが大切です。社内ツールに導入する場合は、導入したことを従業員に周知し、社内メールなどで「新しくチャットボットを導入した」ことを伝えましょう。あわせて、チャットボットを使うことで何が解決できるのか、その利便性も伝えて利用を促進します。
チャットボットは画面の目立つ位置に設置することが重要です。訪問者が自然に目にすることで、利用者が増え、問い合わせの効率が向上します。
チャットボットに任せる範囲と人間が担当する範囲を明確にする
チャットボットと人間が担当する範囲をあいまいにしてしまうと、「前回チャットボットに質問した内容と、今回担当者からの返答が異なる」といった状況になり、利用者を混乱させてしまいます。この状況を避けるためには、それぞれの役割を明確に定めることが大切です。
また、チャットボットが担当する範囲と人間が担当する範囲を適切に分けないと、問い合わせ担当者の負担が減らない可能性もあります。責任範囲をはっきりさせて、どの部分をチャットボットがカバーするのかを具体的に決めましょう。
運用体制を構築する
チャットボットを導入したら、スムーズに運用できる体制を整えることが重要です。チャットボットの運用チェック・メンテナンスは誰が行うのか、不具合などがあった場合の問い合わせ先はどこか、ベンダーとの窓口となる人は誰かなど、担当者を選出し、責任の所在を明らかにしておきましょう。
運用体制がしっかりと構築できれば、問題が起きた場合も素早く対応でき、サービスの品質を保つことができます。
定期的にメンテナンスを行う
チャットボットは一度導入すれば完了、というわけではありません。
企業の方針の変化、問い合わせ内容の変化があれば、メンテナンスを行ってシナリオを最適化する必要があります。また、利用者からのフィードバックや苦情も反映させて、チャットボットの内容をアップデートすることも重要です。定期的にメンテナンスを行うことで、常に使いやすく、適切な情報を提供できる状態を維持できます。
問い合わせ対応のチャットボットの導入事例
チャットボットを活用して成果を上げた事例を3社ご紹介します。各社がどのようにチャットボットを利用しているのか、参考にしてください。
200時間の業務時間削減に成功|株式会社レオパレス21
株式会社レオパレス21は、電話やメールでの問い合わせ対応に多くの時間を費やしており、業務負担が課題となっていたことから、チャットボットの導入を決意しました。AIとシナリオ型を検討しましたが、AIはまだ発達段階ということもあり、シナリオ型を選択します。
導入の結果、よくある質問への自動応答が可能になり、問い合わせ効率が大幅に向上。営業時間外でも顧客対応ができるようになり、月間約200時間の業務時間削減を実現しました。
さらに、設問項目に答えていくことで、セールスを受けていると感じさせず、無理なく次のステップへと誘導できるようにもなりました。営業電話を嫌がる顧客も、チャットボットであれば返信をしてくれることが多く、有人対応のみでは得られなかった新しい情報が獲得できるようになったことも、導入の成果に挙げています。
事例詳細:IZANAI導入により、200時間の業務時間削減!コスパよし、操作性よし、100点満点のツールです。|株式会社レオパレス21様
電話対応数が導入前の2割にまで減少|Fukuoka Growth Next
Fukuoka Growth Nextは、福岡市が運営するスタートアップ支援施設です。施設利用に関する問い合わせ対応の負担が大きく、スタッフの業務効率が低下が課題となっていました。
そこで、AIチャットボットをWebサイトに導入し、利用者からの質問に自動対応できる仕組みを構築。これにより、基本的な問い合わせの多くをチャットボットで解決できるようになりました。その結果、導入後1ヶ月で電話対応数が80%削減され、スタッフは他の業務に集中できるようになりました。
また、チャットボットの会話ログを分析することで、利用者がどのような情報を求めているかを把握しやすくなりました。事前に必要な情報を提供することで、問い合わせの削減と満足度の向上につながっています。
社内問い合わせ対応の効率化を実現|株式会社NTTドコモ
株式会社NTTドコモは、社内の問い合わせ対応をメール中心に行っていたところ、進捗管理ができず対応漏れや引き継ぎの手間が発生する、という課題がありました。そこで、チャットボットを含む問い合わせ管理ツールを導入。問い合わせの一元管理を行います。
導入後、一元管理により担当者は状況を把握しやすくなり、チャットボットがよくある質問に自動対応することで、負担も軽減されました。
その結果、問い合わせ対応の平均時間が大幅に減少。以前は回答に1日以上かかっていたものが、1営業日以内で対応できるようになりました。
さらに、過去の問い合わせとその回答が蓄積されることで、FAQとして活用できるようになります。社員が自分で疑問を解決できることが増え、問い合わせの数を減らすことにもつながりました。
自社の課題や目的に合わせて、適切なチャットボットを導入しよう
問い合わせ対応の負担を軽減し、業務を効率化するには、自社の課題に合ったチャットボットの導入が欠かせません。そのためには、導入の目的を明確にして、トライアルなどを活用し、必要な機能や運用方法をじっくり確かめてみてください。
チャットボットをうまく活用できれば、負担軽減、業務効率化、顧客満足度の情報などさまざまなメリットが得られます。上手に活用して、問い合わせ対応の質を高めていきましょう。


