チャットボットの導入に成功した事例10選|成功のポイントも解説
最終更新日2025/04/28
公開日 2025/04/23
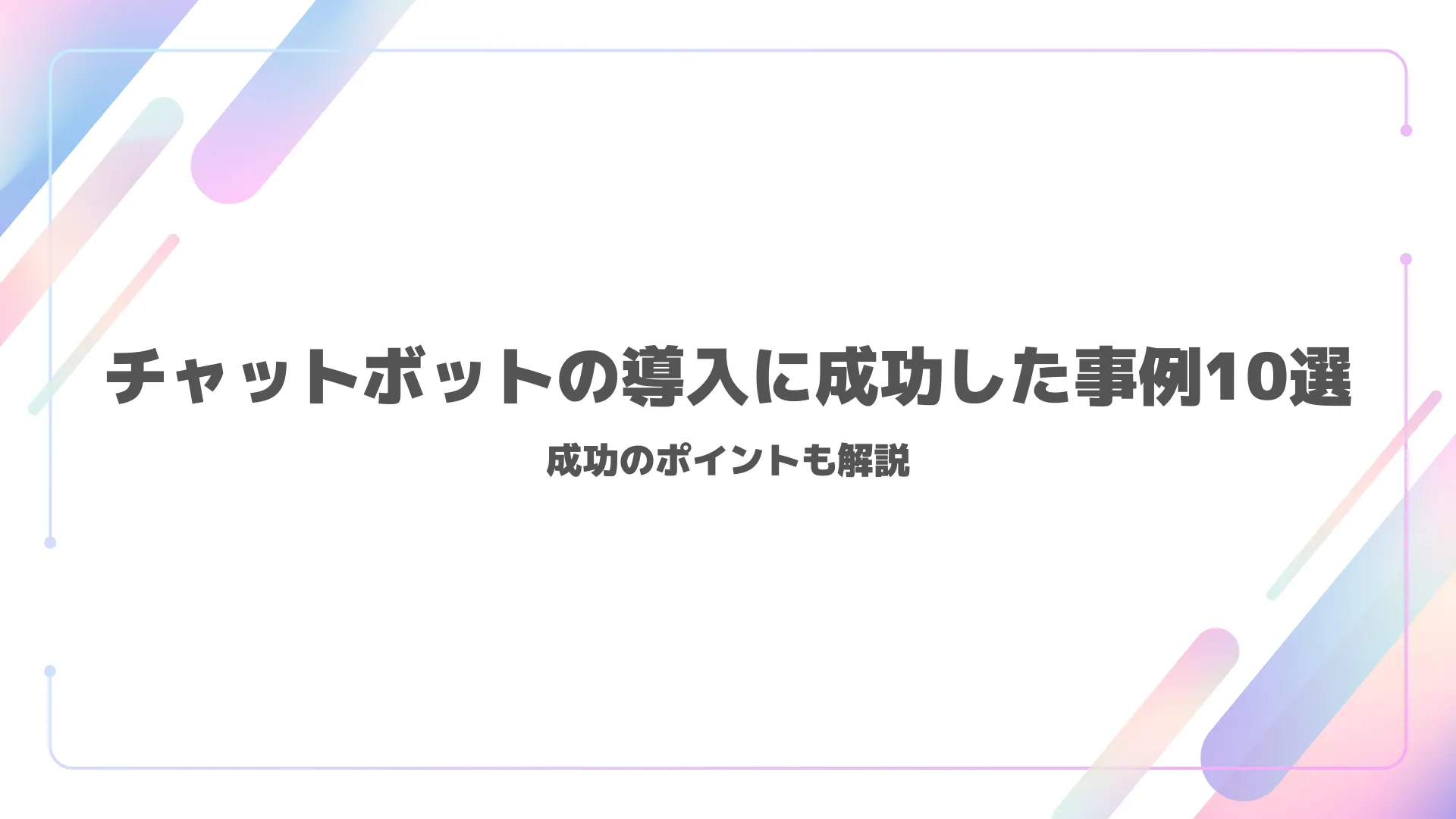
「問い合わせ対応に追われ、本来の業務に手が回らない」「顧客満足度を高めるために、24時間対応できる窓口が欲しい」
こうした悩みを抱える企業は少なくありません。人手不足が深刻化するなかで、その解決策としてAIを活用したチャットボットが注目を集めています。
チャットボットは、問い合わせ対応を自動化することで、業務効率化やコスト削減、顧客満足度の向上を実現できます。しかし、「導入しても効果があるのか」「自社に合った活用方法がわからない」と、不安を感じる方もいるのではないでしょうか。
そこで本記事では、業界別のチャットボット導入成功事例10選をご紹介します。不動産・ECサイト・観光・自治体など、各業界で企業が抱えていた課題を、チャットボットがどのように解決し、どんな成果を生み出したのかを具体的に解説します。
導入を検討中の企業はもちろん、すでに運用している企業にとっても、自社に最適な活用方法が見つかるはずです。ぜひ最後までご覧ください。
目次
チャットボットとは?
チャットボットは、人工知能(AI)を活用した自動会話プログラムです。ユーザーからの質問や要望に対して、あらかじめ設定された回答やAIが生成した回答を返すことで、人間のオペレーターに代わってコミュニケーションを行います。
チャットボットは大きく分けて、以下の2種類があります。
- シナリオ型チャットボット:あらかじめ設定されたシナリオに沿って会話を進めるタイプで、決まった質問に対して決まった回答を返します。設定した範囲内の質問にはスピーディに対応できますが、想定外の質問には対応しづらいという特徴があります。
- AI型チャットボット:自然言語処理技術を用いて、ユーザーの意図を理解し回答を生成するタイプです。学習していくことで精度が向上し、シナリオ型よりも柔軟な対応が可能です。最近では、ChatGPTなどの生成AIを活用したものも増えてきました。
企業のWebサイトやアプリ、SNSなど様々なチャネルに導入され、24時間365日休むことなく対応することで、顧客満足度の向上や業務効率化に役立てられています。
チャットボットでできること
チャットボットを導入することで、企業にはどのようなメリットがあるのでしょうか。主なメリットを4つご紹介します。
コールセンターの負担軽減
コールセンターでは、日々寄せられる問い合わせのうち、多くが製品の基本的な使い方や料金に関するものなど、比較的簡単な内容です。チャットボットを導入することで、これらの定型的な問い合わせを自動で処理できます。オペレーターはより専門的な知識や対応スキルが求められる相談に集中できるようになり、業務効率が向上します。
顧客にとっても、電話回線の混雑を気にすることなく、知りたい情報をすぐに得られるため、待ち時間によるストレスが軽減されます。有人対応が必要な場合でも、チャットボットが事前に顧客の基本的な情報をヒアリングしておくことで、オペレーターはスムーズに状況を把握し、迅速かつ的確な対応を行えます。
お問い合わせ数や新規顧客の増加
Webサイトにチャットボットを設置することで、製品やサービスに関心を持った顧客が抱える疑問に即座に対応できます。「この製品の具体的なメリットは?」「複数のプランの違いは何?」といった質問に対し、リアルタイムで的確な回答を提供することで、顧客は安心して検討を進めることができます。
これにより、購入や契約へのハードルが下がり、成約率の向上が期待できます。企業側にとっても、これまで人的リソースの制約から対応しきれなかった潜在顧客の疑問を解消できるため、新たな顧客層の開拓につながります。チャットボットとのやり取りは全て記録されるため、顧客がどのような情報に関心を持っているのかを分析し、マーケティング戦略や製品開発にも活用できます。
海外のお客様とのコミュニケーションの円滑化
グローバル展開を目指す企業にとって、多言語対応可能なチャットボットは効果的です。英語や中国語をはじめとする複数の言語に対応したチャットボットを導入することで、外国人顧客も自国語で必要な情報をスムーズに取得できるようになります。
特に海外市場に進出する企業や、外国人顧客の利用が多い業界では、言語の壁による問い合わせ対応の負担を軽減しつつ、質の高い顧客体験を提供できるようになります。言語の障壁を取り除くことで、海外市場への参入障壁を下げ、事業展開を促進します。
社内業務の効率化
社内の業務改善にも、チャットボットは有効な手段です。従業員が人事・総務・IT部門によく行う問い合わせ、例えば「有給休暇の申請方法」「経費精算の手順」などをチャットボットが自動で回答することで、管理部門の負担を削減できます。
従業員は必要な情報をすぐに自己解決できるため、業務の遅れを防ぎ、生産性の向上につながります。また、過去の問い合わせ内容を分析することで、よくある質問とその回答をまとめ、FAQの充実や社内マニュアルの改善に役立てることも可能です。チャットボットによって組織全体の生産性を高め、従業員が業務に集中できる環境を整備できます。
チャットボットの導入に成功した事例10選
ここからは、業界別にチャットボット導入の成功事例をご紹介します。各企業がどのような課題を抱え、チャットボットでどう解決したのか、具体的な成果も含めて解説します。
1.【不動産】業務時間を200時間削減|株式会社レオパレス21
株式会社レオパレス21は、全国に約56万室のアパート管理を展開する大手不動産会社です。営業時間外の問い合わせが全体の50%を超え、人件費と業務管理コストの増加が課題となっていました。多言語対応が必要な外国籍顧客への対応も含め、効率的な顧客対応の仕組みを模索していた同社は、チャットボットツール「IZANAI」を導入しました。
導入後は、顧客が24時間いつでも必要な情報を入力できるようになったため、物件見学や来店など次のステップへの誘導がスムーズになりました。特に電話対応を好まない顧客層からの反応が向上し、これまで獲得できなかった顧客情報の収集に成功しています。
その結果、部署全体で約200時間の業務時間削減を達成。今後は入居者向けFAQやメンテナンス依頼への対応など、活用範囲をさらに拡大する計画です。
関連記事:IZANAI導入により、200時間の業務時間削減!コスパよし、操作性よし、100点満点のツールです。
2.【不動産】新しい潜在顧客にアプローチ|相鉄不動産販売株式会社
相鉄不動産販売株式会社は、神奈川県内で不動産仲介や中古不動産のリノベーション事業を展開する総合不動産企業です。スマートフォンからの物件検索が主流となる中、従来の入力項目が多い問い合わせフォームでは拾いきれない潜在的なニーズに対応すべく、IZANAIを導入しました。
チャットボットの活用により、物件探しの問い合わせ件数が前年比150%に増加。なかでも女性からの問い合わせが多く、情報収集段階からの顧客接点が広がりました。従来の問い合わせフォームでは獲得できなかった「希望条件に合う物件が出たら連絡してほしい」という新たな潜在層の開拓に成功しています。
今後は来店客の情報入力業務の効率化など、チャットボットの活用領域を広げる計画です。問い合わせハードルを下げることで、顧客体験向上と業務効率化を同時に実現した好例といえるでしょう。
関連記事:不動産でチャットボットを導入し、新しい潜在顧客へのアプローチが可能に
3.【EC・小売】ECサイトで商品の購入を後押し|Plant Hunt合同会社
Plant Hunt合同会社は、厳選した観葉植物をECサイトで販売する企業です。実店舗のような顧客体験をオンラインで提供するため、IZANAIとARマーケティングツール「LESSAR」を導入しました。
導入背景には、ECサイト特有の「商品を直接見られない」「店員に相談できない」という課題がありました。顧客接点の強化と購入前の商品イメージを向上させる手段として、チャットボットとARの組み合わせを採用しています。
導入後は両ツールを用いた独自コンテンツ「植物診断」を開発。チャットボットで顧客の環境や好みを診断して最適な植物を提案し、ARでその植物を自宅に置いたイメージを確認できる仕組みを作りました。ユーザーが理解しやすいよう「腰の高さ」といった体感的な表現を用いるなど、顧客目線の工夫も施しています。
「一鉢目」の購入ハードルを下げ、長期的な顧客関係の構築を目指す同社の取り組みは、EC業界における新たな顧客体験創出のモデルケースとなるでしょう。
関連記事:ECサイトでチャットボットを活用した「植物診断」!ARを組み合わせることで購入前の試し置きを実現し「一鉢目」の購入を後押し
4.【人材サービス】求人サイトの応募数が増加|シーデーピージャパン株式会社
シーデーピージャパン株式会社は、製造系人材派遣を中心とした総合人材サービスを提供する企業です。同社は「ジョブベリー工場」と「期間工ジョブ」の2つの求人サイトを運営していましたが、膨大な求人情報から求職者が希望の仕事を見つけられず、サイトから離脱するケースが課題でした。
複数のチャットボットツールを比較検討した結果、優れたコストパフォーマンスと使いやすい操作性が決め手となりIZANAIを採用。誰でも簡単にチャットボットを構築できるIZANAIの特長により、システム設定にかかる時間を抑え、チームは工数の多くを質の高いシナリオ設計に集中。求職者が自分に合った求人へスムーズに辿り着ける導線を構築しました。
その結果、2つの求人サイトからの月間応募数は前年比約1.5倍に増加。ウィジェットデザインの改善後は応募数も向上し、一人あたり数千円という従来の求人媒体と比較して効率的なコストで採用につながりました。
今後はコーポレートサイトのリニューアルに合わせ、採用ページへのチャットボット設置など、利用シーンの拡大を予定しています。
関連記事:求人サイトでチャットボット活用!ちょっとした工夫で高コスパかつ応募数が激増!
5.【教育】資料請求や来校予約の足掛かりに|学校法人創志学園 クラーク記念国際高等学校
学校法人創志学園 クラーク記念国際高等学校は、全国から海外まで50以上の拠点を持つ通信制高校です。同校はWebサイトの来校促進や資料請求の導線構築に課題を感じており、サイトリニューアルと同時にIZANAIと電子ブック作成ツール「ActiBook」を導入しました。
Webサイトでの来校促進のため、IZANAIをトップページに設置し、最短で資料請求・来校予約ができるよう誘導。また中学生・保護者の興味関心を高める簡単な質問コンテンツも作成しました。ActiBookでは資料請求者向けの電子パンフレットや募集要項を公開し、その中にもIZANAIを組み込むことで予約しやすい導線を構築しています。
これらの施策により、電子ブックの閲覧数は大幅に増加し、特に募集要項は多くの方に見られるようになりました。チャットボット経由での資料請求者は来校率が高い傾向にあり、入学意欲の高い志願者獲得につながっています。
今後は、中学生や保護者が求める情報に対応するコンテンツの充実と、来校予約数の増加に向けた取り組みを進めていく方針です。
関連記事:サイトリニューアルを機にチャットボットと電子ブックを導入来校促進の足がかりに!
6.【通販】コールセンターの応答性をチャットボットで改善|株式会社テレビショッピング研究所
株式会社テレビショッピング研究所は、テレビCMを中心とした通信販売事業を展開し、主に50~70代の顧客に健康食品や生活雑貨を提供しています。同社のアフターフォローコールセンターでは、入電予測の難しさと問い合わせ内容の多様性から、顧客対応の効率化が課題となっていました。
そこで自動音声対話システム「PKSHA Voicebot」を導入し、同社のヒット商品であるノンワイヤー下着「ジニエブラ」のサイズ交換からスタート。高齢顧客でも使いやすいよう質問項目を工夫し、「XL」を「LL」と言うなどの言葉のゆらぎをAIに学習させました。対話精度を高めたのち、主力商品である健康飲料「青汁三昧」の配送日変更へと範囲を広げています。
導入効果としては、「ジニエブラ」のサイズ交換では音声対話システム内での完結率が75%超、「青汁三昧」では70%超を達成。問い合わせの約半数が自動対応されるようになり、オペレーターが複雑な対応に集中できる体制が整いました。特にコロナ禍の受注急増時には応答率の低下防止に役立ち、顧客の待ち時間短縮に貢献しています。
7.【航空】AIチャットボットで24時間365日問い合わせ対応が可能に|日本航空株式会社
日本航空株式会社は、24時間365日利用できるAIチャットボット「チャット自動応答サービス」を提供しています。このサービスはパソコンやスマートフォンから簡単にアクセスでき、国内・国際線の運航情報から予約・購入、搭乗手続き、手荷物に関する問い合わせまで幅広く対応しています。
回答率は92%以上を誇り、PCR検査の規定や検疫体制、入国制限、減便・運休情報など、状況に応じた最新情報も迅速に提供、利用者の疑問をその場で解決します。利用方法もシンプルで、サポートページ右下のアイコンから質問カテゴリを選ぶか、直接質問を入力するだけで必要な情報が得られます。
また、JALマイレージバンクに関する問い合わせでは、自動応答だけでなく必要に応じてチャットオペレーターへの接続も可能です。この高い安定性と回答精度がJALの顧客満足度向上につながっています。
参考:JAL「チャット自動応答サービス/JALメッセージサポートのご案内」
8.【宿泊・ホテル】多言語対応のチャットボットで海外のお客様の利便性が向上|JR西日本ホテルズ
JR西日本グループの宿泊事業を担うJR西日本ホテルズは、西日本エリアを中心に全11ホテルを展開する鉄道系ホテルチェーンです。2022年5月に、顧客満足度向上を目指して多言語AIチャットボット「talkappi CHATBOT」を導入。翌年には旅ナカアプリ「VERY」をグループ全11ホテルに展開し、デジタル顧客体験を強化しました。
多言語AIチャットボット導入の主な目的は電話問合せの削減でした。たとえば全国旅行支援開始前には、Webサイト上に「よくある質問はこちら」などのボタンを設置して誘導したところ、かなりの流入数があり、各ホテルへの問合せ削減に効果を発揮しました。
ツールの導入により外国人旅行者の情報アクセスが向上し、スタッフの外国語対応負担も軽減。LINE連携によって公式アカウントのフォロワーも約16,000人に達し、データを活用した効果的な情報発信も進んでいます。デジタル化と顧客接点強化を両立した取り組みは、ホスピタリティ業界におけるデジタル変革の好例として注目されています。
9.【行政】LINEを活用したチャットボットで住民からの質問に回答|福島県会津若松市
会津若松市では、市民の日常生活をサポートするため「LINE de ちゃチャット問い合わせサービス」を導入しています。AIを搭載したチャットボット「マッシュくん」が市民からの問い合わせに自動で回答する仕組みです。
「マッシュくん」は「会津若松市役所職員見習い」という設定で、市民の生活に密着した質問に24時間対応します。休日・夜間の診療可能な病院案内、ごみの分別方法、各種証明書の発行手続きなど基本的な問い合わせから、会津地域特有の課題である冬季の除雪車運行状況まで幅広い情報を提供しています。
利用方法は簡単で、「@mushkunchat」を検索して友だち登録するか、市が配布するQRコードを読み込むことで始められます。スマートフォンの普及に伴い、多くの市民が日常的に使用するLINEをプラットフォームとして選択することで、行政情報へのアクセスをより身近なものとしました。
本サービスは、市民がいつでも必要な情報を得られる環境を整備し、行政サービスのデジタル化を推進する事例として評価されています。
参考:福島県会津若松市「LINE de ちゃチャット問い合わせサービス」
10.【製造】バックオフィスへの問合せを20%削減|帝⼈株式会社
帝人株式会社は、1918年創業の高機能繊維や医薬品の研究開発・製造・販売を行う企業です。同社では各部署が独自のイントラサイトを構築していたため情報が散在し、社員が必要な情報を見つけにくく、バックオフィスへの問い合わせが集中する状況が課題となっていました。
この問題解決のため、AIチャットボット「OfficeBot」を導入。まずは最も頻度の高い200件のFAQを登録して試験運用を開始し、その効果を確認しながら600件、1,000件と段階的に内容を拡充しました。問い合わせ頻度と回答難易度を基準に優先順位を設定することで、効率的なナレッジベースを構築しています。
導入効果として、東京総務グループでは問い合わせが20%削減され、同一内容の問い合わせが大きく減少。担当者の負担が軽減されたほか、回答の均質化と社内ナレッジ共有にも役立っています。
この成果を受け、帝人では他部門やグループ会社へも展開を進め、全社的な働き方改革推進の一環として位置づけられています。問い合わせが集中する時期の業務負担を抑えるとともに、社員が必要な情報に迅速にアクセスできる環境を整えています。
チャットボットの導入を成功させるためのポイント
顧客対応の効率化や24時間対応の実現など、さまざまなメリットをもたらすチャットボットですが、導入しても、期待した効果が得られないケースも少なくありません。チャットボットで成果を上げるには、計画的な導入と戦略的な運用が不可欠です。ここでは、チャットボット導入を成功に導く7つのポイントを解説します。
導入目的を明確にして、目的に合ったシステムを導入する
チャットボット導入の第一歩は、明確な目標設定です。単にツールを導入するのではなく、「実現したいこと」や「解決したい課題」を事前に具体化しておくことが大切です。例えば、多言語対応が必要であるにもかかわらず、日本語のみのシステムを選んでも期待する成果は得られません。顧客からの問い合わせ処理を効率化したいのか、常時サポート体制を構築したいのかといった目的によって、選ぶべきチャットボットの機能や種類は異なります。
抱える課題を丁寧に分析し、必要な機能を備えたチャットボットを選ぶことが、導入後の成果に大きく影響します。
利用者のニーズを正しく分析する
チャットボットの成功には、利用者が求めることを正確に把握することが不可欠です。ただ「よくある質問」をまとめるだけでは不十分で、顧客の課題を深く掘り下げ、具体的な利用シーンを想定することが求められます。
例えば、ECサイトの場合、商品検索、注文、配送、返品といった利用者の行動フローを分析し、それぞれの段階で生じる疑問や問題を特定します。質問の種類を徹底的に洗い出すために、過去の問い合わせ履歴、FAQの検索キーワード、SNS上の顧客の声を分析するのも効果的です。
Google Analyticsなどのログ分析ツールを活用することで、利用者の行動パターンや離脱ポイントを可視化し、改善すべき点を明確にできます。
チャットボットの運用体制を整える
導入後の継続的な運用と改善を見据え、適切な管理体制を構築しましょう。情報の追加や更新を担当する責任者を決め、運用チームを編成することが大切です。
役割を明確にすることで、それぞれの専門性を活かした運用が可能になります。プロジェクトマネージャー、シナリオライター、エンジニア、データアナリストなどの役割を設定し、それぞれが定期的にチャットボットのパフォーマンスを評価します。緊急時の対応フローも明確にし、システムトラブルやセキュリティインシデント発生時の連絡経路や対応手順を事前に決めておくことで、迅速な対処が可能になります。
分析の頻度も決めておきましょう。週次でアクセス数や解決率をチェックし、月次ではユーザーの行動や満足度を評価します。さらに、四半期ごとに改善計画を見直すことで運用の質を高められます。
有人対応とチャットボット対応の境界を決める
チャットボットは便利なツールですが、すべての問い合わせに対応できるわけではありません。特に、複雑な質問や専門知識が必要な場合には、人間のオペレーターによる対応が求められます。
そのため、チャットボットと有人対応の切り替えルールを明確にしましょう。以下のような条件で有人対応に切り替えると望ましいです。
- 「クレーム」「返品」など特定のキーワードを含む場合
- 同じ質問が一定回数以上繰り返された場合(例:3回以上)
- 利用者がオペレーターとの会話を希望した場合
また、スムーズな引き継ぎのために、チャットボットのログをオペレーターに共有できる機能を導入しましょう。CRMと連携することで、オペレーターが利用者の状況を正しく把握し、適切な対応がしやすくなります。
チャットボットが回答できない場合の対策を考える
どれだけ準備をしても、チャットボットが対応できない質問は必ず発生します。その際、利用者にストレスを感じさせないように、適切な対応策を用意しておくことが重要です。
例えば、以下のような方法が有効です。
- 有人対応へスムーズに切り替える
- FAQページへのリンクを提示し、自己解決を促す
- 問い合わせフォームを表示する
また、「申し訳ございません。〇〇については現在対応しておりません。FAQページをご参照いただくか、お問い合わせフォームをご利用ください。」といった具体的なメッセージを準備しておくことで、利用者が混乱しにくくなります。
チャットボットが回答できなかったケースを記録し、改善につなげる仕組みも重要です。利用者に簡単なフィードバックを求めたり、アンケートを実施したりすることで、ボットの弱点を特定し、対応精度を高められます。未対応の質問については定期的にレビューミーティングを開催し、優先度をつけて対応を検討する体制を構築しましょう。
本格運用前に十分なテストを行う
チャットボットを公開する前に、動作確認を徹底しましょう。テストでは、想定される質問だけでなく、予期しない質問や誤入力、曖昧な表現、感情的な表現にも対応できるかを確認します。
テストの際は、専用ツールを活用し、テストケースの作成、実行、結果記録を行いましょう。社内スタッフだけでなく、実際の利用者にテストへ参加してもらうと、より実用的なフィードバックが得られます。
チャットボットの応答速度や処理能力も重要です。負荷テストツールを使い、想定される最大同時接続数での動作を確認し、応答時間やエラー率などの指標をチェックしましょう。
運用開始後も継続的に改善を行う
チャットボットの運用を成功させるには、導入後の継続的な分析と改善が欠かせません。
運用開始時に以下のようなKPI(重要業績評価指標)を設定し、Google Data StudioなどのBIツールを活用して定期的にモニタリングします。
- 利用率
- 解決率
- 顧客満足度
- コンバージョン率
- コスト削減効果
アンケートやレビュー、SNSでの意見を収集し、顧客満足度も定期的に測定します。集めたデータは専用ツールやスプレッドシートで整理し、改善点を分析しましょう。
運用データや顧客のフィードバックを基に、シナリオや回答内容の見直しを行い、FAQを追加・修正します。プロジェクト管理ツールを活用し、優先順位をつけながら改善計画を立て、実施と効果測定を繰り返すことで、運用の質を向上させます。競合他社のチャットボットやカスタマーサポート施策のベンチマーキングも定期的に行い、業界トレンドや最新技術を取り入れる機会を逃さないようにしましょう。
定期的な分析と改善を行うことで、チャットボットの運用効果を最大限に高めることができます。
導入するチャットボットツールを決めるときに確認すると良い項目
チャットボットツールは数多く存在し、それぞれ特徴や機能が異なります。自社の目的やニーズに合ったツールを選ぶためには、以下の項目を確認すると良いでしょう。
- 自社に必要な機能があるか:導入目的を達成するために必要な機能が備わっているかを確認します。例えば、多言語対応、API連携、自然言語処理の精度など、具体的な要件に合わせて検討しましょう。
- 費用:ツールの導入費用や運用費用は、予算内に収まるかを確認します。初期費用だけでなく、月額費用や従量課金など、料金体系も比較検討することが大切です。
- サポートの有無・充実度:導入時や運用時に困ったことがあった場合に、適切なサポートを受けられるかを確認します。サポート体制が充実しているツールを選ぶことで、安心して利用できます。
- トライアルの有無:実際にツールを試せるトライアル期間があるかを確認します。トライアル期間を利用して、自社の環境で問題なく動作するか、使いやすいかなどを確認することで、導入後のミスマッチを防ぐことができます。
これらの項目に加えて、セキュリティ対策や拡張性なども考慮し、自社にとって最適なチャットボットツールを選定することが、導入の成功につながります。
まとめ|チャットボットで顧客体験を向上させよう
本記事では、各業界のチャットボット導入成功事例から導入を成功させるためのポイントまで解説しました。
チャットボットは問い合わせ対応の自動化ツールにとどまらず、顧客体験の向上や新たな営業機会の創出、業務効率化など、ビジネスに多面的な価値をもたらします。特に昨今の人手不足や働き方改革の流れを受け、その重要性はますます高まっています。
導入を検討する際は、自社の課題や目的を明確にし、段階的に機能を拡張していくことが大切です。また、継続的な学習と改善を行うことで、より賢く、顧客ニーズに応えるチャットボットへと進化させることができます。
「どのようなチャットボットが自社に適しているのか」「どのように導入・運用すべきか」など、具体的な疑問については、専門のベンダーやコンサルタントに相談するのも一つの方法です。業界の動向や最新技術を踏まえた適切なアドバイスを受けることで、効果的な導入が期待できます。
チャットボットを活用し、顧客満足度の向上と業務効率化の両立を実現しましょう。そこから得られるデータや知見を新たな事業に活かすことで、ビジネスの可能性が広がります。


