AIチャットボットの導入事例10選|問い合わせ対応やヘルプデスクなどを紹介
公開日 2025/04/28
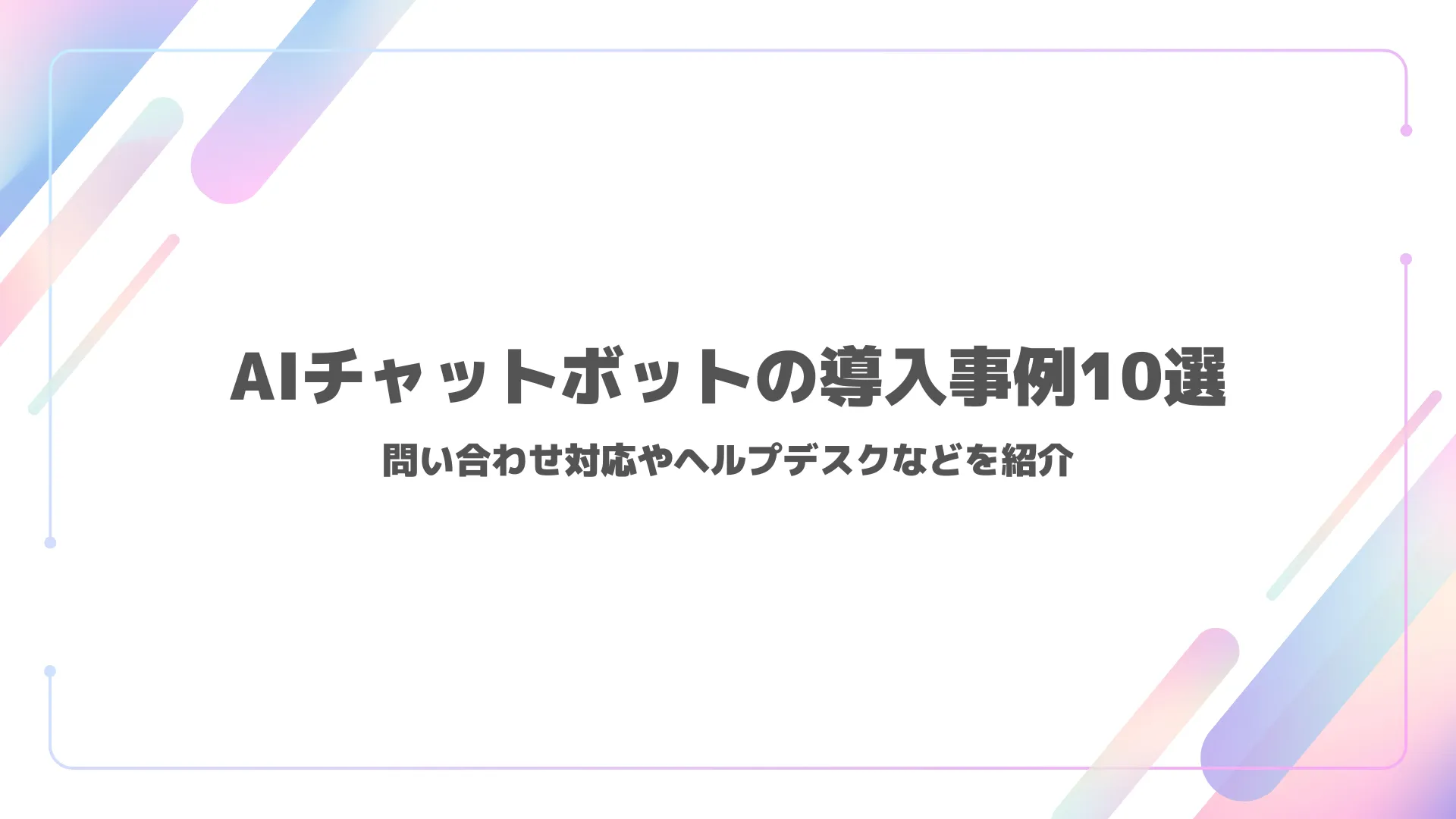
AIチャットボットとは、人工知能技術を活用して自然な会話形式でユーザーとやり取りするシステムです。従来型のチャットボットとは異なり、自己学習能力を持ち、柔軟な対応が可能なのが特長です。
たとえば「問い合わせ対応の負担を減らしたい」「社内の情報共有を効率化したい」といった課題に対し、AIチャットボットは有効な選択肢となります。
本記事では、実際にAIチャットボットを導入して成果を上げた10社の事例を紹介します。あわせて通常のチャットボットとの違いや、成功するポイントについても解説します。ぜひ自社で導入を検討する際の参考にしてみてください。
目次
AIチャットボットとは
AIチャットボットは、事前に登録されたデータやユーザーの操作履歴をもとに学習を行い、自動で会話のやり取りを進めるプログラムです。ユーザーからの質問に対し、蓄積された情報をもとに最適な回答を提示します。
使い続けることで学習が進み、回答の精度が向上するのが大きな特長です。定型的な受け答えだけでなく、雑談を含めた自然な会話にも対応できるようになるため、より人間に近いコミュニケーションが可能になります。
近年では、ECサイトや企業のWebサイト、さらにはLINEアプリなどとも連携し、ビジネスシーンでの活用が広がっています。問い合わせ対応や24時間のサポート体制構築にも役立ち、業務の効率化と顧客満足度の向上に貢献しています。
AIチャットボットと通常のチャットボットの違い
AIチャットボットは、従来型のチャットボットと比べて、どのような違いがあるのでしょうか。代表的な3つの違いをわかりやすく紹介します。
AIチャットボットは自己学習ができる
AIチャットボットの大きな違いは、ユーザーとのやり取りを通じて自ら学び、精度を高めていく点です。質問と回答の履歴やユーザー行動のデータを読み込みながら、継続的に内容を改善していきます。
一方、従来のチャットボット(シナリオ型)は、あらかじめ設定されたルールに従って対応する仕組みのため、想定外の質問には対応できません。その都度、人の手で情報を更新する必要があるため、運用の負担も大きくなります。
AIチャットボットには、「機械学習型」と「独自AI型」の2つのタイプがあります。前者は継続的なデータ投入と調整が求められますが、後者はFAQを登録するだけで利用を始められるため、導入のしやすさが特長です。
AIチャットボットは自然な会話形式でのやり取りが得意
AIチャットボットは、自然言語処理(NLP)の技術を活用することで、人間らしい会話を実現できます。類義語や言い回しの違いにも柔軟に対応できるため、ユーザーが少し表現を変えても、意図を正確に理解しやすくなります。
従来型のチャットボットは、選択肢を提示する形式が主流で、会話というよりもアンケートのような印象を与えがちでした。それに対し、AIチャットボットは自由な質問にもスムーズに応じられ、より自然な対話が可能です。
ユーザーが相手を「プログラム」と意識せずやり取りできる点も、接客やサポートの質を高めるポイントとなります。
AIチャットボットはより柔軟な対応が可能
柔軟性の高さもAIチャットボットの魅力です。文脈を理解しながら、最適な返答を導き出せるため、事前に学習したデータや過去の応答履歴をもとに複雑な質問にも対応できます。
たとえば、複数の条件を含んだ質問に対しても、適切に情報を整理しながら返答を行います。また、必要に応じて追加質問を投げかけ、ユーザーの意図を深掘りすることも可能です。
従来のチャットボットでは、あらかじめ決められたシナリオから外れると対応が難しく、柔軟な対話には限界がありました。
AIチャットボットの導入事例10選
ここからは、実際にAIチャットボットを導入して成果を上げている企業・団体の事例を紹介します。
サントリーホールディングス|年間約1,000時間の問い合せ対応時間の削減に成功
サントリーホールディングスでは、人事・給与関連の問い合わせに対応するため、社内向けサイトにQ&Aを掲載していました。しかし、約3,000件にもおよぶ情報量に加え、グループ会社ごとに異なる制度があるため、情報管理と対応が大きな課題となっていました。問い合わせ対応には1日あたり約3時間を費やしており、業務効率の向上が急務でした。
当初は、辞書型チャットボットを導入したものの、同義語登録などの管理負担が大きく、表現の違いに対応しきれない問題が発生。そこでAI搭載型チャットボットへ切り替えたところ、年間で約1,000時間の対応時間を削減でき、社員が本来の業務に集中できるようになりました。正答率の向上により利便性も高まり、利用者数は増加傾向にあります。
今後は、人事・給与・総務領域にとどまらず、全社の問い合わせ対応を担う窓口としての拡張も検討されています。
参考:QuickQA人事総務
京都銀行|行内からの問い合わせ数が2割減少
京都銀行では、2020年4月からの第7次中期経営計画で「デジタルコネクト」を掲げ、業務と顧客対応のデジタル化を推進。各部門の業務分析により、営業店から本部への電話問い合わせが多く、業務負担となっていることが判明しました。部署によっては、一日に数百件の電話が入る状況だったといいます。
とくに国際営業部では、電話応対によって作業が中断されることで、ミスの発生や生産性の低下が問題となっていました。こうした課題を解消する手段として、AIチャットボットを導入。回答精度の高さと、管理画面の使いやすさが導入の決め手となりました。
結果として、行内からの電話問い合わせが約2割減少。本部の営業時間外にも情報確認が可能になり、休日営業店舗での顧客対応もスムーズになりました。
参考:行内外に全面導入 – 京都銀行のコミュニケーション改革によるDX – | エンタープライズ向けAI SaaS
株式会社フラッグシステム|月間300件の問い合わせ対応の効率化に成功
イベント管理システム「イーベ!」を展開するフラッグシステムでは、利用者増加に伴い、問い合わせ対応にかかる負担が大きくなっていました。人手不足の中、対応効率を高める必要があり、応答品質に優れたAIチャットボットの導入を決定しました。
サービスサイトや会員専用の管理画面にAIチャットボットを設置。導入当初は単語による質問が多かったものの、文章での問い合わせを促した結果、より自然な対話が可能になりました。マニュアルを学習させたAIは、ログを定期的に分析し、回答できなかった質問に対して順次対応を追加するなど、継続的に精度を向上させています。
その結果、以前導入していたFAQツールを上回る月間約300件の対応を実現し、利用者の満足度も8割に達しています。「ありがとう」といった声が増えるなど、顧客体験の向上にもつながっています。
参考:生成AIチャットボット×VOC自動分析で顧客満足度8割超え!月間300件の問い合わせを効率化しROI 1.5倍に
株式会社アガルート|オンライン法律顧問サービスを開始
オンライン予備校運営などを手がけるアガルートは、法律相談のニーズ増加を予測し、IT技術を駆使した新たな法律サービスの開発に取り組みました。とくに、費用面の制約で顧問弁護士を雇うことが難しい中小企業向けに、信頼性の高い情報を手軽に入手できるオンライン法律相談窓口の設置を目指しました。
しかし、当初導入を検討していたチャットボットでは、期待していた回答スピードや精度に届きませんでした。そこで、質問の意味を理解して、最適な答えを導き出すAIチャットボットを採用。法律の専門知識がない人でもわかるよう、丁寧な説明を心がけた「AIリーガルコモン」を開発しました。
料金も手頃に設定し、これまで顧問弁護士の利用をためらっていた中小企業やスタートアップの潜在的なニーズに応えています。AIでの対応が難しい場合は、弁護士による個別相談にも対応可能です。今後は多言語対応も進め、海外展開を視野に入れたサービス拡充を進める予定です。
参考:導入事例 株式会社アガルート | NTTコミュニケーションズ 法人のお客さま
株式会社ライダース・パブリシティ|ユーザーへの情報提供とサポートが可能に
総合住宅展示場の運営を行うライダース・パブリシティでは、家づくりを検討しているユーザーに向けて、より分かりやすく最新情報を届ける手段を模索していました。その解決策として、WebサイトにAIチャットボットを導入しました。
展示場情報の案内をはじめ、住まいに関する相談、見学予約やカタログ請求まで幅広くサポート。ユーザーの関心をAIが的確に把握し、必要な情報を対話形式で提示するのが特徴です。
導入により、見学予約への誘導もスムーズになり、ユーザーはサイト上で迷うことなく目的の情報にたどり着けるようになりました。住宅メーカーと見込み顧客をつなぐ橋渡しとして、商談の効率化にも貢献しています。全国の住宅展示場情報に対応し、24時間365日利用可能なガイド役として機能しています。
参考:株式会社ライダース・パブリシティ | AIさくらさん導入事例
Peach Aviation 株式会社|7か国語に対応&コールセンターへの入電数を大幅削減
2012年に就航したPeach Aviationは、「アジアのかけ橋」を目指して国内外に路線を拡大する中、LCCをはじめて利用するお客様からの問い合わせが急増していました。とくに、日本語と多言語の窓口が分かれていたため、情報共有や対応スピードに課題がありました。
これを受け、窓口を一本化し、Webサイトに7か国語に対応したAIチャットボットを導入。海外のお客様も母国語で気軽に質問できる環境を構築しました。チャットボットでの対応が難しい場合は、有人スタッフが引き継ぎ、支払いなど必要に応じて電話窓口へ案内する体制も整えています。
導入からわずか3か月で、日本語対応だけでも1日1,300件以上の利用があり、コンタクトセンターの業務負担を大きく軽減しました。さらに、AIチャットボットの利用ログをもとに、お客さまの疑問点やつまずきやすい箇所を分析し、FAQやサイト構成の改善にもつなげています。
参考:お客さまの旅をより良いものに 多言語AIチャット導入でスピーディーな解決を実現!
アイリスオーヤマ株式会社|営業メンバーの業務をサポート
家電や生活用品の製造・販売を手がけるアイリスオーヤマ株式会社では、社内からの問い合わせ対応に多くの工数がかかっていることが課題となっていました。
25,000種類以上の商品を取り扱っているため、商品情報や社内ルールに関する質問が、管理部門や特定の詳しい社員に集中。とくに営業担当者からは、「商品の詳細について誰に聞けばいいかわからない」「必要な資料を探すのに時間がかかる」といった声が寄せられていました。
こうした背景から、AIチャットボットの導入を決定。商品に関する質問や本社への問い合わせに自動で対応する仕組みを構築しました。品番を入力することで、詳細データを確認できる機能も搭載されており、商品データベースとしても活用されています。
導入後は、社員から「回答の精度が向上した」との評価が寄せられ、「誰に聞けばよいか分からない」といった不安も軽減されました。社員自身が必要な情報を短時間で見つけられるようになったことで、資料検索にかかっていた時間が削減され、営業活動の効率化にもつながっています。
参考:AIチャットボット & Slack連携により営業生産性の向上へ
株式会社フェリーさんふらわあ|毎月5万件もの問い合わせをAIチャットボットが対応
関西と九州を結ぶ長距離フェリーを運航するフェリーさんふらわあは、電話での問い合わせ対応が追いつかないという課題を抱えていました。とくに繁忙期には電話が集中し、対応が追いつかない状況が続いていたことから、サイト上での自動応答による負担軽減と顧客の利便性向上を目指し、AIチャットボットを導入しました。
AIチャットボットは、同社のWebサイトとフェリーターミナル(デジタルサイネージ)双方で活躍しています。Webサイト上では、運賃案内や予約方法、船内設備など幅広い質問に24時間365日対応。ターミナルでは、フェリーの案内に加え、周辺施設の情報も提供しています。コロナ禍では、非接触での案内ツールとしても有効でした。
導入後はフリーダイヤルへの電話件数が大幅に減少し、繁忙期には月5万件を超える問い合わせをチャットボットが処理。コールセンターの負担軽減に加え、営業時間外の対応も実現しました。さらに、やり取りのデータを蓄積・分析することで、これまで見えづらかった顧客ニーズを把握でき、サービスの改善にもつながっています。
参考:「AIさくらさん」がフェリーさんふらわあ様のフェリーターミナル・Webサイト上に導入されました
龍谷大学|入試部の残業時間の3時間削減に成功
龍谷大学の入試部では、入学試験やオープンキャンパスの時期に問い合わせが集中し、通常業務との両立が難しく、残業が常態化していました。とくに休暇明けには、10回線すべてが鳴りっぱなしになる状況が発生していました。
問い合わせ内容の約8割は、FAQに掲載されている定型的な質問だったことから、学内DXの試験導入としてAIチャットボットの活用を決定。質問の意図を読み取る高精度の検索機能と、導入後も継続的に支援を受けられるサポート体制が選定の決め手となりました。
まずはWebサイトの問い合わせフォームに設置し、効果を見ながら検索ボックスの追加、ナビダイヤルとの連携へと段階的に拡張。導入後は問い合わせ数が約3分の1に減少し、残業時間も30%削減されました。また、印刷して配布していたFAQをQRコードに切り替えることで、ペーパーレス化とコスト削減にも成功しています。
参考:導入事例 龍谷大学 | NTTコミュニケーションズ 法人のお客さま
東京都三鷹市|ゴミの分別方法をAIチャットボットで市民に案内
東京都三鷹市では、「みらいを創る三鷹デジタル社会ビジョン」に基づき、市民サービスの向上と業務の効率化を進めていました。ごみ対策課には毎日80〜100件の電話が寄せられており、その多くが収集日や分別方法に関する内容だったことから、24時間対応可能なAIチャットボットの導入を検討しました。
ごみの分別は明確なルールが求められる分野であり、AIチャットボットとの相性が良いと判断。複数のサービスを比較検討した結果、操作が直感的で使いやすく、回答精度を手動で調整できる柔軟な機能を持つチャットボットを選定しました。
導入準備は約1か月半と短期間で完了し、2020年1月より運用を開始。導入後は毎月2,000件前後の利用があり、とくに窓口が閉まっている夜間や休日のアクセスが多く見られました。市のホームページから気軽に利用できる点も好評で、市民満足度は90%を超える高評価を得ています。
参考:市民からお褒めの声も!サービス満足度90%を達成 ごみ分別をチャットボットで案内、業務効率化へ
AIチャットボットの導入を成功させるためのポイント
AIチャットボットを効果的に活用するには、導入前の準備が重要です。ここでは、導入をスムーズに進め、成果につなげるために押さえておきたい4つのポイントを紹介します。
導入する目的・解決したい課題を明確にする
最初に取り組むのは、「なぜAIチャットボットを導入するのか」「どのような解決したいのか」といった目的や課題を明確にすることです。
たとえば、「問い合わせ対応にかかる時間を短縮したい」「24時間対応で顧客対応を実現したい」など、導入目的はさまざまです。目的がはっきりすれば、必要な機能や最適なチャットボットも選びやすくなります。
反対に、目的があいまいなままでは期待した効果を得にくく、導入そのものがムダになってしまう恐れもあるため注意が必要です。
回答の生成に必要な情報・データを集める
AIチャットボットは学習機能を備えていますが、元となる情報がなければ、的確な回答は期待できません。適切な回答を引き出すには、事前に必要なデータをしっかり整備しておきましょう。
たとえば、「よくある質問(FAQ)とその回答」「商品やサービスの詳細情報」「社内マニュアル」など、チャットボットが参照すべき情報は多岐にわたります。これらを網羅的に収集し、わかりやすく整理しておくことで、回答の質が高まります。
もし古い情報や不十分なデータしか用意されていなければ、ユーザーの期待に応えることが難しくなり、結果的に信頼を損なう可能性もあります。
AIチャットボットの存在を周知する
どれだけ高性能なAIチャットボットを導入しても、その存在が知られていなければ利用されません。顧客向けか、社内向けか、誰に使ってもらいたいのかを明確にしたうえで、適切な手段で周知することが大切です。
たとえば、Webサイトであれば、トップページや問い合わせページなど目立つ場所に設置するのが効果的です。社内向けの場合は、ポータルサイトへの掲載、社内メールでの案内、操作方法を紹介する簡単なセミナーなども有効でしょう。
さらに、「どのような場面で使えるのか」「どういった質問に対応できるのか」といった具体的な事例を伝えることで、活用のイメージが湧きやすくなり、利用促進にもつながります。利用者が増えれば増えるほど、AIチャットボットの精度も向上していきます。
運用体制を整えておく
AIチャットボットは、導入すれば終わりではなく、運用を通じて成長させていく必要があります。そのためには、あらかじめ運用体制を整えておくことが重要です。
まずは、誰が管理・運用を担当するのかを明確にしましょう。担当者は、利用状況を定期的に確認し、うまく回答できなかった質問には、必要な情報を追加したり、回答表現を改善したりと、継続的に改善を進めます。
また、チャットボットが対応すべき範囲と、人が対応すべき範囲をあらかじめ線引きしておくことも大切です。加えて、定期的なメンテナンス計画を立てて改善のサイクルを回すことで、長期的に安定した運用が可能になります。
単に導入するだけでなく、「育てていく」意識を持ち、チーム全体で運用に取り組める体制を築きましょう。
AIチャットボットのサービス選びのコツ
AIチャットボットは、自社の状況や目的に合ったサービスを選ぶことが大切です。多くの選択肢の中から最適なものを見つけるために、以下の3つのポイントをチェックしましょう。
1. 目的に合った機能が備わっているか
まず、AIチャットボットを導入する目的を明確にし、それを実現できる機能が備わっているか確認しましょう。たとえば、「問い合わせ対応を効率化したい」「社内のヘルプデスクとして活用したい」「多言語で案内したい」など、目的によって必要な機能は異なります。
たとえば、人による対応への切り替え機能、多言語対応、利用状況の分析などが挙げられます。将来的な活用も視野に入れながら、柔軟に対応できるサービスを選ぶことがポイントです。
2. 導入・運用を支援するサポートはあるか
AIチャットボットの導入後には、FAQの更新や効果の分析など、さまざまな場面で疑問が出てくることがあります。そのため、ベンダーによるサポートの有無は重要な判断材料です。
初期設定のサポートや運用に関するアドバイス、定期的なレポートの提供など、どのような支援が受けられるのかを事前に確認しておきましょう。また、サポート範囲や追加費用の有無についても、導入前に把握しておくと安心です。
3. 無料でお試しできる期間(トライアル)はあるか
多くのサービスでは、正式導入前に無料トライアル期間が用意されています。実際に試すことで、管理画面の使いやすさや回答精度、サポート対応の質など、資料だけではわからない点を確認できます。
サービスごとに機能や使い勝手は異なるため、自社との相性を見極めるうえでもトライアルの活用がおすすめです。導入後のミスマッチを防ぐためにも、試用期間を積極的に利用しましょう。
導入事例を参考に、自社に適したAIチャットボットを選ぼう!
AIチャットボットの導入事例を見ると、問い合わせ対応の効率化、多言語対応、業務負担の軽減など、さまざまな面で活躍していることがわかります。導入を成功に導くためには、目的の明確化、必要なデータの整備、そして社内への適切な周知や運用体制の構築が欠かせません。
最近では、業種や企業規模を問わず多くの企業がAIチャットボットを導入しており、以前に比べて導入のハードルも下がってきました。自社の課題やニーズに合ったAIチャットボットを選ぶことで、顧客満足度の向上と業務の効率化を両立できます。
まずは無料トライアルからスタートし、効果を確認しながら徐々に活用範囲を広げていきましょう。


