チャットボットツール選定ガイド タイプ・機能・活用例をくわしく解説
公開日 2025/04/28
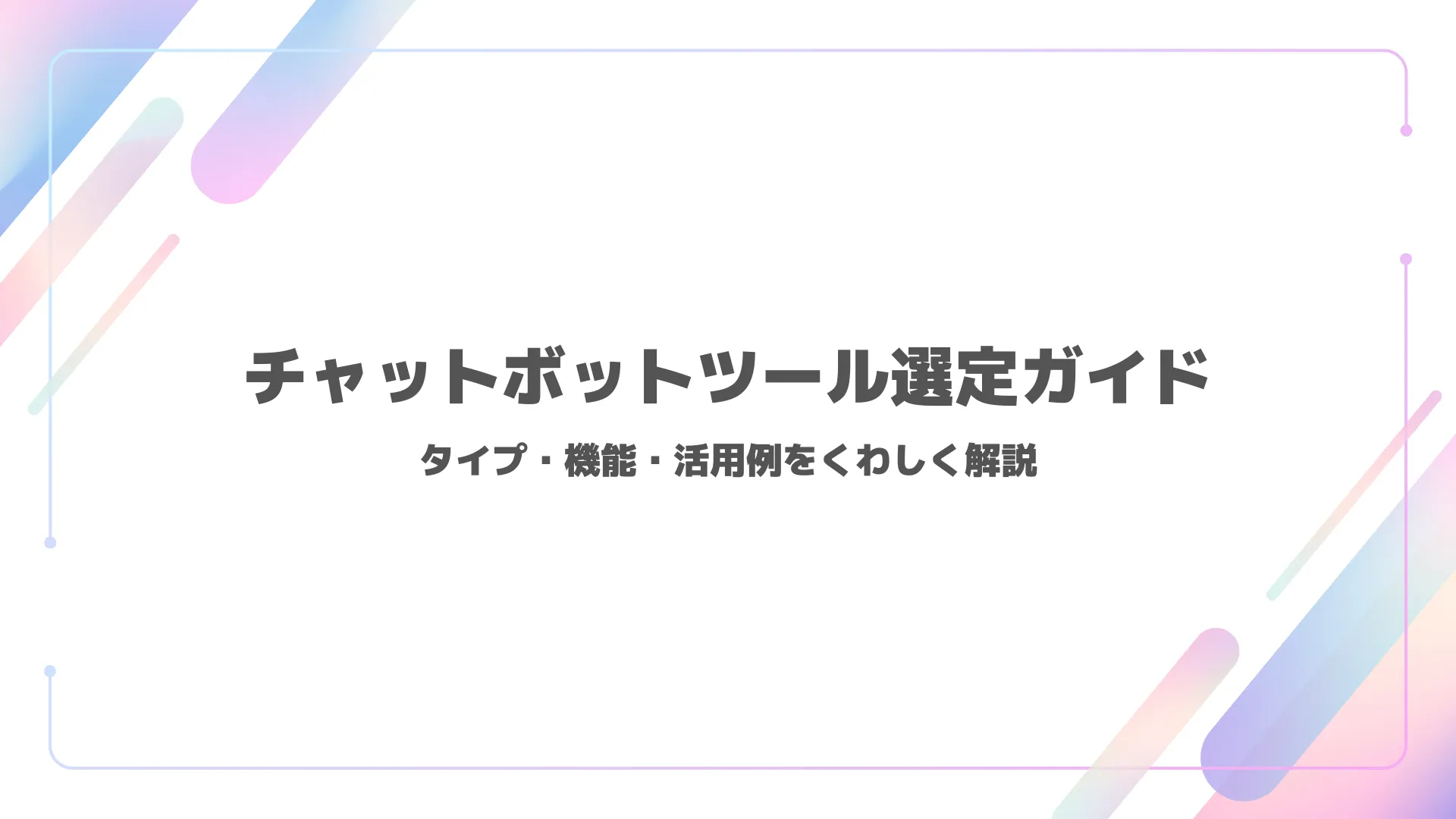
チャットボットツールの導入を検討しているものの、種類が多く「どれが自社に合うのか分からない」と悩む企業も多いのではないでしょうか。
本記事では、チャットボットのタイプや機能の違い、導入時に押さえるべき選定基準をわかりやすく解説します。自社に最適なツール選びのヒントとして、ぜひ参考にしてください。
目次
チャットボットツールの基礎知識
まずは、チャットボットツールを正しく選ぶために欠かせない基礎知識を解説します。
チャットボットツールとはユーザーと自動で会話を行うためのソフト
チャットボット(Chatbot)とは、「チャット(対話)」と「ボット(ロボット)」を組み合わせた言葉で、ユーザーの質問やメッセージに自動で返答する自動会話プログラムを指します。
チャットボットツールは、こうしたプログラムを活用できるソフトウェアやプラットフォームのことです。LINEやFacebook、企業のWebサイトなど、さまざまな場所で導入されており、問い合わせ対応やカスタマーサポートの自動化に役立ちます。
チャットボットツールを導入するメリット
チャットボットツールを導入することで、中小企業には次のようなメリットがあります。
- 24時間対応で顧客満足度が向上
- 人件費や工数の削減によるコスト効率化
- 回答品質の均一化による信頼性向上
- 会話データの蓄積によるニーズ把握
- 問い合わせ対応の効果測定が可能
これらの効果を最大限に活かすには、自社の目的や課題に応じたチャットボットの種類を選ぶことが重要です。次に、具体的な活用方法について紹介します。
【タイプ別】チャットボットツールの活用方法
チャットボットツールにはいくつかのタイプがあり、それぞれ適した活用方法があります。ここでは、雑談型・辞書型・FAQ型・配信型といった代表的なタイプごとの特徴や活用シーンを紹介します。
シナリオ型ツール|シンプルな業務を自動化
シナリオ型チャットボットは、あらかじめ設定した選択肢やルールに沿って会話を進めるAI非搭載のツールです。
ユーザーは選択肢をクリックするだけで目的の情報にたどり着けるため、操作が簡単で、問い合わせの種類が限定されている業務に向いています。初期費用や運用コストが比較的安く、導入しやすい点が魅力です。以下に代表的な活用例を紹介します。
| 活用例 | 内容 |
|---|---|
| FAQ対応 | よくある質問に対して定型の選択肢を用意し、 素早く回答を案内できる |
| 予約受付 | 来店予約やサービス予約などを、 選択式で簡単に受け付け可能 |
| アンケート収集 | 質問形式でユーザーに選択肢を提示し、 回答データを自動で蓄積・集計できる |
雑談型ツール|共感や気晴らしを提供
雑談型チャットボットは、ユーザーとの気軽な会話を目的としたツールです。多くのツールはAIを搭載し、人間らしい自然なやり取りができます。
直接的な売上にはつながりにくいものの、ユーザーとの接点を増やし、企業への親近感や好印象の醸成につながります。継続的な会話体験を通じて、ファン化やロイヤリティ向上を図る活用に効果的です。
| 活用例 | 内容 |
|---|---|
| ユーザーとの雑談対応 | 気軽な会話で共感や癒しを提供し、 企業やブランドへの親しみを醸成 |
| ファン育成 | 雑談を通じて継続的な関係を築き、 商品やサービスへの関心を高める |
| SNS連携施策 | 雑談ボットをSNSと連携し、 話題性やエンタメ性で拡散や話題づくりに貢献 |
辞書型ツール|質問に対して定義や情報を簡潔に回答
辞書型チャットボットは、事前に登録した「キーワード」と「回答」をもとに、自動応答を行うタイプのツールです。ユーザーが入力した語句をもとに関連情報を表示するため、定義や情報、ルールなどを簡潔に伝える用途に向いています。
入力内容から自動的に情報へ導くことで、スムーズな自己解決を促進でき、業務効率化にも貢献します。一方、導入時は膨大なキーワードと回答を登録する作業が発生するため、事前準備が重要です。
| 活用例 | 内容 |
|---|---|
| 商品情報の提供 | 商品名や価格、仕様などに関する 質問に対して詳細情報を表示 |
| 利用規約の説明 | キーワードに基づき、契約内容や 注意事項などを簡潔に提示 |
| 社内マニュアル検索 | 社員からの業務関連の質問に対し、 対応マニュアルや手順を表示 |
FAQ型ツール|事前に用意された回答を自動で対応
FAQ型チャットボットは、よくある質問とその回答を事前に登録し、ユーザーからの問い合わせに自動で対応するツールです。従来のFAQページでは、情報を探す手間がかかり、ユーザーの満足度が低くなりがちでしたが、FAQ型チャットボットは質問を入力すれば、瞬時に最適な回答を提供できます。
そのため、問い合わせ対応にかかるコスト削減や業務効率化、社員の負担軽減につながります。また、求められた情報がFAQにない場合は、オペレーターへの切り替えも可能です。
| 活用例 | 内容 |
|---|---|
| 顧客からの製品情報の問い合わせ | 商品の特徴や価格、在庫状況など、 よくある製品関連の質問に自動で対応 |
| 返品・返金に関する質問 | 返品手続きや返金のプロセスに 関する質問を自動で処理 |
| サービス利用方法の説明 | サービスやアプリの使い方、 利用規約に関する質問に自動で回答 |
配信型ツール|決まったタイミングや条件で情報を提供発信
配信型チャットボットは、ユーザーとの対話よりも情報を定期的に発信することに特化したタイプです。主に、セールやキャンペーン、商品発送の通知、リマインダーなど、特定のタイミングや条件に基づいて情報を届けるために利用されます。
たとえば、公式LINEアカウントでの新製品の情報通知や、顧客が購入した商品の配送日の自動通知ができます。メルマガに似た運用であり、リアルタイムに通知ができるため、親近感を持たせつつ、ブランディングにも役立ちます。社内での活用例としては、会議やイベントのリマインダーを一斉配信することも可能です。
| 活用例 | 内容 |
|---|---|
| 顧客への新製品・セール情報の配信 | 顧客に対して、LINEやメールで 新製品やキャンペーン情報を配信 |
| 配送日・発送通知 | 購入後の顧客へ配送日や 発送状況を自動で通知 |
| 社内リマインダー | 会議やイベントの前に メンバーにリマインダーを配信 |
チャットボットツールAIあり・なしの違いを比較
チャットボットにはAI搭載のものと、非搭載のものがあります。両者の違いについて解説します。
カスタマーサポートの高度化にはAI搭載がおすすめ
AI搭載型のチャットボットは、自然言語処理と機械学習を活用し、曖昧な質問や感情を含む会話にも柔軟に対応できるのが特徴です。複雑な質問にも的確に回答できるため、カスタマーサポートや社内ヘルプデスクに適しています。
非搭載型に比べ、AIチャットボットは表記揺れや類義語にも対応し、回答の精度が高い点が特徴です。運用を続けることで学習し、応答精度が向上するため、長期的にはコスト削減にも寄与します。ただ、高精度な分、初期費用や導入、運用にかかるコストが高くなる傾向にあります。
シンプルな定型業務の自動化にはAIなしのツールがおすすめ
AI非搭載型チャットボットは、事前に設定したシナリオにもとづき、ユーザーの選択肢に応じた自動回答を提供します。そのため、予約受付や注文、フォーム入力の代替など、シンプルで予測可能な業務に特に適しています。
AIなしのツールは設定が簡単で、コストを抑えられるのが大きな魅力です。ただし、学習機能がないため、柔軟な対応が難しく、問い合わせ内容が多様な場合には不向きです。
チャットボットツールの選び方
チャットボットツールを選定する際に、具体的にはどのようなポイントに注目すればいいでしょうか?具体的な選び方を解説します。
目的に合わせて選ぶ
チャットボットツールを選ぶ際は、まず「何を実現したいのか」という導入目的を明確にし、それに適した機能を持つツールを選ぶことが大切です。
たとえば、カスタマーサポートの効率化を目指す場合は、複雑な問い合わせにも対応できるAI搭載型がおすすめです。一方で、予約や注文などの定型業務には、シンプルでコストを抑えられる非搭載型が適しています。
目的や課題によって必要な機能や対応チャネルが異なるため、まずはチャットボット導入の目的を明確にしましょう。
使いやすさで選ぶ
チャットボットツールを選ぶ際は、操作のしやすさも重要なポイントです。特にプログラミングの知識がない担当者が運用を行う場合は、ノーコードでシナリオ作成や編集ができるツールが適しています。直感的なUIで簡単に管理できれば、導入から運用までスムーズに進められます。
一方で、高度なカスタマイズや外部システムとの連携を重視する場合は、開発者向けの自由度が高いツールを選ぶのが望ましいでしょう。運用体制に合わせて使いやすさを確認することが大切です。
対応プラットフォームで選ぶ
チャットボットツールを選ぶ際は、Webサイトやメール、SNSなど、自社が活用したいプラットフォームに対応しているかを確認することが大切です。ユーザーとの接点が多いチャネルに対応していれば、利便性が高まり、利用率の向上が期待できます。
また、メールやSNS、業務ツールとの連携も可能なツールを選ぶことで業務は効率化し、社内外での活用幅が広がります。必要なプラットフォームに応じて対応可否をチェックし、自社に最適なツールを選びましょう。
予算で選ぶ
チャットボットツールを選ぶ際は、初期費用や月額費用が予算内に収まるかを確認する必要もあります。無料プランや従量課金制のツールなどは導入ハードルが下がり、自社の利用規模に合わせて利用しやすいため、しっかりと確認したうえで導入することが大切です。
ただし、安価なプランでは必要な機能が制限されるケースや、サポートが不十分な場合もあるため注意が必要です。費用だけで判断せず、機能やサポート体制とのバランスを見て、コストパフォーマンスの高いツールを選ぶことが重要です。
サポート体制で選ぶ
チャットボットツールを選ぶ際は、日本語対応や技術支援の有無など、充実したサポート体制があるかどうかを確認することも重要です。特に初めて導入する企業は、導入前後で気軽に相談できる窓口や、専任担当によるサポートがあるかもチェックしておきましょう。
また、FAQの構築やシナリオ設計を支援してくれるサービスもあります。トラブルや疑問への対応力も選定基準のひとつです。導入・運用時のサポート体制がしっかりしているツールを選ぶことで、スムーズかつ効果的に活用できます。
無料トライアルの有無で選ぶ
チャットボットツールを選ぶ際は、無料トライアルの有無も重要なポイントです。操作のしやすさや管理画面の使い勝手、業務への適合性などは、実際に触ってみないと分からないことも多くあります。
導入後に「使いづらい」「機能が足りない」といったギャップを避けるためにも、まずは無料トライアルでテスト運用し、自社に合っているかを確認しましょう。複数のツールを比較検討する際にも役立ちます。
チャットボットツールは無料と有料どちらを選ぶべき?
無料ツールは手軽に試せる点が魅力ですが、業務にしっかり活用したい場合は、有料のチャットボットがおすすめです。カスタマイズ性やセキュリティ、サポートの充実度などの違いを以下の表にまとめました。
企業利用における安心感と効率性を重視するなら、有料ツールを選びましょう。
| 項目 | 無料チャットボット | 有料チャットボット |
|---|---|---|
| 初期費用・月額費用 | なし〜低価格 | 数千〜数万円以上 |
| カスタマイズ性 | 限定的 | 自由度が高い |
| セキュリティ | 基本的な対策のみ | 法人利用を想定した 強固なセキュリティ体制 |
| サポート体制 | なし、または限定的 | 専任担当による 手厚いサポートあり |
| API連携 | 制限あり、 または利用不可 |
外部システムとの 連携が可能 |
適切なチャットボットツール導入で業務効率化を実現しよう
本記事では、チャットボットのタイプや機能の違い、導入時に押さえるべき選定基準を解説しました。
チャットボットツールは、業務の自動化や顧客対応の効率化を実現する有効な手段です。シナリオ型やAI搭載型など、用途に応じたタイプを選ぶことで、導入効果を最大化できます。
選定時は、目的・使いやすさ・対応プラットフォーム・予算・サポート体制などを比較し、自社に最適なツールを見極めましょう。まずは、お試し感覚で無料トライアルを活用し、実際の使用感を確かめてみることをおすすめします。


