なぜ内部リソースが足りないのか?3つの原因と7つの業務改善の具体策
公開日 2025/11/14
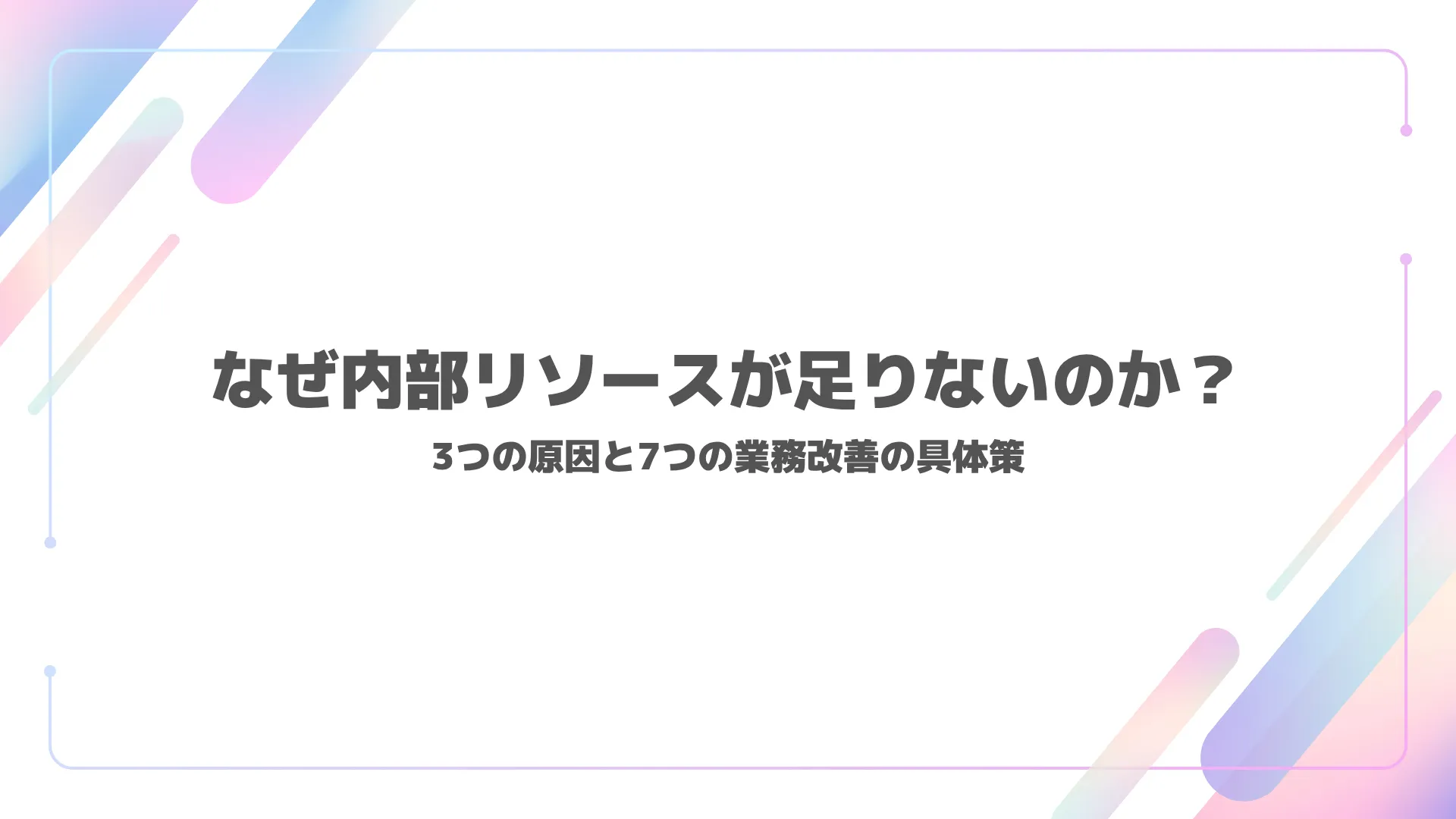
内部リソースの不足は、いまや多くの企業が抱える共通の課題となっています。採用市場は年々厳しさを増し、条件を整えても思うように人材を確保できません。即戦力を求めれば採用コストが膨らみ、負担はさらに大きくなります。
また、社内にも別の問題が潜んでいます。業務の属人化や複雑なフロー、スキルの偏りが積み重なり、組織全体の動きを鈍らせています。外部からただ人を雇うだけでは、この構造的な問題を解消できません。限られた人員を有効に活かすには、業務改善によって組織全体の力を底上げすることが大切です。
本記事では、内部リソース不足を引き起こす3つの原因から、業務改善につながる7つの方法まで解説します。
目次
なぜ内部リソースが足りないのか
リソース不足は人手不足の問題にとどまらず、組織運営の歪みが重なった結果として生じる構造的な課題です。以下では「属人化」「非効率なフロー」「スキルの不一致」の3つを軸に解説します。
1.業務の属人化とブラックボックス化
リソース不足の原因として真っ先に挙げられるのが、担当者への業務集中とブラックボックス化です。特定の社員しか把握していない作業が増えると、休暇や退職のたびに業務が止まり、周囲が対応に追われます。知識が共有されなければ業務はブラックボックス化し、担当者の急な不在に対応できません。この状態が続くことで新人育成も進まなくなり、組織全体の柔軟性が徐々に損なわれていきます。
2.非効率な業務フロー
次に問題となるのは、業務フローの非効率さです。属人化が進む環境では、業務プロセスの改善が後回しになりやすくなります。その結果、紙による申請やアナログな入力、目的が曖昧な会議などが残り続けます。社員は本来取り組むべき業務に時間を割けず、遅延や品質低下を招きます。無駄が積み重なることで、顧客からの信頼や社員の定着率にまで影響が及びます。
3.スキル不足と即戦力確保の難しさ
さらに深刻なのは、スキル不足と即戦力の確保の難しさです。人数がそろっていても知識や資格が足りなければ業務は停滞します。教育体制が整わない環境では担当者依存が加速し、属人化を一層強めます。外部から即戦力を採用しようとしても市場競争は厳しく、採用コストが増大します。属人化・非効率・スキル不足が連鎖することで、慢性的なリソース不足に陥ります。
業務改善で内部リソースを生み出す7つの方法
リソース不足は避けにくい課題ですが、改善の道筋を描けば状況は変えられます。ここでは社内で実行しやすい7つの方法を解説します。
1.業務プロセスを見直して標準化する
最初に取り組むべきは、属人化の解消です。担当者ごとにやり方が異なる業務は、引き継ぎのたびに混乱を招きます。業務手順を整理し、マニュアルやルールを整えれば、誰が担当しても同じ基準で作業を進められます。人事手続きや経費精算など、日常的に発生する業務こそ標準化が有効です。標準化を徹底すれば教育の負担を抑え、組織の安定性を高められます。
2.定型業務を自動化する
標準化が進めば、次は自動化を検討できます。日報作成やデータ入力のような単純作業は、社員の時間を奪う業務のひとつです。自動化ツールを導入すれば入力ミスを減らし、作業速度も向上します。自動化によって単純作業から解放された時間を、より価値の高い業務に振り向けられます。
3.情報共有の仕組みを整える
業務が自動化されても、情報が探しづらければ効率は上がりません。そこで行いたいのが情報共有の環境整備です。クラウドストレージや社内ポータルで一元管理すれば、必要な資料をすぐに探せます。マニュアルが即座に確認できる状況を作ることで、担当者の不在による作業の中断を防げます。情報が行き渡る体制をつくることが、組織全体の連携を後押しします。
4.従業員のスキルアップを促進する
仕組みが整ったら、次は人材の強化です。いくら環境が整っても、社員にスキルが不足していれば業務は進みません。研修や資格支援を通じて能力を底上げすれば、一人ひとりの生産性が高まります。特に営業スキルの向上やITリテラシーの習得は、多くの企業で成果を生み出す領域です。人材育成は長期的なリソース確保にも役立つ投資です。
5.一部の業務を外部に委託する
人材育成と並行して考えたいのが外部委託です。専門性が高く社内で対応しきれない業務は、外部に任せる方が効率的な場合があります。経理処理やデザイン制作などをアウトソースすれば、社内リソースを戦略領域に集中させられます。外部委託は内部の余力を生み出す手段のひとつです。
6.顧客対応・社内問い合わせを自動化する
社外からの問い合わせや社内の質問対応は、担当者にとって大きな負担です。FAQやチャットボットを導入すれば、よくある質問を即座に処理でき、担当者は高度な業務に集中できます。近年ではAIチャットボットサービスが注目されており、社内資料やWebサイトを登録するだけで導入できるものも登場しています。導入後すぐに活用できることから、多くの企業の注目を集めています。
7.紙の書類や契約業務を電子化する
最後のステップは、紙中心の業務からの脱却です。契約書やマニュアルを電子化すれば、検索や共有が容易になり、印刷・郵送コストも削減できます。稟議書や発注書など、紙で回すことが多い業務を電子化するだけでも負担は軽減されます。電子化は効率化とコスト削減に最適な手段です。
AIチャットボットを利用してリソース確保を|IZANAI(イザナイ)

毎日の問い合わせ業務に時間を取られていませんか?AIチャットボット「IZANAI(イザナイ)」は、FAQやマニュアルの情報をもとに、自動で高精度に回答する生成AIチャットボットです。ノーコードで誰でもすぐに導入でき、カスタマーサポートの定型対応を大幅に削減。
人が対応すべき「本当に重要な問い合わせ」に、もっと集中できる環境を作りましょう。
IZANAI(イザナイ)の主な特徴
- 社内資料やWebページを登録するだけで回答が可能
- PDF・Excel・WebサイトのURLなど、複数ソースを同時に学習
- FAQ整備が不十分でも、曖昧な質問に対応
- 面倒なシナリオ設計が不要
- 2週間の無料トライアル可能
参考:FAQを最適化するAIチャットボット|IZANAI Powered by OpenAI
業務改善を成功に導く5つのステップ
業務改善は思い付きで進めても成果が限定されます。現状を把握し、課題を整理し、改善策を実行し、振り返りを行う。この流れを段階的に踏むことで、取り組みは定着しやすくなります。ここでは「問い合わせ削減」をテーマに、具体的な進め方を5つのステップに分けて解説します。
ステップ1:業務の可視化と現状把握
最初に行うべきは業務の棚卸しです。まずは誰がどの作業にどれだけの時間を使っているのかを整理しましょう。日報やExcelの記録を集計し、部署ごとの業務量を数値で把握すれば、問題の所在が明らかになります。
「パスワード再発行に関する問い合わせが月50件以上ある」「経費精算ルールの質問が毎週繰り返されている」といったデータを可視化できれば、改善すべき領域が明確になります。曖昧な感覚に頼らず、数値に基づいて現状を把握することが大切です。
ステップ2:課題の整理と優先順位付け
把握したデータを基に、課題を整理します。問い合わせ内容は多岐にわたるため、影響の大きさや対応のしやすさを基準に優先順位を決める必要があります。
課題整理の例は以下のとおりです。
- 定型的な質問が繰り返し発生している
- 部署ごとに対応ルールが異なり、回答にばらつきがある
- 回答を探すのに時間がかかり、他業務に支障が出ている
整理した結果、短期で対応できる課題と中長期で取り組むべき課題に分けられます。
具体的には、「定型的な質問が繰り返し発生している」場合は、FAQを整備することで短期間で改善が見込めます。対して「部署ごとに対応ルールが異なり、回答にばらつきがある」場合は、ルール統一や承認フローの見直しなど、中長期的な施策が求められます。
このように優先順位を整理することで、どの課題から取り組むべきかが明確になり、次の行動に移しやすくなります。
ステップ3:改善目標の設定とKPI策定
課題が整理できたら、改善目標を数値で設定します。目標を決めなければ進捗を測れず、改善の勢いが続きません。
問い合わせ削減を目的とするなら、「半年以内に件数を30%減らす」「3ヶ月以内に一次回答率を80%へ引き上げる」といった明確な数値設定が効果的です。また、KPI(重要業績評価指標)は最終的な成果だけでなく中間指標も定めましょう。「FAQの閲覧数を月500回に増やす」「自己解決率を60%に高める」といった設定があれば、進捗を定量的に追いやすくなります。数値目標は改善の道しるべとなり、関わる全員の意識を統一する効果があります。
ステップ4:改善策の立案と実行計画策定
目標を定めた後は、達成に向けた行動計画を具体化します。漠然と「問い合わせを減らす」と掲げても実行にはつながりません。たとえば、「よくある質問をFAQにまとめて社内ポータルに掲載する」「経費精算ルールを図解付きでマニュアル化する」といったように、行動ベースへ落とし込むことが大切です。
さらに各施策には担当者を割り当て、期限を設けて進捗を確認できる体制を整えます。問い合わせのログを定期的に分析すれば、施策が実際に効果を生んでいるかを検証できます。計画を役割や数値に置き換えることで、取り組みは一過性に終わらず、継続して機能します。
ステップ5:実行・評価・改善のPDCAサイクル
改善は一度実施して終わるものではありません。効果を検証して次の施策へつなげていきましょう。計画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→改善(Action)のPDCAサイクルを回すことで精度は高まります。
FAQを整備した後でも、「問い合わせ件数が10%しか減っていない」とわかれば、内容や検索性の改善が必要だと判断できます。また、一次対応をAIチャットボットに任せるなど、新しい施策を加えるのも有効です。改善を積み重ねることで、業務効率が向上し、組織全体の競争力を強化できます。
業務改善を続けることで働きやすい環境を育てる
本記事では、内部リソース不足を引き起こす原因から、業務改善を図る方法まで解説しました。属人化や非効率な業務は一朝一夕に解消できませんが、標準化や自動化を積み重ねれば確実に改善が進みます。業務改善は短期的な施策ではなく、未来を見据えた投資です。
中でも問い合わせ対応の効率化は、効果を実感しやすい分野です。繰り返し発生する質問を減らすことで担当者は本来業務に集中でき、生産性が高まります。クラウドサーカスが提供するAIチャットボットサービス「IZANAI Powered by OpenAI」もその解決策のひとつです。社内規程やマニュアルを登録するだけで、自然な回答を生成することできます。また、対話ログを分析して改善に活かせるため、効率化とナレッジ活用を支援します。
内部リソース不足に悩む企業にとって、IZANAI OpenAIは人に依存しない問い合わせ対応を実現し、働きやすい環境づくりを後押しするパートナーとなります。限られたリソースで組織の成長を目指すのであれば、導入する価値は十分にあります。


