業務の属人化で起こる課題|原因と解消するための対策を解説
公開日 2025/11/14
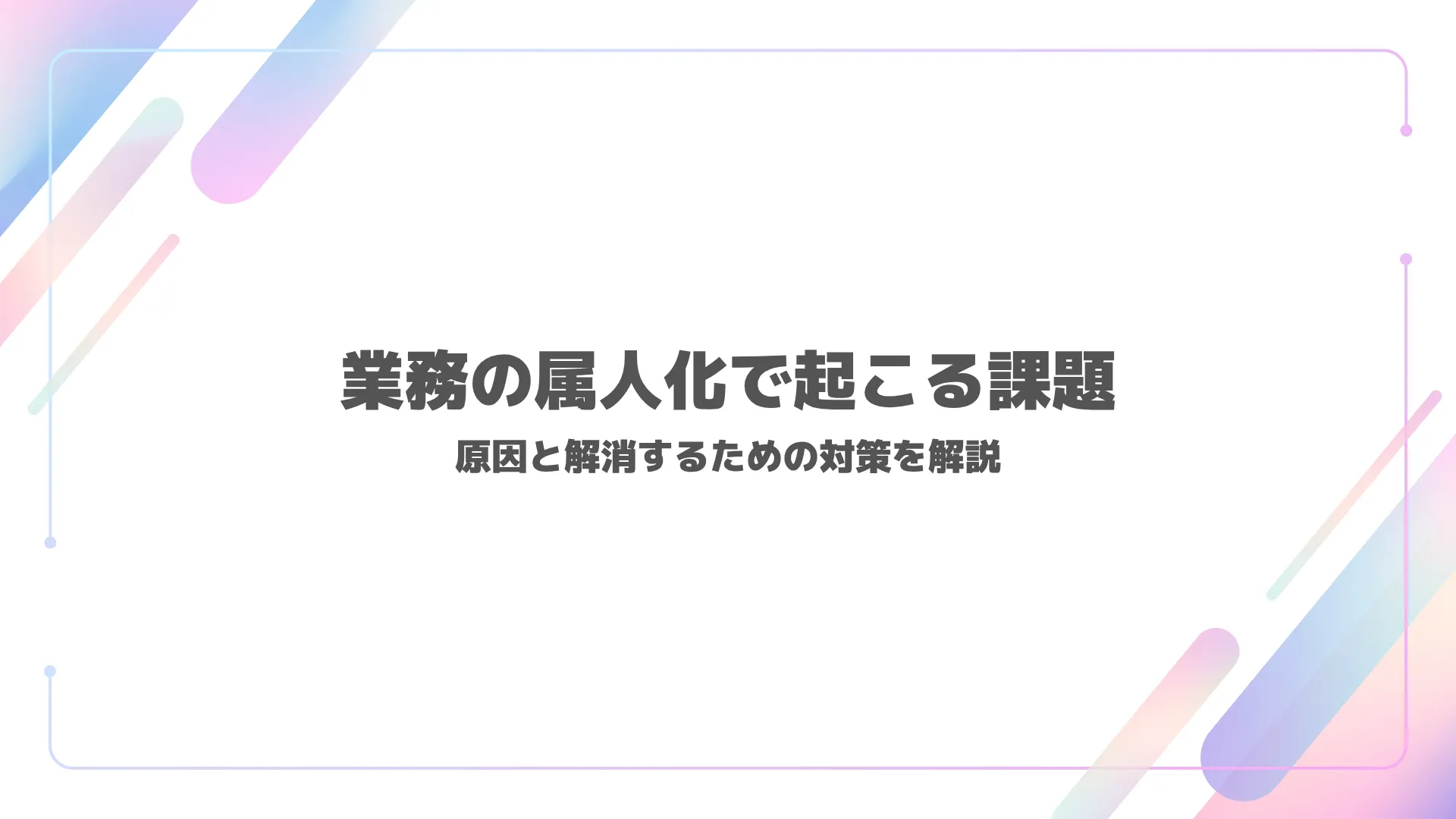
業務の属人化とは、特定の社員だけが業務の手順や判断基準を把握している状態を指します。属人化が進めば進むほど、組織は柔軟性を失い、変化に対応しにくい体制となります。そこで近年は、業務を標準化しながら知識を共有するために、業務を自動化・効率化できるデジタルツールの活用が注目されています。
本記事では、業務の属人化で起こる原因や解消するための対策、属人化対策におすすめのツールまでわかりやすく解説します。
目次
業務の属人化とは?
業務の属人化とは、知識や手順が一部の社員に集中し、他の人が代わりに進められない状態を指します。業務の流れが明文化されないまま進むと、引き継ぎが難しくなり、担当者が不在の際に停滞が生じやすくなります。
とりわけ中小企業では、人材や資源が限られるため、一人に業務が集中する傾向が強まります。教育や研修に十分な時間を割けず、経験や勘に依存した体制が固定化され、特定の社員しか全体像を把握できない状況に陥ることもあります。その結果、組織として柔軟に対応できなくなります。
属人化は表面上「担当者がいるので業務は回っている」ように見えても、裏側では問題が積み重なっています。放置すれば改善の選択肢を狭め、企業の成長を阻害する要因となります。
業務の属人化で起こる可能性がある4つの課題
業務の属人化は短期的には効率的に思えても、長期的には深刻な問題を引き起こします。ここでは、それぞれの側面から代表的な課題を4つに分けて解説します。
①業務の効率低下
属人化が進むと担当者以外が業務の流れを把握できないため、引き継ぎや代替が難しくなります。急な不在時には他の社員が手探りで対応せざるを得ず、業務に遅れが生じます。また、担当者が抱える業務が過剰になれば、作業スピードは落ち、全体の効率が下がります。本来は複数人で分担できる業務が一人に偏ることで、組織全体の処理能力が制限されます。
②品質の不安定化
担当者ごとの判断や進め方に依存してしまうと、成果物の品質にばらつきが生じます。標準化された手順が存在しない場合、対応する社員によって内容や結果に差が出やすく、顧客や取引先に提供するサービスの信頼性が損なわれる恐れがあります。また、改善点やノウハウが共有されないまま業務が継続されるため、品質を高める取り組みが難しくなります。こうした不安定さは、企業の信用低下にもつながりかねません。
③情報漏洩リスクの増加
業務の進め方や判断基準が担当者に依存していると、情報の管理体制も属人的になりがちです。担当者しか把握していない手順やデータが存在すると、退職や異動時に適切な引き継ぎが行われず、重要な情報が外部に流出する危険性が高くなります。また、アクセス権限や情報の扱いが個人の裁量に任されている状態は、セキュリティ上のリスクを増幅させます。組織として一元的に情報を管理できなければ、情報資産を守ることは困難です。
④モチベーション低下
属人化した業務を抱える社員は、休暇を取りづらく、常に対応を求められる状況に置かれます。負担が重なれば心身の疲弊を招き、やる気の低下を引き起こします。責任が一人に集中することで不公平感が生まれ、チーム全体の士気が下がる場合もあります。退職や離職なども起こりやすくなり、人材の流出という新たな課題も生じます。属人化が従業員の働きやすさや職場環境にも影響を及ぼす点は、見過ごせない問題です。
業務の属人化が起こる主な7つの原因
ここまで属人化がもたらす課題を見てきました。それでは、なぜ属人化は起きてしまうのでしょうか。その背景には、人手不足や情報共有の不備、教育体制の弱さといった組織的な問題が横たわっています。
以下では、属人化が進行する原因を7つに分け、それぞれの特徴を解説します。
①マンパワー不足
中小企業でよく見られるのが、人手不足による業務過多です。限られた人員で多岐にわたる業務を回す必要があるため、特定の社員が複数の業務を抱え込む状況が発生します。人材が足りないと分担や引き継ぎが後回しになり、属人化が一気に進みます。 業務量が増えるほど教育や共有の時間は削られ、組織全体の効率低下を招きます。
②特定の担当者に頼った業務対応
専門的な知識や経験を要する業務は、どうしても特定の担当者に依存しがちです。特に熟練者の勘や判断が求められる場面では、他の社員が業務に入り込めず、対応が固定化されてしまいます。「この人がいなければ進まない」という状態は、組織の柔軟性を奪う典型例です。 短期的には効率的に見えても、長期的には深刻な問題を抱えることになります。
③人材育成の遅れ
教育や研修の機会が不足すると、業務を担える人材が育ちません。現場では目の前の業務に追われて人材育成が後回しにされることが多く、特定の社員しか業務を理解していない状態が続きます。研修不足は属人化を解消するチャンスを奪い、長期的に組織力を弱めます。 新人や若手が育たない環境では、知識の片寄りが固定化されてしまいます。
④情報共有の仕組み不足
属人化を加速させる主な原因が、情報共有の仕組み不足です。業務の手順や判断基準が文書化されず、担当者の頭の中だけに留まっている状態では、他の社員が代替するのは困難です。情報が個人の記憶に依存している状態では、緊急時に混乱が生じます。会議や口頭の引き継ぎだけでは、情報が正確に伝わらない恐れがあります。
⑤個人の成果独占
評価制度や職場の文化によっては、担当者が自分の成果を独占しようとする場合があります。知識やノウハウを共有せず、自分だけが価値を発揮できる状態を保つことで立場を強めようとする意識が働きます。成果が個人に偏る環境では、情報共有のメリットが生まれにくくなり、属人化が強まります。 本人に悪意がなくても、組織文化が属人化を後押ししてしまうことがあります。
⑥レガシーシステムの使用
古いシステムや手作業に依存していると、操作や運用方法が属人化しやすい状態に陥ります。システムに関する知識が特定のベテラン社員だけに蓄積され、他の社員が触れにくい環境では、業務の幅は限られます。レガシーシステムは属人化の温床となり、改善を阻む要因です。 サポート情報が不足していることも多く、引き継ぎが難しい状況をつくり出します。
⑦デジタル化の遅れ
システム化やデジタル化が進まない組織では、業務が人の経験や勘に頼ったまま進められます。特に専門性の高い業務は自動化や標準化が難しく、担当者しか対応できない状態が固定化されます。デジタル化の遅れは、属人化を解消する機会を奪い、改善の取り組みを妨げます。 その結果、業務効率化や新しい施策の導入が後手に回ってしまいます。
業務の属人化で起こる課題と5つの対策
属人化は組織に深刻な問題をもたらしますが、適切な対策を講じれば防ぐことが可能です。ここでは、現場で取り組みやすく、改善の効果が期待できる5つの方法を紹介します。
①業務の可視化
まず取り組むべきは、業務の内容を正確に把握することです。担当者が日常的に行っている作業を洗い出し、誰がどの業務を担っているかを整理します。これにより、負荷が1人にかかっている部分や担当者が限定されている業務が浮き彫りになります。業務を見える化することで、属人化の実態を正しく把握できます。 可視化されたデータは、改善や分担の検討にも活用でき、属人化解消の第一歩となります。
②マニュアル作成
業務手順を標準化し、誰でも理解できるように文書化することは欠かせません。マニュアルを作成することで、担当者が不在でも他の社員が対応できる体制が整います。ポイントは、誰が読んでも同じように再現できる内容に仕上げることです。手順を文書として残すことが、知識を共有財産に変える最も有効な方法です。 マニュアルがあれば教育や引き継ぎもスムーズになり、属人化を防ぎます。
③情報共有の仕組み作り
マニュアルや手順だけでなく、日々の情報を共有する体制を整えることが必要です。社内ポータルやナレッジ共有ツールを活用し、情報を蓄積・検索できる状態にしておくと、属人化リスクが軽減されます。さらに、従業員同士で進捗や知見を共有する文化を育むことも大切です。情報が全員に届く環境をつくることで、属人化を組織全体で予防できます。 情報をただ共有するのではなく、連携を前提にした枠組みの構築が求められます。
④担当者のローテーション制度
担当者を固定せず、業務を定期的に入れ替える制度も効果的です。複数人が同じ業務に触れることで、知識や経験が広がり、特定の人に依存しない体制をつくれます。ローテーションは時間や労力を要しますが、長期的に見れば組織の安定性を高める効果があります。業務の権限を分散させることが、属人化を防ぐ確実な手段のひとつです。 チーム全体で知識を共有し、担当者にかかる心理的負担を軽減する効果も期待できます。
⑤AIツールの活用
近年は、AIツールを取り入れて業務を効率化する動きが広がっています。AIを活用することで、情報共有や業務標準化をサポートでき、属人化の解消につながります。具体的には次のようなメリットがあります。
- 定型業務を自動化し、担当者の負担を軽減できる
- 過去のデータやナレッジを蓄積し、誰でもアクセス可能にできる
- 問い合わせ対応やFAQを自動化し、担当者依存を減らせる
- 分析機能により業務改善のポイントを客観的に把握できる
AIツールは「人にしかできない」と思われていた業務を代替・補助するため、属人化を防げます。 導入初期は自社の業務に合わせた設定や使い方が必要ですが、長期的には大きな効果が見込めます。
参考:AIチャットボットで社内外の問い合わせを効率化|IZANAI(イザナイ)
業務の属人化対策におすすめのツール
業務の属人化は、担当者不在による停滞や品質のばらつき、人材流出など、多くの組織で深刻な課題となっています。そこで注目されているのがデジタルツールの活用です。ここでは、AIチャットボットやナレッジ管理、マニュアル作成など、属人化の防止に有効なツールを5つ紹介します。
AIチャットボットツール
問い合わせ対応や社内の質問受付を自動化できるのがAIチャットボットです。FAQやマニュアルを学習させることで、従業員や顧客からの質問に即座に回答できる体制を構築できます。担当者に依存せず、誰でも同じ回答が得られる点が最大の強みです。
たとえば、クラウドサーカスが提供する「IZANAI Powered by OpenAI」は、OpenAIの生成AI技術をベースにした高精度な自然言語処理を備えており、人に近い自然な応答が可能です。社内規程やマニュアル検索に加え、顧客からの問い合わせ対応にも活用でき、社内外の情報窓口を一元化できることが特長です。
また、やり取りのログを蓄積して分析できるため、利用状況を把握しながら回答精度を継続的に改善できます。業務の標準化を進めたい企業や問い合わせの負担を減らしたい組織に最適です。
参考:AIチャットボットでFAQを最適化「IZANAI Powered by OpenAI」
ナレッジマネジメントツールとは
ナレッジマネジメントツールは、社内に蓄積された情報やノウハウを整理し、誰もが利用できるようにする仕組みです。業務手順や事例を体系的にまとめて管理でき、必要なときにすぐ情報を探せる利便性を備えています。知識が一部の人に偏在せず、全員が同じ情報をもとに動ける体制を整えられるので、組織全体の生産性を高められます。情報を共有資産として活かせるメリットは大きく、教育や研修、日常の業務改善にも広く活用できます。
マニュアル作成ツールとは
マニュアル作成ツールは、業務の流れを整理して記録し、誰が見ても同じ手順で作業できるように設計できるツールです。近年ではテキストだけでなく、画面キャプチャや動画を組み合わせて、直感的に理解できるように工夫されたものも増えています。担当者が変わっても一定の品質で業務を進められることから、マニュアルの再現性が高いのが特長です。新人教育や業務の標準化を進めたい組織に向いています。
プロジェクト管理ツールとは
プロジェクト管理ツールは、タスクや進捗をチーム全体で把握しながら業務を進めるツールです。担当者やスケジュールを可視化することで、誰がどの作業を担当しているかが明確になり、業務が停滞しにくくなります。さらに、進捗が共有されることでチームの見通しが良くなる効果があります。部署をまたぐ取り組みや複数人での協働をスムーズにしたい企業におすすめです。
CRMツールとは
CRMツールは、顧客情報ややり取りの履歴を一元的に管理し、営業やサポートを支えるシステムです。過去の商談や問い合わせ内容を組織全体で把握でき、担当者が交代してもスムーズに引き継げます。顧客との接点を強化できる点がCRMの魅力であり、安定した顧客対応と信頼関係の維持に役立ちます。主に営業活動やカスタマーサポートを強化したい組織に適しています。
その問い合わせ、AIが答えます|IZANAI(イザナイ)

毎日の問い合わせ業務に時間を取られていませんか?AIチャットボット「IZANAI(イザナイ)」は、FAQやマニュアルの情報をもとに、自動で高精度に回答する生成AIチャットボットです。ノーコードで誰でもすぐに導入でき、カスタマーサポートの定型対応を大幅に削減。
人が対応すべき「本当に重要な問い合わせ」に、もっと集中できる環境を作りましょう。
IZANAI(イザナイ)の主な特徴
- 社内資料やWebページを登録するだけで回答が可能
- PDF・Excel・WebサイトのURLなど、複数ソースを同時に学習
- FAQ整備が不十分でも、曖昧な質問に対応
- 面倒なシナリオ設計が不要
- 2週間の無料トライアル可能
参考:FAQを最適化するAIチャットボット|IZANAI Powered by OpenAI
AI活用で「属人化しない組織」へ
属人化は放置すれば業務効率や品質を損なうだけでなく、従業員のモチベーション低下や情報管理にも悪影響を及ぼします。しかし、業務の可視化やマニュアル整備、AIツールの導入といった取り組みを進めれば、属人化は確実に解消へ向かいます。
なかでもAIチャットボット「IZANAI Powered by OpenAI」は、属人化に頼らない働き方を後押しします。繰り返される問い合わせを自動化することで、社員は本来の業務に専念でき、社内のナレッジも蓄積されていきます。
属人化を抑え、安心して成長を続けられる体制を整えるには、テクノロジーを味方につけることが重要です。まずは無理のない範囲から、「IZANAI Powered by OpenAI」のようなAIチャットボットの導入を検討してみてはいかがでしょうか。


