ナレッジマネジメントツールとは?比較表や選ぶポイントを解説
公開日 2025/10/03
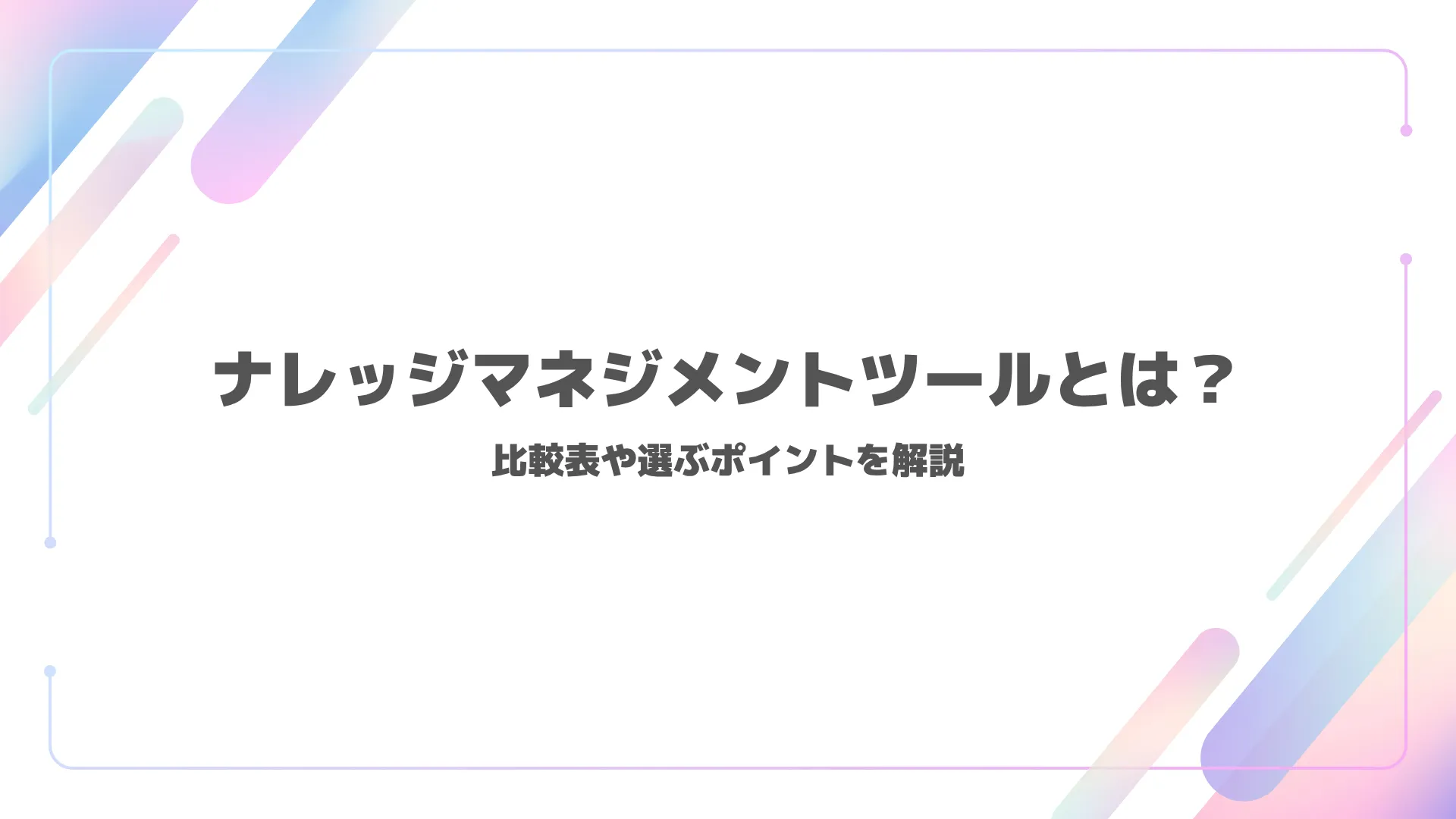
ナレッジマネジメントツールとは、企業内に蓄積された情報やノウハウを一元管理し、社内で共有するためのツールです。業務の効率化を図ると同時に、組織全体で知識を活用できる仕組みをつくります。FAQやマニュアル、業務手順を整理し、誰でもアクセスできる状態に整備することで、情報の属人化や、業務のムダを防ぐのに役立ちます。
とくに部門や拠点が複数ある企業では、情報が散らばったり、更新が追いつかなかったりするケースが少なくありません。そうした状況では、ナレッジをうまく蓄積・再利用する仕組みが、生産性向上に直結します。
本記事では、ナレッジマネジメントツールの基本的な機能や種類、代表的な5つのツールもご紹介していきます。
目次
ナレッジマネジメントツールとは
ナレッジマネジメントツールとは、社内にある知識やノウハウを整理し、共有しやすくするためのツールです。業務マニュアルや手順書、成功事例などの情報を一か所にまとめて、誰でもアクセスできるようにする仕組みです。イメージとしては、会社の「図書館」のような役割を果たします。
情報が部署ごとにバラバラだったり、特定の人しか知らなかったりすると、必要な情報にたどり着くまでに時間がかかってしまいます。ナレッジマネジメントツールを使えば、こうしたムダを減らし、スムーズに情報へたどり着ける環境を整えられます。
ナレッジを「会社の資産」として活かす手段として、非常に有効なツールといえるでしょう。
参考:ナレッジマネジメントの7つのメリット|デメリットや導入成功事例も解説
ナレッジマネジメントツールが必要な理由
なぜナレッジマネジメントツールが注目されているのでしょうか。ここからは、活用が求められる5つの理由を解説します。
情報がバラバラな問題の解決|情報検索の効率化
メールの添付ファイル、PCのフォルダ、共有ドライブ、紙の資料など、必要な情報があちこちに散らばっていて、「どこにあるのかわからない」と感じた経験はないでしょうか。探しているうちに時間ばかりが過ぎてしまい、業務が止まってしまうこともあります。
ナレッジマネジメントツールを導入すれば、分散している情報を一か所にまとめて管理できます。検索性が向上し、必要なときにすぐ情報へアクセスできる環境が整います。担当者が不在でも他のメンバーが情報を引き継げるため、作業も滞りません。
知識の消失問題の解決|属人化の防止
「その人しか知らない」情報が、退職や異動とともに失われてしまう。こうした“属人化”は、多くの現場で課題となっています。
ナレッジマネジメントツールを使えば、業務手順や対応のコツ、よくある質問などを記録として残すことが可能です。個人の頭の中にあるノウハウをチーム全体で共有できるようになり、担当が変わってもスムーズに業務を引き継ぐことができます。
また、情報が見える化されていれば「誰が何を知っているのか」「どこを見ればわかるのか」がひと目でわかります。これにより、特定の人に頼りすぎない安定した運用体制が実現します。
マニュアルや手順書など|業務の標準化
作業の進め方が人によって異なると、対応や成果にムラが出てしまいます。ナレッジマネジメントツールを活用すれば、マニュアルや手順書をチームで共有し、業務プロセスを統一しやすくなります。
たとえば、ベテラン社員の工夫や、ミスを防ぐためのポイントをツールに記録しておけば、ほかのメンバーもすぐに参考にできます。属人化を避けながら、再現性のある業務フローが構築可能です。誰もが同じ手順で作業できるようになれば、品質の安定にもつながります。
新入社員へのサポート|人材育成
新入社員が早く業務に慣れるには、必要な情報にすぐアクセスできる仕組みが必要です。ナレッジマネジメントツールを使えば、業務の流れや社内ルール、過去の事例などを一元管理できます。
教育担当者の説明に頼らず、自分でナレッジを見ながら学べるようになると、学習スピードも上がります。情報が共有されていれば、特定の人が何度も教える必要もなくなります。
「この作業はどこを見ればいいのか」が明確になれば、業務の理解も深まり、質問の数も減っていきます。結果として、新人も周囲もスムーズに働ける環境づくりにつながるでしょう。
ナレッジマネジメントツールの種類
ここからは、ナレッジマネジメントツールの代表的な4つのタイプを紹介します。
FAQ管理タイプ
FAQ管理タイプは、よくある質問とその回答をまとめて共有できるナレッジマネジメントツールです。繰り返し出てくる質問や、問い合わせの多い項目を一覧で整理し、誰でもすぐに必要な情報にアクセスできるようにします。
カテゴリやタグの付与、検索機能が備わっているため、情報を簡単に探せます。また、編集機能も搭載されているため、内容の追加や更新にも柔軟に対応できます。
社内システムの操作方法、経費精算の手順、定型業務の進め方などは、FAQが整っていれば、わざわざ質問しなくても自己解決しやすくなります。チーム全体で知識を共有する土台としても取り入れやすく、導入のハードルが低いのも特長です。
参考:FAQを最適化するAIチャットボット「IZANAI Powered by OpenAI」
文書管理タイプ
社内のマニュアルや報告書、業務資料などを一元的に整理・管理できるツールです。個人のフォルダで情報を持つよりも効率がよく、情報を探す手間も減らせます。
業務の属人化を防ぐためには、誰でも社内ドキュメントを見られるようにしておくことが大切です。たとえば、営業やマーケティングのメンバーが、他部署の過去の資料や施策内容を確認する場面でも、スムーズに情報を把握できます。
検索機能やタグ付けなどの機能を活用すれば、必要な情報にすぐたどり着けます。チーム全員が共通の資料をもとに業務を進めることで、情報のばらつきも抑えられます。
業務プロセスタイプ
業務の知識やルールだけでなく、進め方そのものをナレッジとして共有するためのツールです。人によってやり方が異なりやすい業務に対して、手順を標準化し、対応のムラを減らす役割を担います。
たとえば、コールセンターでは対応フローや過去のやり取りを共有することで、顧客からの質問やクレームにも迅速かつ一定の品質で対応できるようになります。
マニュアルではカバーしきれない例外対応や、ありがちなミスのパターンも記録しておくことで、実務に強いナレッジが構築されます。チーム全体で使いながらブラッシュアップしていける点も、このタイプならではのメリットです。
ベストプラクティス共有タイプ
成果を上げている社員のノウハウや工夫をチームに共有するためのツールです。属人化しがちな知見をいつでも再現できるようにすることで、全体のパフォーマンス向上を目指します。
たとえば、営業成績の高い社員のトーク例や提案資料、商談の進め方などを記録し、ほかのメンバーが参考にできるようにします。これにより、個人の経験に頼らず、チーム全体で一定の成果を出しやすくなります。
ただし、情報を引き出やすくするための工夫や、継続的に活用される仕組みを整えることも必要です。共有方法を見直しながら運用していくことで、チームの成長を支えるナレッジとして機能します。
ナレッジマネジメントおすすめツール比較5選
ここでは、代表的なナレッジマネジメントツールを5つを紹介します。各ツールの特長や向いている企業、料金プランについてもあわせて解説します。
1. Notion(ノーション)

画像引用元: Notion (ノーション)
Notionは、ドキュメント作成・タスク管理・データベース管理などをひとつにまとめたオールインワンツールです。社内マニュアルの整備や業務メモの作成、プロジェクトの進捗管理など、幅広い用途に対応できます。
コメント機能や共有設定も充実しており、チーム全体で情報を整理・共有しながら使える点も魅力です。カスタマイズ性が高く、用途に合わせて自由にページを設計できます。
| タイプ | 文書管理タイプ × 業務プロセスタイプ(オールインワン型) |
|---|---|
| 向いている企業 | 小〜中規模のチームや、部署を越えてナレッジを共有したい企業に適しています。特に、メンバーが複数の業務を兼任している環境で効果を発揮します。 |
| 料金プラン | 無料プラン:個人利用向け。 基本機能をすべて利用可能プラス:月額1,650円 (年払い/チームでの共同作業や無制限のファイルアップロードが可能) ビジネス:月額3,150円(年払い/セキュリティや管理機能が強化) |
2. Confluence(コンフルエンス)

画像引用元:Confluence
Confluenceは、チームでのドキュメント作成やナレッジ共有に特化したコラボレーションツールです。リアルタイム編集を使って、会議メモやアイデア出し、プロジェクトの計画を整理できます。コメントやいいね!、絵文字などの視覚要素も利用でき、コミュニケーションが取りやすいのも特長です。
テンプレートも豊富に用意されているため、誰でも簡単にナレッジ共有をはじめられます。ファイルや動画、ホワイトボードなども一か所に集約でき、情報を整理しやすくなります。
| タイプ | 文書管理タイプ × 業務プロセスタイプ |
|---|---|
| 向いている企業 | 中規模以上のチームで、複数部署にまたがるプロジェクトを進めている企業に向いています。特に、情報共有の仕組みづくりに課題を感じている組織におすすめです。 |
| 料金プラン | 無料プラン:最大10ユーザーまで利用可能 有料プラン:ユーザー数により変動。 Enterpriseは個別見積もり (AI機能・管理機能・サポート体制はプランにより異なります) |
3. Microsoft SharePoint(マイクロソフト シェアポイント)

画像引用元:Microsoft SharePoint
Microsoft SharePointは、ドキュメント管理や社内情報の整理・共有に特化したクラウド型のナレッジマネジメントツールです。社内専用のカスタムワークフローを作成し、ファイルの共同編集や掲示板機能を通じて情報を一元的に管理できます。
業務フローの自動化やアクセス制御など、セキュリティと効率化の両立にも配慮されており、Microsoft 365との連携によって社内全体の情報共有がよりスムーズになります。
| タイプ | 文書管理タイプ × 業務プロセスタイプ |
|---|---|
| 向いている企業 | 中〜大規模の企業で、部門間の連携を重視する組織に適しています。 すでにMicrosoft 365を導入している場合は、導入・運用もスムーズです。 |
| 料金プラン | 無料プラン:なし(無料トライアルあり) 有料プラン: SharePoint Online 単体:月額749円〜(1ユーザー/年払い) Microsoft 365 Business Standard:月額1,874円〜(1ユーザー/年払い) |
4. Slack(スラック)

画像引用元:Slack
Slackは、日常のコミュニケーションと情報共有を一元化できるチャットツールです。チャンネルごとに会話を整理できるため、過去のやり取りや添付ファイルを簡単に振り返ることができ、ナレッジの蓄積にも役立ちます。
さらに、AI機能や外部アプリとの連携を活用すれば、社内情報を探す手間を減らし、チーム全体で知識をスムーズに共有できます。重要な情報をまとめて管理できるキャンバスもあり、リモートワークや部門間の連携強化を図りたい企業に適しています。
| タイプ | ベストプラクティス共有タイプ |
|---|---|
| 向いている企業 | 小〜中規模のチームで、チャットを中心にナレッジ共有を進めたい企業に向いています。日常のやり取りとナレッジ蓄積を同時に行いたい場合に効果的です。 |
| 料金プラン | 無料プラン:あり(90日間のメッセージ履歴など一部機能) 有料プラン:月額525円〜 (3か月間50%オフ、通常価格は1,050円〜/1ユーザー) ビジネスプラス、Enterprise+も用意 |
5. Microsoft 365(マイクロソフト365)

画像引用元: Microsoft 365
Microsoft 365は、Officeアプリ、クラウドストレージ、チャット、会議機能などをまとめた統合型の業務支援ツールです。OneNoteやLoopを使ってナレッジを管理したり、SharePointやOneDriveに資料を保存したりすることで、情報の整理と共有がしやすくなります。
Microsoft Teamsとの連携により、ドキュメントの共同編集や履歴の管理もスムーズに行えます。チームで知識を蓄積しながら、業務全体の効率化を目指す企業に適しています。
| タイプ | 文書管理タイプ |
|---|---|
| 向いている企業 | 中小企業から大企業まで、幅広い業種・規模で導入されています。 特に、複数部門間でのファイル共有や共同作業を重視する組織に向いています。 |
| 料金プラン | 無料プラン:なし(OneDrive個人向けに無料枠あり) 有料プラン: Microsoft 365 Business Basic:月額899円(年払い/1ユーザー) Business Standard:月額1,874円(年払い/1ユーザー) Business Premium:月額3,298円(年払い/1ユーザー) ※個人・家庭向けプランも別途あり |
ナレッジマネジメントツール選びのポイント
ここからは、ナレッジマネジメントツールを選ぶ際に押さえておきたい4つのポイントを紹介します。
使いやすさ
ナレッジマネジメントツールを選ぶうえで、まず重視したいのが「使いやすさ」です。どれほど多機能でも、操作が複雑で現場で使いこなせなければ意味がありません。画面の構成やボタンの配置がわかりやすく、はじめて使う人でも迷わず操作できるかを確認しましょう。
検索スピードも見逃せないポイントです。必要な情報をすぐに探し出せるツールなら、業務の流れが止まらず、自然と生産性も上がります。また、スマートフォンやタブレットに対応していれば、外出先や在宅勤務中でも社内情報にアクセスできます。お客様とのやりとりにも柔軟に対応できるようになり、業務の幅が広がります。
搭載機能
ナレッジマネジメントツールを選ぶ際は、搭載されている機能にも注目しましょう。まず重要なのは、検索機能です。資料やマニュアルをスムーズに探せる仕組みが整っているかどうかがポイントになります。
次に、情報を整理・分類できるかどうかもチェックしましょう。フォルダやタグで整理できると、情報の全体像が把握しやすく、必要な内容にすばやくたどり着けます。あわせて、情報を手軽に更新できる仕組みがあれば、常に最新の状態を保てます。
共有機能も大切です。チーム内でスムーズに情報を共有できれば、コミュニケーションの質が高まり、属人化の防止にもつながります。
他のツールとの連携
ナレッジマネジメントツールを選ぶ際は、すでに使っている他の業務ツールとスムーズに連携できるかも確認しておきましょう。たとえば、チャットツールやグループウェアと連携できれば、日々のやりとりを自動でナレッジに反映させることができます。ファイル共有サービスとつながっていれば、ナレッジ内から直接資料を開くことも可能です。
さらに、会議ツールと連携すれば、議事録の自動作成や保存も行えます。こうした連携によって、情報の重複や作業の手間が減り、全体の業務効率が上がります。
セキュリティ対策
ナレッジマネジメントツールでは、社内のノウハウや顧客情報といった機密情報を扱うため、セキュリティ対策がどの程度整っているのかを必ずチェックしましょう。
たとえば、通信内容や保存データが暗号化されているか、アクセス権限を細かく設定できるかは必ず確認しておきたいポイントです。二要素認証の有無や、操作ログを記録・監視する機能があれば、より安全に利用できます。
クラウド型のツールの場合は、定期的なセキュリティアップデートが実施されているかも確認しておくと安心です。
セキュリティ対策が不十分なツールを使うと、情報漏洩や不正アクセスにつながる可能性があります。導入前に十分な対策が講じられているかを見極め、信頼できるツールを選びましょう。
ナレッジマネジメントツールを上手に使うコツ
最後に、ナレッジマネジメントを効果的に運用するための3つのポイントを紹介します。
スモールスタートで段階的な導入をする
ナレッジマネジメントツールの導入は、まずは小さな範囲からはじめて、徐々に広げていくのがおすすめです。いきなり全社展開を目指すと、運用ルールが浸透しづらく、現場が混乱するリスクがあります。
最初は、一部の部署やチームで試験的に導入し、実際の活用状況や課題を見極めながら、少しずつ他部署にも展開していきましょう。導入初期はツール内の情報が少なく、効果を実感しにくいこともありますが、小規模な成功事例を積み重ねていくことで、自然と社内への広がりが生まれます。
現場の声を反映した運用ルールを策定する
ナレッジマネジメントツールを定着させるには、実際に使う現場の声を取り入れた運用ルールが欠かせません。業務内容や必要な情報は部門によって異なるため、画一的なルールでは運用しづらくなります。
たとえば、営業部門では提案資料や商談の成功事例が重要になり、カスタマーサポート部門では対応履歴やFAQが中心になります。こうしたニーズを丁寧にくみ取り、各部門に適したルールや活用方法を設計することがポイントです。
また、情報の登録や更新、閲覧といったフローも、実際の業務に合った形に整えることが求められます。使いやすさを第一に設計することで、ナレッジが自然と活用されるようになります。
明確な目的設定をする
導入にあたっては、「なぜナレッジマネジメントツールが必要なのか」を明確にすることからはじめましょう。業務の属人化を解消したいのか、問い合わせ対応のスピードを上げたいのか。それによって必要な機能や、重視すべきポイントは異なります。
目的があいまいなままだと、使いにくいシステムになってしまい、現場への定着も進みにくくなります。また、導入後の運用体制や更新のルールも、事前に整理しておくことが大切です。
ナレッジマネジメントツールを活用して業務効率を高めよう
ナレッジマネジメントツールは、単なる「情報の保管庫」ではありません。社内にある知識やノウハウを資産として活用し、組織の成長を支えるための仕組みです。情報を一元化することで、業務の属人化を防ぎ、ミスの削減や引き継ぎの効率化、新人教育の強化など、さまざまな業務改善につながります。
ツールを選ぶ際には、使いやすさや搭載機能だけでなく、「FAQ管理タイプ」「文書管理タイプ」といった中から、自社の目的に合ったものを見極めることが大切です。また、他の業務ツールとの連携性やセキュリティ面もあわせてチェックしましょう。
ツールをうまく活用することで、組織全体のパフォーマンスを底上げできます。ぜひこの機会に、自社に合ったツールを選び、ナレッジ共有の文化を育てていきましょう。


