営業アシスタントの業務改善の方法を解説|改善に成功した事例も紹介
公開日 2025/07/25
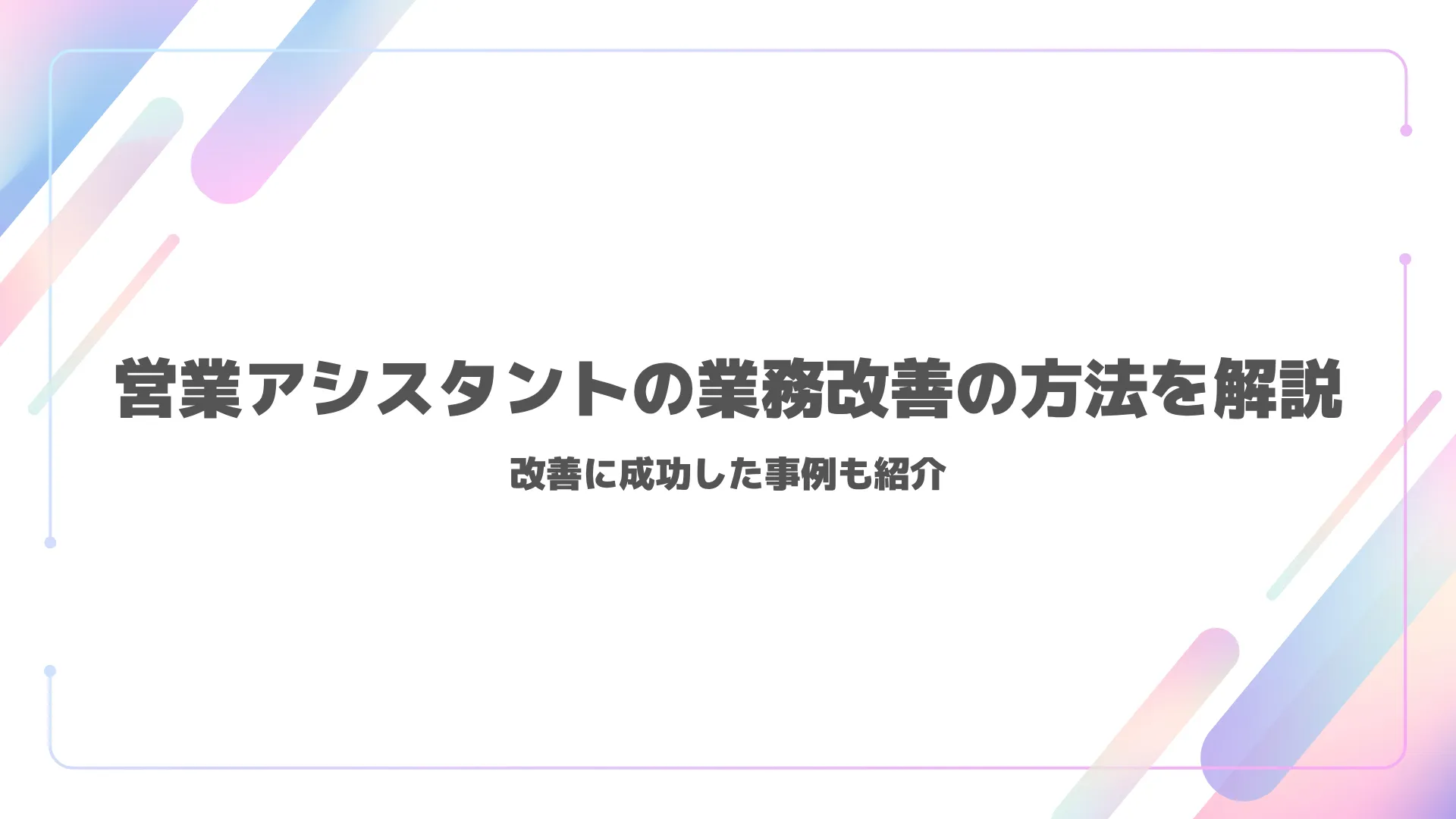
「資料作成に追われて本来の業務が後回しになる」
「業務の範囲が広すぎて、効率が上がらない」
営業アシスタントの現場では、こうした課題が多く見受けられます。
営業活動を支える立場として、営業アシスタントが担う業務は多岐にわたります。見積書や議事録の作成、顧客対応、スケジュール調整など、対応すべき業務が積み重なる中で、日々の負担を感じている方も多いのではないでしょうか。
業務がうまく整理されていない状態では、ミスのリスクや残業の増加といった問題にも起こりかねません。
本記事では、営業アシスタントの仕事内容を整理しながら、現場で起きやすい課題とその改善方法を解説します。成功事例や業務支援ツールの紹介も交えつつ、業務効率を見直すためのヒントをお届けします。
目次
営業アシスタントの業務内容
営業アシスタントは、営業担当が提案や商談に集中できるよう、さまざまな業務を担っています。書類作成や日程調整に加え、資料の準備や社内外との連携対応など、業務の種類は多く、柔軟な対応が求められます。ここでは、6つの基本的な業務について解説します。
書類作成
営業に関わる見積書や請求書、契約書の作成は、アシスタントが日常的に対応する業務のひとつです。営業担当が商談や提案に集中できるよう、情報を整理し、正確かつスピーディーに仕上げることが求められます。
書類を作成する際には、過去の取引データや社内システムを参照し、不足している情報を自ら補う判断も必要です。顧客ごとに条件が異なるため、ひな形の流用だけでは対応しきれない場合もあります。背景を把握しないまま進めると、後で確認作業が発生し、手間が増える原因になります。事前準備と情報共有を丁寧に行うことが、書類の完成度を高めるポイントです。
資料作成
提案資料や説明用スライドの作成は、営業アシスタントが関わる機会の多い業務です。営業担当の意図をくみ取りながら、構成や表現を調整し、内容を整えていきます。
「前と同じ雰囲気で」「ざっくりでいい」といったあいまいな依頼を受けることもあるため、背景や目的を把握したうえで、状況に応じて内容を再構成する判断も求められます。過去の資料を参考にしながら、伝えるべきポイントが相手にしっかり届くよう、構成を工夫することが欠かせません。
また、社内会議に同席する際には議事録の作成を担当する場面もあります。会話の流れを整理し、後から見返しても内容がすぐに把握できるようにまとめておくことが大切です。
お客様対応
営業担当が不在のとき、顧客からの問い合わせに対応するのもアシスタントの業務です。納期の調整や在庫の確認、製品の仕様に関する質問などに対し、状況を判断しながら進めていきます。
急ぎの依頼や問い合わせ内容によっては、社内調整や関係部署への確認が避けて通れない場合もあります。落ち着いた対応を心がけながら、やり取りの履歴をきちんと記録し、営業担当へ情報を共有しておくことが、後々のトラブル防止にも役立ちます。取引先との関係づくりを支えるうえでも重要な役割です。
受発注業務
注文が確定したあとは、社内での発注手続きや関係部署とのやり取りが発生します。受注内容を確認しながら納期や在庫状況をふまえて、社内の調整を進めていきます。
一見すると定型的な作業に見えるかもしれませんが、製品仕様の変更や納期調整などが加わると、一気に複雑化します。状況を正確に把握し、関係部署との橋渡しを意識して動くことがポイントです。事務処理をする際は、現場全体を見渡しながら調整できると、業務も滞りにくくなります。
スケジュール管理
スケジュール管理は、営業アシスタントが関わる場面の多い業務です。商談や会議、出張などに応じて予定を整理し、営業担当が無理なく行動できるよう整えていきます。予定の重なりや移動時間に気を配りながら、日程に無理が出ないよう調整を進めます。
変更が生じた場合には、関係者へ速やかに連絡を取り、予定の再調整にあたります。カレンダーへの入力時には細かなズレにも注意し、事前に確認を重ねておくと安心です。こうしたサポートが、営業活動を滞りなく進めるための支えになります。
商談のサポート
顧客訪問に同行する場面では、営業担当が安心して商談に集中できるよう、資料の準備や段取りの確認を行います。当日は、資料の提示や画面操作の補助などを通じて、商談がスムーズに進むよう臨機応変に立ち回ることも重要です。
また、商談が終わった後には、議事録の作成や、次の提案へつなげるフォローメールの準備なども担います。事後対応がスムーズに進むことで、提案全体の質が高まり、営業活動全体に良い流れをもたらします。
営業アシスタントが重要な理由
営業チームの成果は、外部とのやり取りだけでなく、日々の業務がどれだけ整っているかにも左右されます。アシスタントが裏側から業務を支えることで、営業担当の動きがスムーズになり、チーム全体の生産性にも影響が出てきます。ここでは、営業アシスタントが果たす役割と、その働きがもたらす具体的な効果を解説します。
営業担当者の負担を軽減できる
営業担当は、商談対応や顧客訪問、新規開拓といった対外業務に多くの時間を費やしています。その一方で、社内での書類作成や他部署とのやり取り、問い合わせ対応など、裏方の作業も同時に発生します。 すべての業務を一人で抱える状況では、判断の精度が落ちたり、対応が後手に回ったりする恐れがあります。アシスタントが社内処理を引き受けることで、営業担当は提案準備や顧客との関係構築に集中しやすくなります。 役割を分けることで業務の精度が高まり、全体のリズムも整ってきます。
営業の効率を向上させられる
アシスタントが資料の準備やスケジュールの調整を担うことで、営業担当は一日の動きを計画的に進められます。書類や予定があらかじめ整っていれば、移動や準備の段取りもつけやすく、突発的な対応にも落ち着いて臨めます。対応に余裕が生まれれば、提案内容の質を高めたり、相手ごとに情報を補足したりと、準備の幅も広がります。 こうした積み重ねが、業務全体の動きをスムーズにし、成果の安定にもつながっていきます。
会社の売上増加に効果が期待できる
営業体制が整っていれば、商談の機会を逃さず、提案の内容も丁寧に磨き込めるようになります。相手のニーズに合わせた資料や説明が準備できれば、やり取りの質が上がり、信頼も得やすくなります。 特に提案力が問われる場面では、準備の丁寧さが成約に直結するケースも少なくありません。 アシスタントの働きによって営業チーム全体の動きが安定すれば、収益面にも良い影響をもたらします。
営業アシスタントの業務の課題
営業アシスタントは、さまざまな業務に携わる中で、関係部署との連携や臨機応変な対応が求められます。体制が十分に整っていない場合には、業務負担が大きくなりがちです。ここでは、現場で発生しやすい課題について解説します。
対応する業務範囲が広い
営業アシスタントの業務は、書類作成やスケジュール調整に加え、顧客対応、社内連携、データ入力など多くの業務をこなします。それぞれに異なる進め方やルールが存在するため、作業の全体像を把握しながら効率的に動く力が求められます。
また、誰がどこまでを担当するのかが曖昧なまま進むと、タスクの重複や漏れといったリスクが高まります。業務ごとの棚卸しやフローの見直しを通じて、役割や優先順位を明確にしておくことで、日々の進行に余裕を持たせることができます。
素早い対応が求められる場面が多い
営業の現場では、「至急資料を用意してほしい」「予定を変更したい」といった依頼が突然舞い込むことも多いです。その場に応じて計画を柔軟に組み直し、優先度を判断する力が問われます。突発的な対応が重なると、本来予定していた作業が遅れたり、確認不足による手戻りが生じたりすることもあります。特に繁忙期やメンバーが限られている時期には、対応範囲が広がりやすいため、業務の進め方に工夫が必要です。
業界や商品に関する専門知識が求められる
営業アシスタントは、営業担当の意図を読み取りながら、わかりやすく説得力のある資料を整える役割も担います。そのためには、自社の製品やサービスに関する理解はもちろん、業界全体の動向や競合との違いについても把握しておくことが望まれます。営業資料の構成やビジュアル面にも工夫が求められるため、マーケティング知識や資料作成のスキルも常にアップデートすることが重要です。担当者と連携しながら、内容を深めていく姿勢が成果に結びつきます。
1つのミスが大きな損失を出す可能性がある
営業アシスタントが扱う業務の多くは、顧客対応や契約関連など、正確さが問われる内容です。発注先の入力ミスやダブルブッキングなどが発生すれば、取引先との信頼関係が揺らぐ恐れがあります。また、自分の判断だけで完結できない業務も多いため、周囲との情報共有や連携も欠かせません。プレッシャーの中でも安定した対応が求められる仕事です。
営業担当者と顧客の間で板挟みになる場合がある
顧客からの依頼が社内の判断や状況と食い違う場合、その調整を営業アシスタントが担うことがあります。たとえば、納期の短縮や価格の再提示といった相談には、その場で明確な返答ができず、間に立つことで精神的な負担を感じる場面もあるでしょう。
こうした対応では、顧客と社内の双方に配慮した言葉選びと、状況を正しく把握する力が欠かせません。やわらかい対応を心がけつつも、必要なときには立場を明確にして調整を進める姿勢が重要です。
営業アシスタントの業務を効率化する方法
日々の業務に追われがちな営業アシスタントですが、進め方を少し工夫するだけでも、業務全体の流れに余裕が生まれます。マニュアルの見直しや業務の自動化、ツールの導入といった改善策を通じて、現場の負担を軽減することが可能です。ここでは、すぐに取り入れやすい具体的な方法をご紹介します。
業務マニュアルの見直し・作成
担当者ごとに作業のやり方や判断基準が異なると、業務の引き継ぎや対応品質にばらつきが出やすくなります。マニュアルを整えておくことで、作業の再現性が高まり、誰が担当しても安定した対応が可能になります。
営業アシスタントは複数の業務を並行して行うため、手順やルールが整理されていると、判断や作業にかかる時間を短縮できます。既存のマニュアルが現場の実情に合っていない場合は、定期的な見直しも必要です。
定型業務の自動化
あらかじめ形式が決まっている書類の作成や、繰り返し発生する作業は、自動化の対象として検討できます。具体的には、フォーマットへのデータ入力や集計、ファイル名の付け替えといった工程は、RPA(業務自動化ツール)などを用いることで効率化できます。
アシスタントは確認と修正に専念できるようになり、単純作業にかかる負担を減らせます。人的ミスの防止にもなり、全体の作業品質を底上げする効果も見込めます。
アウトソーシングの活用
業務の一部を外部の専門業者に委託するアウトソーシングも、負担の分散に有効です。データ入力や資料の体裁調整といった業務は、社外に任せることで社内の人的リソースを確保しやすくなります。
営業アシスタントの手が空くことで、社内調整や提案準備などの対応に時間を割けるようになります。外部に任せる際は、情報管理や品質のチェック体制を事前に整えておくことが前提です。
営業支援ツールの導入
営業支援ツールとは、顧客情報や案件の進捗、営業活動の履歴などを一元管理できるシステムです。SFA(営業支援システム)やCRM(顧客関係管理)などが代表的で、営業チーム内の情報共有や業務の見える化を後押しします。
案件管理や顧客情報の整理といった手間のかかる作業は、こうしたツールの活用によって簡素化できます。必要なデータにすぐアクセスできるようになり、確認や修正の作業時間を削減できます。また、アシスタントが担う業務の流れも可視化されるため、チーム内の連携をスムーズに整える効果も期待できます。
チャットツールの導入
チャットツールとは、短いメッセージのやり取りをリアルタイムで行えるコミュニケーションツールです。 SlackやMicrosoft Teams、Chatworkなどが代表的で、社内連絡のスピードアップに役立ちます。
メールだけでやり取りしていると、返信が遅れたり、内容を見落としたりすることがありますが、チャットツールを活用することでそうしたリスクを減らせます。既読機能によって伝達状況を把握しやすくなり、ファイルの共有やグループでの連絡にも対応可能です。場所を問わずに使える点も、働き方の多様化に合った手段といえます。
インサイドセールスの実施
インサイドセールスとは、電話やメール、Web会議など非対面で行う営業活動のことを指します。営業担当者が社内にいる時間が増えるため、アシスタントとの連携も取りやすくなります。
また、資料の受け渡しや顧客情報の共有などがスムーズになり、業務の中断や待ち時間を減らせます。営業スタイルを見直すことが、社内オペレーションの効率にも波及する好例です。
テレワーク・Web商談の実施
営業アシスタントの業務の多くは、パソコンとネット環境があれば自宅でも対応可能です。テレワークを取り入れることで、通勤時間を削減でき、業務への集中度が高まるという効果もあります。
また、空いた時間をスキルアップや業務改善の検討に活用できるようになれば、個人の成長にもつながります。Web商談と組み合わせれば、営業全体の柔軟性を高めながら、生産性を保つ働き方が整います。
営業アシスタントの業務改善の流れ
営業アシスタントの業務は属人化しやすく、改善の効果も見えづらい傾向があります。だからこそ、順序立てて見直すことで、課題の所在や改善策が明確になります。ここでは、業務改善を進める際に意識したい4つのステップを紹介します。
1. 現状を把握して問題点や課題を明確にする
まず取り掛かりたいのは、現在の業務内容を細かく洗い出す作業です。営業アシスタントが担当しているタスクをすべて一覧化し、それぞれにかかる時間や対応の頻度を可視化していきます。具体的には、「月末の集計作業に3時間」「商談資料の準備に毎回1時間以上かかる」など、数字で示すことで業務の負荷が可視化されます。
営業アシスタント本人へのヒアリングも有効です。どの作業に手間がかかっているのか、どの場面でミスが起きやすいと感じているのかなど、主観的な感覚も整理することで、課題の輪郭がより明確になります。また、営業担当者の声にも耳を傾けましょう。依頼の偏りや情報伝達のズレといった構造的な課題が明らかになる可能性もあります。
現場の声と業務の実態を丁寧にすり合わせていくことで、改善すべきポイントが浮き彫りになります。何から手を付けるべきかが見えてくれば、その後の検討も進めやすくなります。
2. 業務フローを見直す
現状把握の次は、業務の流れを見直す段階です。図や一覧表にまとめることで、どこが滞っているか、何が負担の原因になっているかが整理されます。以下のような観点から洗い出すと、改善の手がかりが得られます。
- 承認や確認に関わる人が多く、対応に時間がかかっている
- ファイルや情報の保管場所がバラバラで探すのに手間がかかる
- 業務が属人化していて、引き継ぎや代行が困難になっている
- 目的が不明瞭な作業が、習慣として残っている
上記のようなポイントを見直すだけでも、工程の簡素化や作業時間の削減が見込めます。「当たり前」とされてきた手順ほど、見直しによる効果が大きくなりやすいです。
業務フローを可視化しておくと、改善提案の根拠にもなります。図やフローチャートで整理すれば、上司や他部署との共有もスムーズになり、改善活動の協力が得やすくなります。
3. 業務改善の方法を考える
改善の方向性が明らかになったら、次は具体的な対応策を検討します。「ファイルの場所がわかりにくい」といった課題がある場合は、フォルダ構成や命名ルールを整理し、クラウド上で共有する体制に切り替えます。「対応のばらつきがある」といった場合には、マニュアルやテンプレートの整備が有効です。
対応策は一つではありません。複数の課題がある場合は、以下のような視点で優先順位をつけると、着手しやすくなります。
- 作業負荷が高く、早急な対応が求められるもの
- チーム全体に影響が及ぶもの
- 比較的手間をかけずに改善できるもの
改善は一度きりの取り組みではなく、継続的な取り組みとして捉えることが大切です。最初から完璧を求めず、できる範囲から取り組む姿勢が、現場の負担を増やさずに継続しやすくなります。
4. 業務改善をした結果の分析
改善策を実施したあとは、振り返りと検証のプロセスが重要となります。以下のような観点で変化を確認してみましょう。
- どれくらい作業時間が短縮されたか
- 担当者の心理的な負担は軽減されたか
- 引き継ぎやチーム間のやり取りがスムーズになったか
こうした変化を把握するには、処理時間や対応件数といった数値データに加え、現場の声や手応えなどもあわせて見ることが大切です。改善によって何が変わったのかを多角的に確認することで、取り組みの成果が明確になります。
もし想定どおりの結果が出なかったとしても、その要因を振り返ること自体が新たな気づきにもなります。改善は一度きりの取り組みではなく、日々の業務のなかで小さな調整を積み重ねていくものです。「もっとやりやすくならないか」「もう少し整理できないか」と考え続ける姿勢が、品質を少しずつ高めていく力になります。
営業アシスタントの業務改善の成功事例
業務の見直しは、現場の負担軽減だけでなく、営業チーム全体の動きを整える機会にもなります。ここでは、実際に業務改善に取り組み、成果を上げた企業の事例をご紹介します。
【株式会社TVer】リモートアシスタントの活用で営業リソースを確保、商談数の増加を実現
株式会社TVerは、在京・在阪の民放各社が共同出資する企業で、民放公式テレビ配信サービス「TVer」の運営を行っています。サービスの成長に伴い、営業部門ではCM枠販売業務が急増し、請求データの突合や資料作成などの事務業務に多くの時間が割かれるようになっていました。月末月初の処理には毎月20時間以上を要し、本来注力すべき商談活動に支障が出る場面もあったといいます。
この課題に対して、同社はオンラインリモートサービスを導入。請求業務のマニュアル化と業務の切り分けを進め、社内システムへのデータ入力や資料作成などを委託する体制を整えました。あわせて、CSVでの一括処理や定例ミーティングによる業務改善も実施しました。
その結果、営業担当が商談や問い合わせ対応に十分な時間を確保できるようになり、月あたり約5時間の工数削減を実現。売上も拡大し、営業組織の人員が増加する中でも、現体制を維持したまま業務効率化に成功しています。
詳しくは、こちらの導入事例記事をご覧ください。
【東亜薬品工業株式会社】営業プロセスの可視化で情報共有を促進、売上は約2.4倍に成長
東亜薬品工業株式会社は、医薬部外品や動物用の生菌製剤を手がける企業で、プロバイオティクス市場のリーダーとして、製品の研究・開発に注力しています。営業部門では、従来の代理店中心の営業体制から、最終ユーザーである生産者に向けた提案活動へと軸足を移す中で、情報の属人化や目標管理の曖昧さが課題となっていました。
このような背景から、業務の見える化と情報共有を目的に、新たな業務管理システムを取り入れました。商談履歴や対応状況、営業プロセスを日報ベースで蓄積できる仕組みにより、属人的だった営業情報が全社で共有できるようになりました。地方拠点や駐在員との横断的な情報連携もスムーズになり、過去の活動履歴を踏まえた提案や対応が可能に。営業担当者間のナレッジ共有が進み、個人依存の業務体制からチームで動ける組織へと変化を遂げています。
導入以降、売上は約239%にまで成長。現場では「誰がどのように動き、どんな結果を得たか」が明確になったことで、営業活動の効率化が向上しているといいます。
詳しくは、こちらの導入事例記事をご覧ください。
【東海東京証券株式会社】非対面面談の導入で訪問時間を削減、商談数と生産性が向上
東海東京証券株式会社は、個人投資家を対象としたリテール営業を展開する中で、「対面での丁寧な提案」を重視する営業スタイルを築いてきました。しかし、感染症拡大の影響により訪問や来店対応が制限されたことから、従来の営業手法が難しくなり、対応力の維持が課題となっていました。
こうした状況に対応するため、非対面での提案を可能にするオンラインツールを取り入れました。専門用語が多く、視覚情報の補助が欠かせない金融商品の提案においても、画面越しで資料を見ながら丁寧に説明できる環境を整えました。顧客の反応や表情を確認しながら進められるため、対面と遜色ない提案が可能となり、高齢層を含む顧客からも好評を得ています。
この変化により、1件あたりの訪問時間が削減され、移動にかかる負担も大幅に軽減。1日の対応件数が増加し、残業時間の削減にもつながっています。成約率の維持と生産性の向上を両立させながら、営業の幅を広げる施策として、今後もさらなる活用拡大が見込まれています。
詳しくは、こちらの導入事例記事をご覧ください。
営業アシスタントの業務改善に役立つツール
営業活動の裏側を支えるアシスタント業務では、情報の収集や資料整理、問い合わせ対応など、細かな作業が日々発生します。こうした業務を効率化するには、目的に合ったツールの活用が欠かせません。ここでは、業務の自動化や資料共有に役立つ2つのツールをご紹介します。
IZANAI Powered by OpenAI(イザナイ パワード バイ オープンエーアイ)
IZANAI Powered by OpenAIは、PDFやWebサイトの内容を読み取り、その情報に基づいて自然な対話形式でFAQに回答するAIチャットボットです。専門知識が不要なため、導入も簡易で、社内外の問い合わせ対応に活用されています。
営業アシスタントの業務では、商品説明や社内ルールに関する質問が多く寄せられます。IZANAIを使えば、問い合わせにAIが即時対応するため、担当者の負担を軽減できます。文脈を踏まえた回答ができるため、テンプレートでは対応しきれなかった質問にも柔軟に応答可能です。導入企業では、営業担当からの「すぐに確認したい」に応える内製FAQとしても活用が進んでいます。
ActiBook(アクティブック)
ActiBookは、PDFや動画、音声ファイルなどの資料をWebブックとして公開・共有できるツールです。資料をそのままWeb化でき、URLでの送付や閲覧履歴の把握が可能になるため、営業活動の見える化や提案プロセスの改善に役立ちます。
営業アシスタントが資料送付や説明補助を担う場面では、ActiBookの活用によって、担当者が口頭で説明しきれない内容をスムーズに補足できます。営業資料の改訂やバージョン管理も容易で、常に最新情報を共有できる点もメリットです。動画やアニメーションによる説明を組み込めるため、視覚的に訴求力のある提案資料づくりにも適しています。
IZANAI Powered by OpenAIとActiBookの比較
| 項目 | IZANAI Powered by OpenAI | ActiBook |
|---|---|---|
| 主な機能 | 登録したPDFやWebサイト情報を もとに、自然な会話で質問に回答 |
PDF・動画・音声などのデータを Webブックとして公開・共有 |
| 対応形式 | テキスト(チャット形式) | PDF、動画、音声、画像 |
| 主な対象 ユーザー |
社内ヘルプデスク、 営業部門のFAQ整備担当 |
営業アシスタント、 営業推進チーム、 マーケティング担当 |
| 活用される 業務例 |
|
|
| 強み |
|
|
営業アシスタント業務を整えることで、チームの動きが変わりはじめる
営業アシスタントの仕事には、書類作成や日程調整をはじめ、営業活動を円滑に進めるための多くの業務が含まれています。日々の進め方を少し見直すだけでも、改善のきっかけが生まれます。マニュアルの整備や対応ルールの明確化に加え、業務の負担を減らすツールの導入も有効です。
もし、社内からの問い合わせ対応に時間がかかっているのであれば、IZANAI Powered by OpenAI(イザナイ パワード バイ オープンエーアイ)のようなAIチャットボットツールの導入がおすすめです。登録したPDFやWebページの情報をもとに、AIが自然な対話形式で回答してくれるため、同じ質問への繰り返し対応に追われる場面を減らすことができます。
よくある質問や社内ルール、商品情報などを事前に読み込ませておけば、部署をまたぐ問い合わせにもスムーズに対応できるようになります。業務の一部が自動化されれば、より集中すべき業務に注力する時間が生まれ、現場にも余裕が出てきます。
ツールや仕組みを上手に取り入れながら、より働きやすく成果につながる環境づくりを進めていきましょう。


