導入3ヶ月で問い合わせ数が3倍に!AIチャットボットが変えた建築会社の顧客接点|株式会社BLISS様
公開日 2025/09/04
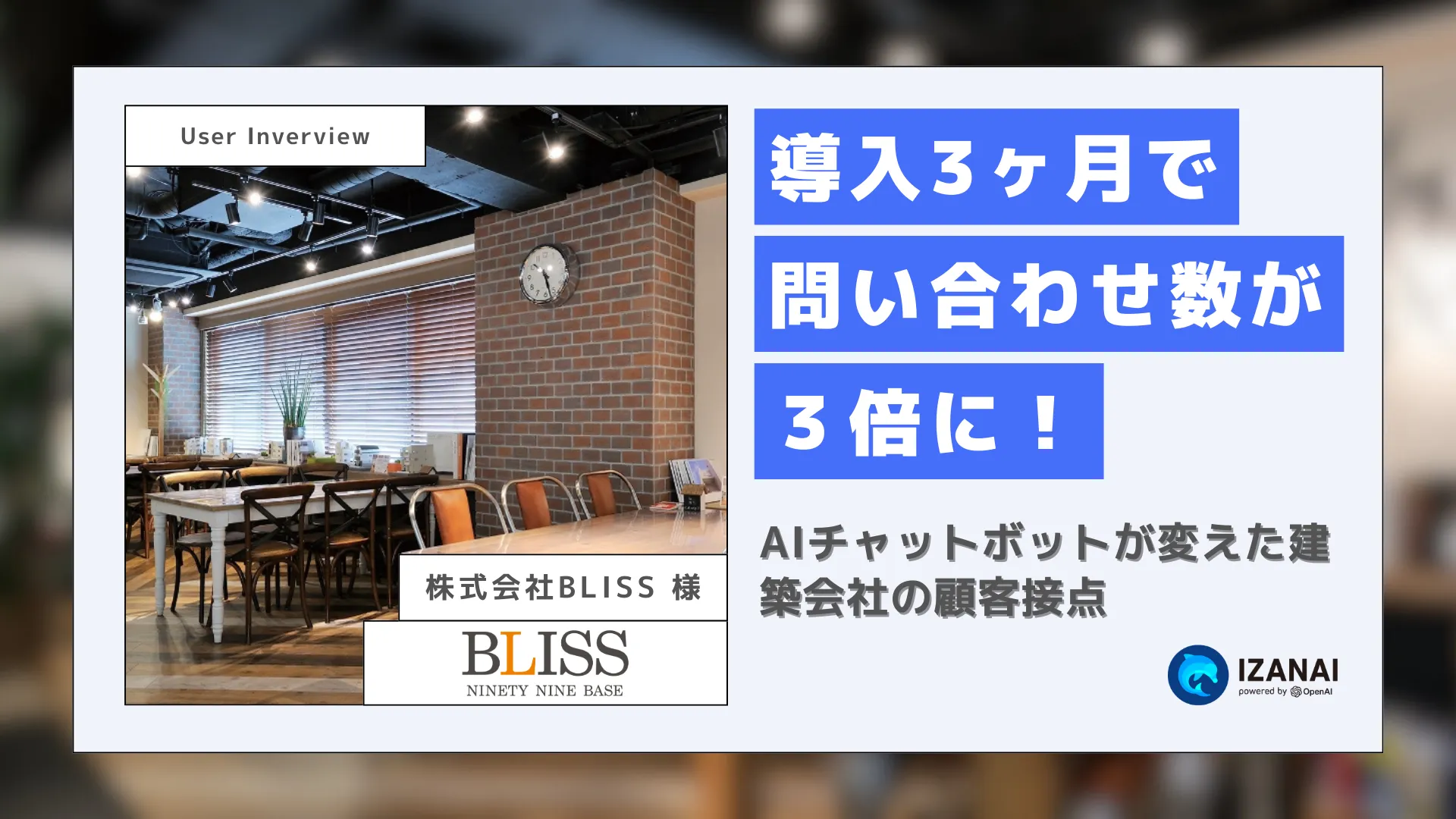
クラウドサーカス株式会社が提供するAIチャットボット『IZANAI Powered by OpenAI』(以下IZANAI OpenAI)を導入されているお客様の事例をご紹介します。
今回は株式会社BLISSの鈴木様に取材をさせていただきました。
株式会社BLISS様
https://bliss-d.com/目次
事業内容
株式会社BLISS様は、2003年に設立された都市型住宅に強みを持つ建築会社です。東京都文京区に本社を構え、限られた敷地を活かした狭小住宅や変形地住宅の設計・施工を中心に展開しています。
「暮らしに、あそびを。」をコンセプトに、お客様の趣味やライフスタイルを反映した家づくりを得意としており、ガレージハウスやボードハウス、ホームシアター付き住宅など、多様なニーズに応じた住まいを提供しています。
自社一貫体制による品質管理のもと、ZEH対応の高性能住宅に加え、リノベーションや賃貸併用住宅にも注力。都市生活に遊び心を添える住宅を提案しています。
導入の経緯
――IZANAI OpenAIを導入される前、どのような課題を抱えていましたか?
鈴木様:私は社内でWebサイトの運営全般を担当しており、アクセスの推移や反響をもとに、日々ページの改善や更新を行っています。数値が安定している間は様子を見ることが多いのですが、数字が落ち込んだ際にどこを改善すべきか分からず、対応に悩むことがありました。
なかでも課題として感じていたのが、お客様の反応が見えにくいことです。どの情報が役立っているのか、逆にどのページが探しづらいのかといった利用実態が把握しづらく、感覚に頼った改善では方向性を誤る恐れがありました。まずはお客様の声を把握したいという思いが、AIチャットボット導入を検討するきっかけでした。
――AIチャットボットに着目された理由をお聞かせください。
鈴木様:人ではなくAIが相手であれば、お客様の率直な声が集まりやすいのではないかと考えたためです。また、WebサイトにはFAQ形式の「よくある質問」ページが設けられていますが、個人的にスムーズな利用体験という点で物足りなさを感じていました。目的の回答がなかなか見つからなかったり、ようやく見つけても内容が抽象的であったりと、十分に機能しているとは言えない場面が多く見受けられました。
その点、AIチャットボットは知りたいことを入力するだけですぐに回答を得られます。検索やページ遷移といった操作も必要なく、必要な情報にたどり着けるのも魅力でした。
また、チャットログを分析することで、Webサイト上に不足している情報やお客様がどのような内容を求めているのかといったニーズを読み取ることができます。問い合わせ対応にとどまらず、データをもとにコンテンツの企画や改善にも応用できると思いました。
選定理由
――IZANAI OpenAIやクラウドサーカスを知ったきっかけを教えてください。
鈴木様:クラウドサーカスを知ったのは、パンフレットの電子化を検討していた際に、電子ブック作成ツール「ActiBook」を調べたのがきっかけでした。最終的に導入には至らなかったものの、当時から社名は記憶に残っていました。
その後、2025年2月に開催された展示会イベント「DX 総合EXPO 2025【春】」でブースを拝見し、AIチャットボットの提供も行っていると知りました。それを機に、サービスの内容や活用事例を調べるようになり、導入を前向きに考えるようになりました。
――導入にあたって、他社サービスとの比較もされたのでしょうか?
鈴木様:IZANAI OpenAIを含めて6社ほど検討しました。弊社のWebサイトはWordPressで構築しているため、プラグインとして連携可能かどうかが前提条件でした。また、追加費用を抑えた形で導入できるかどうかも重視しており、API連携が必要なものやランニングコストが見えにくいものは外しました。
海外製のサービスも候補には挙がりましたが、サポート対応の不安や導入後のトラブル対応に時間がかかるリスクを考慮し、最終的には国内企業に絞って検討しました。
――数あるツールの中から、IZANAI OpenAIを選ばれた決め手は何でしたか?
鈴木様:最終的な決め手は、導入のしやすさと価格のわかりやすさです。AIチャットボットは高額な印象がありましたが、その中でもIZANAI OpenAIは非常にリーズナブルで、比較した中でも最も導入ハードルが低いと感じました。
また、デモ環境で操作してみた際のUIが非常にシンプルで、直感的に扱えるところも評価ポイントでした。使い方のイメージがすぐに掴めたことで、社内でも「これなら運用できそう」と好意的な反応があり、導入をスムーズに進められました。
活用状況と効果
――IZANAI OpenAIは、業務でどのように活用されていますか?
鈴木様:主に、Webサイトに訪問されたお客様からの問い合わせ対応に利用しています。定型的なQ&Aにとどまらず、質問の意図をくみ取ってその場で応答できるため、自社のオペレーターのような存在です。
――運用の工夫についてもお聞かせください。
鈴木様:運用で意識しているのは、プロンプト※の内容を日々見直すことです。お客様とのやり取りログを確認し、「もっとこう答えたほうがよかった」という内容があれば、その都度プロンプトに反映させています。月単位でまとめて行うのではなく、毎日15分から30分程度の短時間で継続的に調整を加えています。設定したら終わりではなく、お客様目線に寄り添いながら改善を続ける姿勢が大切だと考えています。
※プロンプトとは:AIへの指示や質問。AIに何をしてほしいかを伝える文章のこと。
――導入後、具体的にどのような成果がありましたか?
鈴木様:2025年4月に導入してから6月末までの3ヶ月間で、AIチャットボット経由の問い合わせ件数は、従来のお問い合わせフォームの約3倍に達しました。当初は利用が限定的になると想定していましたが、想像以上に多くの方に活用いただいており、驚いています。
――問い合わせ内容にも違いがあるのでしょうか?
鈴木様:フォームから寄せられる問い合わせは、比較的具体的でしっかりと検討された内容が多く、住宅の仕様や費用、所有している土地に住宅が建築できるかなどに関する相談がメインです。それに対して、AIチャットボット経由ではちょっと気になったことを聞いてみるといった、日常的な疑問が多いですね。
実際にログ履歴を見ていても、まるで隣に座っている社員に気軽に尋ねるような感覚で使っていただいているように思います。IZANAI OpenAIで対応している内容は、基本的にはWebサイトに掲載している情報の範囲内ですが、それでも「質問してすぐ返ってくる」という体験があることで、利用のハードルが下がっているのではないでしょうか。
より深い相談や、学習内容の範囲を超えるような質問については、引き続きフォームを通じてお問い合わせいただく流れになっています。質問の内容に応じて、AIチャットボットとフォームがそれぞれ適した役割を担っている印象です。
――IZANAI OpenAIを運用する中で、特に印象的だったことがあれば教えてください。
鈴木様:AIの回答が、自分の予想を超えるケースがたびたびありました。特に印象に残っているのは、「自分ならこう答えるだろう」と思っていた内容に対して、より踏み込んだ説明が返ってきたことです。人が対応する場合には省略しがちな部分でも、学習済みの情報に基づいて丁寧に補足されており、伝えるべき内容を過不足なく届けてくれていると感じました。
今後の展望
――今後、IZANAI OpenAIの活用について、どのような展望をお持ちでしょうか?
鈴木様:今後は、IZANAI OpenAIに蓄積されたログデータを活用し、お客様がどのようなことに関心を寄せているかを可視化していく予定です。現在のWebサイトは、商品紹介やサービス案内など企業の視点で構成された内容が中心であり、お客様の目線が十分に反映されているとは言えません。
そこで、従来のコラムや施工事例とは異なる、お客様の疑問や悩みに寄り添うかたちで、新たなコンテンツを展開していきたいです。お客様を「よくある質問」ページへ誘導するのではなく、コンテンツの閲覧を通じて「ちょうど知りたかったことがここでわかった」と思っていただける構成を目指しています。
あわせて、社内でもログデータを共有し、「最近は〇〇に関する問い合わせが多い」といった動きを定期的に発信することで、全社でお客様の関心を把握しやすくなるよう働きかけていきたいと思います。
お客様の声
――IZANAI OpenAIの導入を検討している企業様へ、メッセージをお願いします。
鈴木様:IZANAI OpenAIは、導入時に複雑な設定を必要とせず、社内でも迷うことなく立ち上げられました。ITに詳しくない方でも扱いやすく、初期段階から無理なく運用できる点が特長だと捉えています。
問い合わせ対応に課題がある企業や、ユーザーの声をサービス改善に活かしたいと考えている方には、試してみる価値があると思います。費用を抑えつつ導入できるため、AIの活用がはじめてという企業にも向いていると思います。

