AIチャットボットの種類を解説!自社に合うサービスの選び方も紹介
公開日 2025/05/21
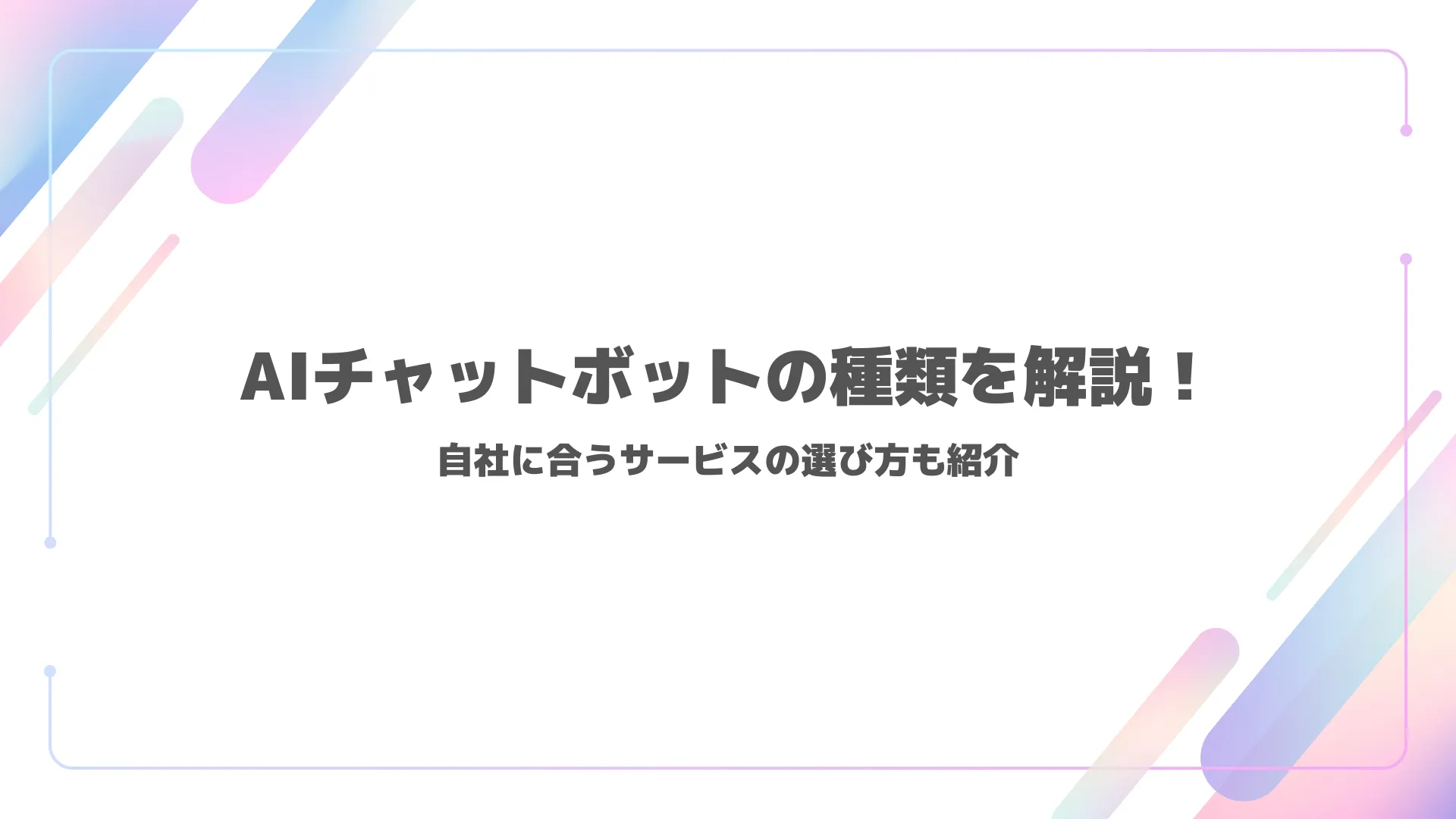
近年、業務効率化や顧客対応の品質向上を目的に、AIチャットボットを導入する企業や自治体が増加しています。一口にAIチャットボットといっても、その仕組みや機能、目的に応じた種類はさまざまです。
本記事では、AIチャットボットの基本から機能・会話形式ごとのタイプ、自社に最適なサービスの選び方、導入事例までを徹底解説。導入を検討している方にとって、実践的な指針となる内容をお届けします。
目次
AIチャットボットとは
AIチャットボットは、あらかじめ学習したデータやユーザーとの会話ログをもとに、自動で質問に回答するプログラムです。データやログの蓄積によって回答の精度は継続的に向上し、次第に人間と対話しているかのような自然なコミュニケーションができるといった特徴があります。
ユーザーの入力内容を自然言語で理解するため、自然で適切な回答を返せる点も魅力です。形式的な定型文だけでなく、柔軟な受け答えや雑談にも対応できるため、カスタマーサポートや社内問い合わせ対応など、さまざまなビジネスシーンで活用されています。
AIチャットボットの基本の種類
AIチャットボットにはいくつかのタイプがあり、導入目的や社内リソースによって最適な種類は異なります。ここでは、代表的なチャットボットの種類と、それぞれの特徴を解説します。
機械学習型
機械学習型のAIチャットボットは、あらかじめ登録したFAQやユーザーとの会話データをもとにAIが学習し、適切な回答を生成します。継続的な学習により精度が向上しますが、初期導入には多くの準備が必要です。
具体的には、FAQの登録や類義語の設定、回答の正確性評価などを行う必要があり、公開までに時間がかかるケースも少なくありません。丁寧な運用体制が求められる分、応用範囲は広く、高度な対応が可能です。
独自AI型
独自AI型チャットボットは、FAQを登録するだけで構築・運用が可能な手軽さが魅力のチャットボットです。従来の機械学習型と異なり、AIが自動で学習と精度向上を行うため、人間による回答評価や類義語登録といった作業が不要といった特徴があります。
運用担当者の負担を軽減しつつも、ユーザーからの多様な表現にも柔軟に対応できます。ただし、AIの性能によっては応答精度に差が出るため、導入前の検証が必要です。
RAG型
RAG型チャットボットは、「検索」と「生成」のAI技術を組み合わせることで回答精度を向上し、より自然で的確な回答を提供できるタイプのチャットボットです。登録された文書の中から関連情報を検索し、それをAIが要約・生成して回答として提示します。
FAQのような専用データを整備しなくても、既存資料を活用するだけで導入が可能なため、初期準備や運用の手間を大幅に削減できるのが特徴です。複雑な問い合わせにも柔軟に対応できるといった魅力もあります。
【機能別】AIチャットボットの種類
AIチャットボットは搭載する機能によって得意分野が異なります。ここでは、FAQ型や処理代行型、配信型、雑談型の、主な4つの機能別チャットボットの特徴をわかりやすく解説します。
FAQ型
FAQ型チャットボットは、あらかじめ登録されたよくある質問(FAQ)をもとに、ユーザーの問い合わせに自動で回答する機能を備えたチャットボットです。社内の業務サポートや顧客からの質問対応など、幅広いシーンで活用されており、人的対応の手間を削減できます。
ユーザーは大量のFAQから自力で探す必要がなく、知りたい情報にすぐアクセスできる点も大きなメリットです。業務効率化や対応品質の向上にもつながります。
処理代行型
処理代行型チャットボットは、ユーザーとの会話を通じて情報を収集し、実際の業務処理まで自動で行う高機能なチャットボットです。たとえば、ホテル予約やイベント申し込みでは、氏名・連絡先・希望日時などを聞き出し、そのまま予約システムに情報を反映させます。
人の手を介さずに処理が完了するため、ユーザーの利便性が向上し、企業側も業務負担の大幅な軽減が可能になります。予約業務以外にも幅広い自動処理に応用可能です。
配信型
配信型チャットボットは、情報を一方的に届けることに特化したチャットボットです。たとえば、キャンペーンやセール、新商品の発売などの告知をチャット形式でリアルタイムに配信でき、ユーザーとの距離感を縮める効果も期待できます。
また、購入商品の配送予定日を自動で通知したり、社内では会議前のリマインド通知としても活用可能です。メルマガの代替手段としても有効で、効率的な情報伝達や顧客との継続的な接点づくりに貢献します。
雑談型
雑談型チャットボットは、ユーザーとの自然な会話を楽しむことを目的としたチャットボットです。直接的な売上に貢献するわけではありませんが、ユーザーに親しみや安心感を与えることで企業への好感度を高める効果があります。
たとえば、気軽なやり取りのなかでユーザーが企業のファンになれば、将来的に商品やサービスの購入につながる可能性も見込めます。ブランディングや顧客ロイヤリティの向上に役立つタイプのチャットボットです。
【会話の仕組み別】AIチャットボットの種類
AIチャットボットには、さまざまな会話の仕組みがあります。企業のニーズや目的に応じて、選択肢型や辞書型、ログ型など、最適なタイプを選ぶことが重要です。
本章では、各タイプの特徴と導入に適したシーンを解説します。
選択肢型
選択肢型チャットボットは、ユーザーが提示された選択肢の中から選択することで会話を進める仕組みで、質問を考える手間が省けるといった点がメリットです。
基本的にはAIを搭載しないシナリオ型チャットボットに利用されていますが、後述する辞書型と組み合わせる形でAIチャットボットにも取り入れられており、柔軟な対応が可能になります。ただし、選択肢が多くなると選びづらくなるため、問い合わせ内容が少ない場面に適しています。
辞書型
辞書型チャットボットは、あらかじめ登録されたキーワードとその答えをもとに、ユーザーの質問に自動で答える仕組みのチャットボットです。たとえば、「予約方法を知りたい」と入力すると、予約に関する情報やフォームが表示されます。
ユーザーが目的の情報に簡単にアクセスできる点が魅力ですが、キーワードとその回答を多数登録する必要があり、準備に時間と労力がかかるという側面もあります。
選択肢型×辞書型
選択肢型と辞書型を組み合わせたハイブリッド型チャットボットは、ユーザーに選択肢を提示しつつ、選択肢に該当しない場合は自由に入力させて回答を導く仕組みです。選択肢にない情報が必要な場合でも柔軟に対応できます。
しかし、選択肢の設計やキーワードの登録が必要で、問い合わせが多い場合は膨大なデータ登録と準備に時間がかかります。運用前の準備が重要で、導入には一定の手間が伴うことを覚えておきましょう。
ログ型(蓄積型)
ログ型(蓄積型)のチャットボットは、ユーザーとのやり取りから得たデータをもとにAIが自動的に回答を生成するタイプです。多くの会話を経験することで、AIはより精度の高い回答を提供できるようになります。
特に、会話が頻繁に発生する環境では、AIが効率よく学習し、問い合わせに対して自然で適切な対応ができるようになります。しかし、会話が少ない場合は学習が進みにくく、精度向上が見込めないため、活発なやり取りが期待される場面での導入が理想的です。
AIチャットボットの選び方のポイント
AIチャットボットを導入する際は、目的に合った機能や使いやすさ、サポート体制などを見極めることが重要です。選定時に特に注目すべきポイントについて解説します。
AIチャットボット導入の目的と目標を明確に設定する
AIチャットボット導入の成功には、目的と目標を明確に設定することが不可欠です。「カスタマーサポートの効率化」や「予約業務の自動化」、「有人対応を20%削減する」など、具体的な目的と達成したい目標を設定します。
目的を明確にすることで、必要な機能を備えたサービスを見つけやすくなり、導入後の成果を測定する基準にもなります。
自社に必要な機能を搭載しているサービスを選ぶ
現在、多くの企業がAIチャットボットサービスを提供していますが、各サービスは搭載している機能や得意とする業務が異なります。そのため、自社の導入目的や目標に合ったものを選ぶことが重要です。
たとえば、カスタマーサポートの効率化を目指すならFAQ対応機能が充実したサービスを選び、予約業務の自動化を望む場合は処理代行機能に強みを持つものが適しています。自社に必要な機能を把握した上で、最適なサービスを選定することで、効果的な導入が可能になります。
操作しやすいサービスを選ぶ
AIチャットボットは導入して終わりではなく、運用中にもFAQの更新やログの確認など、社内での操作が必要になります。そのため、ITに詳しくない担当者でも直感的に操作できる、管理画面がわかりやすいサービスを選ぶことが大切です。
誰でも簡単に扱える設計であれば、社内での活用が進み、導入の効果も高まります。初めて使う人でも迷わず操作できるかを、無料トライアルなどで確認するとよいでしょう。
予算の範囲内で収まるかを確認する
AIチャットボットの導入には、初期費用として10万円以上がかかるケースが一般的です。また、月額費用や運用コストも発生するため、予算内に収まるかを事前に確認しておくことが重要です。
特に、AI搭載型のチャットボットは、性能やカスタマイズの度合いにより費用が大きく異なるため、導入前に必要な機能とコストの見積りを確認する必要があります。
さらに、運用コストを回収できるかどうかも重要な判断材料です。費用対効果をしっかりと検討し、自社の予算に見合った最適なサービスを選びましょう。
サポートの有無を確認する
AIチャットボットサービスを選ぶ際には、サポート体制の有無をしっかりチェックしましょう。サービスによっては、導入前の設定サポートや、導入後のトラブル対応を提供しているところもあります。
特に、社内にAIチャットボットに詳しい担当者がいない場合、充実したサポートがあるサービスを選ぶのも一つの手です。運用開始後も、利用状況の分析や低利用率の改善提案など、継続的なサポートを行ってくれるベンダーを選ぶことで、運用の成功につながりやすくなります。
無料トライアルを活用する
AIチャットボットサービスを選ぶ際、無料トライアルを活用することは非常に有効です。トライアルを通じて、実際にサービスを操作し、自社に合うかどうかを確認しましょう。
重要な確認ポイントは、チャットボットがどのような機能を提供しているか、料金体系が自社の予算に見合うか、実際にどれほど簡単にチャットボットを構築できるか、そして運用・改善にどれくらいの工数がかかるかです。実際に体験することで、導入後のギャップを最小限に抑えられます。
AIチャットボットのメリットとデメリット
AIチャットボットは、24時間対応やコスト削減などのメリットがある一方で、導入コストや運用の難しさといったデメリットも存在します。
本章では、導入検討の際に参考になる、AIチャットボットのメリットとデメリットを詳しく解説します。
メリット
AIチャットボットのメリットは多岐にわたります。
まず、複雑な問い合わせにも対応できるため、顧客の多様なニーズに応えることが可能です。また、運用時間が増えることで回答精度が向上し、より適切で自然な対応が可能になります。
さらに、24時間365日の対応ができるため、営業時間外でも顧客対応が途切れることなく、機会損失の防止や人的リソースの削減にも効果的です。加えて、多言語対応ができるため、海外からの問い合わせにも柔軟に対応できる点も大きな強みです。
デメリット
AIチャットボットにはメリットがある一方で、いくつかデメリットもあります。
まず、導入コストが従来のAI非搭載のチャットボットよりも高くなる傾向があるうえ、運用には定期的なメンテナンスや更新作業が発生し、継続的なコストがかかります。
さらに、運用開始後も精度向上のための調整や学習が必要になるほか、プライバシー保護やセキュリティ対策など、顧客情報を扱う場合は十分な対策が必要です。これらの点を考慮して、導入と運用を慎重に進める必要があります。
AIチャットボット導入時の注意点
AIチャットボットは便利なツールですが、導入すればすぐに効果が出るわけではありません。導入前に注意すべき点を理解しておくことで、スムーズな運用と期待する成果につなげることができます。
導入開始までには時間と手間がかかりやすい
AIチャットボットを導入する際、データの登録や表記統一などの設定が必要です。これらの作業は、AIの応答精度を高めるために欠かせませんが、その分時間と手間がかかります。
初期段階では、回答精度が十分に向上するまで公開することが難しく、運用開始までに時間がかかるのが一般的です。したがって、導入前には必要な準備期間を見積もり、計画的に進める必要があります。
複雑な質問には回答できない場合がある
AIチャットボットは、学習したデータに基づいて応答を行いますが、その学習には限界があります。特に、細かいニュアンスや感情的な部分を正確に理解するのは難しく、複雑な質問や状況に対応できない場合があります。
このような場合、AIチャットボットだけで解決できないことがあるため、有人対応に切り替えるなど、柔軟な対応策を事前に準備しておくことが重要です。
個人情報や機密情報の取り扱いには気を付ける
AIチャットボットを導入する際には、個人情報や機密情報の取り扱いに細心の注意を払う必要があります。一部のAIツールでは、ユーザーからの入力データを学習に使用することがあり、これが情報漏洩のリスクを高める可能性があります。
サービスを利用する前に、必ず利用規約やプライバシーポリシーを確認し、個人情報の取り扱い方法やデータ共有範囲を把握しておきましょう。また、顧客データや機密情報を登録しないように注意し、入力する内容が適切であるか再確認する習慣を身につけることが重要です。
AIチャットボットの導入事例
AIチャットボットは、業種や目的によって多様な形で活用されています。ここでは、実際に導入された企業や自治体の事例を紹介します。
お客様からの問い合わせに24時間365日対応|株式会社商船三井さんふらわあ
株式会社商船三井さんふらわあでは、フェリー利用者からの多様な問い合わせにスムーズに対応するため、AIチャットボット「AIさくらさん」を導入しました。
Webサイトでは運賃や予約方法、設備に関する質問に24時間365日自動応答が可能となり、コールセンターの営業時間外にも対応できる体制を整備。スタッフの負荷軽減に加え、顧客満足度アップを実現しています。
また、ターミナルでは非接触案内を実現し、コロナ禍での安全な接客にも貢献。今後は蓄積された顧客データを活用し、さらなるサービス向上を目指しています。
ITヘルプデスクへの社内問い合わせが半減|キンコーズ・ジャパン株式会社
キンコーズ・ジャパン株式会社では、社内ITヘルプデスクへの問い合わせが集中していた課題を解決するため、AIチャットボット「OfficeBot」を導入しました。
チャットボットを活用し、定型的な質問への自動応答や、複数部署に分散していた問い合わせ先の一本化、FAQへの誘導などを通じて対応業務を効率化。結果として、ITヘルプデスクへの問い合わせを50%削減する効果を得られました。
今後も継続的なFAQの更新により、利用率のさらなる向上を目指しているそうです。
市政に関する質問への回答をAIチャットボットが担当|川崎市
川崎市では、市民サービスの利便性向上を目的に、2021年3月よりAIチャットボットを導入しました。市役所の開庁時間外でも、24時間365日対応可能で、ごみの分別やイベント情報、窓口の混雑状況など幅広い市政関連の質問に自動で回答できます。
市公式サイトやLINEから簡単にアクセスでき、利用者の自己解決を促進。今後は国・地方共通相談チャットボット「Govbot(ガボット)」との連携を通じ、国・自治体共通の課題解決への貢献が期待されています。
おすすめのAIチャットボットサービス5選
AIチャットボットを導入する際は、自社の目的や体制に合ったサービス選びが重要です。ここでは、機能や使いやすさに定評のあるおすすめのチャットボットを5つご紹介します。
Chat Plus|チャットプラス株式会社

Chat Plus(チャットプラス株式会社)は、10,000社以上の導入実績を誇るAIチャットボットサービスです。月額1,500円(税別)から始められ、初期費用は不要。業界別のシナリオテンプレートが用意されており、専門知識がなくても簡単に設定が可能です。
AIによるFAQシステムも搭載されており、ユーザーの自己解決を促進し、運用の手間を軽減できます。詳細なレポート機能に加え、手厚いサポート体制が整っている点も魅力です。10日間の無料トライアルが用意されているため、まずはお試し感覚で利用してみると良いでしょう。
BOTCHAN AI|株式会社wevnal

BOTCHAN AI(株式会社wevnal)は、生成AIと企業独自データを活用し、オンライン接客を自動化できるチャットボットサービスです。公式サイトやLINEなど複数チャネルに対応し、24時間リアルタイムで顧客の疑問に応答。
直感的なUIと、AIと有人対応を切り替えられるハイブリッド設計や、Azure Open AIを利用した安心のセキュリティ面も魅力です。導入後は、専属のカスタマーサクセス部署による対応など、サポート体制も整っています。料金やトライアルは要問い合わせが必要です。
AIチャットボットさくらさん|株式会社ティファナ・ドットコム

AIチャットボットさくらさんは、社内外の問い合わせ対応を自動化し、業務効率を大幅に向上させるAIツールです。生成AIによるFAQの自動作成機能を搭載し、PDFや画像をアップロードするだけで簡単に運用が可能。
1日最大3万件の問い合わせに対応でき、有人チャットとの連携により複雑な質問にも柔軟に対応します。また専任のサポートチームによる手厚い支援があり、初めての導入でも安心です。多様なニーズに応じたカスタマイズにも対応しています。
OfficeBot|ネオス株式会社

OfficeBotは、企業内の膨大な社内資料を活用して、高精度な回答を行う法人向けAIチャットボットです。管理画面から資料をアップロードするだけで、企業専用の生成AIが構築され、総務・人事・情報システム部門などの問い合わせ対応を自動化できます。Azure OpenAI Serviceと連携し、高い検索精度とセキュリティを両立している点も魅力です。
また、専任のカスタマーサクセスが導入・運用を支援するサポート体制が整っているため、レクチャーを受けながら運用方法を習得できます。公式サイトにて、無料のデモを試すことができるため、事前に活用してみると良いでしょう。
zeals|株式会社ZEALS

参考:zeals 公式サイト
zealsは、LINEを活用したチャットコマースを支援するAIチャットボットで、ユーザーの潜在ニーズを引き出し、パーソナライズされた「おもてなし体験」を提供します。
完全成果報酬型で、初期費用や月額料金は一切不要です。専属のコミュニケーションデザイナーが会話設計を担当し、高度な接客体験を構築します。
また、導入工数はほぼゼロで、専任のサポート体制も完備。CRMなどの基幹システムとも連携可能で、LTV最大化にも貢献します。
自社に最適なAIチャットボットを活用して、成果の最大化を目指そう
本記事では、AIチャットボットの基本から機能・会話形式ごとのタイプ、自社に最適なサービスの選び方や導入事例などを解説しました。
現在AIチャットボットは、単なる問い合わせ対応にとどまらず、マーケティングや接客など多彩なシーンで活用が進んでいます。導入にあたっては、目的に合ったチャットボットのタイプやサポート体制、費用体系などをしっかりと比較・検討することが重要です。
自社の課題に最適なツールを見極め、成果を最大化する一歩を踏み出しましょう。


