生成AIで人事労務の業務を効率化|活用シーンや導入事例を紹介
公開日 2025/09/18
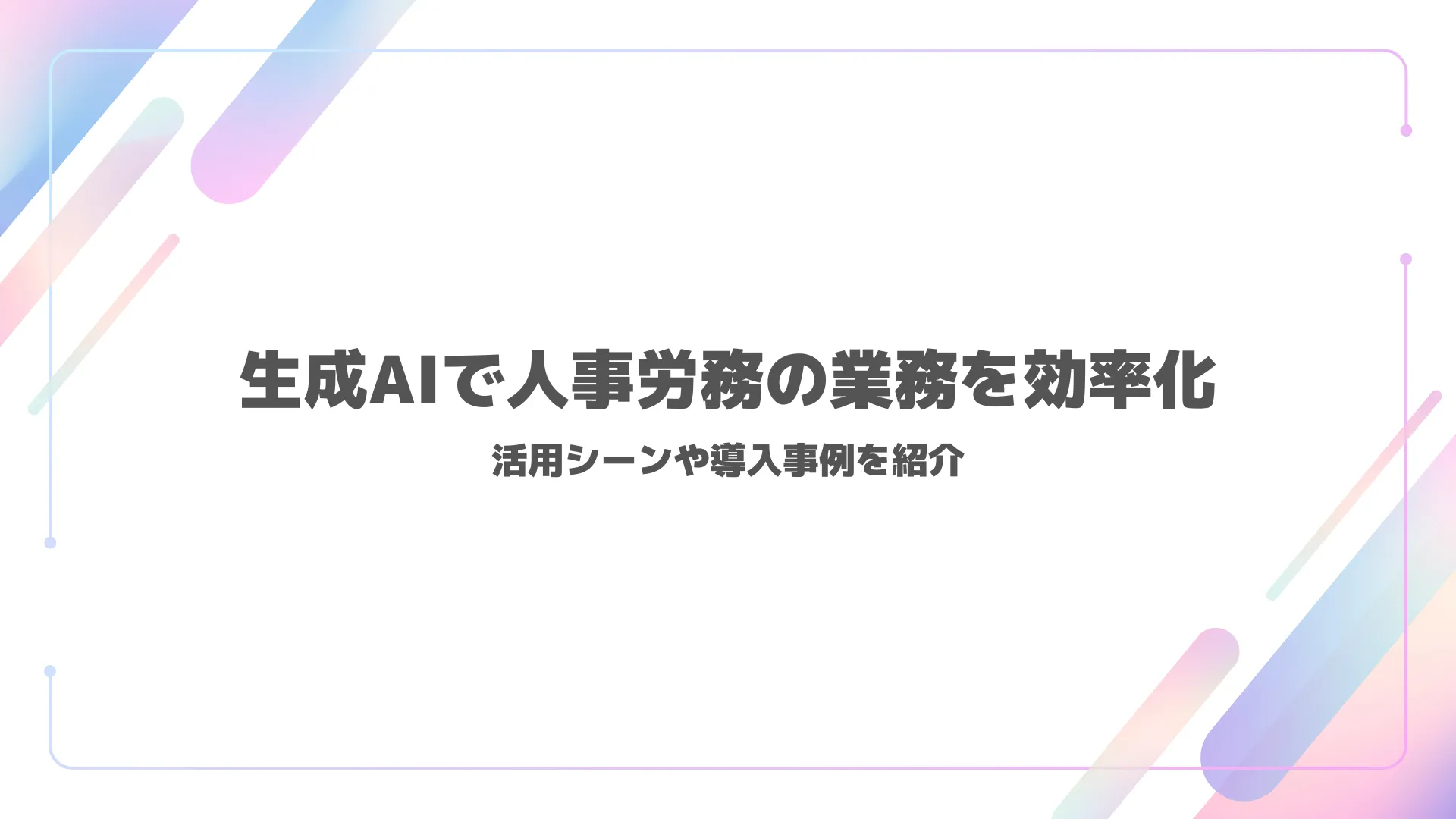
「人事労務の業務負担を減らしたいが、生成AIの導入方法や活用場面が分からない」といった悩みを抱えている方は多いでしょう。
生成AIは採用文書の作成や社内FAQ対応など、人事労務のルーティン業務を効率化できる強力な手段です。人材不足への対応や従業員満足度の向上にもつながるため、多くの企業が導入を進めています。
この記事では、人事労務の業務における生成AIの活用シーンや導入事例、導入時の注意点、さらにおすすめのツールについて紹介します。
目次
生成AIとは
生成AIとは、文章や画像、音声、動画などのコンテンツを新たに作成できる人工知能のことです。
従来のAIが既存のデータをもとに情報を返すのに対し、生成AIは未整理の情報をもとに創造的な出力ができる点が大きな違いです。たとえば、質問に対して自然な文章で回答を生成したり、対話形式で業務をサポートしたりすることが可能です。また、学習を重ねることで出力の品質を向上させられる点も特徴で、継続的に精度を高められます。
現在では、単なる文章作成だけでなく、ビジネスシーンにおける活用も進んでおり、人事労務業務の効率化に貢献する手段としても注目を集めています。
人事労務の仕事で生成AIを活用できる場面
人事労務業務では、採用から社内研修、キャリア支援、問い合わせ対応まで、定型的かつ情報処理を必要とする多くの業務が存在します。生成AIは、そうした場面において業務の自動化や効率化を支える強力なツールとして活用されています。
採用業務に関する文書の自動作成
生成AIは、雇用契約書や採用通知書、求人票といった採用時に必要な文書の作成に活用されています。これまで担当者が一から作成していた文書も、基本的なテンプレートと必要な情報を入力するだけで、短時間で生成することが可能です。
また、履歴書の内容をもとに候補者の特徴を分析し、面接時に適切な質問を作成する用途でも役立ちます。人材の選定や評価を迅速に行えるため、採用プロセス全体の効率化につながります。
社内研修資料の作成・テーマの考案
生成AIは、社内研修で使用するスライド資料やマニュアルの作成にも有効です。業種や職種、受講者のレベルに合わせて内容を調整したうえで、分かりやすく構成された資料を短時間で作成することが可能です。
さらに、企業の課題や従業員のスキル状況をもとに、適切な研修テーマの提案や、個別育成計画の策定も行えます。従業員の成長に合わせた研修を実現することで、教育の質と効果の向上が期待できます。
キャリアパスの相談
働き方の多様化が進むなか、従業員一人ひとりに合わせたキャリアパスの提案が求められています。生成AIは、従業員の過去の業績や評価、取得しているスキルなどの情報を分析し、適性や目標に沿ったキャリアの方向性を提示できます。
これにより、上司や人事担当者が判断に迷う場面でも、一定の指針を得ることが可能となり、従業員の成長意欲を引き出すサポートに役立ちます。キャリア面談や配置転換の場面でも活用が進んでいます。
社内規定やマニュアルの作成・要約
生成AIは、社内規定や業務マニュアルの草案作成にも活用されています。あらかじめ必要な情報やルールを入力することで、制度の概要を整理し、分かりやすく構成された文書を短時間で作成できます。
また、既存の文書が長文で読みにくい場合には、重要なポイントを要約し、伝わりやすい表現に変換することも可能です。文章の読みやすさを向上させたいときや、新入社員向けの資料作成にも効果的です。
FAQの作成・問い合わせ対応
人事労務部門では、給与計算や勤怠ルール、福利厚生などに関する問い合わせが日常的に発生します。生成AIを活用することで、過去の問い合わせ履歴や社内規定をもとに、自動で回答文を生成することが可能になります。
また、よくある質問に対するFAQの草案を作成し、担当者がチェック・編集する形で効率的に整備できます。AIが基本対応を行うことで、担当者は複雑なケースや判断が必要な内容に集中でき、対応品質の向上にもつながります。
参考:FAQを最適化するAIチャットボット|IZANAI Powered by OpenAI
生成AIを人事労務の現場に導入するメリット
生成AIを導入することで、定型業務の効率化や人的負担の軽減が可能となります。加えて、24時間対応や従業員満足度の向上といった面でも効果を発揮し、より戦略的な人事労務業務への移行を促します。
業務の効率化と人手不足の解消
生成AIは、履歴書のスクリーニングや一次面接の対応といった採用業務を自動化することで、業務効率を大きく向上させます。
また、社内ルールに関するよくある質問への対応もAIに任せることで、担当者の負担を軽減できます。これにより、長時間労働の抑制や人的リソースの最適化が図れ、人手不足への対策としても有効です。業務全体のスピードが上がることで、迅速かつ的確な人事判断が可能になります。
参考:FAQを最適化するAIチャットボット|IZANAI Powered by OpenAI
AIでは代替できない業務に集中できる
人事労務には、戦略的な人材配置や従業員の感情に寄り添う個別面談など、人間ならではの判断や対応が求められる業務が数多く存在します。
生成AIの導入によって、こうした業務以外の定型的な作業をAIに任せることで、担当者は本来注力すべき高度な業務に集中しやすくなります。AIと人の役割分担を明確にすることで、人事の専門性を活かした意思決定が可能となり、組織の信頼性や対応力の向上にもつながります。
24時間体制での対応が可能
生成AIを活用すれば、社内外からの問い合わせに対して24時間体制での対応が可能になります。
たとえば、勤怠や給与、各種手続きに関する質問に対し、深夜や休日であっても即座に回答できる環境を整えることができます。これにより、対応の遅延による業務の停滞を防ぎ、従業員からの信頼性も向上します。
また、担当者の勤務時間外に発生した問い合わせにも自動で初期対応できるため、働き方改革の一環としても効果的です。
従業員満足度の向上
生成AIを活用することで、従業員一人ひとりのニーズに合わせたキャリア提案や研修内容のパーソナライズが可能になります。これにより、従業員は自分に合った支援を受けられるようになり、成長への実感や納得感が高まります。
また、問い合わせ対応の迅速化や必要書類の自動作成など、日常業務におけるストレスを軽減することも、満足度の向上に直結します。結果として、離職率の低下やエンゲージメントの向上にもつながります。
人事労務で生成AIを導入する流れ
生成AIを導入する際には、業務内容の整理から検証・修正まで、段階的な準備と実行が重要です。業務の特性や社内体制に合わせて、計画的に導入を進めることが成功の鍵となります。
1. 人事労務の業務内容の整理
生成AIの導入にあたっては、まず人事労務部門で日常的に行っている業務を洗い出すことが出発点です。
とくに、ルーティン業務や定型的な処理が多い業務はAIとの相性が良く、導入効果を得やすい対象です。この段階で、業務ごとの目的やフローを明確にしておくことで、AIにどの部分を担わせるかが判断しやすくなります。将来的な拡張も見据え、業務の棚卸しを丁寧に行うことが求められます。
2. 必要なデータのリストアップ・準備
業務をAIで対応するには、まずAIが学習・処理するためのデータを整理・準備する必要があります。
手順1で整理した業務に対し、関連するマニュアル、過去の対応履歴、社内規定などをリストアップします。これにより、どの業務にどのようなデータが必要かを事前に把握でき、後のAI学習や精度向上に役立ちます。情報の所在や形式を統一しておくことも、導入後の運用をスムーズにするために重要です。
3. 業務手順の具体化
生成AIを活用するためには、対象業務の手順を具体的に定義する必要があります。
人事担当者が日常的に行っている作業の流れを、一つひとつのステップに分けて明文化することで、AIへの指示内容を明確にできます。このプロセスは、新しく配属された社員に業務を教える感覚に近く、AIにとっても学習や処理の精度を高める土台となります。業務の属人化を防ぐ意味でも、この工程は非常に重要です。
4. 生成AIの開発
業務内容と必要データが整理できたら、次は生成AIの開発フェーズに入ります。具体的には、社内データを活用するためのデータ基盤を構築し、生成AIが使いやすい形式で処理できるように整備します。
この作業は自社内で行う場合もありますが、多くの企業では専門の開発会社やツールベンダーに委託するケースが一般的です。外部ツールとの連携やセキュリティ面の設計も、この段階でしっかり対応しておく必要があります。
5. 検証・修正
生成AIの初期構築が完了したら、実際の業務で試験的に運用し、その結果をもとに改善を行います。
現場の担当者に使ってもらい、操作性や精度、実用性についてフィードバックを収集することが重要です。利用中に生じた課題や使いにくさを洗い出し、再学習や設定の見直しを重ねることで、業務により適したAIシステムへと仕上げていきます。この検証と修正のサイクルが、安定運用の鍵を握ります。
人事労務の仕事で生成AIを導入するときの注意点
生成AIの導入には多くのメリットがありますが、個人情報の扱いや誤情報のリスクなど、適切な運用に向けて注意すべき点も存在します。導入前にリスクを把握し、対策を講じることが不可欠です。
個人情報・社外秘の情報の漏洩リスク
生成AIは、入力された情報をもとに学習・出力を行う特性があります。そのため、個人情報や社外秘の情報を不用意に扱うと、意図せず外部に漏洩するリスクが生じます。
とくにクラウド型のAIサービスを利用する場合には、不正アクセスやサイバー攻撃によって情報が流出する危険性も否定できません。こうしたリスクを回避するには、情報の取扱範囲を明確にし、利用するAIサービスのセキュリティ対策や利用規約を十分に確認することが重要です。
誤った情報が生成される可能性がある
生成AIは、大量の情報をもとに関連性の高い言葉を予測して出力を行いますが、その性質上、必ずしも正確な情報を返すとは限りません。特に運用開始直後は、学習データの偏りや設定ミスにより、誤った内容を生成する可能性が高くなります。
このような誤情報が社内に広まると、従業員の混乱や誤った手続きの実行といったトラブルにつながるおそれがあります。初期導入段階では、人によるチェック体制を整えることが不可欠です。
著作権を侵害していないか確認する
生成AIが出力する文章や画像は、既存の著作物に似た表現や構成を含む場合があります。そのため、AIが生成した内容が意図せず他者の著作権を侵害してしまうリスクが存在します。
特に、社内資料や公開文書にAI生成コンテンツを使用する際は、十分な注意が必要です。著作権のトラブルを避けるためには、生成したコンテンツをそのまま使用せず、必要に応じて修正を加えること、また利用目的に応じて著作権の確認を行うことが求められます。
人事労務の仕事で生成AIを導入した事例
実際に生成AIを人事労務に導入している企業では、業務時間の削減や対応品質の向上といった成果が報告されています。ここでは、3社の導入事例を紹介します。
株式会社吉野家|AI面接の導入で店長の負担を軽減
株式会社吉野家では、店舗の採用活動にかかる負担を軽減するため、生成AIによるAI面接を導入しました。これにより、応募者の基本的な情報収集や適性の初期評価をAIが担うようになり、店長が対応する面接件数が大幅に減少しました。
また、AIが一貫した基準で対応することで、採用のばらつきが抑えられ、判断の公平性も向上しています。今後はより高度な面接サポートや、採用後の教育支援への応用も期待されています。
参考:AI面接の導入は、応募者側のニーズに寄り添うために | SHaiN | 場所と時間はあなたが決める!AI面接サービス
福島市|過去の異動関連データ・関連データをもとに人事異動案を作成
福島市では、職員の異動に関する業務の効率化と公正性の確保を目的に、生成AIを活用した人事異動案の作成を開始しました。AIは過去の人事異動データや職員のスキル、所属部署の実績などをもとに、最適な異動案を自動で提示します。従来は時間と労力を要していた人事異動の検討が、データに基づく客観的かつ迅速な判断に変わり、職員配置の適正化にも寄与しています。今後は他部門への展開も視野に入れた取り組みが進められています。
参考:人事異動AI支援ソリューション: 自治体ソリューション | NECソリューションイノベータ
JA全農たまご株式会社|年間1,000時間の業務削減に成功
JA全農たまご株式会社では、社内業務の効率化を目的に生成AIを導入しました。導入後は、社内問い合わせへの自動応答や文書作成の自動化が進み、年間で約1,000時間もの業務時間の削減に成功しています。担当者の負担が軽減されたことで、より重要な業務への集中が可能になり、全体の業務品質も向上しました。今後は、さらに活用範囲を拡大し、組織全体での生産性向上を目指す取り組みが続けられています。
参考:ChatAIで年間1,000時間の業務削減を実現 社内報・勉強会で利用促進、導入9ヶ月で利用者9倍へ
人事労務の業務効率化におすすめのツールを紹介
人事労務における生成AI活用をより手軽に実現するには、専用のツールを導入するのが効果的です。ここでは、実務で役立つ代表的な2つのツール「IZANAI」と「ActiBook」について紹介します。
FAQを最適化するAIチャットボット|IZANAI(イザナイ)
「IZANAI(イザナイ)」は、社内外のFAQ対応を効率化し、担当者の負担を大幅に軽減できるAI型チャットボットです。従来のFAQシステムのように、質問と回答を一つずつ手入力する必要はありません。社内資料やウェブサイトのURLを登録するだけで、AIが自動的に回答を生成するため、簡単な設定で導入できます。
曖昧な質問に対しても、サジェスト機能やAI-OCR、表読み込み機能を活用して、正確な情報へと導くことが可能です。営業サポートの現場では、製品情報やサービス内容に関する顧客からの問い合わせ対応、あるいは社内で繰り返される質問への回答において、大きな力を発揮します。
IZANAIを使うことで、営業事務は問い合わせ対応にかかる時間を削減でき、より複雑な業務や営業担当者の支援に集中することが可能です。結果として、全体の業務効率化にもつながります。
参考:FAQを最適化するAIチャットボット|IZANAI Powered by OpenAI
資料・動画を誰でも簡単に配信|ActiBook(アクティブック)
「ActiBook(アクティブック)」は、紙の資料やPDFなどをデジタル化し、社内外で共有・活用できる電子ブック作成ツールです。
人事労務の分野では、マニュアルや社内規定、研修資料などを電子化し、誰でもアクセスしやすい状態に整える用途で活用されています。閲覧ログの取得や検索機能も備えており、情報の利便性を高めながら管理コストを抑えることができます。紙資料からの脱却と業務効率化を同時に実現したい企業に適したツールです。
生成AIで人事労務業務はもっと効率化できる
生成AIは、人事労務の働き方を根本から変える力を持っています。
定型業務の効率化だけでなく、社員対応の質向上や人的リソースの最適化といった面でも、すでに多くの企業が成果を上げ始めています。導入には準備と配慮も必要ですが、リスクを正しく管理すれば、十分に大きなリターンが見込めるでしょう。
まずは小さな業務から、生成AI活用の一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。


