生成AI導入で業務効率化|成功事例や導入メリット・リスク対策を解説
公開日 2025/11/12
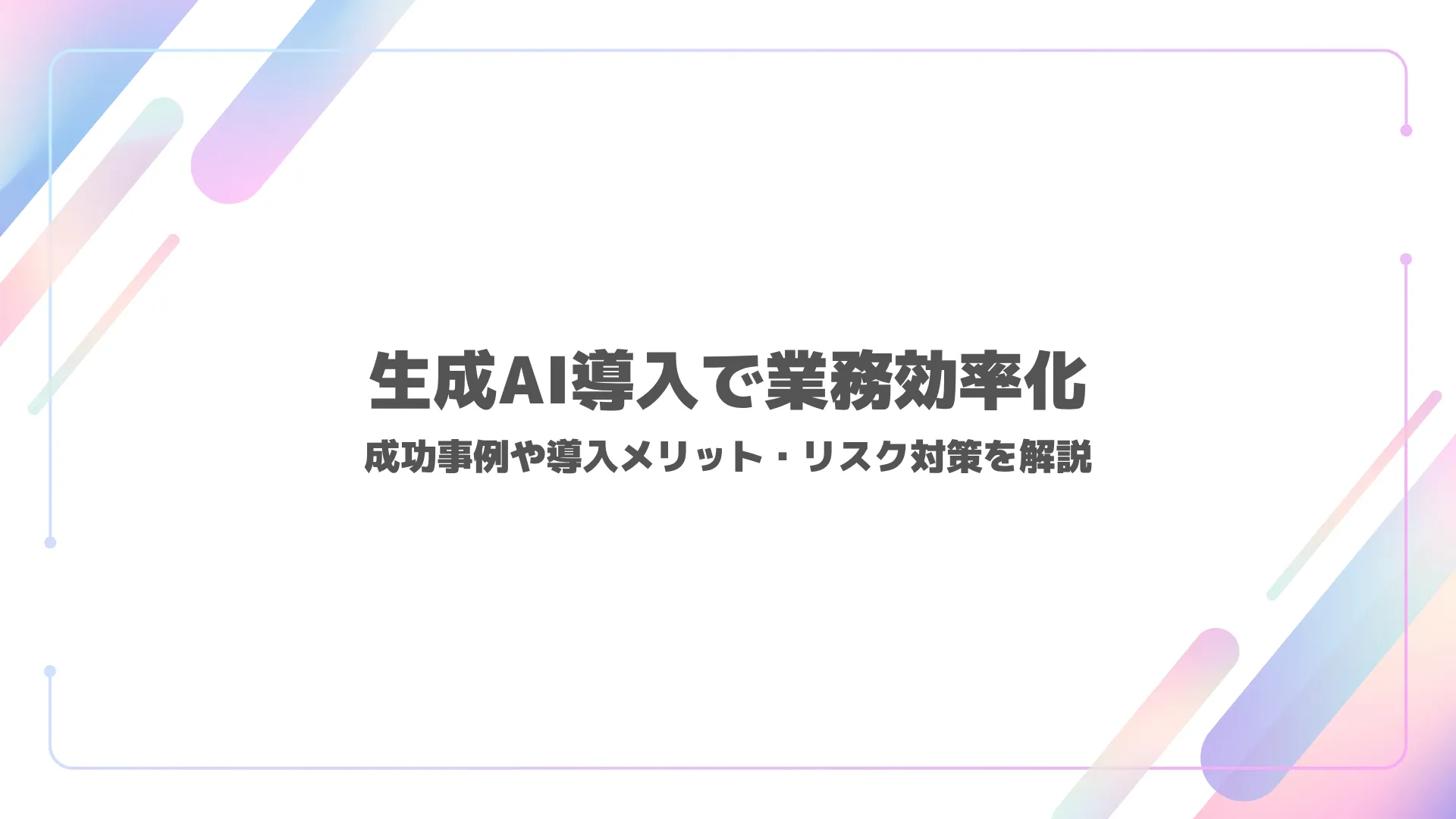
近年、文章や画像、動画などを自動生成できる「生成AI」の業務活用が急速に広がっています。
適切に導入すれば、単純業務の効率化やコスト削減につながり、企業競争力の向上につながります。一方で、誤情報や権利侵害などのリスクも存在するため、正しい理解と運用ルールが欠かせません。
本記事では、生成AIの基礎知識から具体的な活用事例、導入時の注意点とリスク対策までをわかりやすく解説します。
目次
生成AIとは?
生成AIとは、ディープラーニングを活用し、人間のように文章や画像、動画、音声といった多様なコンテンツを創り出す人工知能です。
ここでは従来AIとの違いや、業務利用が急速に広がる理由を解説します。
生成AIと従来AIの違い
生成AIは、ディープラーニングを活用してテキスト・画像・音声などの新しいコンテンツを生み出す人工知能で、創造的なアウトプットを得意とします。
これに対し従来のAIは、与えられたデータをもとに分析や予測を行い、特定のタスクを自動化することが主な役割でした。
つまり「0から1を生み出す」のが生成AI、「1をより正確に活用する」のが従来AIといえます。従来AIが判断や分類に強みを持つのに対し、生成AIは学習成果をもとに新たな表現を創造できる点で異なります。
生成AIの業務利用が急速に広がる理由
生成AIの業務利用が急速に広がる背景には、多くの企業が抱える経営課題、たとえばコスト削減や業務効率化、そして人手不足の解消への有効な解決策として注目されているからです。
生成AIは、文章や画像の生成作業を自動化し、作業時間を大幅に短縮できます。これにより、社員は定型業務から解放され、より創造的で付加価値の高い業務に集中できるようになります。また、プログラミングなどの専門知識がなくても誰でも簡単に利用できる利便性と、ChatGPTに代表されるような精度の高い生成能力が、企業での導入を後押ししました。
これらの要因が重なり、今や生成AIは単なるトレンドではなく、ビジネスの成長に不可欠なツールとして、多くの企業で導入が加速しています。
参考:ChatGPTとは?仕組み・使い方・できること・活用事例などを紹介!
その問い合わせ、AIが答えます|IZANAI(イザナイ)

毎日の問い合わせ業務に時間を取られていませんか?AIチャットボット「IZANAI(イザナイ)」は、FAQやマニュアルの情報をもとに、自動で高精度に回答する生成AIチャットボットです。ノーコードで誰でもすぐに導入でき、カスタマーサポートの定型対応を大幅に削減。
人が対応すべき「本当に重要な問い合わせ」に、もっと集中できる環境を作りましょう。
IZANAI(イザナイ)の主な特徴
- 社内資料やWebページを登録するだけで回答が可能
- PDF・Excel・WebサイトのURLなど、複数ソースを同時に学習
- FAQ整備が不十分でも、曖昧な質問に対応
- 面倒なシナリオ設計が不要
- 2週間の無料トライアル可能
参考:FAQを最適化するAIチャットボット|IZANAI Powered by OpenAI
生成AIを業務利用するメリット
生成AIを業務に活用することで、業務効率化、コスト削減、業務品質の向上など、多くのメリットを得られます。ここでは、業務に生成AIを導入する主な3つのメリットを紹介します。
業務効率化によるコスト削減
生成AIは、定型的なデータ処理や情報収集、文書作成などの繰り返し作業を効率的に自動化できる点が大きなメリットです。
従業員はAIが生成した成果物の最終確認や調整に時間をかけるだけで済み、作業時間を大幅に短縮できます。その結果、残業時間の削減や人件費の最適化につながり、限られた人的資源をより創造的で付加価値の高い業務に充てられます。
このように、日々の業務効率が積み重なることで、企業全体の運営コスト削減を実現できるのです。
業務品質の向上・標準化
生成AIは、大量のデータをもとに正確で一貫性のあるアウトプットを生成できるため、従業員の経験やスキル差に左右されない業務品質を維持できます。特に、個人の知識や経験に依存しがちな「属人化」しやすい業務を標準化するうえで、生成AIは非常に有効です。
たとえば、顧客からのFAQ対応や社内マニュアルの作成など、高い正確性が求められる分野では、生成AIが素早く質の高い回答や文書を生成することで、組織全体の業務品質向上とナレッジ共有につながります。
参考:FAQを最適化するAIチャットボット「IZANAI Powered by OpenAI」
新たな価値の創造
生成AIは、人間の発想だけでは生まれにくいアイデアを創出したり、膨大なデータを分析して新たなビジネスの可能性を発見したりすることができます。そのため、新商品やサービスの開発、新規事業の立案、さらには顧客ニーズの深掘りにもつながります。
ブレインストーミングを行う際に活用することで、従来の枠を超えた革新的なアイデアが生まれやすくなり、企業の競争力を高め、持続的な成長を支えることができます。
生成AIの業務利用の成功事例5選
ここからは企業が生成AIを活用した事例を紹介します。
パナソニックコネクト|AIアシスタントで年間18.6万時間削減
パナソニックコネクトは、業務効率化と社員のAIリテラシー向上を目的に、OpenAIの大規模言語モデルを基盤とした自社AIアシスタント「ConnectAI」を全社員へ展開しました。
従来は資料作成や調査に時間がかかることが課題でしたが、導入により自然言語で指示を入力するだけで情報整理や分析が可能となり、社員の作業効率が大幅に改善。結果として、1年間で累計18.6万時間もの労働時間削減を実現しました。
検索代替のような簡易利用から、戦略立案の基礎資料作成といった高度な業務まで幅広く活用され、生産性の向上に直結しています。
参考:パナソニック コネクト 生成AI導入1年の実績と今後の活用構想
コカ・コーラ|生成AIを使用したCMを作成
コカ・コーラは毎年恒例のホリデーCMにおいて、新たな挑戦として生成AIを活用しました。
従来は大規模な撮影体制が必要で制作コストも膨大でしたが、1995年の人気CM「クリスマス・キャラバン」をAIでリメイクし、少人数かつ効率的な制作を実現しました。公開された映像はリアルとバーチャルの境界が曖昧で、一部には「不自然で不気味」との批判も寄せられた一方、「懐かしさを感じる」と歓迎する声もあり、消費者の反応は賛否両論でした。
結果として、制作効率を大幅に高めつつ、AIが広告表現の新たな可能性を拓くことを示す象徴的な事例となりました。
参考:コカ・コーラ恒例のホリデーCM。今年は、ほっこりどころか賛否両論 | ギズモード・ジャパン
LINE|エンジニアの作業時間を1日2時間削減
LINEヤフーは、約7,000人のエンジニアを対象にAIペアプログラマー「GitHub Copilot for Business」を導入しました。同ツールは、実装したい機能や動作に必要なコードをAIが自動生成して提案するものです。
テスト導入の結果、1人あたり1日約1〜2時間の作業時間削減が確認され、正式導入に至りました。生成コードの信頼性を確保するため、複数レビューの実施やeラーニングによるルール周知も行われています。
生まれた時間は、コーディング以外の新たなサービス開発など、より創造的な業務に活用されることを目指しています。
参考:LINEヤフーの全エンジニア約7,000名を対象にAIペアプログラマー「GitHub Copilot for Business」の導入を開始|LINEヤフー株式会社
アサヒビール|社内情報検索の効率化
アサヒビールは、生成AIを活用した社内情報検索システム「Azure OpenAI Service」(日本マイクロソフト株式会社)を導入し、従業員の情報取得を効率化しています。
同ツールは、PDFやPowerPoint、Wordなどさまざまな形式の資料を横断的に検索できます。社内の膨大なデータを一括で管理できるほか、検索結果には要約も表示されるため、必要な情報へのアクセス時間を大幅に短縮することが可能です。
現在は主に研究開発部門で試験運用を行い、将来的にはアサヒグループ全社に展開することで、商品開発力の強化や業務効率向上につなげる計画です。
参考:生成AIを用いた社内情報検索システムを導入 研究所を中心に9月上旬から試験運用を開始 商品開発力強化やグループ間のイノベーション創出を目指す
株式会社サンキュー|チャットボットによるWeb投票でコスト削減
株式会社サンキューでは、従来紙で行っていた「ツエーゲン金沢総選挙」の投票をWeb化し、チャットボット「IZANAI」を活用する施策を実施しました。導入前は、各店舗で紙の投票用紙を集計し、本社でまとめる作業に大きな負担がかかっていました。
Web投票に切り替えたことで、集計やデータ化が自動化され、印刷・輸送コストの削減と業務負荷の軽減、さらには人件費の削減に成功。Web投票は現地での投票参加を促進し、投票体験の向上にもつながりました。
今後は顧客問い合わせ対応にチャットボットを活用し、業務効率化と顧客満足度向上を目指しています。
参考:「ツエーゲン金沢総選挙」を紙からWeb投票にしてコストを削減!Web上での集計・データ化を実現して業務の負担軽減にも成功|株式会社サンキュー様
生成AIの業務利用アイデア5選
生成AIは多くの分野で注目されていますが、業務効率化には具体的にどのように活用できるのでしょうか。ここでは、生成AIが特に得意とする以下の5つの活用方法を紹介します。
文書作成・資料作成
生成AIは、報告書や企画書、メールなどの文書作成を自動化し、短時間で高品質な文章を生成できます。長文の要約や多言語翻訳にも対応しており、従来は人手と時間を要していた作業を効率的に進められます。
さらに、下書きや資料の骨子をAIに任せることで、担当者は内容の精査や付加価値の高い業務に集中できるため、全体の作業時間を大幅に短縮可能です。生成AIの活用は、業務のスピードと品質を同時に高めることにつながります。
カスタマーサポート・問い合わせ対応
生成AIを搭載したチャットボットを導入することで、顧客からのよくある質問や社内FAQへの回答を自動化し、応答時間を大幅に短縮できます。
従来のルールベース型チャットボットと異なり、生成AIは学習した膨大なデータを活用して自然な文章を生成できるため、複雑な質問にも柔軟に対応可能です。また、対応内容の記録や要約も自動で行えるため、サポート業務全体の効率化につながります。
さらに24時間365日稼働できるため、顧客は必要なときに即座に回答を得られ、利便性の向上にも有効です。担当者は個別対応が必要な高度な案件に集中できるようになり、サポート品質と顧客満足度の向上が見込めます。
参考:AIチャットボットで社内外の問い合わせを効率化|IZANAI(イザナイ)
マーケティング・コンテンツ制作
生成AIは、広告コピーやSNS投稿、ブログ記事に加え、画像や動画といったマーケティング素材の生成を自動化し、クリエイティブ制作にかかる工数を大幅に削減できます。さらに、SEOを意識した文章作成や多言語翻訳にも対応でき、国内外に向けた発信の効率化にも有効です。
AIが作成した素材を基に調整や改善を加えることで、短時間で質の高いコンテンツを制作でき、スピードと品質を両立したマーケティング活動を実現できます。
データ分析・集計
大量のデータの短時間での分析や、レポート生成の自動化にも生成AIが役立ちます。特に、売上や市場動向の集計、競合調査、消費者行動の分析など、人手では時間と労力がかかる作業を効率化でき、迅速な意思決定をサポートします。
さらに、膨大な情報をもとに従来の視点では見落としがちな傾向やインサイトを抽出することも可能です。精度の高いデータ活用によって、より効果的な戦略立案や業務改善につなげられます。
プログラミング・コード生成
プログラムコードの自動生成やバグ修正、テストコード作成など、開発業務全体の効率化にも、生成AIの活用が効果的です。自然言語で要件を入力するだけでAIがコードを生成できるため、従来の手作業によるコーディングの負担を大幅に軽減できます。
さらに、リアルタイムでエラーチェックやセキュリティ問題の検出も可能。品質を維持しながら開発速度を向上できます。
生成AI導入時の注意点
生成AIは業務効率化に役立つ一方、使用する際には注意が必要です。ここでは、実務での活用時に押さえておきたいポイントを解説します。
機密情報・個人情報は入力しない
生成AIに社内の機密情報や個人情報を入力すると、それがAIの学習データとして活用され、他のユーザーの回答に反映される可能性があります。そのため、顧客情報や従業員データ、企業機密などの重要情報は絶対に入力しないことが重要です。
安全に活用するためには、入力情報を厳密に区別し、従業員にルールを周知する必要があります。また、学習データとして利用されないビジネス向けサービスや、閉域環境の導入も検討するとよいでしょう。
ハルシネーションがないか確認する
生成AIは内容を理解しているわけではなく、見た目が正確に見える文章を生成するだけです。そのため、実際には存在しない情報や誤ったデータをあたかも事実のように提示する「ハルシネーション」が発生することがあります。
特に専門性やリアルタイム性が求められる情報では精度が低くなりがちです。生成AIを業務で活用する際は、出力内容の真偽を人の手で必ず確認し、ファクトチェックを徹底しましょう。
著作権・知的財産権侵害に注意する
生成AIは、既存の著作物に類似したコンテンツを生成することがあり、知らず知らずのうちに知的財産権を侵害するリスクがあります。特に、生成された文章や画像が特定の著作物に依拠していた場合、著作権侵害と判断される可能性が高まります。
商用利用を検討する際も、生成物が第三者の権利を侵害していないか確認することが不可欠です。AI生成物の利用では、権利関係に十分注意し、必要に応じて編集やオリジナルデータでの学習モデルを活用しましょう。
生成AIを積極的に活用して業務効率化を図ろう
生成AIは文書作成や資料作成、カスタマーサポート、マーケティング、プログラミングなど、幅広い業務を効率化できる革新的なツールです。本記事で紹介した企業事例からも、作業時間削減や業務品質向上、新たな価値創造への活用が進んでいることがわかります。
導入にあたってはリスクへの配慮も大切ですが、適切に活用を進めることで、業務効率化や生産性向上につながります。
この記事でご紹介した内容を参考に、生成AIを取り入れて業務の効率化を図り、ビジネスの成長につなげてみてください。


