情報システム部門(情シス)でのAIの活用法|役立つ場面や導入の流れを解説
公開日 2025/11/12
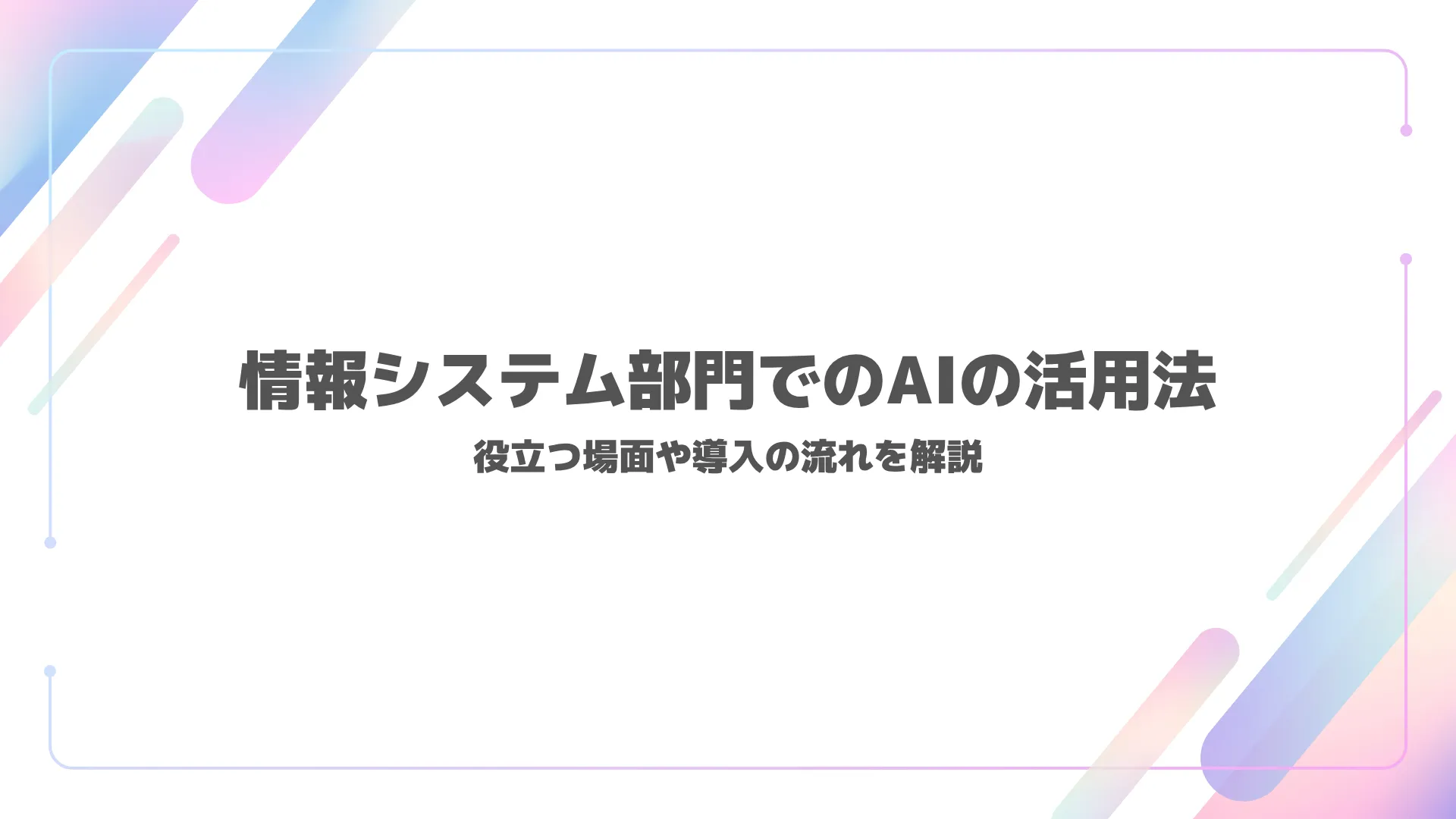
企業のIT活用が進むなか、情報システム部門(情シス)はシステムの安定稼働からセキュリティ対策、社員からの問い合わせ対応まで幅広い役割を担っています。しかし、限られた人員で膨大な業務をこなさなければならず、業務負担の増加や人材不足が大きな課題となっています。
こうした状況を解決する手段として注目されているのがAIの活用です。
この記事では、情報システム部門におけるAI活用の具体的な場面や、導入の流れについて解説していきます。さらに、AIを活用する時の注意点や実際の成功事例、役立つツールなども紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
目次
情報システム部門(情シス)とは
情報システム部門(情シス)とは、企業内の情報システムやIT環境を総合的に管理する重要部署です。主な業務は以下の通り、多岐に渡ります。
- 社内システムの開発・管理
- サーバーやPCなどIT機器の運用・保守
- セキュリティ対策の実施
- 企業の成長を支えるIT戦略の立案と実行 など
業務部門が効率的に成果を出せるよう、最適なシステムを提供・改善することが情シスの大きな役割です。
一方で、日常的なヘルプデスク対応やインフラ維持など定型業務も多く、慢性的な人手不足に陥りやすい点が課題とされています。そのため近年では、AIや自動化ツールを活用し、限られたリソースの中で生産性を高める取り組みが求められています。
情報システム部門(情シス)がAIを活用できる場面
情報システム部門では、AIをどのように活用できるのでしょうか?ここでは、以下の主な7つの活用場面について解説します。
参考:情報システム部門(情シス)の業務効率化を進めるには?DXとの違いや具体的な方法を解説
社内問い合わせへの対応
情報システム部門には「PCが動かない」「プリンタ設定が分からない」といった日常的な問い合わせが頻繁に寄せられます。こうしたよくある質問にAIを活用すれば、チャットボットでの自動応答が可能になり、社員はスピーディに問題を自己解決できます。
一方、担当者は繰り返し作業から解放され、より高度な課題への対応やIT戦略立案に時間を使えるようになります。
マニュアルの作成・更新
社内システムの利用方法やトラブル対応をまとめたマニュアルやFAQの作成は、情報システム部門にとって負担の大きい業務です。AIを活用すれば、既存資料や対応履歴を学習して、その内容をもとに文章を自動生成できるため、効率的にマニュアルを整備・更新できます。
また、情報を一元管理できるため、更新が必要な箇所を素早く反映でき、常に最新の状態を保つことが可能です。結果として社員が自己解決しやすくなり、情シスへの問い合わせ削減にもつながります。
システムの運用・保守
社内システムの運用・保守に関する業務の一部にAIを活用する機会も増加しています。
システムの運用・保守では、トラブル対応や障害復旧など負荷の高い業務が多く発生します。AIを活用してログや監視データをもとに初期診断を行い、過去事例を参考に最適な対応手順を自動提案することが可能です。これにより、ダウンタイムを短縮し人的ミスも削減できます。
さらに定期的な運用レポートの自動生成なども行えるため、担当者の負担を軽減し、より戦略的な業務に集中できる環境づくりにも役立ちます。
プログラミング
AIにはプログラミングコードの生成を得意とするものがあり、定型的なコードや草案を自動で作成できます。情シス担当者はこの生成コードをもとに、設計や複雑なロジックの構築に集中できるため、工数削減や人的ミスの低減に役立ちます。
ただし、最終的な品質確認やバグ修正は人間のチェックが必要です。AIはあくまで補助ツールとして活用することで、効率的かつ高品質なシステム開発を支える役割を果たします。
セキュリティ対策
AIはセキュリティ対策にも活用できます。
AIでは事前に学習したセキュリティリスクの兆候やパターンをもとに、社内ネットワークやシステムの脆弱性を診断できるため、リスクを把握しやすくなります。さらに、ユーザーの行動データを分析して潜在的なリスクを評価することも可能です。
そのため、未知のサイバー攻撃や脅威を早期に発見でき、対策を迅速に講じられます。情報システム部門のセキュリティ管理の、より効率的かつ効果的な強化につながります。
報告書の作成・要約
情報システム部門では、システムトラブル発生時に上層部や関連部署へ状況を報告する必要があります。AIを活用すれば、インシデントの内容や影響範囲、時系列を整理し、報告書のドラフトを自動で作成・要約できます。
これにより、担当者は報告書作成にかかる時間を削減し、迅速な状況把握や対応策の検討といった、より重要な業務に集中可能です。AIの導入は、業務効率化だけでなく、意思決定のスピード向上にも貢献します。
IT戦略・企画書の草案の作成
情報システム部門では、全社的なIT戦略や新規ツール導入の企画などを立案する必要があります。AIに目的や予算、背景情報を伝えることで、企画書の骨子や導入スケジュールのたたき台を作成可能です。
ゼロから考える手間を省けるため、担当者は分析や検討、他の重要業務に時間を割くことができ、より効率的かつ創造的な戦略立案に取り組めます。
情報システム部門(情シス)でAIを活用するメリット
情報システム部門においてAIを活用すると、人手不足の解消や属人化の防止など、様々な効果が期待できます。ここでは、具体的なメリットをわかりやすく解説します。
人手不足の解消
情報システム部門は、日常の運用や問い合わせ対応など業務量が多く、人手不足に陥りやすい部署です。
AIを導入することで、定型的な作業やルーチン業務を自動化でき、従業員一人ひとりの負担を軽減できます。そのため、担当者はより高度な業務や戦略的な課題に集中できるようになります。
限られた人員でも効率的に業務を回せる環境を構築できるのは、AI活用の大きなメリットです。
意思決定のスピードが速くなる
情報システム部門では、サーバーログや契約書、脅威レポートなど膨大なデータを日々扱います。生成AIに分析を任せることで、必要な情報を迅速に整理・要約でき、状況把握や意思決定をよりスムーズに行えるようになります。
具体的には、インシデント発生時の原因特定や、新規システム導入の検討などのケースにおいてAIが活躍します。従来時間のかかっていた情報収集・比較作業を大幅に短縮でき、業務のスピードと精度を同時に高めることが可能です。
コア業務に集中しやすくなる
情報システム部門のコア業務とは、IT戦略の立案や新技術の評価・導入、全社的なDX推進など、企業の成長や競争力に直接関わる重要な業務です。
AIに定型作業や単純業務を任せることで、担当者は日常的なトラブル対応や資料作成に時間を取られず、こうしたコア業務にリソースを集中できます。その結果、業務効率の向上と専門性の深化、企業内での価値創造が促進されます。
属人化の防止に繋がる
AIを活用すれば、マニュアル作成や問い合わせ対応を迅速に行えるだけでなく、業務の属人化を防げる点も大きなメリットです。
また、ベテラン社員の知識や経験をAIが整理・蓄積することで、退職や異動があっても手順書やドキュメントを活用して、安定した運営が可能になります。
特定の担当者に依存せず、組織全体で業務品質を維持できるため、人員の入れ替わりがあってもスムーズに引き継ぎや人員配置を行えます。
人為的なミスの防止・削減
生成AIは指示に従って正確に作業を行うため、人間が犯しやすい誤字脱字や数字の入力ミスを防ぐことができます。書類作成やデータ入力など、正確性が求められる業務でもミスの発生を最小限に抑えられます。
また、人が作業した後のチェックにもAIを活用すれば、見落としやすい誤りも修正でき、品質向上と作業効率の改善に大きく貢献します。
情報システム部門(情シス)にAIを導入する流れ
情報システム部門でのAI導入について解説しましたが、実際にはどのように進めればよいのでしょうか。以下から、導入の流れを6つのステップに分けて紹介します。
AIを導入する目的や目標を明確にする
AI導入の第一歩は、解決したい課題や目的を明確化することです。たとえば「問い合わせ対応の負担を減らしたい」「残業時間を短縮したい」といった現場の悩みを洗い出します。
そのうえで、「問い合わせを30%減らす」「週○時間削減する」など、定量的な目標を設定しましょう。具体的な数値で設定することで、現場と情報システム部門で共通認識を持ちやすく、導入効果の評価や改善施策の検討もスムーズになります。
AIの利用範囲を決める
AIには対応が難しい業務もあるため、導入前に任せる範囲を明確に決めることが重要です。たとえば、定型的な問い合わせ対応や簡易レポート作成はAIに任せつつ、判断や意思決定が必要な業務は人間が担当するといった区分です。
範囲があいまいだと指示系統が混乱しやすいため、業務の種類や責任範囲を具体的に整理し、AIと人間の役割をはっきりさせることで、より円滑な運用につながります。
AIの運用体制を整える
AI導入後の運用を円滑にするため、責任範囲や予算の割り振りなども明確にしておきましょう。具体的には、AI開発者との連絡窓口担当者や、運用開始後の保守担当者を事前に決定します。
また、業務ごとにAIと人間の責任範囲を整理することで、問題発生時の対応や意思決定が迅速化され、安定した運用体制を構築できます。
PoC(試行)として小さい範囲でAIを導入する
AIを広範囲で一気に導入すると現場が混乱しやすく、トラブル発生時の対応も困難です。まずは効果が見えやすく優先度の高い1つの業務や部署でPoCとして導入し、技術的な実現性や業務改善効果を検証する必要があります。
この段階で得られたフィードバックをもとに改善点を洗い出すことで、安全かつ効果的に本格導入への準備を進められます。
本番システムを開発・導入する
PoCで得られたフィードバックを反映し、改善点や修正点を解消したうえで本番システムの開発・導入に着手します。必要に応じて追加データを用意して学習させ、精度や利便性を高めることも大切です。
まずは特定部署で運用を開始し、段階的に全社へ展開します。利用ガイドラインやトレーニングを整備し、安定稼働と活用促進を図ることで、効果を持続的に測定・改善できる体制を構築できます。
導入後の成果や改善点を分析する
AI導入後は、定期的に成果や改善点を分析し、作業時間の短縮やエラー削減といった効果を可視化することが重要です。不具合が発生した場合には迅速に対応できる体制を整え、学習データや運用手順が古くなった際は適宜更新して、最新の状態を維持しましょう。
分析結果を社内で共有し、次の改善や新たな活用に反映させることで、AIの効果を持続的に高め、業務効率化や品質向上につなげられます。
情報システム部門でAIを活用するときの注意点
情報システム部門でAIを活用する際には、注意すべきポイントがいくつかあります。本章では、導入時に意識すべきリスクや留意点を解説します。
情報漏洩のリスクがある
AIの中には、入力されたプロンプトや情報を学習データとして活用するものがあります。そのため、機密情報や個人情報を入力すると、社外に情報が生成される可能性があります。
対策として、入力データを再学習に使用させない設定が可能なサービスや、セキュリティ対策が強固なサービスを選ぶことが重要です。また、定期的な脆弱性診断や不正アクセス防止策も併せて実施する必要があります。
誤った情報・実在しない情報を生成する可能性がある
生成AIが出力する内容は、必ずしも正確とは限りません。もっともらしく見えても誤情報や存在しないデータを含む場合があるため、そのまま業務に利用すると大きなリスクにつながります。
AIが生成した内容は必ず人の目で確認し、必要に応じて修正する体制を整えることが重要です。また、社内全体でITリテラシーを高め、誤った情報を見抜けるスキルを養うことも欠かせません。
費用対効果をよく検討する
AIを搭載したシステムやツールは、高度な機能を備える分、従来型よりもコストが高くなる傾向があります。そのため、導入前に「どれだけ工数削減や効率化につながるか」を数値で見積もり、費用対効果を慎重に確認しましょう。
効果が不明確なまま投資すると、期待外れの結果に終わる可能性があります。明確なKPIを設定し、小規模検証で成果を確認してから本格導入に進むのが望ましいです。
情報システム部門(情シス)でAIを活用している事例
実際に情報システム部門でAIを活用している企業の事例を紹介します。具体的な取り組みや効果を紹介するので、自社導入の際の参考にしてください。
損保ジャパンパートナーズ株式会社|システム操作マニュアルを素早く作成
損保ジャパンパートナーズ株式会社では、社内システム刷新に伴い大量の操作マニュアルを短期間で整備する必要がありました。しかし従来は作成者ごとにWordやPowerPointを使用していたため体裁が不統一で、現場から「マニュアルが探しにくい」との声も多く課題となっていました。
そこで同社は、フォーマット統一やバージョン管理に優れた、マニュアル作成・共有ツール「COCOMITE」を導入。閲覧導線が整理され、スマートフォンからも容易にアクセスできるようになり、照会対応の手間を削減できました。作成側にとっても工数が減り、改訂や目次作成が効率化されています。
今後は複数システムのマニュアルを一元管理し、閲覧ログや検索データを活用することで、さらなる運用改善を目指しています。
参考:オンラインマニュアル作成・運用サービス COCOMITE(ココミテ)導入事例
株式会社NTTドコモ|AIの活用で社内問い合わせの対応を効率化!
NTTドコモでは、クラウド活用を推進する「CCoE(Cloud Center of Excellence)」というエキスパートチームが社内からの問い合わせ対応を担ってきました。しかし、従来のメール中心の対応は進捗管理や情報共有が難しく、担当変更や類似質問への再対応など非効率が課題となっていました。
そこでZendeskを導入し、問い合わせをチケットで一元管理、ナレッジをFAQ化する仕組みを整備。結果として対応漏れが減少し、平均回答時間も大幅に短縮されました。さらに問い合わせ内容の蓄積を活かし、自己解決率も向上しています。
今後は脱メール化をさらに進め、部門横断でのナレッジ共有の強化などを視野に入れていることが伺えます。
参考:Zendesk 導入事例
情報システム部門(情シス)でAIを活用するときに役立つツール
情報システム部門でのAI活用を検討している方に向けて、便利なツール「IZANAI(イザナイ)」と「ActiBook(アクティブック)」を紹介します。両ツールの特徴や強みを、以下の表にまとめました。
| ツール名 | IZANAI(イザナイ) | ActiBook(アクティブック) |
|---|---|---|
| 概要 | 生成AIを活用した社内FAQ・問い合わせ 対応用チャットボット。 資料やWebサイトを登録することで、 最適な回答を生成可能。 |
PDFや動画、Officeファイルを簡単に 電子ブック化できるクラウドツール。 資料配布や閲覧ログ分析に強みあり。 |
| 主な特徴 | AIが曖昧な質問にも回答。 ノーコードで短時間な導入が可能。 |
3ステップで電子ブック作成が完了する。 閲覧制限・ログ分析可能。 オンラインで常に最新版を共有できる。 |
| 情シス部門での 活用場面 |
|
|
| 強み・メリット |
|
|
| 対応データ・機能 |
|
|
それぞれのツールについて以下で解説します。
AIチャットボットで社内外の問い合わせを効率化|IZANAI(イザナイ)
IZANAIは、社内外のFAQ対応を効率化できる生成AI型チャットボットです。従来のように質問と回答を一つずつ登録する必要がなく、PDFやWebサイトのURLをアップロードするだけでAIが自動的に回答を生成します。最短3分で導入でき、複雑なシナリオ設計も不要な点が大きな特長です。
情報システム部門でIZANAIを導入すれば、担当者が個別に対応する手間を大幅に削減でき、ナレッジの抜け漏れ防止にもつながります。また、複数ファイルの同時学習にも対応しており、マニュアルや技術資料の一括管理も可能です。
コストを抑えつつ、問い合わせ対応の品質とスピードを向上させられる点で、多忙な情報システム部門に最適なツールといえます。
参考:AIチャットボットでFAQを最適化「IZANAI Powered by OpenAI」
3ステップで電子ブックの作成から配信まで可能|ActiBook(アクティブック)

ActiBookは、PDFやOfficeファイル、動画をクラウドにアップロードするだけで、誰でも簡単に電子ブック化できるツールです。閲覧制限やアクセスログの取得にも対応しており、社内資料やマニュアルの配布を効率的に行える点が特徴です。
情報システム部門では、システム操作手順書や社内向けの運用ガイドを電子ブック化することで、最新版を常にオンラインで共有でき、印刷・配布コストの削減にもつながります。
さらに、閲覧状況の分析機能を活用すれば、利用頻度の高いマニュアルや参照されていない資料を把握でき、改善に役立てることが可能です。無料で利用できるフリープランも提供されているため、まずは小規模に導入して効果を試してみることをおすすめします。
AIを活用して情報システム部門(情シス)の業務効率化を
情報システム部門は、社内システムの運用から問い合わせ対応、セキュリティ対策まで幅広い役割を担い、常に多忙な部署です。AIを活用することで、マニュアル作成や問い合わせ対応の効率化、業務の属人化防止、意思決定の迅速化など多くのメリットが期待できます。
情報システム部門でのAI活用を成功させるためには、まず小規模な範囲で試行し、成果を分析しながら段階的に広げていくことが重要です。AIをうまく取り入れ、情報システム部門の業務効率化と品質向上を実現しましょう。


