ヘルプデスクを効率化|課題や具体的な改善例を紹介
公開日 2025/08/18
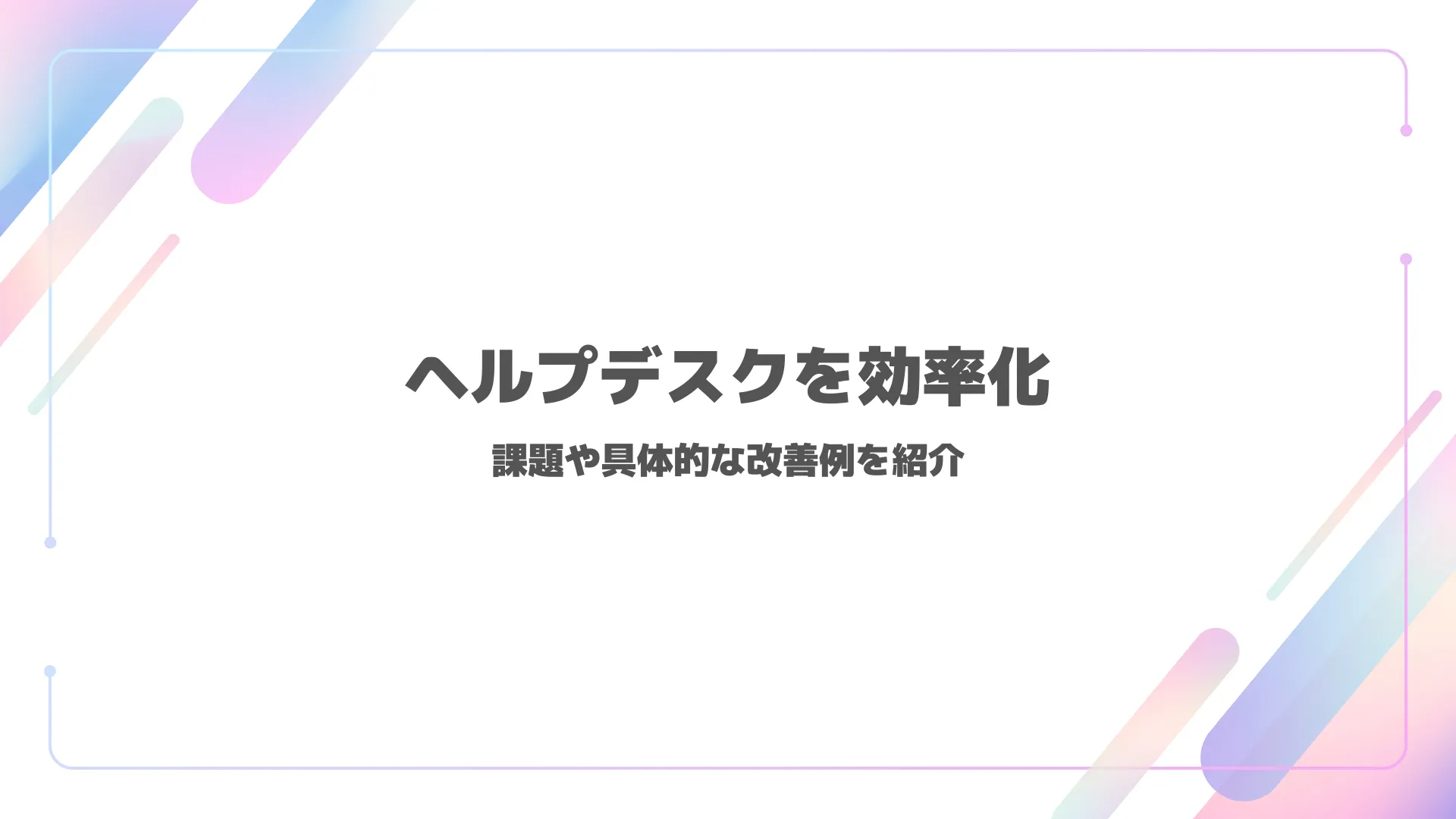
顧客や従業員からの問い合わせに対応するヘルプデスクは、企業運営において不可欠な部門です。しかし、「問い合わせ対応に時間がかかる」「顧客や従業員の不満が増加している」「リソース不足で顧客満足度維持に限界がある」「導入すべきシステムやツールが分からない」といった課題に直面し、その業務効率が低下している企業も少なくありません。
対応の遅れは顧客離れや社内業務の停滞、ひいてはコスト増大に直結します。本記事では、ヘルプデスク効率化を実現するための具体的な理由と、社内外ヘルプデスクが抱える共通の課題を深く掘り下げ、具体的な改善策や導入を検討すべきツールの選び方を解説します。
目次
ヘルプデスクを効率化する理由
ヘルプデスクには、大きく分けて2種類あります。一つは、社内のIT機器やシステム操作に関する問題をサポートする社内ヘルプデスクであり、もう一つは、自社の製品やサービスに関する問い合わせに対応する社外ヘルプデスクです。
社内ヘルプデスクは、社員の業務を円滑に進める役割を担い、社外ヘルプデスクは、顧客満足度の向上に貢献します。どちらの場合でも、業務を効率化することは非常に重要です。以下に、その主な理由を紹介します。
- 対応時間を短縮できる:業務を効率化することで、ユーザーからの問い合わせに迅速に対応可能です。待ち時間の短縮やスムーズな問題解決が実現し、結果として利用者の満足度向上につながります。
- 顧客満足度を向上させられる:スムーズで質の高いサポートを提供することで、社内外のユーザーから信頼を得られます。これにより、顧客満足度が高まり、企業全体の印象や評価の向上にもつながります。
- スタッフの負担を軽減できる:問い合わせが集中する状況を防ぐことで、対応スタッフへの業務負荷の軽減が可能です。効率化により、担当者の身体的・精神的なストレスが抑えられ、本来の業務にも集中しやすくなります。
社内ヘルプデスクが抱える4つの課題
社内ヘルプデスクは、社員からのIT関連の問い合わせ対応やシステム管理を担う、重要な部門です。しかし現在、その業務効率を妨げるさまざまな課題に直面しています。これらの課題は社員の業務を停滞させ、ヘルプデスク担当者の負担をさらに増加させる要因となっています。
1)対応範囲の広さ
社内ヘルプデスクには、社内で利用されているすべてのシステムやITツールに関する問い合わせが集中しています。新しいシステムが導入されるたびに、対応範囲も広がっていきます。加えて、ITに関する内容だけでなく、経費精算や有給申請など、システムとは直接関係のない事務的な質問も多く寄せられています。
こうした背景から、社内ヘルプデスクは「何でも屋」のような役割を担うようになり、担当者の負担が大きくなっているのが実情です。その結果、本来注力すべきITサポート業務にまで影響が及んでいます。
2)知識の属人化
情報共有の仕組みが整っていない場合、社内ヘルプデスクの知識や業務が特定の担当者に偏ってしまいます。このような状況は、「ナレッジの不足」や「人材育成の遅れ」といった課題を引き起こし、担当者によって対応の質や回答内容に差が出る原因です。
特定の社員が不在の際にはトラブル対応が滞りやすくなり、一部の社員に業務が集中することで負担が大きくなる傾向が見られます。さらに問題なことは、豊富な知識を持つ社員が退職する際に、十分な引き継ぎが行われなければ、比較的容易な問題であっても対応に時間がかかる恐れがあることです。
その結果として、問い合わせ対応の質が低下し、最終的には社員の信頼を損なうことにつながります。
3)対応時間の集中と制約
社内ヘルプデスクには、「ネットワークに繋がらない」といった緊急性の高い問い合わせが集中するため、即時の対応が求められます。マニュアルが十分に活用されていないことなどにより、問い合わせの件数はなかなか減りません。そのため、担当者は常に対応に追われているのが現状です。
本来予定していた業務にまで手が回らなくなるケースも珍しくありません。会社の利益に関わるトラブルが発生した場合には、業務時間外や休日にも対応が必要となることがあります。加えて、同じ質問に何度も対応することによってストレスが蓄積し、担当者への負担が深刻になる要因です。
4)システムの複雑化
IT技術の進歩やDX推進により、企業では多様なシステムやツールが導入され、それぞれの機能はますます高度化しています。これにより、社員の業務効率は向上している一方で、システム操作に関する疑問やトラブルが発生しやすくなっているのも事実です。
社内ヘルプデスクは、日々変化するシステムや頻繁な機能改修に対応するため、自らの知識を継続的に更新し続ける必要があります。しかし、日常的な対応に追われる中で情報のキャッチアップが難しく、問い合わせを受けたその場で調べながら回答する場面が増えている状況です。
その結果、返答までに時間がかかることが多くなり、利用者に不信感を与える原因となっています。
社外ヘルプデスクが抱える4つの課題
社外ヘルプデスクは、顧客からの問い合わせに対応し、顧客満足度向上に貢献する重要な役割を担っています。しかし、その業務運用においては、複数の課題に直面しています。これらの課題は、サービスの品質低下や顧客離れを引き起こす可能性があり、企業にとって大きな問題です。
1)迅速な対応の難しさ
社外ヘルプデスクには、製品やサービスに関する疑問だけでなく、緊急性の高いトラブルの連絡も多く寄せられます。顧客は迅速な問題解決を期待しているため、対応に時間がかかると不満につながることがあります。さらに、突発的な問い合わせや複雑な内容が同時に発生した場合、担当者は業務計画を立てにくい状況です。
予測のつかない残業が発生することもあるため、業務負荷が高まる要因です。このような状況が続くと、個別の問い合わせ対応に時間がかかり、結果として顧客満足度が低下します。
2)担当者の不足
多くの企業で、ヘルプデスクの人材不足は共通の課題です。特に社外ヘルプデスクでは、顧客からの多種多様な問い合わせに対応できる専門知識を持つ担当者が求められています。しかし、直接的な収益に繋がりにくい部門と見なされることもあり、既存の人員が他業務と兼任するケースも少なくありません。
問い合わせが集中した際には、兼任担当者に過度な負担がかかり、未対応の問い合わせが蓄積する事態に陥ることがあります。こうした状況が続くと業務に支障をきたし、最終的には顧客満足度の低下につながります。
3)問い合わせ件数の多さ
社外ヘルプデスクには、自社の商品やサービスを利用する顧客から、日々多くの問い合わせが寄せられます。事業が好調で顧客数が増えると、それに比例して問い合わせの件数も増え、ヘルプデスクの業務は逼迫しやすい傾向です。
また、マニュアルを見れば自己解決できるような簡単な質問であっても、多くのユーザーが直接ヘルプデスクに連絡してきます。同じような質問への対応を繰り返すことにより、担当者の業務負担が増え、本来時間をかけるべき複雑な問題への対応が遅れる原因です。
4)知識のアップデート不足
ヘルプデスクにはIT分野に関する幅広い知識が求められますが、特に社外ヘルプデスクでは、顧客の使用環境が多岐にわたるため、さまざまなOSやソフトウェアの最新情報を常に把握しておく必要があります。
IT技術は急速に進化しており、新しい製品やサービス、システムが頻繁にリリース・アップデートされることから、担当者は自身の知識を継続的に更新しなければなりません。しかし、日々の問い合わせ対応に追われる中で、最新情報の学習時間を確保するのは難しいです。
知識のアップデートが追いつかない場合には、適切な回答に時間がかかったり、対応の質にばらつきが生じたりします。
ヘルプデスクを効率化するための課題改善策と事例
ヘルプデスクが直面する様々な課題を乗り越え、その業務を効率化することは、顧客満足度や社内全体の生産性向上に直結します。ここでは、具体的な改善策とその導入事例を通じて、ヘルプデスクが抱える問題をどのように解決できるかを紹介します。
ナレッジベースの整備|情報の共有化を図り知識不足を補う
ヘルプデスクが直面する様々な課題を乗り越え、その業務を効率化することは、顧客満足度や社内全体の生産性向上に直結します。ここでは、具体的な改善策とその導入事例を通じて、ヘルプデスクが抱える問題をどのように解決できるかを紹介します。
ナレッジベースの整備|情報の共有化を図り知識不足を補う
ヘルプデスクの課題の一つに、知識や業務が特定の担当者に偏る「知識の属人化」が挙げられます。これを解決するには、日々の業務を通じて得られるナレッジやノウハウを組織全体で共有するナレッジベースの整備が不可欠です。社内外からの問い合わせ件数を削減するためには、顧客や従業員が自身で問題を解決できる環境を整えることが重要です。
たとえば、FAQページやトラブルシューティングガイドを自社のポータルサイトに設け、よくある質問とその回答を整理しておくことで、利用者が必要な情報に簡単にアクセスできるようになります。問い合わせ件数が減ることで、担当者はより複雑で重要な案件に集中しやすくなります。
さらに、問い合わせ内容や対応履歴を一元管理できるシステムの導入も有効であり、マニュアルを定期的に見直し・更新することで、知識の均一化と業務の効率化を図ることが可能です。
管理システムを導入|問い合わせの状況をリアルタイムで把握
ヘルプデスク業務において、問い合わせの量が増加すると対応が追いつかなくなり、担当者の負担が増大する問題に直面します。これを抜本的に改善するためには、問い合わせ管理システムの導入が非常に効果的です。このシステムを活用すれば、メール、電話、チャット、SNSなど複数のチャネルからの問い合わせを一元的に管理できます。
また、問い合わせのステータス(対応中、未対応、完了など)をリアルタイムでチーム全体で共有できるようになり、業務の重複や対応漏れを防ぐ効果も期待できます。さらに、過去の対応履歴を自動的に記録し蓄積できるため、ナレッジの共有と活用にも役立ち、チーム全体の対応力も上げることが可能です。
自動化ツールを導入|AIチャットボットを導入し負担を軽減
ヘルプデスクの業務負荷を軽減するためには、AIやチャットボットといった自動化ツールの導入が有効な解決策となります。特にチャットボットは、24時間体制で利用者の基本的な問い合わせに自動で対応できるため、業務時間外の負担を大幅に軽減することが可能です。その結果、スタッフはより複雑で緊急性の高い案件に集中しやすくなります。
AIは問い合わせ内容を解析し、最適な回答を迅速に提供する強力なツールです。過去の対応履歴を学習させることで精度が向上し、問い合わせ傾向の自動抽出や予測分析の効率化にもつながります。たとえば、「メールディーラー」のAIクレーム検知機能のように、問い合わせメールの感情を読み取り、優先順位を自動で判断する仕組みも実用化されています。
スタッフや担当者の教育|トレーニングや資格取得を支援
ヘルプデスクの対応品質にばらつきがあることや、知識が不足していることは、顧客満足度を低下させる大きな要因となります。こうした課題に対応するには、スタッフのスキルを高めるための教育体制を強化することが欠かせません。
具体的な事例を取り入れた研修や、顧客対応を想定したシミュレーションを通じて、実践的な力を養うことが重要です。また、IT技術の進化や新たな製品・サービスの導入にあわせて、定期的なトレーニングを実施し、常に最新の知識を身につける必要があります。
さらに、担当者が安心して悩みを共有できる面談の機会を設けることで、モチベーションの維持と応対品質の向上にもつながります。ヘルプデスク業務は経験に基づく判断が求められるため、人材の育成には時間がかかるため、継続的な支援体制の整備が重要です。
ヘルプデスクの効率化に役立つおすすめのツール
ヘルプデスクの業務効率化は、顧客満足度だけでなく、社内全体の生産性向上にも不可欠な要素です。現代では、多様な課題に対応するため、さまざまな機能を持つ専門ツールが登場しています。これらのツールを適切に導入すれば、問い合わせ対応のスピードが向上し、情報共有が円滑になり、対応品質も均一に保つことが可能です。
ただし、ツールの選定から導入、その後の運用に至るまでには、初期コストや従業員への十分な教育、継続的なメンテナンスと改善が必要です。単に導入するだけでは不十分であり、こうした要素を総合的に考慮したうえで、自社に最適なツールを見極めることが成功への鍵となります。
| 分類/目的 (メリット) |
チケット管理システム | AIチャットボット (自動応答ツール) |
ナレッジベースツール | オムニチャネル 管理ツール |
RPAツール | 分析・レポートツール |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 概要 | 顧客や従業員からの問い合わせを「チケット」として記録・追跡・解決するソフトウェア。タスクの可視化と進捗管理に優れる。 | AI技術を活用し、人間との対話を自動化するプログラム。自然言語処理や機械学習を基盤とし、24時間対応が可能。 | 社内の情報やノウハウ、FAQなどを一元管理し、効率的に共有できるシステム。 | 電話・メール・チャット・SNSなど複数チャネルからの問い合わせを一元管理し、シームレスな顧客対応を可能にするツール。 | 定型的なPC業務をソフトウェアロボットで自動化するツール。 | ヘルプデスクのパフォーマンスや顧客行動をデータ分析・可視化するツール。 |
| 主な機能 | 問い合わせの記録、優先度付け、担当者への割り当て、履歴参照、チャネル統合、ステータス管理、アラート通知、レポート・分析機能など。 | テキスト/音声入力の解析と応答、FAQ自動回答、関連情報の提案、有人対応への転送、感情分析、優先順位付けなど。 | FAQ・ガイド整備、多言語対応、検索機能、対応履歴の蓄積、マニュアルの更新など。 | 問い合わせの一元管理、受信トレイの集約、チャネル間の履歴引き継ぎ、顧客データの一元表示、自動分類・優先順位付け・割り当てなど。 | データ入力・集計、テンプレート応答、チャットボット連携、メール自動送信、文書発行、内容の集計・分析。 | 問い合わせデータの収集・分析、レポート作成、対応傾向の可視化、グラフ表示、パフォーマンス監視、ニーズ抽出など。 |
| 導入メリット | 情報の一元管理、対応漏れ防止、品質の均一化、業務負担軽減、分析による改善、顧客満足度向上。 | 24時間対応、人手不足解消、業務効率化、コスト削減、対応処理能力の向上、スタッフ負担軽減。 | 属人化の防止、組織のスキル向上、自己解決促進、問い合わせ削減、品質の均一化。 | 顧客ごとのチャネル選択に対応、ツール切り替えの不要化、迅速で効率的な対応、対応漏れ防止、顧客体験の向上。 | 担当者負担軽減、品質の均一化、人件費削減、24時間対応、ミス防止、サービス力向上。 | サービス改善、チーム可視化、顧客理解の深化、戦略最適化、インシデント分析、人事評価への活用など。 |
| 関連ツール例 | Zendesk、Jira Service Management、Freshdesk、Zoho Desk、Salesforce Service Cloud、メールディーラー、FastHelp5 ほか | IZANAI(イザナイ)、ANAチャットボット、ユニクロ「IQ」、PayPay銀行、住信SBIネット銀行、武蔵野採用ボット、PKSHA AIヘルプデスク ほか | Microsoft SharePoint、Help Scout、SolarWinds、Zoho Desk、Zendesk、QuickSolution ほか | Zendesk、Freshdesk、HubSpot、メールディーラー、Re:lation、Zoho Desk、LiveAgent ほか | RaBit | Zendesk、HubSpot、Jira、SolarWinds、メールディーラー、LMIS ほか |
ヘルプデスクの効率化ツールを選ぶには?
ヘルプデスクの業務効率化を実現するためには、適切なツールの選定が不可欠です。市場には多種多様なヘルプデスクツールが存在しており、自社の課題や目的に合致したものを見極めることが、導入成功への鍵です。以下のポイントを参考に、最適なツールを選びましょう。
課題に合うツール機能を搭載したツールを選ぶ
ヘルプデスクツールを選ぶ際に重視すべきことは、自社が抱える問い合わせ対応業務の課題を解決できる機能が備わっているかという点です。レポート作成や自動回答、テンプレート作成など、多くのツールに共通する機能がある一方で、業種や会社の規模によって優先すべき機能は異なります。
例えば、リアルタイムな顧客コミュニケーションが必要な場合、チャットや電話対応機能を優先します。問い合わせ数が膨大であれば、自動化ツールが業務負荷軽減に有効です。自社の具体的なニーズと照らし合わせ、優先順位の高い機能が充実した製品を見極めることが重要です。
既存システムとのスムーズな統合が可能なツールを選ぶ
ヘルプデスクツール選定では、既存システムとの連携性が非常に重要なポイントです。例えば、顧客管理(CRM)や営業支援システムなどと連携できれば、ヘルプデスク担当者は顧客の購入履歴や契約状況を即座に参照し、より的確なサポートを提供できます。
もしツールが社内システムと孤立すると、データの二重入力や照合に手間が生じ、かえって非効率になります。導入時に必要な機能だけでなく、将来的に導入する可能性のあるFAQシステムやチャットボットなどとの互換性も考慮し、シームレスなデータ連携が可能な製品を選ぶことがおすすめです。
直感的なUI/UXを持つツールを選ぶ
ヘルプデスクツールは、現場の担当者やオペレーターが日々利用するものです。そのため、直感的で使いやすい操作性(UI/UX)を持つ製品を選ぶことが極めて大切です。たとえ高機能なツールであっても、操作が複雑で習熟に時間がかかると、業務効率がかえって低下します。
分かりやすいインターフェースであれば、問い合わせに対してより迅速に対応できるようになり、導入後のトレーニング期間も短縮できます。無料トライアルなどを活用し、実際に担当者が操作感を試し、現場でのフィット感を確認することがおすすめです。
ベンダーのサポート体制でツールを選ぶ
ヘルプデスクツールを導入し、社内に定着させるまでには一定の期間が必要です。そのため、ツール提供ベンダーのサポート体制が充実しているかどうかは、重要な選定基準となります。導入時の支援や運用に関する手厚いフォローが提供されているかを、事前に確認しましょう。
導入実績が豊富なベンダーであれば、蓄積されたノウハウを活かし、疑問点やトラブルにも迅速に対応できます。さらに、ツールの不具合やセキュリティに関する定期的な更新、長期的な保守体制、運用コストについても確認が必要です。導入後も継続的なサポートが受けられる体制であるかを見極めることが大切です。
ヘルプデスクの効率化の第一歩を踏み出そう
ヘルプデスクの効率化は、迅速な対応や顧客満足度の向上、スタッフの負担軽減に直結する重要な取り組みです。本記事では、「対応範囲の広さ」「知識の属人化」「対応時間の集中」「システムの複雑化」といった課題と、その改善策である「ナレッジベースの整備」「ツールの導入」「スタッフ教育」を紹介しました。
ツール選定では、自社課題との適合性、既存システムとの連携、使いやすさ、サポート体制が重要です。AIチャットボット「IZANAI(イザナイ)」や電子ブック作成ツール「ActiBook」は、こうした課題の解決に役立つツールです。ぜひ無料トライアルや資料ダウンロードをしてみてください。


