社内問い合わせを効率化する方法|コスト・時間を削減するためのポイントを解説
公開日 2025/08/18
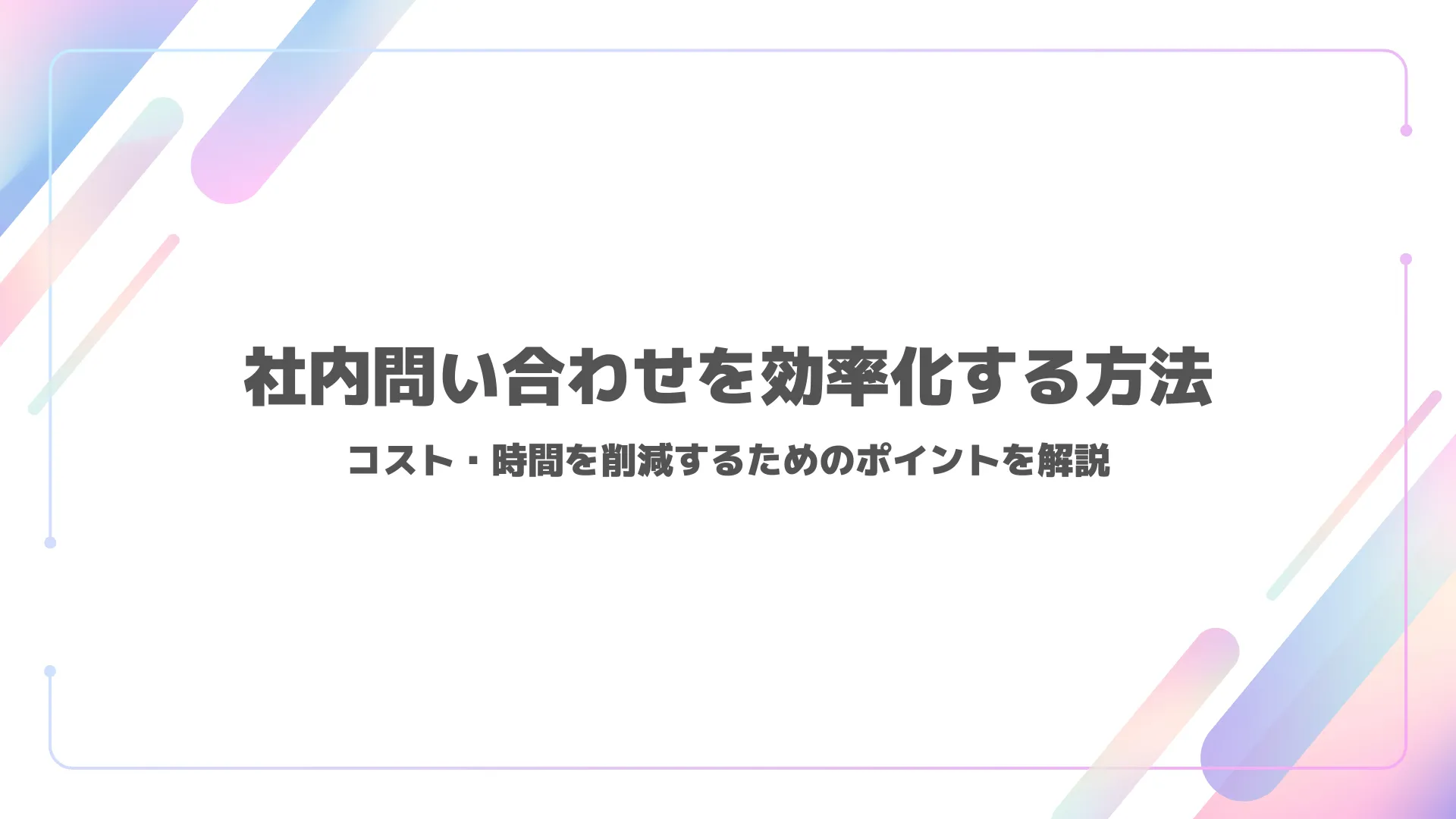
社内問い合わせとは、従業員が業務上の疑問やトラブルを社内の担当部署へ質問・相談することです。企業の成長とともにその件数は増え、対応部署の負担が増すだけでなく、従業員の生産性を下げる要因にもなりかねません。
この記事では、社内問い合わせが非効率になる原因を掘り下げたうえで、すぐに実践できる効率化の方法を、事例を交えてわかりやすく紹介します。さらに、取り組みを成功させるために欠かせないポイントについても触れています。
目次
社内問い合わせ効率化の必要性
企業規模が拡大するにつれて、人事や経理、情報システム部門といった部署には、従業員からの多岐にわたる問い合わせが増加します。これに対応しきれない場合、業務の停滞や生産性の低下を招きかねません。
業務・生産性アップ:企業成長のためのコア業務への集中
社内問い合わせを効率化すると、対応に要する時間が大幅に短縮され、人件費を含めた社内コストの削減につながります。これにより、問い合わせ対応と本来の業務を兼任していた従業員は、より多くの時間とエネルギーをコア業務に注力できるようになり、組織全体の生産性向上が可能です。
また、迅速かつ的確な回答が得られることで、従業員のストレスが軽減し、業務が円滑に進むため、従業員満足度の改善にも寄与します。
属人化の解消:担当者不在での業務停滞リスクの防止
社内の問い合わせ対応は、特定の担当者に専門知識が偏りがちで、対応が属人化する傾向があります。そのため、担当者が不在になると業務が滞り、組織全体の効率にも影響が出てしまいます。
こうした課題を解消するには、マニュアルやFAQ、AIチャットボットなどを活用して、知識を一元的に管理し、対応方法を標準化することが効果的です。体制を整えることで、特定の担当者に頼らずに誰でもスムーズに対応できるようになり、業務の継続性と生産性の向上が期待できます。
社内問い合わせ効率化で抱える問題
社内問い合わせの効率化に取り組む中で、多くの企業が「問い合わせ量の多さ」「システムの使いにくさ」「情報共有の不十分さ」といった課題に直面しています。ここからは、それぞれの問題について見ていきます。
問い合わせ量の多さ
社内問い合わせ対応において、最も大きな課題として挙げられるのは問い合わせ件数の多さです。企業の規模拡大やITツールの普及に伴い、システムの利用方法やトラブルに関する問い合わせが増加する傾向にあります。これにより、対応を行う担当部署はキャパシティを超え、慢性的なリソース不足や人手不足に陥るケースが少なくありません。
結果として、問い合わせ対応が追いつかず、回答を得るまでに時間がかかるため、問い合わせを行った社員の業務が停滞し、企業全体の生産性低下を招く懸念があります。また、他の業務と兼任している担当者の場合、問い合わせ対応に時間を取られ、本来の業務がおろそかになるという問題も発生するでしょう。
システムの使いにくさ
社内問い合わせの効率化を目的に、FAQやマニュアルなどのサポートコンテンツを導入しても、「使いにくければ活用されません。
さらに、内容が読みにくい、情報が古いまま更新されていない、検索しても目的の情報にたどり着けないといった「質の低さ」がある場合、社員は自己解決を諦め、直接問い合わせるケースが多くなります。
このように、導入したツールが社員にとって使いにくい状態では、利用率が下がり、結果として効率化の取り組みが十分な効果を発揮しなくなってしまいます。
情報共有の不十分さ
社内問い合わせ対応において、情報共有の方法が確立されていないことは大きな課題です。特定の担当者に業務の知識やノウハウが集中する「属人化」が発生すると、その担当者が不在の際に他の社員が対応できず、業務が滞ってしまうリスクがあります。
また、対応部署内で問い合わせ内容や進捗、対応履歴が適切に共有されていない場合、同じ問い合わせに対して二重で対応してしまったり、対応漏れが発生したりする懸念が生じます。
さらに、過去の問い合わせ内容や対応履歴が活用されない状況では、社内の問題や課題の解決に役立つ貴重な情報が埋もれてしまい、業務改善に繋げることが難しいでしょう。このような情報共有の不十分さは、業務効率の著しい低下を招く原因となります。
社内問い合わせを効率化する方法|事例と削減効果
社内問い合わせの効率化は、担当部署の業務負荷軽減や組織全体の生産性向上に不可欠な要素です。日々の業務で実践できる簡易な工夫から、専門的なツールの導入まで、その方法は多岐にわたります。ここでは、具体的な効率化手法とそれによって得られる削減効果を、導入事例を交えながら紹介します。
返信テンプレートの活用
社内問い合わせ対応において、同じ内容の質問に毎回個別に回答を作成することは、担当者にとって大きな負担となります。このような状況を改善するために、あらかじめ回答のテンプレートを用意しておく方法は非常に有効です。
テンプレートを活用することで、対応に要する時間を大幅に短縮できるだけでなく、回答内容の均質化が図られ、担当者による回答のばらつきや人的ミスの発生を未然に防ぐことが可能になります。
さらに、テンプレート内にマニュアルやFAQへの参照リンクを記載しておくと、より詳細な情報を求める問い合わせ者に対して迅速に誘導できるため、自己解決を促進する効果も期待できるでしょう。これは、担当者の負担軽減だけでなく、問い合わせる側のストレス緩和にも繋がります。
FAQシステムの導入
社内問い合わせの効率化において、FAQシステムは自己解決を促し、問い合わせ数自体を削減する代表的なツールです。よくある質問とその回答をデータベースとして集約し、従業員がキーワードや単語を入力して必要な情報を自分で検索できる環境を提供します。特に、似たような内容の問い合わせが多い部門や、一問一答で解決できる内容に適しています。
FAQシステムの導入は比較的安価で簡単に行える傾向があり、専門知識がなくても質疑応答の登録が可能です。これにより、専門部署は本来のコア業務に集中できるようになります。例えば、パーソルプロセス&テクノロジー株式会社では、FAQシステム「Helpfeel」の導入により、わずか1ヶ月で問い合わせ率を約25%減少させました。
また、デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社も同システムの導入で、従業員が増加する中でも問い合わせ数の削減を実現しています。
チャットボットの活用
チャットボットを導入することで、担当者が直接対応する工数を大幅に削減し、迅速な問い合わせ対応を実現できます。
チャットボットはシステムが稼働している限り24時間365日対応が可能なため、時間や場所の制約なく問い合わせができるようになり、従業員の利便性を大きく高めるメリットがあります。これにより、従業員は回答を待つことなく業務を円滑に進められます。
株式会社学研メディカルサポートでは、FAQチャットボット「さっとFAQ」の導入により、年間工数を400時間、費用を80万円削減することに成功しました。また、株式会社テンダも同システムの導入で、月間約40%の質問を自動的に解決できるようになったと報告しています。
問い合わせ窓口の一本化
社内問い合わせにおいて、どこに質問すれば良いか明確でない場合、従業員は問い合わせ先に迷ったり、誤った部署に連絡してしまったりすることが頻繁に発生します。このような状況は、無駄なコミュニケーションや「たらい回し」を引き起こし、問題解決までの時間と手間を増大させる要因となります。
そこで、問い合わせ窓口を明確にし、一本化することは非常に重要です。単一の窓口として社内ポータルに問い合わせフォームを設置し、そこからすべての問い合わせを受け付けるようにすると、情報が集約され、対応履歴の管理も容易になります。これにより、従業員は迷うことなく問い合わせができ、担当部署も効率的に対応を進められます。
たとえば、老舗メーカーではresearcHRを導入し問い合わせ窓口を一本化した結果、FAQ生成やレコメンドによる類似問い合わせ削減効果が得られました。また、滋賀県庁では社内ポータルに重要なシステム情報を掲示することで、問い合わせ対応時間の短縮に成功しています。
社内問い合わせの効率化を成功させる4つの重要ポイント
社内問い合わせの効率化を実現するためには、単にツールを導入するだけでなく、体系的なアプローチが欠かせません。問い合わせ対応の質を高め、コストと時間を削減するためには、現状把握から運用改善、そして適切なツールの選定まで、複数の重要ポイントを網羅的に押さえることが大切です。
ここでは、効率化を成功に導くための具体的な4つのポイントを紹介いたします。
1.問い合わせの収集と記録
社内問い合わせの効率化を図る第一歩として、寄せられる全ての問い合わせを適切に「収集」し、詳細に「記録」することが重要です。電話、メール、チャットなど、多岐にわたるチャネルから来る問い合わせを一元的に集約し、専用のシステムやツールで記録管理することで、問い合わせ内容や対応履歴の可視化が可能となります。
問い合わせ情報が見える形で整理されることで、個別の対応状況を把握しやすくなり、対応漏れや重複の防止につながります。さらに、蓄積されたデータを活用すれば、よくある質問や従業員がつまずきやすいポイントが明確になり、根本的な課題解決に向けた有効な手がかりが得られます。
2.問い合わせ内容の分析と分類
収集された社内問い合わせのデータは、単に記録するだけでなく、その内容を詳細に「分析」し、適切な「分類」を行うことで、効率化に向けた具体的な対策を立てる基盤となります。たとえば、問い合わせの種類を「システムトラブル」「操作方法」「マニュアルに関する質問」など、テーマやカテゴリごとに明確な基準を設けて分類することが効果的です。
こうした分類を行うことで、どの分野に問い合わせが集中しているのか、解決に時間がかかるボトルネックはどこにあるのか、といった傾向を可視化できます。その傾向をもとに、FAQの充実やマニュアルの改善、さらには特定の業務フローの見直しなど、より的確な施策の計画と実行が可能になります。
3.対応担当者の明確化
社内問い合わせの効率化を推進するためには、各問い合わせカテゴリに対応する担当部署や担当者を明確に割り当てることが不可欠です。問い合わせ先が不明確だと、従業員はどこに質問すべきか迷ったり、誤った部署に連絡してしまったりすることで、無駄なコミュニケーションや「たらい回し」が発生し、問題解決までの時間と手間が増大する原因となります。
そのため、IT関連の問い合わせはIT部門、経理関連は経理部門、人事関連は人事部門といったように、問い合わせ内容に応じた責任部門を明確にすることが重要です。情報が適切に集約されることで、担当者はより迅速かつ的確に対応できるようになり、結果として問い合わせの重複や遅延が防がれ、全体としての対応効率の向上が期待できます。
4.使いやすさを重視したAIツールを導入する
社内問い合わせの効率化を成功させるには、従業員が積極的に使いたくなる「使いやすさ」を重視したAIツールの導入が欠かせません。どれほど高機能なシステムであっても、操作が複雑だったり、検索しづらかったりすると、結局は利用されず、問い合わせが減らないという結果につながってしまいます。
その点、AIチャットボット「IZANAI(イザナイ)」のようなツールは、複雑なツリー構造ではなくステップ構造で会話フローを簡単に設定できるため、初めて使う場合でも安心して導入を始められます。会話フローテンプレートが用意されており、自社向けにカスタマイズするだけでスムーズに利用開始できるのも魅力です。
さらに、導入効果をしっかり把握するには、グラフィカルな分析機能で自動レポートを作成できるツールを選ぶと便利です。どの質問で離脱が多いか、回答にどのくらい時間がかかったかなどが一目でわかるようになり、改善にもつなげやすくなります。
必要に応じて有人チャットに切り替えられる柔軟さもあり、さまざまな状況に対応できるのも大きな利点です。また、導入時の負担を軽減するためには、ベンダーのサポート体制が整っているかどうかも事前に確認しておくと安心です。
課題解決の鍵は“仕組み化”と“ツール選び”
社内問い合わせの効率化は、企業の成長や従業員満足度の向上に欠かせない取り組みです。問い合わせ件数の多さやシステムの使いにくさ、情報共有の不足といった課題に対しては、返信テンプレートの整備やFAQシステム、チャットボットの導入、そして窓口の一本化が効果を発揮します。
こうした効率化を実現するには、問い合わせ内容の収集・記録・分析に加えて、担当者の明確化と、誰でも使いやすいAIツールの導入が欠かせません。その中でもAIチャットボット「IZANAI(イザナイ)」は、直感的な操作性と優れた分析機能を備えており、社内対応の最適化を力強くサポートします。導入により業務負担の軽減やコスト削減、生産性の向上といった効果への期待が可能です。


