社内FAQを導入するメリットとは?効果や作り方・注意点を解説
公開日 2025/08/18
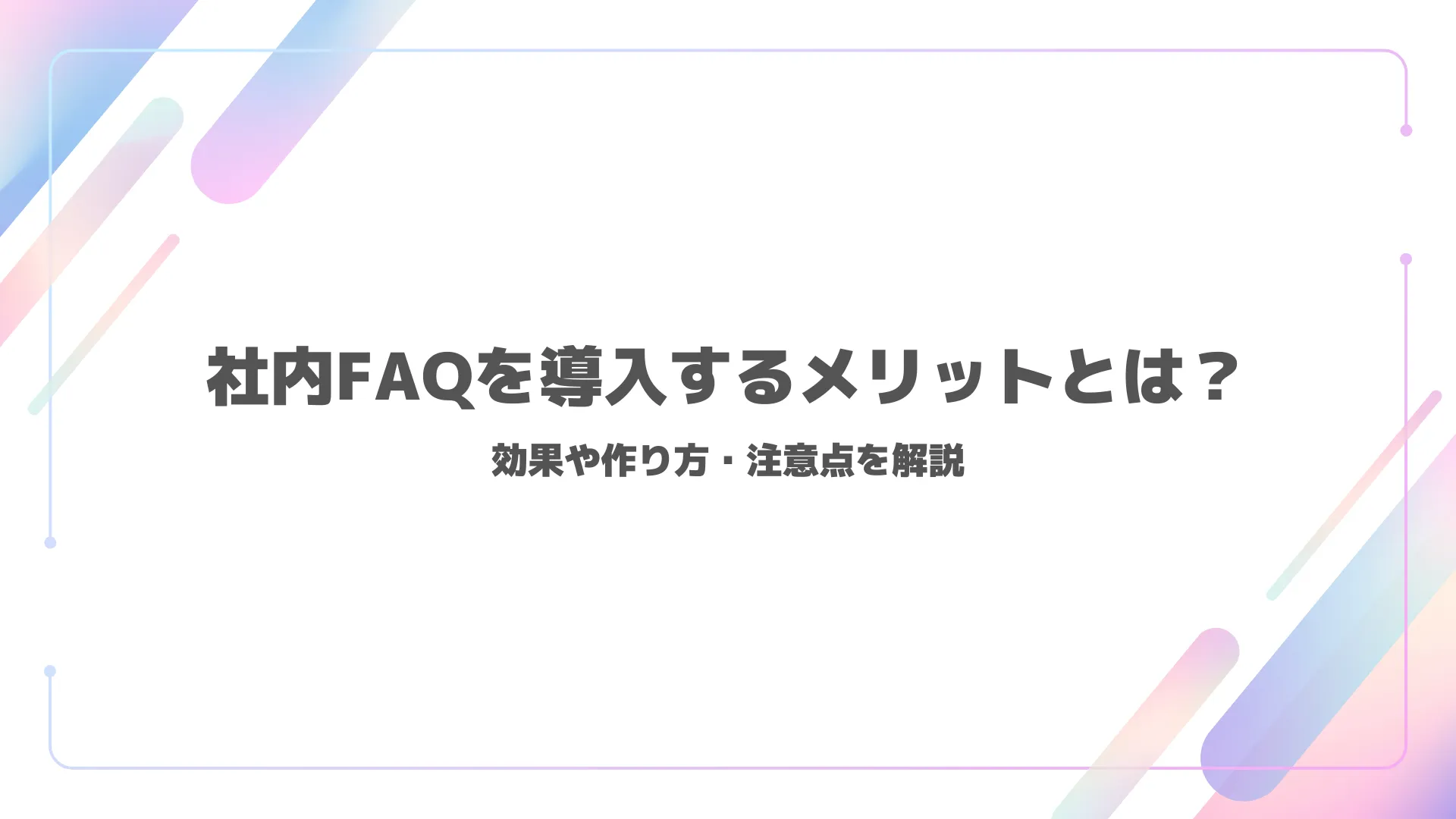
「従業員から同じ質問が繰り返され、対応に時間を取られている」「社内の情報共有がうまくいかず、業務に支障が出ている」、そんな課題を抱えていませんか?経営者や人事・総務部門の担当者にとって、社内コミュニケーションの改善や業務効率化は大きなテーマです。そこで注目されているのが、社内FAQの活用になります。
社内FAQとは、よくある質問とその回答をあらかじめまとめておくことで、社員が自ら疑問を解消できる仕組みです。本記事では、社内FAQのメリットから作り方、設計のポイント、導入・運用時の注意点までをわかりやすく解説します。
目次
社内FAQとは?
社内FAQは、「Frequently Asked Questions(よくある質問)」の略称で、企業内でよく発生する質問とそれに対する回答をまとめた情報共有の手法です。顧客向けFAQとは異なり、従業員が業務上の疑問を自分で解決できるようにすることが目的です。
社内FAQの主な目的は、社内の各部署に頻繁に寄せられる共通の質問に対し、全社員がアクセス可能な形式で回答を提供することです。同じ問い合わせに繰り返し対応する担当部署の負担を大幅に軽減し、社員自身が迅速に疑問を自己解決できるよう促す、重要な窓口として機能します。
社内FAQ設置で期待できるメリット
社内FAQの導入は、企業内のさまざまな課題を解決し、組織全体の生産性向上に大きく貢献します。担当部署の負担軽減から社員の自己解決促進、さらには組織の知識資産形成に至るまで、具体的なメリットを解説します。
社員による自己解決を促し、問い合わせ件数を削減
社内FAQの最大の利点の1つは、社員が自ら疑問を解消する能力を高めることです。よくある質問への回答をまとめておくことで、社員は担当部署に問い合わせる手間を省き、自身の業務を中断することなく、素早く問題解決へと導くことが可能です。
同じ内容の問い合わせが繰り返し寄せられることで生じる担当部署の負担が大幅に軽減され、問い合わせ件数そのものを削減する効果も期待できます。例えば、ある企業ではFAQサイト導入後、初歩的な問い合わせが実質的に皆無になったという事例もあります。
業務知識の蓄積・共有不足の解消
社内FAQは、これまで個々の社員に依存しがちだった業務ノウハウや知識を、組織全体で効率的に蓄積・共有するための基盤となります。ベテラン社員の持つ貴重な知識や、各部署で発生した具体的な問題の解決策などがFAQとして形式化されることで、時間や場所を問わず全社員のアクセスが可能です。
特定の個人しか知らない情報という属人化の問題が解消され、社員間で情報格差が生じることを防ぐことができます。常に最新の情報に更新することで、業務品質の標準化にも貢献します。
業務効率化を促進し生産性向上に貢献
社内FAQは、担当部署が頻繁な問い合わせ対応に追われる非効率な状況を改善し、組織全体の業務効率化を促進します。質問対応に費やされていた時間と労力を削減できるため、バックオフィス部門の担当者はより専門性の高い業務や優先度の高い課題に集中することが可能です。
また、社員が疑問を即座に自己解決できるようになることで、業務の中断が減り、本来の業務に集中できる時間が増加します。結果として、個々の社員だけでなく組織全体の生産性向上が見込まれるというメリットが生まれます。
社員への教育コストを削減
社内FAQは、新人や中途入社の社員に対する教育コストを大幅に削減できる、非常に有効なツールです。業務に関する基本的なルールや、よくある質問とその回答をFAQとして整理しておくことで、新入社員は疑問が生じた際、毎回先輩社員に尋ねることなく、自ら情報を参照して学習を進められます。
これにより、教育担当者の負担が軽減されるだけでなく、教える内容が標準化されるため、誰が指導しても一定の質を保った教育が可能になります。また、専門用語には注釈を付けるなど、社員の経験に関わらず理解しやすい内容にすることが大切です。
社内FAQに設置するカテゴリの種類
社内FAQでは、社員が必要な情報を効率よく見つけられるよう、カテゴリによる分類が不可欠です。質問内容や関連部門ごとに情報を整理し、階層化することで、検索性を大幅に向上させることが可能です。
社内FAQのカテゴリ例には以下があります。
- 人事・労務
- システム
- 財務・経理
- 社内オフィス
- 業務プロセス
これらのカテゴリは、会社の規模や業種に応じて追加・調整することが可能です。たとえば、製造業であれば「安全管理」、医療機関であれば「患者対応」といった固有のカテゴリを設定することで、より実用的な社内FAQが実現できます。
社内FAQを構築する3つの手段
社内FAQの導入を検討する際、その構築方法にはさまざまな選択肢があります。それぞれの手法が持つ特徴や利点を正しく理解することは、自社にとって最適な方法を選ぶうえで重要です。ここでは、一般的な3つの構築手段について、具体例を交えながら解説します。
エクセルを利用する
社内FAQを手軽に構築する方法の一つに、Excelやスプレッドシートの活用があります。これらは無償で利用できるため、新たなシステムを導入する際のコストを抑えられる点が大きな利点です。多くの社員が日常的にExcelを使い慣れているため、新しい操作を覚える必要がほとんどなく、導入のハードルも低くなります。
質問と回答をセルに入力するだけで、すぐにFAQを作成でき、特別なシステムがなくても運用が可能です。作成したFAQは日々の業務の一部として自然に活用され、情報の共有や管理もスムーズに進みます。
社内ポータルサイトを利用する
すでに運用されている社内WebサイトにFAQページを追加するのも、有効な方法の一つです。既存のWebサイトにFAQを設けることで、社員は必要な情報にすぐアクセスできるようになります。この方法では、インデックスページの設定やキーワード検索機能の導入、カテゴリーやタグの活用によって、情報の閲覧性や検索性を高めることが可能です。
通常は、社内ポータルサイトの担当者や各部署の社員が、日常的に受けた質問とその回答を収集し、手動でFAQコンテンツとして作成・追加していく運用が行われます。ただし、Webページの作成や管理には、HTMLなどの専門的な知識が求められる場合もあります。
生成AIツールを利用する
AIを活用したFAQシステムやチャットボットも、社内FAQの構築手段の1つとして注目されています。チャットボットは、社員が質問を入力するとAIが答えを導き出してくれるツールです。運用を通じてデータを収集し、精度を向上させていくため、事前に多くの質問と回答を用意する必要がない場合があるという特徴があります。
たとえば、あるFAQシステムには、約7万語の概念知識と約1,200万語の言語辞書を搭載した言語理解エンジンが備わっており、検索する単語が異なっても必要な情報にアクセスしやすいように設計されています。
社内FAQの作り方の手順
社内FAQを効果的に運用し、社員の自己解決を促進するには、計画的な作成プロセスが欠かせません。闇雲に情報を集めるのではなく、明確な手順を踏むことで、より使いやすく、継続的に活用されるFAQを構築できます。ここでは、その具体的な4つのステップを紹介します。
STEP1:ニーズ収集
社内FAQの構築で最も重要な初期ステップは、社員が本当に必要としている情報を見極めることです。この基盤づくりが、FAQの実用性や価値を大きく左右します。具体的には、人事部・情報システム部・経理部など、各部署の担当者にヒアリングを行い、頻繁に寄せられる質問を洗い出します。
あわせて、メール・チャット・Webフォームなどに寄せられた実際の問い合わせ記録も収集します。たとえば「経費精算の締め日はいつですか?」といった具体的な業務上の疑問や、社員が日々の業務で感じているモヤモヤを積極的に拾い上げることが重要です。
STEP2:カテゴリ設計
収集した質問は、ただ羅列するのではなく、体系的に整理することで検索しやすくなります。この段階では、情報の構造化と整理がカギになります。まずは、質問の「緊急性」や「優先度」を考慮し、問い合わせ頻度の高いものから順に並べ替えるのがおすすめです。
さらに、質問の内容や関連部署に応じて「タグ」や「フォルダ」を活用し、カテゴリごとに分類すると、情報が格段に探しやすくなります。こうしたテーマ別の分類によって、社員は必要な情報に素早くたどり着けるようになり、FAQ全体の使いやすさも向上します。
STEP3:コンテンツ作成
質問とカテゴリの設計が整ったら、次は具体的で分かりやすい回答を作成する段階です。各質問には、簡潔かつ明確な回答を心がけましょう。必要に応じて参考資料のURLなどを添えることで、利用者の理解が深まります。
AIツールを活用すれば、既存のドキュメントファイルをもとに、AIが自動でナレッジを生成してくれるため、FAQコンテンツの作成がよりスムーズです。作成したFAQは、社員が日常的に利用する社内ポータルサイトなどに組み込むことで、情報へのアクセスがしやすくなり、疑問の解消までの時間も短縮されます。
STEP4:テストと公開
社内FAQのコンテンツが整ったら、公開前に必ずテストを行い、品質をしっかり確認しておくことが重要です。実際に社員に使ってもらい、必要な情報にスムーズにたどり着けるか、回答の内容が正確で分かりやすいかどうかをチェックします。
FAQは一度作って終わりではなく、仕様変更や機能追加、新たな疑問の発生にあわせて、定期的に見直し・更新していく必要があります。また、FAQの存在が知られていなければ活用されないため、全社員に向けてその存在と使い方をしっかり周知し、日常的に活用してもらえるよう働きかけていくことも大切です。
社内FAQ設置時の注意点
社内FAQの導入は業務効率化に大きく貢献しますが、その効果を最大限に引き出すためには、いくつか注意すべき点があります。まず、従業員がスムーズに利用できるよう、使いやすさを重視することが欠かせません。あわせて、情報の正確性を常に保ち、最新の内容を提供し続けることが、信頼性を維持するうえで重要です。
さらに、社内全体にFAQの存在と活用方法を周知し、日常的な利用を促す工夫も必要です。加えて、機密情報を含む場合には、厳格なアクセス管理とセキュリティ対策を講じ、体制を整えることが求められます。これらのポイントを意識しながら、実用性の高いFAQを構築していきましょう。
効果的な社内FAQ構築で、業務効率とナレッジ共有を実現
社内FAQは、社員の疑問を迅速に解消し、自己解決を促すための重要なツールです。これにより、担当部署の問い合わせ対応の負担が軽減され、業務の効率化や生産性の向上に大きく貢献します。また、個人に属人化していた業務知識が組織全体で共有・蓄積され、新人教育にかかるコストの削減にもつながります。
社内FAQは「答えを探す仕組み」から「組織を育てる仕組み」へと進化しています。社内に散らばる情報や知見を資産として活用することで、持続的な業務改善と人材育成の基盤を築くこと重要です。


