人事労務とは?仕事内容や向いている人の特徴・課題と解決策を解説
公開日 2025/10/03
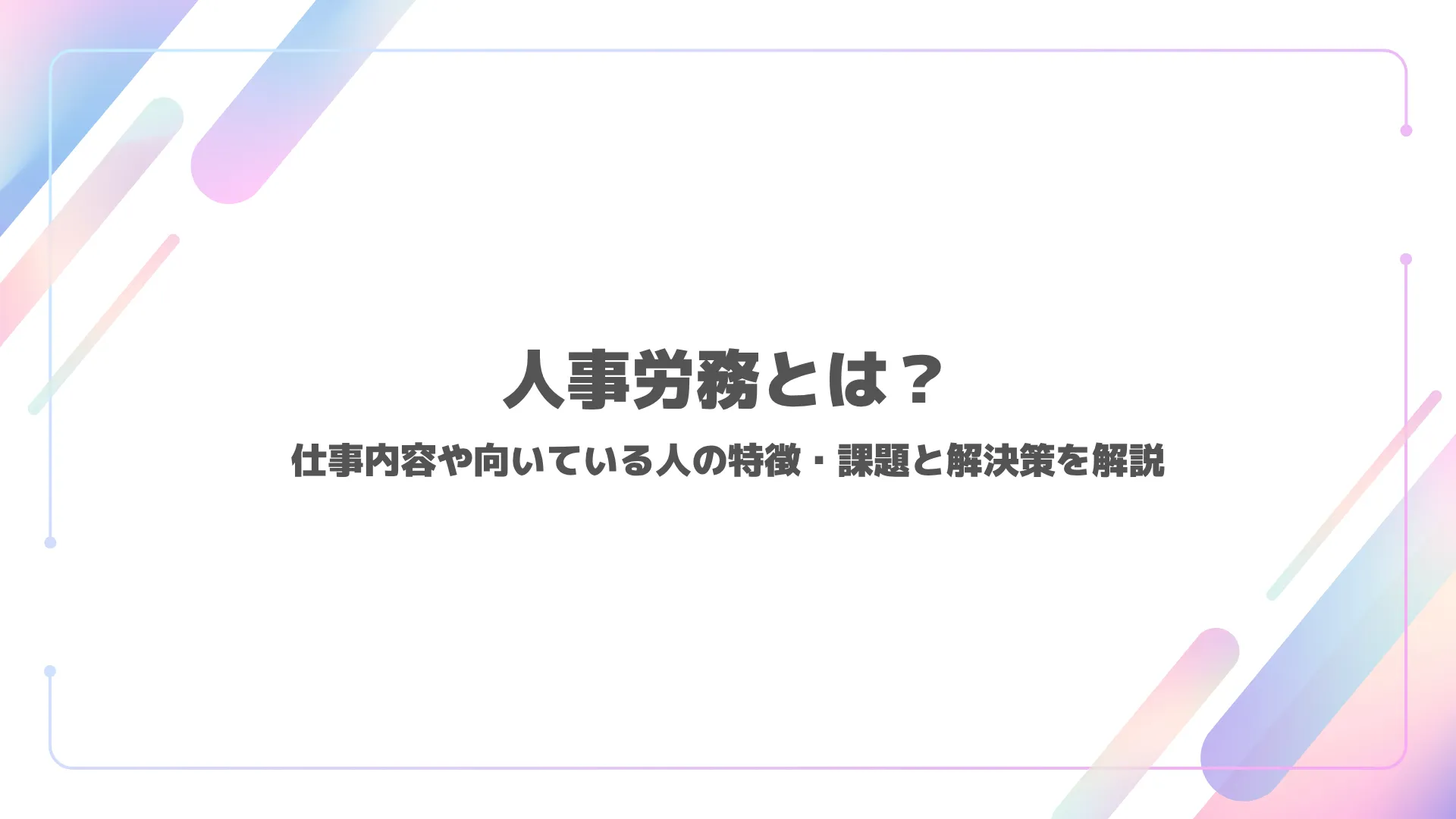
人事労務は、採用活動や人材育成などの組織における人材戦略を支える「人事」と、給与計算や勤怠管理など、社員が安心して働ける環境づくりを担う「労務」にわかれます。どちらも企業の成長と従業員の働きやすさを支える重要な役割を担います。
本記事では、人事労務の幅広い仕事内容をはじめ、求められるスキルや役立つ資格、仕事のやりがいや直面する課題などを網羅的に解説。さらに、人事労務の仕事に役立つITツールも紹介します。
目次
人事労務とは
人事労務とは、企業で働く従業員に関する業務全般を指す言葉として使われています。業務内容は大きく「人事管理」と「労務管理」に分かれますが、いずれも人材を対象とするため、まとめて「人事労務」と呼ばれるのが一般的です。
人事管理は、採用活動や人材育成、評価制度の構築などを通じて、従業員の能力を最大限に引き出し、組織の活性化を図る役割があります。
一方、労務管理は、就業規則の作成・改定、給与計算、勤怠管理、社会保険手続きなどを通じて、従業員が安心して働ける職場環境を整えることが目的です。
中小企業では人事と労務を1人の担当者が兼務するケースも多い一方、従業員数の多い企業では、それぞれ専門部署として分かれている場合もあります。業務領域は異なりますが、どちらも従業員の働きやすさと組織の成長に直結する、非常に重要な領域です。
人事労務の仕事内容|人事編
人事は採用から社員教育、人事評価や人員配置まで幅広く担当し、社員の特性を理解しながら組織の活性化と成長を支える重要な役割を担います。
ここでは、人事における主な仕事内容について紹介します。
新入社員や中途社員の採用
人事の重要な業務の一つが、新卒採用や中途採用などの人材の確保です。採用活動では、会社の経営戦略や各部門の人員ニーズを踏まえ、必要な人材を見極める力が求められます。
新卒採用は将来性やポテンシャルを重視し、毎年一定の時期に計画的に行われます。一方、中途採用は欠員対応や事業拡大などに応じて随時実施され、即戦力としてのスキルや経験が重視されます。いずれも戦略的な視点と現場理解が欠かせません。
社内の人材育成
人事の業務には、社員の成長を支援する「人材育成」も含まれます。社内教育や研修を通じて、業務に必要な知識やスキル、コンプライアンス意識の向上を図ります。
たとえば、新人研修では企業理念や経営方針の理解を促し、ビジネスマナーや基本的な業務知識を教えるのが一般的です。研修は勤続年数や職種に応じて継続的に行われ、社員一人ひとりの成長を後押しすることで、組織全体の力を高める役割を担います。
人事評価制度の作成
人事評価制度の作成は、従業員の給与や賞与に影響するため、公平性を確保することが不可欠です。業績やスキル、目標達成度などにもとづいた明確な評価基準を設け、上司の主観に左右されない仕組みを整える必要があります。
社内研修や1on1ミーティングと連携させることで、成長過程や日々の努力をより適切に評価でき、従業員の納得感やモチベーションの向上につながります。人事評価制度の整備は、従業員の働きがいを高め、企業の持続的な成長を支える重要な業務です。
配置・異動などの人材配置の検討
人材配置の検討では、経営層と連携し、新入社員の配属先の決定をはじめ、従業員の部署異動、昇格・降格などを行います。企業によっては、他社への出向などを決定するケースもあります。
これらの判断は、事業戦略や組織の課題に応じて実施されますが、従業員の希望や適性、キャリア志向を考慮することも重要です。適切な人材配置は、業務の活性化や個々の能力発揮につながり、企業全体の生産性向上にもつながります。
人事労務の仕事内容|労務編
労務は給与計算や社会保険手続きのほか、従業員が安全かつ快適に働ける環境づくりを担います。ここでは、労務における主な仕事内容について紹介します。
給与計算
給与計算は、労務業務の中でも特に正確さが求められる重要な業務です。基本給に加え、時間外労働や深夜勤務に対する割増賃金、通勤手当や家族手当などの各種手当を反映させる必要があります。
また、社会保険料や所得税などの法定控除も正しく計算しなければなりません。従業員一人ひとりの勤務状況や契約内容に応じて計算を行うため、細かな確認と慎重な対応が求められます。
勤怠管理
給与計算と同様に、勤怠管理も労務業務の中で非常に重要な役割を担っています。従業員の出退勤時刻や休憩時間、時間外労働、休日出勤、有給休暇の取得状況などを正確に把握・記録することが求められます。
これらの情報は給与計算の基礎となるだけでなく、長時間労働の抑制や法令違反の未然防止にも有効です。従業員の健康管理や企業のコンプライアンス強化にもつながります。
社会保険等の手続き
労務業務では、健康保険、厚生年金、雇用保険などの社会保険手続きを従業員に代わって行います。入社や退職、異動、出産、労災など、さまざまな場面で迅速かつ正確な対応が求められます。
保険料の計算や申請に加え、関連する書類の作成・提出も担当するケースが多く、企業と従業員の双方にとって欠かせない仕事です。
就業規則等の社内規定の作成
就業規則などの社内規定の作成は、従業員が安心して働くための基本的なルールを整える重要な業務です。労働時間や休憩、休日、給与といった労働条件を明文化し、労使間のトラブルを未然に防ぐ役割も果たします。
これらの規定は、労働基準法をはじめとする関連法令に則って作成する必要があり、自社の都合だけで自由に決められるものではありません。法改正や組織の変化に応じて、定期的な見直しや周知も求められます。
従業員の健康・安全衛生の管理
従業員の健康・安全衛生の管理は、職場環境を整えるうえで重要な労務の業務です。定期健康診断の実施は法的に義務づけられており、入社時や年1回以上の実施が必要です。さらに、近年では従業員のメンタルヘルスを守るためにストレスチェックの導入も進んでいます。
特に建設業や運送業では、安全衛生に関する法的な基準が他業種より厳しく定められており、より一層の配慮が求められます。
労務トラブルへの対応
労務は、パワハラやセクハラといったハラスメント、賃金の支払いに関するトラブル、人間関係の摩擦など、職場で起こるさまざまなトラブルへの対応も担います。こうした問題は職場全体の士気に影響を及ぼすため、迅速かつ丁寧な対応が不可欠です。
また、社内の相談窓口を労務が担当するケースも多く、社員が安心して働ける環境づくりに貢献しています。適切な対応により、信頼感の向上や離職率の低下にもつながります。
人事労務に向いている人の特徴
人事労務の仕事には、対人対応と正確な事務処理の両面が求められるため、幅広いスキルが必要です。人事労務に向いている人の特徴を以下にまとめました。
- コミュニケーション能力が高い人
- 観察力がある人
- 事務能力が高い人
- 労働関連法に関する知識がある人
- 問題解決能力がある人
まず、人事では採用や面談、社内調整など人と関わる機会が多いため、信頼関係を築けるコミュニケーション能力がある人が向いています。また、従業員の変化や組織の課題を見抜く観察力も重宝されます。
一方、労務では給与計算や手続き業務など正確さが問われる場面が多く、事務能力が高い人が適任です。労働関係法への理解がないと法的トラブルに発展する恐れがあるため、基礎的な知識の習得も欠かせません。
日々発生する問題に対し、冷静かつ柔軟に対応できる問題解決力がある人が、人事労務に向いている人だといえるでしょう。
人事労務に求められるスキル
人事労務の仕事内容や向いている人の特徴を紹介しました。では、この仕事で求められる具体的な能力とは何でしょうか?
ここでは、特に重要な4つのスキルについてわかりやすく解説します。
コミュニケーション能力
人事労務では、採用や人事評価をはじめ、労務管理の現場でも多くの人と話す機会があります。当事者から丁寧に話を聞き、相手の意図を正確に汲み取る能力が求められます。
そのうえで、分かりやすく説明や回答を行い、誤解を防ぐ力も必要です。こうしたコミュニケーション能力は、働きやすい環境づくりや信頼関係の構築など、人事労務領域で特に欠かせないスキルです。
正確な法律・制度の知識
人事労務の業務は、労働基準法や職業安定法、男女雇用機会均等法など多くの法律に関わります。これらの法律を正確に理解し遵守することは、労務トラブルの防止につながり、従業員が安心して働ける環境を整えるうえで欠かせません。
また、法改正にも敏感に対応し、常に最新の知識をアップデートし続ける姿勢が求められます。こうした法律・制度に関する正確な知識の習得や、そしてそれを遵守する姿勢は、人事労務担当者にとって最も重要な能力の一つです。
業務を正確に進める能力
人事労務の業務は、給与計算や社会保険の手続きなど、細かい計算や正確な処理が求められるため、ミスは許されません。そのため、丁寧に仕事を進められる人や、根気強く業務に取り組める人が向いています。
また、ダブルチェックやトリプルチェックなど、ミスを防ぐための確認体制を整えることも重要です。業務に集中して取り組めるようにスケジュール管理を徹底し、余裕をもって業務にあたることが求められます。
コンプライアンス意識の高さ
人事労務の業務では、従業員や入社希望者の個人情報を取り扱う機会が多くあります。そのため、人事労務の業務につく人には、情報漏えいを防ぐための社外秘密保持の徹底や、厳格な情報・セキュリティ管理など、高いコンプライアンス意識が必要です。
個人情報の適切な取り扱いは、従業員の信頼を守り、企業の社会的信用を維持するうえで非常に重要です。担当者は常にルールにもとづいた適切な情報管理を意識しなければなりません。
人事労務の仕事で役立つ資格
人事労務の仕事を効率的に進めるためには、専門的な資格が大いに役立ちます。ここでは、人事労務の仕事で役立つ代表的な資格をいくつかご紹介します。
社会保険労務士
社会保険労務士は、労働や社会保険に関する法律の専門知識を有する国家資格です。労働・社会保険に関する手続きの代行が法的に認められている唯一の資格であり、行政機関への書類提出、就業規則の作成、労務トラブルの予防・対応など、幅広い実務で活躍できます。
この資格を取得することで、人事労務の現場で専門性を発揮しやすくなり、キャリアアップや独立開業にもつながります。
キャリアコンサルタント
キャリアコンサルタントは、職業選択や能力開発などに関する相談・助言を行う国家資格です。人事労務の現場では、従業員一人ひとりの適性や希望を把握したうえでの人材配置や、キャリア形成の支援に役立ちます。
また、個別面談の際に、従業員の本音や悩みを引き出すコミュニケーションスキルとしても有効です。組織全体の人材育成・定着を支えるうえで、非常に有用な資格といえるでしょう。
参考:厚生労働省「キャリアコンサルティング・キャリアコンサルタント」
ファイナンシャル・プランニング技能検定
ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)は、保険・年金・税金・資産運用など、個人のライフプランに関わる幅広い知識を問う国家資格です。人事労務の現場では、退職金制度や企業年金などの福利厚生設計や運用をサポートする際に活かせるほか、従業員の安心感や満足度の向上、離職率の低下やモチベーション維持につながります。
また、従業員向けの資産形成セミナーの企画など、ライフプラン支援などにも活用できます。資産形成や老後設計を支援する際に、専門的なアドバイスができる点が強みです。
メンタルヘルス・マネジメント検定
メンタルヘルス・マネジメント検定は、職場におけるメンタルヘルス管理の知識と対処法にフォーカスした資格です。Ⅰ種からⅢ種まであり、人事労務に特に役立つのは最上級のⅠ種「マスターコース」です。
この資格を持つことで、従業員のストレスや心の不調を早期に発見し、適切な対応や環境改善を図れます。従業員の健康管理や職場の安全衛生向上に貢献できる重要な資格といえます。
人事労務の仕事のやりがい
人事のやりがいは、会社の組織づくりに直接関われる点にあります。経営陣から学生まで幅広い層と関わることで、多様な視点を吸収でき、従業員の成長を間近で見守ることができます。こうした経験を通じて、会社の顔としての責任感や達成感を感じられるのも魅力です。
一方、労務の仕事は、従業員のライフイベントをサポートしながら、安心して働ける環境づくりに貢献できる点が大きなやりがいとなります。法律や制度に基づき、従業員と企業の双方を守っているという実感が得られ、働くために必要な専門知識も身につきます。
こうした役割を通じて、会社全体の安定と成長に寄与できることが人事労務の仕事の魅力です。
人事労務の仕事の課題
人事労務担当者は、働き方の変化やペーパーレス化、複雑な社会保険手続きなど、さまざまな新課題に直面しています。
ここでは、現在多くの企業が抱えている、人事労務部門における課題を紹介します。
雇用形態・働き方の多様化
勤務形態は正社員だけでなく、契約社員、派遣社員、パート・アルバイト、業務委託など多様化しています。また、働き方も出社だけでなく、テレワークや時短勤務などさまざまです。
こうした多様化に対応するために、人事労務は雇用形態ごとの労働条件の管理や就業規則の整備、労働時間の適切な管理が求められます。変化する働き方に柔軟に対応することが、人事労務の重要な課題となっています。
ペーパーレスへの対応
コスト削減や環境負荷の低減を目的に、これまで紙で管理していた人事労務の書類や記録をデジタル化する動きが加速しています。しかし、システムの導入には初期投資や運用コストがかかるほか、社員のITスキル向上も不可欠です。
人事労務分野において、こうした課題をクリアしながら、効率的かつ正確なデジタル管理体制を構築すること求められています。
社会保険手続きの複雑さ
社会保険の手続きは非常に複雑で、専門知識があっても多くの時間を要するため、人事労務担当者の負担が大きくなりがちです。この負担は、残業時間の増加や業務への不満につながる可能性もあります。
人事労務部門の業務負担を軽減して効率化を図るためには、社会保険関連業務を一元管理できる勤怠管理システムやITツールの導入が不可欠です。
人事労務の仕事の課題を解決するにはITツールの導入が効果的
人事労務の業務効率化には、労務管理システムや給与計算システムの導入が非常に効果的です。これらのシステムを活用することで、入退社や社会保険の手続き、勤怠管理、給与計算や給与明細の発行、さらにはマイナンバーの管理まで、一元的かつ効率的に行えます。
また、従来の手作業によるデータ転記や計算ミスを減らし、担当者の負担を大幅に軽減可能です。さらに、法改正にもシステムが自動対応するため、常に最新の制度にもとづいた処理ができ、安心して業務を進められます。
労務管理システムと給与計算システムを連携させることで、データ管理の簡略化と業務のスムーズな運営が実現するといったメリットもあります。
人事労務の仕事に役立つITツール
ここでは、人事労務の仕事に役立つチャットボットツール「IZANAI(イザナイ)」と、「ActiBook(アクティブック)」について紹介します。
FAQを最適化するAIチャットボット「IZANAI(イザナイ)」
「IZANAI(イザナイ)」は、生成AIを活用したチャットボットツールです。社内規定や福利厚生、勤怠管理に関する問い合わせ対応を自動化・効率化し、人事労務部門の定型業務負担を大幅に軽減します。24時間365日対応可能で、従業員の利便性向上にもつながります。
また、社内規定や研修資料を学習させることで、従業員の自己学習を支援し、人材育成の効率化にも有効です。
資料やWebサイト、PDFやExcelファイルを簡単に登録でき、ノーコードで最短3分で導入できるのが大きな魅力です。社内FAQの改善と業務効率化を通じて、生産性向上に貢献します。
参考:FAQを最適化するAIチャットボット|IZANAI Powered by OpenAI
資料・動画を簡単に電子ブック化「ActiBook(アクティブック)」
「ActiBook(アクティブック)」は、資料や動画を簡単に電子ブック化し、クラウド上で配信できるツールです。
人事労務での活用により、新入社員向けのオンボーディング資料を一元管理できます。また、閲覧状況を可視化することで研修の効果を確認することも可能です。さらに、部署ごとに必要な情報を配信できるため、効率的な情報共有が実現します。
コメント機能やプッシュ通知も備えており、従業員の理解促進やフォローアップにも役立ちます。無料プランから利用でき、導入のハードルが低いのも大きな特徴です。
ITツールを活用して人事労務業務を効率化しよう
人事労務は、従業員の採用・育成から、給与・勤怠管理、社会保険手続きまで、幅広い役割を担う重要な業務です。
人と組織をつなぎ、会社の成長を支えるやりがいのある分野ですが、近年は雇用形態の多様化やペーパーレス化への対応、複雑化する社会保険手続きなど、多くの課題が顕在化しています。
こうした課題を解消し、担当者の負担を軽減するには、ITツールの活用が欠かせません。業務の効率化やミスの防止を図り、人事労務の生産性を高めることができます。
本記事で紹介したITツールには無料トライアルが用意されています。導入を検討中の方は、まずは試しに利用してみるのがおすすめです。
「IZANAI(イザナイ)」の詳細はこちら
「ActiBook(アクティブック)」の詳細はこちら


