情報システム部門(情シス)の問い合わせ対応を効率化するには?具体的な方法やツールを紹介
公開日 2025/10/03
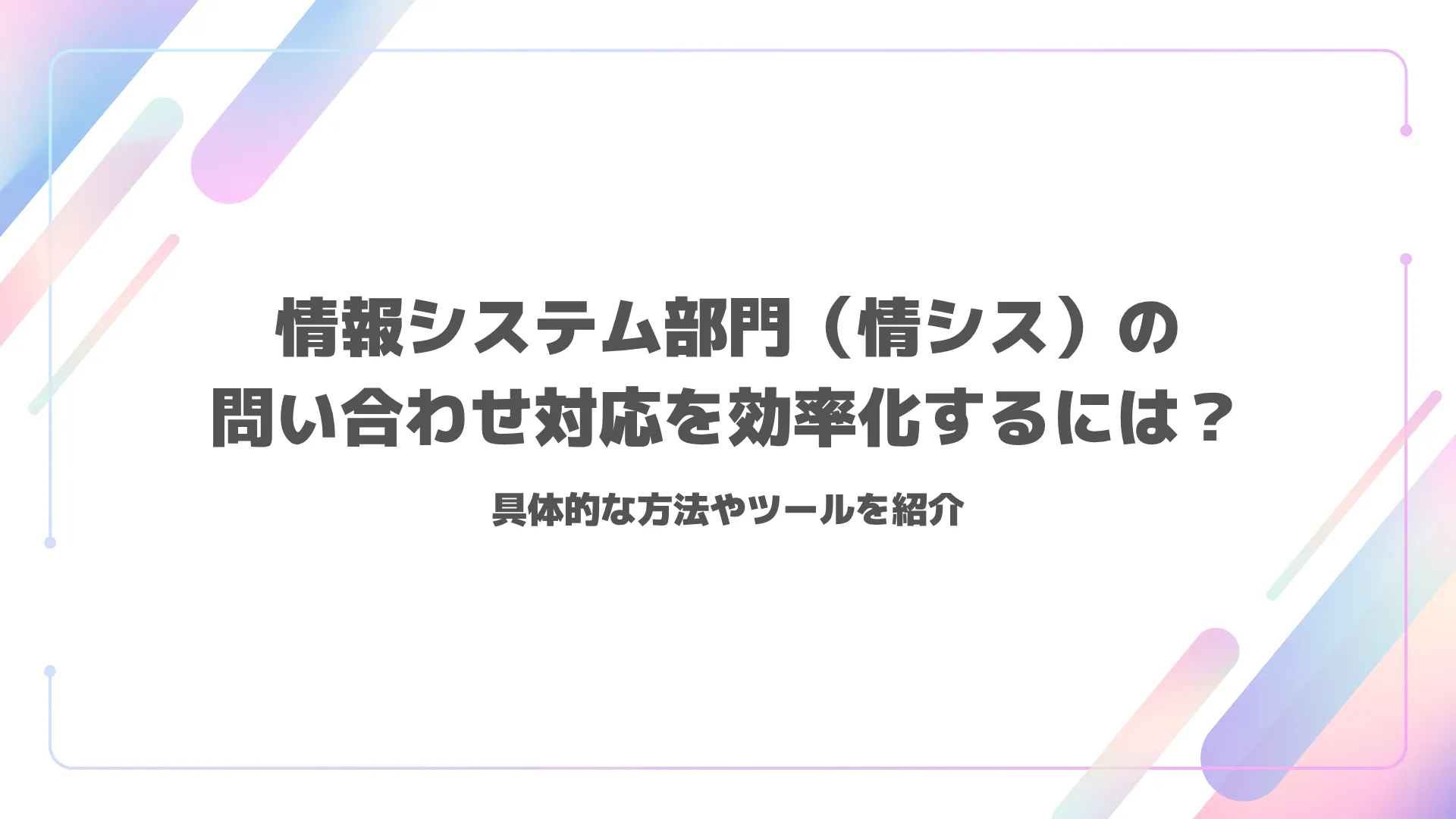
パスワードの再発行やメール設定の不具合、操作方法の確認など、情報システム部門(情シス)には毎日のように問い合わせが届きます。気づけば対応だけで一日が終わり、進めたかった改善や戦略の検討に手をつけられない日もあります。
この状態が続けば、業務は滞り、生産性は下がります。だからこそ、問い合わせ対応に時間を奪われない仕組みを用意し、業務に集中できる環境を作ることが大切です。
そこで本記事では、問い合わせ対応を効率化するための具体的な方法と、負担を減らせるツールを紹介。日々の業務改善から中長期の体制づくりまで、すぐに活用できるヒントを多数解説しています。
目次
情報システム部門(情シス)とは?
情報システム部門(情シス)は、企業のIT環境を安定して運用するための中心的な部署です。システムやネットワークの導入から日常の運用・保守・管理までを幅広く担い、社内のセキュリティ強化やIT戦略の立案、新しいシステムやツールの選定、外部ベンダーとの調整なども担当します。
日々の業務の中では、計画的な改善や戦略業務に加え、ヘルプデスク的な問い合わせ対応も発生します。この負担を減らす仕組みを取り入れることで、部門としての成果を高めやすくなります。
参考:ヘルプデスクとは?役割や仕事内容からメリット・デメリットまで解説
情報システム部門(情シス)が問い合わせ対応に追われる原因
情報システム部門が問い合わせ対応に追われる背景には、人手不足やマニュアル・FAQの整備不足、従業員のITスキルの差などが挙げられます。これらが重なることで、同じ質問や軽微な依頼が繰り返し発生し、業務負担が増え続けます。以下では、それぞれの理由を解説します。
人員が不足している
企業のデジタル化が進み、導入するシステムやツールは年々増えています。一方で、情報システム部門の人員はそれに比例して増えるとは限りません。業務量が増えると、日常の運用や保守に加えて新規導入の対応も重なり、担当者一人あたりの負担は大きくなります。問い合わせ対応に時間を取られれば、後回しの案件が溜まりやすくなり、業務の停滞を招きます。
マニュアルやFAQの準備が不十分
利用者が自分で解決できる仕組みが整っていない場合、問い合わせは増加します。マニュアルやFAQがない、情報が社内に点在している、内容が古く現状と合わないなどの状態では、必要な手順にたどり着けません。説明がわかりにくければ、利用者は直接情シスに依頼するしかなくなり、問い合わせ数が増え続けます。
参考:FAQを最適化するAIチャットボット「IZANAI Powered by OpenAI」
従業員によってITスキルにバラつきがある
社内にはIT操作が得意な人もいれば、基本的な作業に不安を感じる人もいます。初期設定やパスワード変更、メールの設定など、簡単な作業でも自力で対応できないことがあります。そのため、軽い質問や小さな依頼が繰り返され、情シスの時間を圧迫します。スキル差が大きいほど、この傾向は強まります。
「情報システム部門(情シス)に聞けばいい」という意識がある
問い合わせ窓口や対応範囲があいまいなままだと、「とりあえず情シスに聞けばいい」という意識が広がります。結果として、軽い確認や操作方法の質問まで日常的に持ち込まれ、本来の業務や優先順位を考慮しない問い合わせが増えてしまいます。この状態が続けば件数は減らず、計画業務や改善活動に充てられる時間が削られていきます。
情報システム部門(情シス)の問い合わせ対応を効率化するメリット
問い合わせ対応を効率化することは、日常業務の負担軽減だけでなく、IT部門全体の業務品質や組織の推進力を底上げするきっかけになります。対応の流れが整理されれば、従業員の働きやすさが高まり、計画的な業務推進や予算の有効活用にもつながります。
ここでは、その効果を3つの視点から解説します。
情報システム部門(情シス)の従業員の負担を軽減できる
問い合わせが減れば、1件あたりの対応時間や精神的な負荷も下がります。質問内容が整理され、回答までの流れがシンプルになれば、処理のスピードも自然と上がります。日々の負担が軽くなれば、残業を減らしたり休暇を取りやすくなったりと、働きやすい環境が整います。職場の雰囲気が安定すると担当者の定着率も上がり、やる気を持って仕事に取り組める状態が長く続きます。
問い合わせ対応以外のコア業務に集中できる
対応に追われる時間が減ると、ITインフラの運用や保守、セキュリティ対策、IT戦略の立案といった本来の業務に向き合えるようになります。時間に余裕があれば、システムの安定稼働や改善案の検討、新しいプロジェクトの推進もスムーズです。計画的に業務を進められるようになると、企業全体の競争力向上にも結び付きます。短期だけでなく長期的な成長の土台づくりにもなります。
余分なコストを減らせる
問い合わせ対応の効率化は、人員の稼働を改善し、限られたリソースをより価値の高い業務に回せる状態をつくります。追加で人を雇ったり外部に委託したりする必要が減れば、人件費や委託費の削減が見込めます。浮いた予算は、新しいシステムやツールの導入や、社員のスキルアップ研修など、将来の成長を後押しする投資に充てられます。
情報システム部門(情シス)の問い合わせ対応を減らす方法
問い合わせを減らすには、社内の情報提供の方法や従業員教育の仕組みも見直すことが重要です。ここでは、日常業務の負担を軽くし、改善につながる6つの方法を紹介します。
回答に使えるテンプレートを用意する
繰り返し寄せられる質問や依頼には、あらかじめ回答用の定型文や図解入りのひな形を用意しておくと便利です。たとえば「PCがネットに接続できない」など発生頻度の高い問い合わせは、状況確認から解決手順までまとめたテンプレートを作成することで、必要な箇所を少し修正するだけで返答できます。一度作ったテンプレートは再利用できるため、回答スピードの向上が期待できます。
問い合わせの仕方を他部門の従業員に周知する
問い合わせ経路が電話やメール、チャットなど複数あると、担当者は複数の場所を確認する必要があり負担が増します。窓口を1つに集約し、フォームに「対象システム」「発生日時」「状況説明」など必須項目を設定すれば、初回のやり取りから必要情報が揃います。無駄なやり取りが減ることで、処理のスピードと正確性が向上します。
マニュアルを作成・共有する
マニュアルの整備は、情シスの業務負担を軽減するうえで効果の高い方法です。社員が知りたい情報をひとまとめにし、すぐに見つけられる環境を整えておけば、日常的な質問の多くは自力で解決できます。
作成する際は、情シス内部用と他部門向けの2種類を用意するとよいでしょう。情シス向けには、質問別の対応手順を整理した資料を作成し、誰が対応しても一定の品質を保てる状態を目指します。対応基準が統一されていれば、担当者の交代や引き継ぎも円滑に進みます。
他部門向けの場合は、PCの初期設定やアプリの更新、エラー解消の手順などをまとめた操作マニュアルが適しています。印刷設定やネットワーク接続のように複雑な作業には、図解やスクリーンショットを添えることで理解が早まります。
完成したマニュアルは、社内ポータルやクラウド上で共有し、常に最新の状態を維持することが大切です。古い情報が残らないよう定期的に見直せば、問い合わせ件数を抑えやすくなります。
FAQ・チャットボットを導入する
FAQやチャットボットを取り入れることで、パスワード再発行やメール設定など、日常的に繰り返される問い合わせを自動で処理できます。チャットボットには、事前に登録したQ&Aを返すシナリオ型と、入力内容を理解して柔軟に答えるAI型があります。AI型は会話の流れから質問の意図を把握し、状況に合った手順を提示できるため、マニュアル検索が苦手な社員にも扱いやすい点が特長です。
たとえば、社内ポータルに設置したチャットボットに「VPNに接続できない」と入力すると、利用者の状況を確認する質問が返され、その回答に応じて設定手順や確認項目が案内されます。担当者が対応する前に解決するケースも増え、全体の問い合わせ件数を確実に減らせます。精度の高い応答は、最新の言語モデルを活用したツールであれば実現しやすく、導入効果を高めやすくなります。
参考:FAQを最適化するAIチャットボット「IZANAI Powered by OpenAI」
アウトソーシングを利用する
アウトソーシングとは、特定の業務を外部の専門業者に委託する方法です。一部の業務を専門業者に任せれば、情シスはシステム改善や新規プロジェクトといった優先度の高い業務に集中できます。委託先とは定期的に情報共有を行い、対応品質を確認することで、安定した運用を保てます。
ITスキル向上のための研修・講習を実施する
ITスキルを高めるための研修や講習も有効な手段の一つです。社内システムのログイン方法やファイル共有設定、セキュリティ対策などを身につけることで、問い合わせをせずに解決できる場面が増えます。オンライン動画やマニュアルとして記録を残せば、必要なときに繰り返し参照でき、学習効果が長く続きます。
情報システム部門(情シス)の問い合わせ対応を効率化するポイント
情シス部門の負担を減らすためには、やみくもにツールを導入するのではなく、組織の現状や従業員の利用実態を踏まえたうえで改善策を検討する必要があります。特に問い合わせ対応は従業員のITリテラシーや業務理解度によってばらつきが出やすいため、属人的な対応に頼らない仕組みづくりが求められます。
以下では、問い合わせ対応を効率化するうえで押さえておきたい3つの視点を紹介します。
原状や従業員のニーズに合う方法を選ぶ
最初に行うべきは、情報システム部門が現在どのような問い合わせに追われているのかを把握することです。質問の傾向や頻出パターン、発生頻度などを洗い出すことで、対応すべき課題が明確になります。
また、従業員側のニーズや使いづらさも見逃せません。「どこに何が書いてあるのかわからない」「何度も同じことを質問してしまう」といった現場の声に目を向ければ、必要なサポートの方向性が見えてきます。
そのうえで、FAQやチャットボット、マニュアル整備など、課題に合った改善手段を選びましょう。ただツールを導入するのではなく、「現場が使い続けられるかどうか」を判断軸にすることが大切です。
参考:FAQを最適化するAIチャットボット「IZANAI Powered by OpenAI」
従業員が使いこなせるツールを使用する
せっかくツールを導入しても、現場の従業員が操作に戸惑ってしまっては、本来の効果は期待できません。情報システム部門だけでなく、実際に問い合わせを行う従業員側にとっても扱いやすいことが前提になります。
インターフェースの直感性や導線のわかりやすさ、検索性の高さなど、現場の使用感を意識して選ぶことがポイントです。ITに不慣れな人でもスムーズに活用できる設計かどうか、事前に検証しておきましょう。社内説明会の開催や簡単な操作マニュアルを用意するのも効果的です。
マニュアルやツールの運用体制を整える
問い合わせ対応の効率化は、一度ツールやマニュアルを導入すれば完了するものではありません。社内制度やシステム環境の変化に合わせて、内容を定期的に更新・点検する体制が必要です。
特にマニュアル類は、古い情報が放置されたままだと、誤った操作や混乱を招くリスクがあります。更新フローや管理担当を明確にしておき、定期的な見直しを組織内でルール化しておきましょう。
また、更新履歴を記録したり、変更点を周知したりすることで、利用者の混乱も防ぎやすくなります。情報の鮮度と正確性を保つことは、問い合わせ数の削減に効果があります。
ツールを導入し情報システム部門(情シス)の問い合わせ対応を減らした事例
ここでは、チャットボットやマニュアル作成ソフト、ナレッジ管理ツールなどを活用し、情シスの負担軽減に成功した3社の成功事例を紹介します。
株式会社ディー・エヌ・エー|社内ヘルプデスク業務を一元化し、自己解決率を向上
株式会社ディー・エヌ・エーは、ゲームやECをはじめ、ライブストリーミング、ヘルスケア、スポーツなど多様な事業を展開しています。同社では、社内ヘルプデスクの運用負担軽減が長年の課題でした。窓口は一本化されていたものの、対応手段はメールが中心で時間を要し、社内Wikiやポータルに掲載された情報は部門ごとに散在。情報を横断的に検索できず、知識が特定の担当者に依存しやすい状況でした。
こうした背景から、クラウド型カスタマーサービスプラットフォーム「Zendesk」を採用。ヘルプセンターとFAQを活用し、受付から管理までを統合しました。移転や新システム導入など問い合わせが増える局面では、関連FAQを事前に整備し、利用者による自己解決を促進しています。
導入後は、週次の問い合わせ件数が約250件から200件程度に減少。残った相談は高度な専門性を要するものが中心となり、担当者は複雑な案件に集中できるようになりました。対応品質の均一化も進み、今後はナレッジ更新ルールの策定やSlack連携による情報提供体制の強化を予定しています。
参考:効率化のカギは自己解決率アップ 情報収集力に左右されないナレッジ活用の実現へ│Zendesk
内海産業株式会社|マニュアル作成時間を50%削減、業務フローの統一にも成功
内海産業株式会社は、販売促進や購買促進の企画立案、プレミアムグッズやSPツールの制作を手がける企業です。社内では、基幹システムや各支店からの問い合わせ対応を担う応援部が、操作マニュアル作成に多くの時間を費やしていました。従来の手作業による画面キャプチャ方式では、撮り漏れや説明不足が生じやすく、問い合わせ削減や教育効率の向上につながらない状態が続いていました。
解決策として、マニュアル作成ソフト「iTutor」を導入。システム導入時や問い合わせ対応用の手順書を作成し、社内掲示板で共有することで、拠点ごとに異なっていた書式を統一しました。
その結果、作成時間を50%以上削減し、正確で統一感のある手順書の提供が可能になりました。今後は全国の拠点展開や動画マニュアルの活用により、さらなる業務標準化を推進していく計画です。
参考:【導入事例/内海産業株式会社様】社内システムのマニュアル作成にiTutorを活⽤し、作業時間を50%以上削減︕│iTutor
株式会社不動産SHOPナカジツ|情報検索時間をゼロに近づけ、教育期間を大幅短縮
株式会社不動産SHOPナカジツは、不動産仲介、新築住宅、リフォームなど幅広い事業を展開する企業です。店舗拡大を進める中で、社内マニュアルが複数の場所に分散し、情報の所在が不明確な点が課題となっていました。知識が特定の社員に集中し、新入社員への説明も口頭が中心で、効率的な教育体制を整備できない状況でした。
対応策として、ナレッジ共有ツール「NotePM」を導入。社内ドキュメントを「マニュアル」「問い合わせログ」「資料メモ」に分類し、リンクの共有で常に最新版にアクセスできる環境を用意しました。また、「まず検索し、なければ作成して蓄積する」という運用ルールを徹底し、タイムライン機能で新着情報を即座に把握できる仕組みを構築しています。
この体制により、社内システムの操作方法からPC設定までを一括で参照可能になり、教育期間の短縮と情報共有の円滑化を実現。店舗拡大に向けた業務体制の整備も着実に進んでいます。
参考:【導入事例】ナレッジを集約し社内の問い合わせ対応を効率化 株式会社不動産SHOPナカジツ│NotePM
情報システム部門(情シス)の問い合わせ対応の負担を減らせるツール
近年、社内の問い合わせを効率化するため、専門ツールを導入する企業が増えています。ツールを導入することで、パスワード関連や操作説明などの繰り返し業務を自動化し、付加価値の高い業務に集中できる環境を提供することができます。
ここでは、情シスの負担軽減に役立つ5つのツールを紹介します。
IZANAI Powered by OpenAI(イザナイ パワード バイ オープンエーアイ)

出典:IZANAI Powered by OpenAI公式サイト
IZANAI Powered by OpenAIは、社内のマニュアルや技術資料、WebサイトのURLを登録するだけで利用できる生成AI型チャットボットです。RAG(検索拡張生成)を高度化した「ナレッジグラフ(Graph RAG)」技術を搭載しており、複数文書の関連性を整理したうえで回答を提示します。従来のキーワード検索やFAQ参照とは異なり、業務の背景や手順の流れを踏まえた一貫性のある応答が可能です。
日常的に発生するパスワード再設定やシステム利用方法の案内といった対応は、情シス部門にとって負担になりやすい業務です。IZANAI Powered by OpenAIを導入すれば、これらをAIが自動処理し、担当者が改善施策やプロジェクト推進など、より価値の高い業務に集中できる環境を構築できます。
また、利用ログから質問の傾向や不足情報を把握できるため、FAQやマニュアルの品質向上にも役立ちます。初期設定は短時間で完了でき、導入直後から効果を感じやすい設計であることも魅力です。
参考:FAQを最適化するAIチャットボット「IZANAI Powered by OpenAI」
ActiBook(アクティブック)

ActiBookは、PDFやWord、Excel、PowerPointなどのファイルを、パソコン・スマートフォン・タブレットで閲覧可能な電子ブック形式に変換できるツールです。紙冊子のレイアウトを保ちながら、簡単な操作で電子化でき、マニュアルや手順書の共有方法を効率化します。ページ別の閲覧数や検索キーワードなどを記録し、どの情報がよく参照されているかを把握できる機能もあります。
頻繁に改訂が必要な資料は、印刷や再配布の負担が大きくなりがちです。ActiBookを導入すると、電子化した資料をリンクで共有でき、更新後も同じURLからアクセス可能になります。配布作業の手間を減らしつつ最新情報を届けられます。
また、検索機能付きの電子ブックとして活用できるため、必要な情報を探しやすくなります。無料プランも用意されており、初期費用をかけずに効果を検証しながら運用範囲を広げられます。
Zendesk(ゼンデスク)
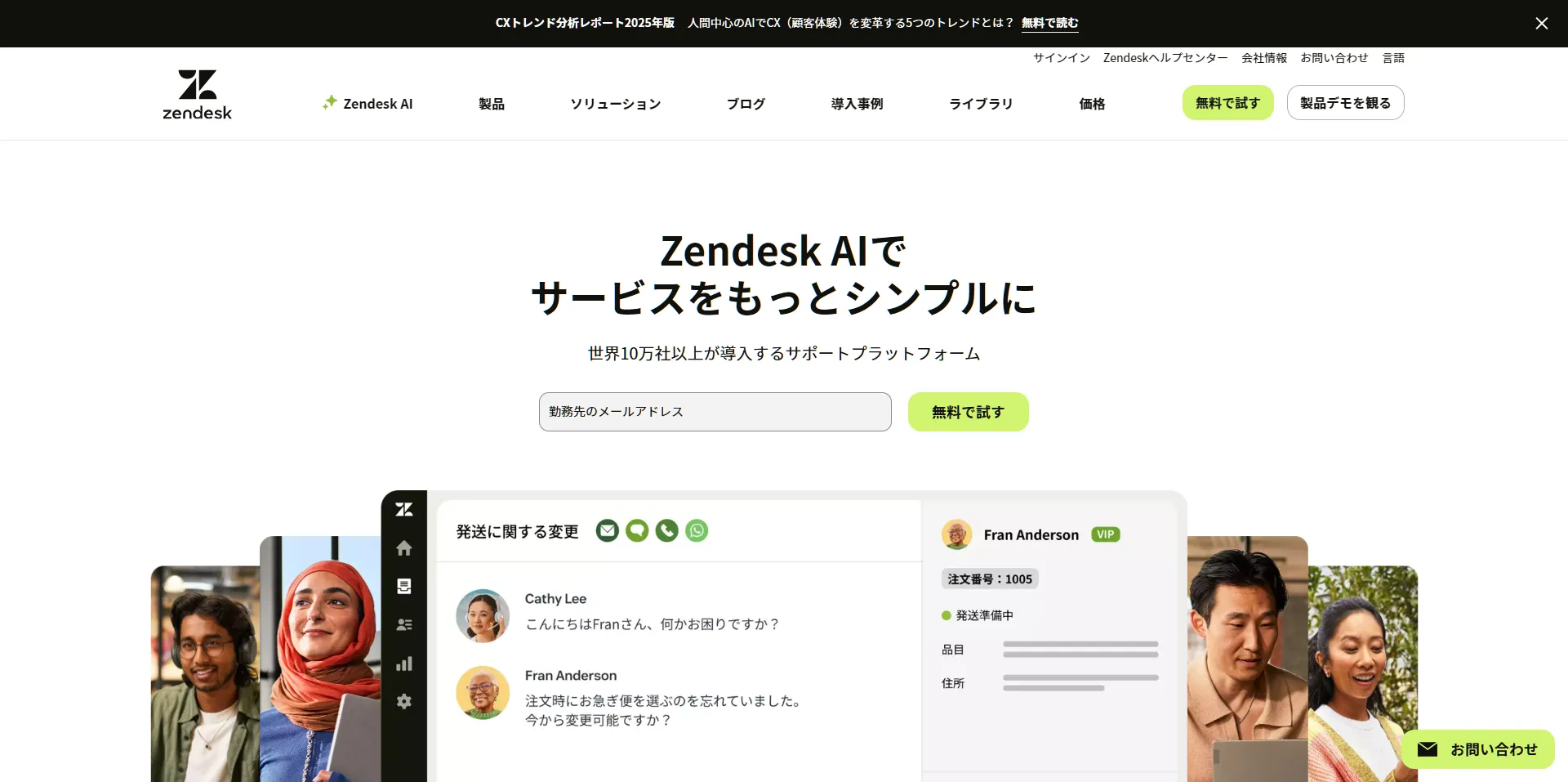
出典:Zendesk公式サイト
Zendeskは、世界10万社以上で導入されている統合型カスタマーサービスソフトです。メールやチャット、電話など複数の窓口から届く問い合わせを一元管理し、FAQサイトやコールセンター機能まで利用できます。テンプレートを選ぶだけでFAQページを公開でき、デザインの変更やコンテンツ履歴の管理、検索用タグの設定にも対応しています。
問い合わせは「チケット」と呼ばれる単位で整理され、進捗や対応時間をひと目で確認できます。FAQと連動してAIが解決策を提示する仕組みもあり、担当者が対応にかける時間を減らしながら、利用者が自分で解決できる環境を整備できます。
クラウド型のため専用設備を用意せずに開始でき、リモートワーク環境にも適しています。企業規模を問わず導入実績があり、場所や環境を選ばず安定した問い合わせ対応体制を築けます。
iTutor(アイチューター)

出典:iTutor公式サイト
iTutorは、PC上の操作を記録するだけで、マニュアルやデモ動画、eラーニング教材を自動生成できるマニュアル作成ソフトです。文字や静止画だけでは伝わりにくい複雑な手順も、動画化することで直感的に理解しやすくなります。録画後はスライド形式で編集でき、テキストの追加や注釈、画像の差し替えなども簡単に行えます。
作成したコンテンツは社内研修やマニュアル配布にそのまま活用でき、更新や再利用も容易です。定期的なシステム更新や新入社員研修など、繰り返し発生する教育業務の負担を減らせます。テスト問題の作成機能も備えており、理解度の確認や習熟度の向上にも役立ちます。
利用環境に合わせた柔軟な運用が可能で、社内の情報共有やスキル定着を後押しします。
NotePM(ノートピーエム)

出典:NotePM公式サイト
NotePMは、社内のマニュアルや業務ノウハウを一元管理できるナレッジ共有ツールです。WordやExcelなどのファイルもインポートでき、これまで部署ごとに分散していた情報をまとめて保存できます。全文検索機能を持ち、登録した文書や添付ファイルの中から必要な情報をすぐに見つけられます。
マニュアルや手順書のほか、過去のトラブル対応記録や参考資料も蓄積でき、担当者が変わっても同じ情報を参照しながら業務を進められます。アクセス権限の設定やコメント機能もあり、編集やフィードバックのやり取りもスムーズです。
社内情報の検索性を高めつつ、ナレッジの更新や共有を継続しやすい環境を維持できます。
問い合わせ対応の改善が、情シスの働き方を変える
問い合わせ対応の効率化は、情シス部門の負担軽減だけでなく、企業全体の生産性向上を高められます。マニュアルやFAQの整備、チャットボットの活用、ナレッジ共有の強化など、日々の業務をスムーズに進めるための手段は数多くあります。大切なのは、自社の課題や利用環境に合わせて導入しやすい方法を選び、運用体制を整えることです。
業務の流れを整理し、問い合わせ件数を減らすことで、担当者は改善やコア業務に時間を割けるようになります。対応の効率が上がれば、IT環境の安定化や従業員の満足度向上を図れます。
小さな改善を積み重ねることが、情シスの働き方をより良い方向へ変えていく力となります。


