ナレッジマネジメントとは?知識共有の仕組み作りとツールの選び方のポイント、成功事例を紹介
公開日 2025/10/21
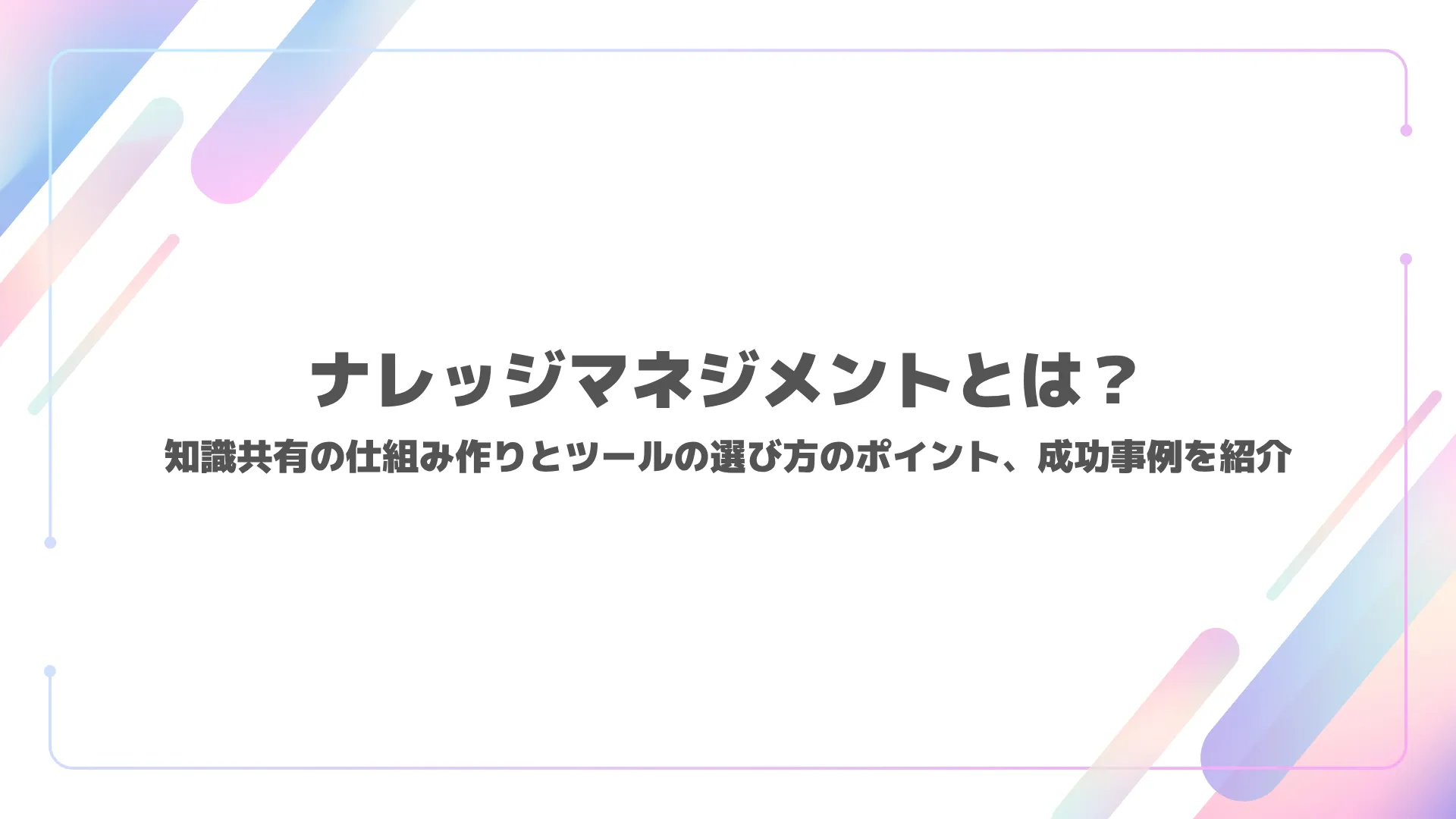
「教える人によって内容が違う」「辞めた人の知識が引き継がれない」「情報が一部の人にしか届かない」──そんな悩みを感じている経営者や管理職の方は多いのではないでしょうか。
ナレッジマネジメントは、働き方の多様化や人材不足が進む今、中小企業にとって欠かせない経営戦略です。属人化やノウハウの散逸といった課題に頭を抱える企業は少なくありません。この記事では、ナレッジマネジメントの基本概念から、実践的な進め方や成功事例、導入を後押しするツール選びのポイントまで解説します。
目次
ナレッジマネジメントとは?
ナレッジマネジメントとは、企業が保有するデータや知識、技能、ノウハウといった「ナレッジ」を組織全体で共有し、新たな知識を生み出すための手法です。これは、個人および組織が持つ知識や経験を、企業の成長や発展に活かすことを目的としています。
具体的には、知識の特定・共有・交換・創造といったプロセスを体系化し、製品やサービス、業務プロセスの革新を通じて、組織の競争力を高めていくことに重点が置かれています。単なる知識の管理にとどまらず、知識を応用してイノベーションを生み出す「知識を活かした経営」を目指すものです。
ナレッジマネジメントをする目的
ナレッジマネジメントの主な目的は、組織内の知識や経験を効果的に管理し、それを最大限に活用することです。これにより、企業は以下のような多様な目標の達成を目指します。
- 意思決定の質の向上:共有された知識や過去の事例に基づくことで、より迅速かつ的確な判断を促進
- イノベーションの促進:異なる知識や視点が結びつくことで、新しいアイデアや解決策が生まれやすくなる
- 競争力の強化:組織全体の知識基盤を強化し、変化の激しい市場環境において持続的な優位性を確立
- 顧客満足度の向上:顧客の意見やニーズに関する知識を共有・分析することで、より質の高いサービスや製品の提供が可能
- 従業員のスキル向上:過去の成功・失敗事例や熟練者のノウハウを学ぶ機会が増え、個人の能力開発が促進されるため、人材育成の効率化にもつながる
そして、これらの目的を実現するためには、体系的なフレームワークの導入が不可欠です。
ナレッジマネジメントのフレームワーク
ナレッジマネジメントにおける知識創造の核となるフレームワークが、一橋大学大学院の野中郁次郎教授らによって提唱された「SECI(セキ)モデル」です。
このモデルでは、説明が難しい個人の経験に基づく「暗黙知」と、マニュアルなどで共有可能な「形式知」という二種類の知識が、組織内で相互に変換される四つのプロセスを通じて、新たな知識が創造されることが体系的に示されています。
これらのプロセスは「知識創造スパイラル」として、絶え間なく繰り返されることで、組織全体の知識が高度化していくとされています。
- 共同化(Socialization) 共同作業や体験を通じて、個人の暗黙知を他者へ移転させるプロセスです。OJT(On-the-Job Training)などがその典型例です
- 表出化(Externalization)暗黙知を文章や図、モデル、マニュアル、動画などの形に変換し、形式知として客観化する段階です
- 連結化(Combination) 既存の形式知と新たに表出された形式知を組み合わせ、より体系的な知識体系を創造するプロセスです。たとえば、異なる部署のマニュアルを統合するようなケースがこれに当たります
- 内面化(Internalization) 連結化によって得られた新たな形式知を、実際の業務や研修を通じて体得し、個人の暗黙知として深化させる過程を指します
ナレッジマネジメントが必要な4つの理由
多くの中小企業は「業務の属人化」や「人材育成の課題」など、さまざまな経営課題に直面しています。こうした課題を解決し、市場の変化に柔軟に対応しながら持続的な成長を実現するには、ナレッジマネジメントの導入が極めて重要です。組織全体のパフォーマンスを高めるためには、知識の活用が欠かせない要素だといえます。
理由1:業務ノウハウの暗黙知化
日本の中小企業では、従業員数が限られる中、熟練の職人やベテラン社員が大きな存在です。しかし、彼らが長年の経験から培ってきた技術やノウハウは、言語化や数値化が難しい「暗黙知」として、本人の中にとどまっている場合が多く見られます。
このような状況は、業務が特定の人に依存する「属人化」を招き、担当者が休職・退職した際に業務が停滞したり、貴重なノウハウが失われたりする大きなリスクとなります。こうした暗黙知を、誰もが使える「形式知」へと変換するナレッジマネジメントは、業務の継続性を保ち、組織全体の知識レベルを高めるうえで不可欠な取り組みです。
理由2:リモートワークで加速する知識の分散
新型コロナウイルス感染症の拡大以降、リモートワークが急速に広まり、企業を取り巻く環境や働き方も大きく変化しました。従業員が離れた場所で働くこのスタイルでは、オフィスでの対面によるコミュニケーションの機会が減少し、日々の情報交換や偶然の知識共有が難しくなります。
特に、経験から得られる「暗黙知」の継承は、対面での共同作業や指導が制限される中で、より一層困難になっている状況です。その結果、業務の属人化が進行し、組織内の知識がバラバラに分散するリスクが高まっています。こうした環境下では、知識をデータとして意識的に残し、オンラインで誰もがアクセスできる仕組みを整えるナレッジマネジメントの重要性が、これまで以上に増しています。
理由3:人材不足での効率的な人材育成
今のビジネス環境では、新入社員の早期離職や人材の流動化が進み、多くの企業が人材面で課題を抱えています。特に、中小企業にとっては採用や教育の時間・コストが大きな負担です。従来のOJTや「見て覚える」方式では、新人の育成に時間がかかり、市場の変化や人手不足に対応できません。
ナレッジマネジメントにより、業務ノウハウや事例を「形式知」として共有すれば、新人教育の効率化と早期戦力化が可能です。育成コストを抑えつつスキルを高め、組織の生産性向上にもつながります。
理由4:急速な市場変化への対応
現在のビジネス環境は競争が激しく、技術革新や市場の変化も非常に速いのが特徴です。企業が成長を続けるには、変化にすばやく対応し、他社より先に新たなアイデアやサービスを生み出す「イノベーション」が必要です。ナレッジマネジメントにより、社内の知識や経験を効率的に集約し、部門を越えて共有すれば、新たな価値創出の基盤となります。
市場の動向を的確に把握し、素早い意思決定を可能にするほか、顧客対応の質や開発スピードの向上にもつながり、競争力の強化に貢献します。
ナレッジマネジメントの4つの実施手法
ナレッジマネジメントには、企業が抱える多様な課題に対応するための、主要な4つの手法があります。それぞれの目的に応じて最適なアプローチを選ぶことが、知識を効果的に活用し、組織全体の力を高めるうえで重要です。
①知的資本集約型|社内で使える知識のデータベース化
知的資本集約型は、社内に点在する特許、製造技術、営業ノウハウなどの貴重な知的資産を効率的に集め、収益向上を目指します。自社に蓄積されたさまざまなナレッジを組み合わせることで、新たな付加価値やサービスの創出ができます。他社の成功事例や強みも参考にしながら、業務プロセスの見直しや経営戦略の策定にも活用できるのが特徴です。
組織全体の知識を集約することで、競争力を高める戦略的なアプローチとして注目されています。
②専門知識型|エキスパートのノウハウを見える化
専門知識型は、社内にいる専門的な知識や高度なスキルを持つ社員のノウハウを体系化し、課題解決のスピードアップを図るものです。専門知識をデータベースとして一元管理することで、必要な情報をすぐに検索できる環境を整えます。
たとえばFAQ管理システムを導入して、よくある質問と回答をまとめれば、社員や顧客からの問い合わせにも効率的に対応可能です。その結果、特定の担当者に頼らずとも業務が進められるようになり、組織全体の知識レベル向上が期待されます。
③ベストプラクティス型|成功例の共有で組織の効率性をUP
ベストプラクティス型は、社内の成功事例や優秀な社員のノウハウ・行動パターンを「ベストプラクティス」として言語化し、組織全体で共有します。たとえば、成績の良い営業担当の商談の進め方や顧客へのヒアリング手法をまとめ、誰でもアクセスできるようにするのです。
これにより、個人の経験に頼っていたスキルやノウハウが組織の資産となり、社員全体のスキル向上や業務改善に直結します。また、既存の成功ノウハウを参考にすることで、新しいナレッジの創出にもつながります。
④顧客知識型|製品・サービスの改善に活用
顧客知識型は、顧客情報や問い合わせ履歴を一元管理し社内の複数部門で共有することで、顧客サービスの質を向上させることが目的です。特にコールセンターやカスタマーサポートなど、顧客と直接やり取りするフロントオフィス部門での導入が進んでいます。
担当者が不在でも、共有された情報を基に他の社員がスムーズに対応できるため、顧客対応の効率化と品質向上に大きく寄与します。さらに部門間の情報連携を強化することで、顧客からの多様な問い合わせにも、より迅速かつ的確な回答が可能です。
ナレッジマネジメントの進め方・4ステップ
ナレッジマネジメントを組織に定着させるには、明確な目的の下、必要なナレッジを段階的に特定・収集・整理・活用していき、さらに継続的な更新と改善で生産性を向上させることが重要です。以下では、その実施に必要な4つのステップを紹介します。
ステップ1:ナレッジの特定と収集
ナレッジマネジメントを始めるうえで最も重要なのは、自社の課題を解決するための目的を明確にすることです。これが定まっていないと、集めるべき知識が曖昧になり、社員の理解や協力も得にくくなります。たとえば、リモート教育の難しさや、特定のベテラン社員への業務の偏りといった課題から、必要なナレッジを洗い出すことが重要です。
目的が明確になったら、アンケートやインタビュー、ヒアリングを通じて暗黙知やノウハウを収集し、整理すべき内容を具体化していきます。
ステップ2:ナレッジの整理と蓄積
収集した知識は、誰にでも理解できるよう文書化・言語化し、「形式知」として見える形にすることが大切です。とくに専門用語や難解な概念は、かみ砕いて伝えるようにしましょう。次に、ナレッジを一元管理・蓄積する保管場所を決めます。専用ツールを導入すれば、情報の整理や検索が効率化され、他システムとの連携も容易です。
こうした環境を整えることで、ナレッジの散逸を防ぎ、必要な情報にすぐアクセスできるようになり、業務の質の均一化にもつながります。
ステップ3:ナレッジの共有と活用
ナレッジマネジメントは、知識を集めるだけでなく、共有し業務に活用してこそ意味があります。そのためには、共有と活用を促す仕組みづくりが欠かせません。たとえば、ナレッジ共有をリードする担当者を任命し、説明会などでツールの使い方を周知します。また、共有に積極的な社員には評価制度やインセンティブを設け、意欲を高める工夫も効果的です。
ステップ4:ナレッジの更新と改善
ナレッジマネジメントは導入して終わりではなく、継続的な評価と改善が欠かせません。共有されたナレッジが活用されているかを定期的に確認するなど古い情報の更新が必要です。また効果を測るには、KGIやKPIを設定し、目標と現状を比較しましょう。PDCAサイクルを回し、運用上の課題を洗い出して改善することが、長期的な成功につながります。
常に質の高いナレッジを保つことで、組織全体の成長を継続的に促せます。
ナレッジマネジメントの成功事例
ナレッジマネジメントは、企業の競争力を高め、業務効率を向上させるうえで不可欠な経営手法です。ここでは、実際にこの手法を導入し、優れた成果を上げている企業や団体の事例を紹介します。
情報の陳腐化対策|国土交通省
国土交通省は、災害対応力の向上を目指して、暗黙知を効率的に抽出し職員間で伝承するナレッジマネジメント手法を研究しています。従来はマニュアルの更新が難しく、必要な情報が見つかりにくいという課題がありました。そこで、災害対応のPDCAに応用的な対処を取り入れ、SECIモデルを活用して知識共有を推進しました。
現場の「気づき」など非定型の情報もそのまま共有できるよう、ブログ形式のツールを導入し、自由な記載と全文検索でアクセス性の向上を図っています。
知識共有システムの開発|富士フイルムビジネスイノベーション株式会社
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社(旧:富士ゼロックス)は、「知の創造と活用を進める環境の構築」をミッションとし、独自の「ナレッジイニシアティブ」を展開してきました。同社は、「知」を管理するのではなく、活用する人々を活気づける経営を目指しています。
SECIモデルを実践し、特にシステム開発では設計変更の課題に対応するため、「全員設計」という相互交流の仕組みを導入しました。現場ノウハウをシステム上に言語化して入力し、上司が有益な情報を特定・登録することで、知識共有が「サイクル」から「スパイラル」へと発展し、新たな知識創造を促進しています。
ナレッジの蓄積とアクセス性を向上|アイザワ証券株式会社
アイザワ証券株式会社は、顧客向け資料のリンク化という課題を解決するため、電子ブック作成ツール「ActiBook」を導入しました。これにより、PDFや動画を電子ブック化してウェブサイト化できるようになっています。特に、顧客がどの情報にどれだけ関心を持っているかを把握できるログ分析機能が導入の決め手となりました。
同社は「アイザワ証券 投資情報サイト」で、アナリストレポートやセミナー動画を配信し、既存顧客だけでなく口座未開設の人にも情報提供の幅を広げています。この取り組みによって、ニーズの把握やレポート作成者のモチベーション向上にもつながり、情報提供の質とアクセシビリティが大きく向上しました。
その問い合わせ、AIが答えます|IZANAI(イザナイ)
毎日の問い合わせ業務に時間を取られていませんか?AIチャットボット「IZANAI(イザナイ)」は、FAQやマニュアルの情報をもとに、自動で高精度に回答する生成AIチャットボットです。ノーコードで誰でもすぐに導入でき、カスタマーサポートの定型対応を大幅に削減。
人が対応すべき「本当に重要な問い合わせ」に、もっと集中できる環境を作りましょう。
IZANAI(イザナイ)の主な特徴
- 社内資料やWebページを登録するだけで回答が可能
- PDF・Excel・WebサイトのURLなど、複数ソースを同時に学習
- FAQ整備が不十分でも、曖昧な質問に対応
- 面倒なシナリオ設計が不要
- 2週間の無料トライアル可能
参考:FAQを最適化するAIチャットボット|IZANAI Powered by OpenAI
ナレッジマネジメントで失敗しないツール選びのポイント
ナレッジマネジメントの導入は、企業の競争力や生産性を高めるうえで欠かせません。ただし、目的に合い、社員が活用しやすいツールを選ばないと期待した効果は得られません。ここでは、選定時に押さえておきたいポイントを解説します。
使いやすさと直感性で選ぶ
ナレッジマネジメントツールは、誰でも使いやすく、知識を共有・活用しやすいことが重要です。操作が複雑だったり、ITリテラシーの低い社員にとって使いにくいと、利用されなくなってしまいます。直感的なUI/UX設計で、マニュアルなしでも操作できるツールを選びましょう。
また、スマートフォンやタブレットでの利用に対応しているかも確認が必要です。導入前に無料トライアルで、実際に操作感を試してもらうのも効果的です。
セキュリティで選ぶ
ナレッジマネジメントツールには、機密情報や重要なノウハウが蓄積されるため、セキュリティ対策が不可欠です。コストを抑えても、対策が不十分なら情報流出のリスクが高まります。情報漏洩を防ぐ高度な機能を備えたツールを選びましょう。
たとえば、Microsoft Azureなど信頼性の高い基盤を使っているか、ユーザー認証やDDoS対策、WAF、IPSといった機能があるかを確認することが大切です。あわせて、定期的なセキュリティチェックを行える体制の有無も確認しておきましょう。
検索機能の性能で選ぶ
ナレッジマネジメントツールには多くの情報が蓄積されるため、必要なナレッジに素早くアクセスできる検索機能が重要です。AIによる自動タグ付けやキーワード抽出があれば、目的の情報を効率よく探せます。ファイル名だけでなく内容まで検索できる機能も有効です。
最近はChatGPTのような生成AIと連携し、社内情報から回答を生成するRAG対応ツールも登場しています。ログ分析でユーザーの関心を可視化できる機能も、選定時のポイントになります。
カスタマイズ性や拡張性で選ぶ
ナレッジマネジメントツールは、社内システムと連携することで運用効率を高められます。CRMやERP、グループウェア、社内SNSなどと連携できるツールを選べば、知識の収集・共有が円滑に進みます。APIが豊富なツールなら、自社の要件に合わせた柔軟な組み込みも可能です。
また、将来の利用者数や情報量の増加に対応できるスケーラビリティや拡張性を備えていることも重要です。これにより、ナレッジマネジメントの運用を長期的に最適化できます。
ナレッジを資産に変え、次の一手へつなげよう
ナレッジマネジメントは、ノウハウの属人化や情報の分散、人材育成の課題といった中小企業の悩みを解決する有効な手段です。実践することで、業務の効率化だけでなく、従業員のスキル向上や顧客満足度の向上にもつながります。
この記事で紹介したフレームワークや手法、成功事例、ツール選びのポイントを参考に、ぜひ自社に合った取り組みを検討してみましょう。


