情シス(情報システム部門)にチャットボットを導入するには?流れやポイント、導入事例を解説
公開日 2025/11/14
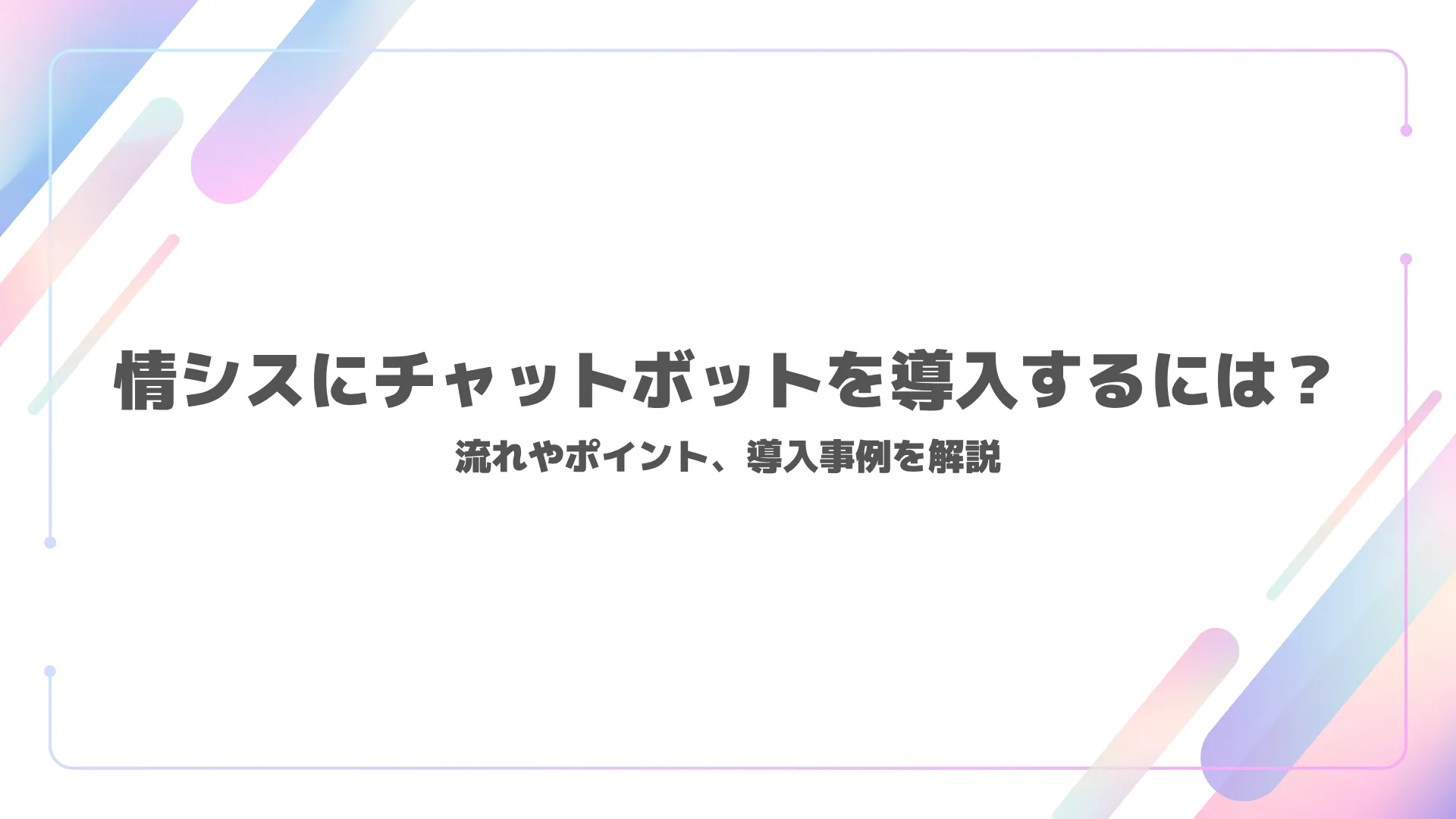
情報システム部門(情シス)は、システム運用やセキュリティ対応に加え、日常的な問い合わせ対応にも多くの時間を費やしています。パスワード再設定や操作方法の質問が積み重なれば本来の業務が滞り、担当者の負担は増す一方です。
こうした課題を解消する手段として注目されているのがチャットボットです。一次対応の自動化に加え、ナレッジ共有やデータ活用にも利用できることから、いまや情シスの標準ツールとなりつつあります。
本記事では、チャットボットの導入の手順や活用ポイント、導入事例を交えて解説します。
目次
情シス(情報システム部門)とは?
情シスとは「情報システム部門」の略称であり、社内のIT環境を支える存在です。具体的には、システムやネットワークの構築・運用、パソコンやサーバーなどの機器管理、セキュリティ対策、従業員からの問い合わせに対応するヘルプデスク業務まで幅広く担当します。
会社によって役割の比重は異なりますが、事業活動を安定的に進めるためには欠かせない部門です。近年では、運用管理にとどまらず、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進やIT戦略の立案を担う役割も増えています。業務の範囲が広いため、業務効率化を進める動きが広がっています。
情シス(情報システム部門)が抱えている課題
役割が広がる一方で、情シスはさまざまな課題を抱えています。大きく分けると、人材・技術・業務環境の3つに整理できます。ここでは、それぞれの面でどのような課題が生じているのかを順に見ていきましょう。
まず人材面では、慢性的な人手不足が深刻で、限られた担当者に業務が集中しやすい傾向があります。担当者が異動や退職すればノウハウが引き継がれず、業務の停滞や品質低下を招く恐れがあります。これは属人化と呼ばれる典型的な問題で、多くの企業に共通しています。
次に技術面です。システムが年々複雑化するなか、サイバー攻撃も巧妙化しており、高度なセキュリティ対策が欠かせません。しかし、専門知識を持つ人材を十分に確保することは難しく、限られたリソースで対応せざるを得ないのが現状です。このギャップがセキュリティリスクを高める要因となっています。
また業務環境においては、パスワード再設定や印刷トラブルなどの突発的な問い合わせが日常的に発生します。一件ごとは小さくても積み重なれば大きな負担となり、担当者は計画的に進めたいプロジェクトに時間を割けません。心理的な負担も増し、業務効率が低下していきます。
このように情シスは慢性的に高い負荷を抱えています。従来の対応では限界が見え始めており、効率化や負担軽減を図る新しい手段を導入することが急務となっています。
参考:情報システム部門(情シス)の業務効率化を進めるには?DXとの違いや具体的な方法を解説
情シス(情報システム部門)にチャットボットを導入できる場面
情シスの業務負担を減らす方法のひとつがチャットボットです。具体的にどのような場面で活かせるのか整理してみましょう。
社内問い合わせへの対応
パスワード再設定やアプリの不具合など、日常的に寄せられる質問は数が多く、担当者を圧迫する要因となります。内容が単純であっても件数が重なれば時間を奪われ、計画的な業務が後回しになります。チャットボットを導入すれば、定型的な問い合わせに即時応答できるため、繰り返しの質問対応から解放される環境を用意できます。
参考:AIチャットボットで社内外の問い合わせを効率化|IZANAI(イザナイ)
知識やノウハウの共有
システム運用のノウハウは担当者ごとの経験に依存しやすく、情報の共有が不十分になることも少なくありません。チャットボットにトラブル解決の手順を登録しておけば、誰でも同じ水準で回答できる環境を構築できます。新人教育の場面でも役立ち、知識を全員が共有できる仕組みとして活用できます。
従業員の業務サポート
チャットボットは情シス担当者を助けるだけでなく、従業員の日常業務にも活かせます。社内規定やマニュアルを検索する手間を減らし、必要な情報をその場で得られる環境を提供できます。新しいツールの操作方法や申請手順なども即時に確認でき、迷いによる作業の停滞を防止できます。従業員一人ひとりの効率を高めることで、組織全体のパフォーマンス向上を図れます。
情シス(情報システム部門)にチャットボットを導入するメリット
チャットボットは情シスの負担を減らせるだけでなく、コスト削減やデータ活用、働きやすい環境づくりにも効果を発揮します。ここでは導入によって得られる7つのメリットを解説します。
1.問い合わせ業務の負担を軽減できる
突発的に発生する問い合わせは、担当者の予定を止める要因となり、業務効率を下げる原因になります。チャットボットが一次対応を担えば、同じ質問に繰り返し答える必要がなくなり、担当者の時間を大幅に節約できます。これにより、システム改善や新規プロジェクトなど付加価値の高い業務へ注力できる体制が整います。
2.コストの削減に効果的
問い合わせ対応を自動化すれば、残業の削減や人員配置の見直しが可能になります。たとえば、新人教育に必要だった基礎的な説明をチャットボットに任せれば、教育時間やコストを減らせます。運用コストを抑えつつ、限られた人材を効率よく活かす仕組みとして機能します。
3.データを蓄積できる
チャットボットは会話履歴を保存できるため、社員がどの部分でつまずいているかを把握できます。頻出する質問を分析すれば、マニュアルの改訂や研修のテーマ設計に活かせます。利用データを定期的に確認することで回答精度が高まり、組織のナレッジが継続的に強化されます。
4.気軽に質問しやすくなる
電話やメールでは「迷惑をかけるのでは」とためらう社員も、チャットボットなら心理的な負担を感じずに問い合わせられます。些細な疑問を即座に解消できれば業務の停滞を防げます。質問しやすい環境が社内の風通しを良くし、意見や相談を持ちかけられる雰囲気を育てます。
5.24時間いつでも問い合わせられる
チャットボットは夜間や休日でも対応可能で、従業員は必要な情報をすぐに得られます。トラブルが起きても翌営業日を待たずに解決できるため、業務の停滞を未然に防ぎます。時間や場所にとらわれない環境は従業員に安心感を与え、業務全体の安定性を高めます。
6.多様な働き方に対応できる
リモートワークや出張先など、オフィス外でも利用できるチャットボットは柔軟な働き方を支える有効な手段です。場所を問わず情報にアクセスできれば、短時間の作業でもスムーズに進められます。モチベーション向上や離職防止をもたらします。
7.メールの確認漏れ・スケジュールの見落としを防げる
チャットボットをメールやカレンダーと連携すれば、予定変更や通知を自動で知らせることが可能です。従業員は見落としを防ぎ、スケジュールを正確に把握できます。情報伝達の精度が高まれば、チーム全体の連携が円滑になり、業務の進行が滞りにくくなります。
情シス(情報システム部門)にチャットボットを導入する流れ
チャットボットの効果を最大限に引き出すには、導入の流れを理解しておくことが重要です。目的の整理からツール選定、テスト運用までを見通しておくことで、スムーズに社内に定着させられます。
ここでは導入の手順をわかりやすく解説します。
1.チャットボットを導入する目的を明確にする
最初に取り組むべきは、導入の目的をはっきりさせることです。情シスの負担を軽くしたいのか、社員が自分で解決できる環境をつくりたいのか、教育コストを抑えたいのか。狙いを整理すれば必要な機能や優先順位が見えやすくなり、ツール選定の軸が定まります。逆に曖昧なまま進めると、導入後に「思っていた効果が出ない」というズレが生じやすくなります。
2.チャットボットの導入方針を決める
次に「どこで使うのか」「どの範囲をカバーするのか」を決めます。社内向けならポータルや社内SNSに設置する方法が一般的ですが、顧客対応も含めるなら設計が変わります。あわせて必要な機能、予算、外部ツールとの連携可否、サポート体制などを整理しておくと判断がしやすくなります。ここで方針を固めておけば、社内の合意も取りやすくなります。
3.チャットボットの導入・運用体制を整える
チャットボットは入れて終わりではなく、改善を続けてこそ効果を発揮します。そのためには運用体制を前もって用意しておくことが欠かせません。ツール選定やベンダー対応を行う担当者を決めるだけでなく、FAQの更新や回答の見直しを担う役割も割り当てます。たとえば月に1回ログを分析し、改善点を洗い出す担当を設ければ、形骸化を防げます。責任の所在を明確にしておくことで、長く安定して運用できます。
4.導入するチャットボットを決める
準備が整ったら導入するツールを選びます。比較の基準は「自社の課題解決に直結するか」です。必要な機能が揃っているか、予算に合うか、サポートは十分かを確認しましょう。操作性や既存ツールとの連携しやすさも重要です。候補が複数ある場合はデモを実際に触ってみて、現場の声を反映すると導入後のギャップを減らせます。
5.ベンダーに相談しながら無料トライアルを利用する
ベンダーは販売だけでなく、導入後のサポートも担う存在です。事例や活用方法を聞けば、自社でのイメージがつかみやすくなります。多くのツールは無料トライアルを提供しているので、実際の問い合わせを登録して試すのが効果的です。数週間の検証を通じて解決度合いを確認し、社内評価を踏まえて最終判断を下します。
クラウドサーカスが提供するAIチャットボット「IZANAI Powered by OpenAI(以下、IZANAI OpenAI)」も2週間の無料トライアルがあり、導入後の運用を想定したテストが行えます。
6.FAQ・シナリオを作る
導入後すぐに運用するには、よくある質問と回答を登録しておく準備が欠かせません。まずは「パスワード再設定」「印刷トラブル」など、頻度の高い問い合わせから始めると効果を実感しやすいです。ベンダー提供のテンプレートを使えば効率化も可能です。最近ではシナリオ作成を不要とするAI型のチャットボットも増えており、FAQ整備の負担を減らしながら運用を始められます。
7.テスト運用をする
最後に、全社展開の前にテスト運用を行います。一部の部署や期間に絞って試すことで、想定外の質問や不足が見えてきます。その際にFAQを追加したり、回答表現を調整したりして精度を高めます。フィードバック収集の仕組みを用意すれば改善が進めやすく、十分な精度に達した段階で全社展開すれば、利用者満足度を維持しながら定着させられます。
情シス(情報システム部門)にチャットボットを導入するまでの期間
情シスにチャットボットを導入した場合、どれくらいの期間がかかるのでしょうか。準備するデータの量や作業内容によって前後しますが、一般的な目安を以下にまとめました。
| 導入状況 | 期間の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| FAQや資料が整理済み | 約1週間~数週間 | 短期間で運用を始められる |
| 一般的な導入 | 1~3ヶ月 | FAQ整備やシステム調整を 含む標準的な流れ |
| 複雑な要件あり | 3ヶ月以上 | シナリオ作成や外部連携に 時間を要する |
準備が整っていれば短期間で運用を始められますが、基本的には1〜3ヶ月程度です。外部システムとの連携や複雑な設計を伴う場合は、さらに時間を要することもあります。事前にFAQや資料を整理しておくことが、導入スピードを高めるポイントになります。
情シス(情報システム部門)にチャットボットを導入するためにかかる費用
チャットボットの導入には、初期費用と月額費用がかかります。初期費用は導入環境の準備や初期設定、月額費用は利用ライセンスや運用サポートが含まれることが多いです。また、AI機能を搭載したツールを使うかどうかでも金額の目安が変わってきます。
概要を表にまとめると次のとおりです。
| 初期費用 | 月額費用 | |
|---|---|---|
| AI非搭載型 | 0〜5万円 | 1〜5万円 |
| AI搭載型 | 10〜100万円 | 10〜100万円 |
AI非搭載型はスモールスタートしたい企業に合い、AI搭載型は高精度な対応を求める場合に向いています。
上記の費用のほか、外部システムとの連携や複数言語対応、デザイン変更、有人チャット切り替えなどのオプション費用がかかることもあります。対応範囲や料金はベンダーごとに異なるため、導入前に確認しておくと良いでしょう。
また、FAQ整備や利用状況の分析を代行してもらう場合は、コンサルティング費用が追加されることもあります。標準プランに含まれることもあり、事前にどこまで対応してもらえるかを把握しておくと無駄なコストを避けられます。
情シス(情報システム部門)にチャットボットを導入するときのポイント
チャットボットを導入して効果を引き出すには、いくつかの工夫が欠かせません。導入目的を達成するための指標づくりから、情報の更新体制、利用者への周知方法、そして担当範囲の切り分けまで、押さえておくべき点があります。ここでは、導入後に運用を安定させるためのポイントを解説します。
KPIを設定する
チャットボットの効果を把握するには、KPI(重要業績評価指標)を設定しておくことが大切です。KPIとは、目標の達成度を数値で確認するための指標を指します。代表的なものには「問い合わせ件数の削減率」「自己解決率」「利用満足度」などが挙げられます。導入後に状況が変われば、当初のKPIが合わなくなることもあります。その場合は定期的に見直し、現場の実態に沿った指標へ更新することが必要です。数値を追いながら調整を重ねれば、目的の達成度を確かめやすくなります。
本格的な運用開始後も定期的に内容を見直す
制度や社内ルールは時間とともに変化し、古い情報を放置すれば利用者の不満につながります。FAQを追加したり表現を改めたりして、常に最新の状態を保ちましょう。利用ログを確認すれば、離脱が多い質問や改善すべき回答を見つけやすくなります。
運用の負担が気になる場合は、IZANAI OpenAIのように資料やWebサイトを登録するだけでAIが回答を生成できるサービスを活用するのも有効です。シナリオ作成に手間をかけず、安定した精度を保てるため、管理側の負荷を軽減しながら利用者に信頼感を与えられます。
利用者にチャットボットの存在を知らせる
導入しても、利用者に知られなければ効果は期待できません。社内ポータルや掲示板での告知、メールでの案内などを通じて周知しておきましょう。必要に応じてマニュアルを配布したり、研修を行ったりすれば、社員が抵抗なく活用できます。利用が広がることで、導入の成果も一層わかりやすくなります。
チャットボットに任せる範囲を明確にしておく
すべての問い合わせをチャットボットに任せるのは難しいため、対応範囲を事前に定めておくことが重要です。複雑な質問や登録されていない内容は担当者へ切り替える仕組みを整えておけば、利用者は迷わず利用できます。役割分担を明確にすることで、利用者にとってもわかりやすく、運用側の負担も軽くなります。
情シス(情報システム部門)にチャットボットを導入した事例
チャットボットは業界を問わず利用が広がっています。ここでは、業種の異なる3社の事例を取り上げ、その活用方法をご紹介します。
【不動産業】大和財託株式会社|チャットボットで緊急対応を自動化、管理者の負担を大幅軽減
大和財託株式会社は、大阪を拠点に収益不動産の建築・販売・賃貸経営を一貫して支援する資産運用会社です。情シス部門にはスマートフォン紛失や盗難への問い合わせが集中し、管理者の業務負担が課題でした。
そこで導入したのが業務自動化ツール「Syncpit」です。社員が普段使うビジネスチャットに「スマホをなくしました」と入力すると、位置情報の確認や端末ロック、データ消去を自動で実行します。従来は管理者が手作業で行っていた対応をセルフサービス化し、即時解決を可能にしました。
導入後は緊急対応にかかる時間を数十分から数分に短縮し、管理者の工数削減と従業員の安心感を両立。今後は定型業務全般の自動化を進め、情シス部門の生産性向上につなげる方針です。
参考:【Syncpit 導入事例】大和財託株式会社様 情シス業務自動化の新サービス「Syncpit」をいち早く導入した理由
【小売業】株式会社ダイエー|AIチャットボット導入で電話対応を削減、残業時間も大幅カット
株式会社ダイエーは、全国に店舗網を展開する大手スーパーマーケットです。システム関連の問い合わせが増加する中、少人数の情報システム部門では対応に限界があり、効率化が求められていました。
同社は社内問い合わせ用のAIチャットボット「AIさくらさん」を導入。社員がシステムの操作やトラブルについて質問すると、24時間リアルタイムで回答が得られる仕組みです。導入初期にはAIキャラクターを表示し、親しみやすさを意識することで利用を促しました。
導入後は電話対応の件数が減少し、問い合わせ時間の短縮で残業削減にも効果を発揮。担当者からは「まずはさくらさんに聞く文化が浸透した」との声もあり、社内に自己解決の文化が広がっています。今後は対応範囲を広げ、機密性の高い業務領域への展開も計画されています。
参考:ダイエー、社内問い合わせ用チャットボット「AIさくらさん」導入により業務効率を大幅改善
【マーケティングリサーチ】株式会社マクロミル|社内1,000名の問い合わせをAIチャットボットで効率化、月100時間削減
株式会社マクロミルは、年間3万件以上の調査を行うマーケティング支援企業です。社員約1,000名を抱える同社では、情シス・人事・総務への問い合わせが増加し、少人数のヘルプデスクでは対応が追いつかない状況にありました。
解決策として導入したのが、社内向けAIチャットボット「My-ope office」です。FAQをもとに即時回答できる一次窓口として運用し、全社員が利用可能に。繰り返し発生する質問を自動で処理し、自己解決を定着させています。
導入効果は大きく、月間約100時間の工数を削減し、新卒70名からの1日120件超の質問にも安定稼働。現在は対話履歴の分析を通じて社員の困りごとを可視化し、社内ポータル改善や情報発信にも活用されています。
参考:情シス、人事、総務部門への社内問合せをAIチャットボットが一括対応。株式会社マクロミル
情シス(情報システム部門)にチャットボットを導入するときに役立つツール
情シス部門が抱える課題を解消するには、業務に合ったツールを選ぶことが大切です。ここでは、AIチャットボット「IZANAI Powered by OpenAI」と、電子ブック作成ツール「ActiBook」を取り上げ、それぞれの特徴を紹介します。
IZANAI Powered by OpenAI(イザナイ パワード バイ オープンエーアイ)

IZANAI OpenAIは、社内資料やWebサイトを読み込ませるだけで回答を生成できるAIチャットボットです。複雑なシナリオを組まなくても自然な会話形式で応答し、日常的な問い合わせ業務を自動化します。
情シスで活用しやすいのは、繰り返される質問対応を減らせる点です。印刷トラブルやネットワーク接続方法などをチャットボットが即時に対応すれば、担当者はトラブルシューティングやセキュリティ強化といった本来の業務に専念できます。
さらに、利用ログを分析することで「社員がどこでつまずいているか」を把握でき、マニュアル改善や研修設計に生かせます。回答ルールのカスタマイズも柔軟に行えるため、導入後も精度を高めながら運用できるのも強みです。
参考:AIチャットボットでFAQを最適化「IZANAI Powered by OpenAI」
ActiBook(アクティブック)

ActiBookは、紙やPDFで管理していたマニュアルや手順書を電子ブック化し、誰でも検索しやすく共有できるようにするツールです。情シスで頻発する「マニュアルを探すのに時間がかかる」「最新情報がどこにあるかわからない」といった課題に対応します。
権限設定やアクセスログ取得にも対応しているため、必要な人に必要な情報を安全に届けられます。FAQやガイドラインを集約する基盤として利用すれば、チャットボットとの併用で問い合わせ削減につながります。
ツールの比較表
| 項目 | IZANAI Powered by OpenAI | ActiBook |
|---|---|---|
| 主な用途 | 社内問い合わせの自動対応 | マニュアルやFAQの 電子化・共有 |
| 特徴 |
|
|
| 情シスで 活用できる場面 |
|
|
IZANAI OpenAIは「問い合わせ対応の自動化」、ActiBookは「情報共有の効率化」という強みを持っています。両者を組み合わせることで、問い合わせの削減と情報資産の有効活用を同時に進められます。
情シス(情報システム部門)の効率化を進める一歩としてチャットボットを
情報システム部門は、社内の問い合わせやシステム運用に追われ、計画的な業務が進みにくい部門です。チャットボットを導入すれば、定型的な質問を自動処理でき、ナレッジ共有や教育も効率化できます。従業員が必要な情報をすぐに得られる環境を整えることで、全社的な生産性向上を促せます。
導入は一度に進める必要はなく、パスワード再設定や印刷トラブルといった頻度の高い問い合わせから始めると、短期間で効果を実感しやすいです。問い合わせ件数の減少や残業時間の削減といった成果は数値で示しやすく、社内の理解も得やすいでしょう。
小さな成功を積み重ねることで利用が広がり、情シスの負担軽減と自己解決の習慣が社内に定着します。


