中小企業の人事労務を効率化|5つの課題と改善プロセス、成功事例を解説
公開日 2025/11/14
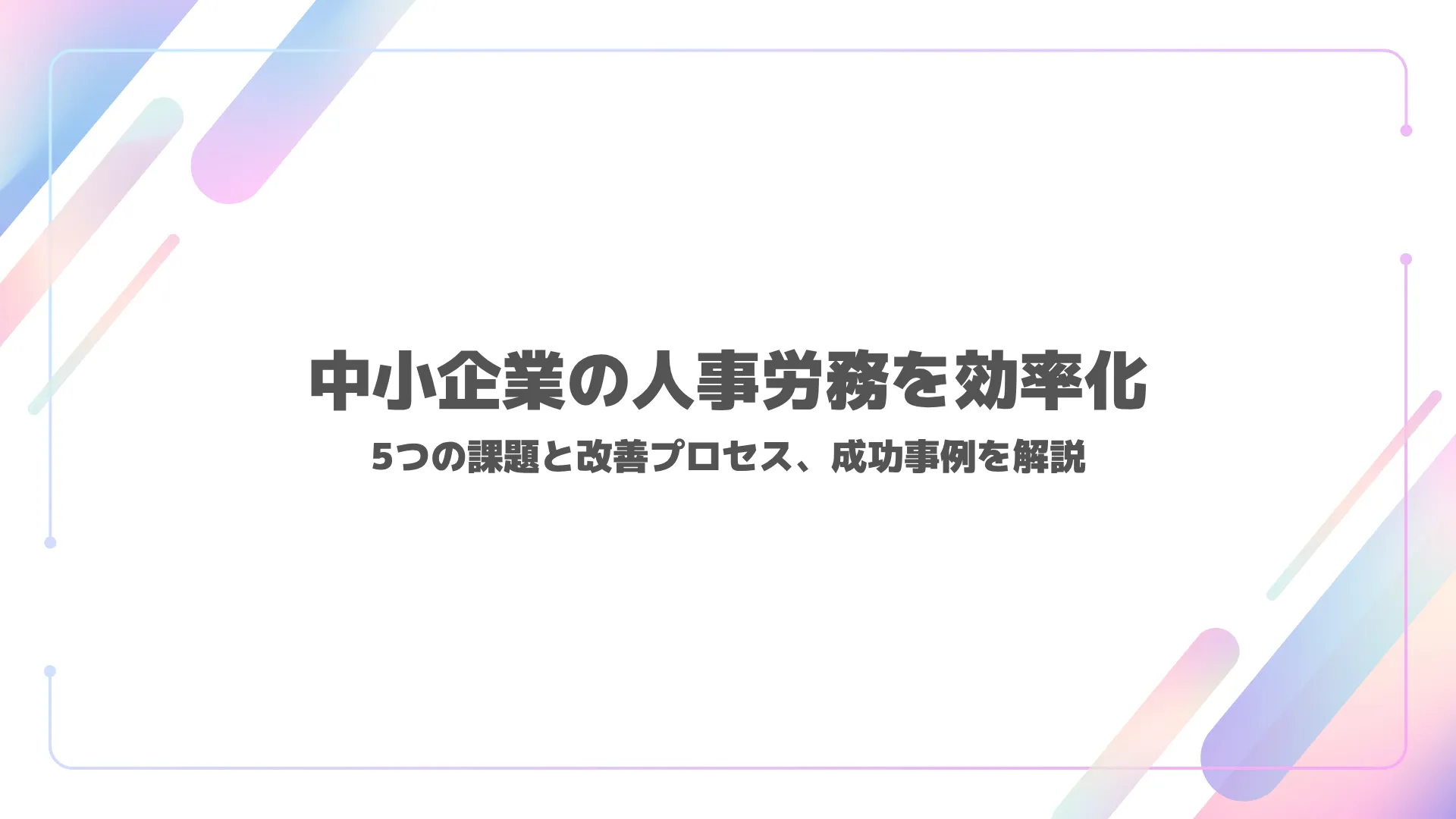
中小企業の人事労務担当者は、給与計算や社会保険の手続きなど日々の業務に追われ、十分な時間を確保しづらいのが実情です。紙やExcelに依存した管理は手間がかかるうえ、わずかな入力ミスが重大なトラブルを招くおそれもあります。
さらに近年は、人材不足や頻発する法改正、リモートワークに伴う勤怠管理の複雑化が重なり、業務負担は増す一方です。改善を後回しにすれば担当者依存が進み、異動や退職によって業務が滞る可能性があります。
本記事では、人事労務を効率化するための具体的な手順や改善の進め方から、成功事例まで解説します。人事労務の効率化に課題を抱える方は、ぜひ参考にしてください。
目次
人事労務の課題とは?
人事労務の業務は、採用や勤怠管理、給与計算、社会保険の手続きなど、人に関わる幅広い領域を含みます。正確さとスピードが求められる一方で、担当範囲が広いために作業が集中しやすく、負担が積み重なりやすい分野でもあります。
また、人事労務ならではの特徴として、制度変更の影響を受けやすいことや、雇用形態の多様化によって管理が複雑になりやすいことが挙げられます。紙やExcelに依存した運用や限られた人員体制も、負担を大きくする背景となっています。
以下では、代表的な課題を整理し、それぞれの背景と注意点を解説します。
参考:人事労務とは?仕事内容や向いている人の特徴・課題と解決策を解説
課題1.人手不足による業務負荷
人材確保が難しい中小企業では、1人が複数の業務を兼任することが珍しくありません。採用から給与計算、労務管理までを少人数で担う状況の場合、繁忙期に業務が滞るだけでなく、作業精度の低下も招きます。限られた人員で対応を続ければ担当者の疲弊が進み、離職や人員交代によってさらに業務が不安定になる可能性があります。
課題2.手作業によるミス
紙やExcelに依存した管理は、転記や集計の過程で誤入力が生じやすい点が課題です。給与計算の計算式を誤ったり、社会保険の申請内容を記載違いのまま提出したりすれば、従業員からの不信感や行政からの指摘を受ける可能性があります。人の目に頼る方法では限界があり、担当者の心理的な負担も増しやすくなります。
課題3.頻繁に改正される法令への対応
労働基準法や社会保険関連の制度は改正の頻度が高いため、常に最新情報を把握することが望ましいです。有給休暇の取得義務化や時間外労働の上限制限、ハラスメント防止策など、対応範囲は年々広がっています。準備が遅れれば、行政対応に追われたり、従業員からの信頼を失ったりするおそれがあります。特に個人情報管理の不備は、企業の信頼性に大きく影響します。
課題4.特定の担当者に頼った業務(属人化)
業務が特定の担当者に集中すると、作業手順や判断基準が共有されないまま進むことがあります。その担当者が休職や退職をすれば業務が停滞し、引き継ぎが難しくなるでしょう。ブラックボックス化が進むと、管理体制そのものが不安定になり、長期的には組織の柔軟性を奪う要因となります。
課題5.雇用形式の多様化による管理の複雑化
正社員に加えて、パート、アルバイト、契約社員、派遣社員など、多様な雇用形態の管理を行う企業が増えています。それぞれ勤務時間や給与規程の取り扱いが異なり、社会保険や契約更新の扱いも複雑です。制度理解や契約内容の反映に手間がかかり、担当者の負荷が増しやすい点が課題となります。
中小企業に最適な人事労務効率化の4つの方法
人事労務業務の負担を軽減するには、段階的に取り組むことが効果的です。ここでは実際の業務で取り入れやすい4つの方法を紹介します。
1.業務プロセスの見える化をする
効率化を進めるには、まず現在の業務を整理することが基本となります。採用から退職までの一連の流れをフロー図やチェックリストで表せば、どの工程に時間がかかっているのか、どこで誤りが発生しやすいのかが見えてきます。承認の段階が多すぎて処理が遅れている、担当者間で引き継ぎが不明確になっているなど、フロー全体を見なければ気づけない問題も浮かび上がります。工程を図で示してチーム全体で確認すれば、問題意識を共有でき、改善への理解も得やすくなります。
2.紙ベース業務のデジタル化をする
人事労務で紙に依存している業務は多くあります。勤怠表や年末調整の申告書、雇用契約書などをデジタル化すれば、保管や転記の負担を減らせます。たとえば年末調整をWebフォーム化すれば、従業員が自分で入力した内容がそのままシステムに反映され、担当者が転記する必要がなくなります。 電子化によってデータ検索や共有が容易になり、リモート環境下でも支障なく処理できるのもメリットのひとつです。
3.コスト効率を重視した外部委託を活用する
すべての業務を社内で抱え込むのは効率的とはいえません。給与計算や社会保険の手続きといった定型的な作業を外部の専門業者に委託すれば、担当者は人材育成や評価制度の整備など、より優先度の高い業務に集中できます。
委託先の専門家は法改正にも精通しているため、制度変更時の混乱を最小限にとどめられます。費用はかかりますが、残業削減や誤処理防止によって修正作業が減り、結果的にコストの抑制にもつながります。人員が限られる組織にとっては、外部委託によって業務を安定して運営しやすくなるのも利点です。
4.AIシステム導入で業務を自動化をする
近年はAIを活用したシステムの普及により、定型業務の自動化が広がっています。勤怠打刻を自動集計するシステムや、給与計算を勤怠データと連動させる仕組みを導入すれば、入力や計算の誤りを防ぎながら処理時間を短縮できます。人事評価もシステム化すれば、基準のばらつきを防ぎ、評価履歴をデータとして蓄積することも可能です。
以下は代表的なシステムとその特徴です。
| システム種類 | 特徴 |
|---|---|
| 給与計算システム | 勤怠データと連携し、自動で給与額を算出。 税金や保険料の控除計算も反映可能 |
| 勤怠管理システム | 出退勤を自動集計し、残業や休暇取得を リアルタイムで把握できる |
| 人事評価システム | 評価基準を統一し、評価履歴を蓄積。 分析や昇進判定にも活用できる |
これらを導入すれば、手作業での入力や確認を大幅に減らせるため、担当者の時間を削減するだけでなく、業務精度の向上も図れます
人事労務の効率化アップのための改善プロセス
効率化を実際に進めるには、思いつきで対策を取るのではなく、手順を整理して取り組むことが重要です。ここでは、人事労務の改善をスムーズに進めるための3つのステップを紹介します。
第1段階:業務の洗い出し
改善に取りかかる前に、まずは人事労務に関わる業務をすべて書き出しましょう。入社手続きや勤怠管理、給与計算といった定型作業から、研修運営や福利厚生対応のような付随業務まで列挙すると、全体像が把握できます。処理にかかる時間や発生頻度もあわせて記録すれば、業務ごとの負担が比較しやすくなります。担当者ごとに担当業務を整理し、誰に負荷が集中しているかを可視化することも大切です。ここまで整理できれば、改善すべき領域を判断するための基盤が整います。
第2段階:ボトルネックの特定
業務を整理したら、効率を下げている要因を明らかにします。処理に時間を要する作業や誤りが多い工程を洗い出し、改善効果の高いものから優先的に取り組むのが基本です。判断の目安としてROI(投資利益率)を使えば、かけるコストと期待できる成果を数値で比較できます。例えば、勤怠集計の自動化に投資する場合、人件費削減や残業時間の減少といった効果を予測します。業務ごとの工数やエラー発生率をチェックシートに整理すると、優先順位を客観的に決められます。
第3段階:実行と効果測定
改善策を決めたら実行に移し、その効果を数値で確認します。ここで押さえておきたいのは、一度で終わらせず、PDCAサイクルを回し続けることです。たとえば勤怠管理をクラウド化した場合、入力時間がどれだけ減ったか、給与計算の誤りがどの程度減少したかを検証します。得られた結果を基に改善策を修正し、再度取り組むことで、現場に即した形で効率化を進められます。数字で振り返る習慣を持てば、改善は自然に定着していきます。
人事労務に最適なツール選びのポイント
人事労務の効率化には、自社の課題に合ったツール選びが不可欠です。ここでは、機能・操作性・サポート体制の3つの視点から確認すべきポイントを整理します。
機能の比較確認
ツールを選ぶ際には、どの機能が自社の課題に有用かを確認しましょう。勤怠管理や給与計算といった基本に加え、承認フローや評価データの管理まで対応できるかどうかを見ておくと選びやすくなります。すべてを一つのシステムでまかなうのか、必要な機能だけを組み合わせるのかを整理すると、運用のイメージが持ちやすくなります。将来的に拡張できる設計かどうかも意識したいポイントです。
操作性の確認
どれほど機能が充実していても、操作が複雑では現場に浸透しにくいものです。入力作業がシンプルか、画面が直感的に扱えるかといった点を確かめることがポイントになります。導入前にデモ画面を利用して、自社の業務にどの程度なじむかを確認すると安心です。複数部門で利用する場合は、部署ごとに操作感を試しておくと導入後の混乱を減らせます。マニュアルやチュートリアルの有無も、初期教育の負担を軽減するうえで役立ちます。
サポート体制の確認
長期的に運用するには、ベンダーの支援体制を事前に把握しておくのも重要です。問い合わせへの対応スピードや導入初期の設定サポート、法改正に合わせたアップデート提供の有無を確認しましょう。トラブル時にすぐ相談できるかどうかで、現場の安心感は大きく変わります。FAQやチャットでの対応、担当者によるフォローが整っているかも比較の基準となります。価格や機能だけでなく、サポートの質を含めて判断する視点が求められます。
その問い合わせ、AIが答えます|IZANAI(イザナイ)

毎日の問い合わせ業務に時間を取られていませんか?AIチャットボット「IZANAI(イザナイ)」は、FAQやマニュアルの情報をもとに、自動で高精度に回答する生成AIチャットボットです。ノーコードで誰でもすぐに導入でき、カスタマーサポートの定型対応を大幅に削減。
人が対応すべき「本当に重要な問い合わせ」に、もっと集中できる環境を作りましょう。
IZANAI(イザナイ)の主な特徴
- 社内資料やWebページを登録するだけで回答が可能
- PDF・Excel・WebサイトのURLなど、複数ソースを同時に学習
- FAQ整備が不十分でも、曖昧な質問に対応
- 面倒なシナリオ設計が不要
- 2週間の無料トライアル可能
参考:FAQを最適化するAIチャットボット|IZANAI Powered by OpenAI
人事労務の効率アップ|システム活用事例
人事労務の効率化には、現場の課題に即したツールの導入が効果を発揮します。ここでは、製造・物流・サービスといった異なる業種で取り入れられた事例を紹介します。
事例1. 製造業|電子ブックによる情報資産の管理強化
化粧品や医薬部外品の企画・製造を手がける株式会社シーエスラボでは、薬機法や広告表現のルールをまとめた「薬事ハンドブック」を冊子で配布していました。しかし、営業現場や在宅勤務では持ち歩きが不便なうえに、社外への情報流出リスクにも対応する必要がありました。
そこで導入したのが電子ブック作成ツール「ActiBook(アクティブック)」です。閲覧権限を部署や個人ごとに細かく設定できるため、必要な人だけに情報を共有できる体制を構築しました。閲覧履歴を記録できる仕組みにより、管理の透明性も高まっています。冊子を持ち歩く必要がなくなり、検索機能で目的の内容を即座に探せるようになったことで、業務効率の改善にもつながっています。
参考:社外秘情報の電子化は情報漏洩対策が必須!電子ブックで課題解決へ|株式会社シーエスラボ様
事例2. 物流・運輸業|RPAによる定型業務の自動化で月間70時間以上を削減
物流や倉庫、引越し事業を展開する株式会社トーショーでは、人事や経理の定型業務が長年の課題でした。システム間のマスタ更新や月次決算資料の作成、500名分の運転者台帳整備を手作業で行っていたため、作業量が膨大で担当者の残業も常態化。属人化も進み、担当者以外が引き継ぎにくい状況でした。
この問題を解消するために導入されたのが、国産RPAツール「RoboTANGO(ロボタンゴ)」です。人事や販売システムからのデータ抽出、インボイス登録確認、決算資料の集計、台帳の更新を自動化したことで、毎月数日かかっていた作業が数時間で済むように変化しました。マスタ更新も夜間に自動処理され、出社後には最新データをもとに業務をすぐ始められるようになっています。
その結果、月間70時間以上の工数削減を実現。担当者は単純作業から解放され、分析や改善提案などの業務に時間を活用できる状況が生まれています。作業精度も安定し、業務の引き継ぎや人手不足の対応にも対応できています。
参考:システム間のデータ連携やExcel業務、データの抽出作業など、単純であるものの煩雑な業務を自動化し月間70時間以上の工数削減を実現│株式会社トーショー様
事例3.サービス業|勤怠管理システムで1,500名の勤務集計を効率化
株式会社ファクトリージャパングループは、整体サロンを全国で展開し、約1,500名の従業員を擁する企業です。従来の勤怠管理システムでは打刻漏れや集計の手間が課題となり、人事部ではExcelを用いた確認作業に丸1日以上を要していました。
解決策としてクラウド型勤怠管理システム「KING OF TIME」を導入。本社ではパスワード認証、店舗ではICカードやモバイル打刻を併用することで、スタッフの打刻習慣が定着しました。勤務時間を週単位で一覧表示でき、給与計算に必要なデータも数秒で抽出できるようになりました。
導入により、従来はExcelで丸1日かかっていた集計作業がわずか2時間程度に短縮され、勤怠管理に伴う事務作業は3分の1に削減。人事部は空いた時間を分析や社員サポートに充てられるようになりました。全国規模で展開するサービス業において、労務負担を軽減した好例といえるでしょう。
参考:約1,500名のデータ出力が数秒で完了。勤怠管理に伴う事務作業は1/3に。│株式会社ファクトリージャパングループ様
人事労務業務の効率化を進める際のコツ
業務改善を進めるには、現場の理解と協力が欠かせません。ここでは、取り組みを定着させるために押さえておきたい3つのポイントを紹介します。
コミュニケーションの徹底
人事労務の効率化は、従業員の働き方や日常業務に影響を与えます。目的や進め方を共有しないまま取り組むと、不安や誤解が生じやすくなり、改善効果が十分に得られません。そのため、導入の背景や目標を丁寧に伝え、疑問を気軽に相談できる場を設けることが大切です。社内掲示板での発信や説明会に加え、質疑応答の場を用意すると理解が深まり協力も得やすくなります。従業員が納得して取り組める体制を整えることが、施策を定着させる近道となります。
教育とスキルアップの奨励
効率化を進めるには、担当者のスキルアップも積極的に行いましょう。システムを導入しても知識が不足していれば十分に使いこなせず、逆に非効率になる場合があります。現状のスキルを把握し、必要な分野を明確にしたうえで、オンライン研修や外部セミナー、社内勉強会などを組み合わせて教育機会を用意すると効果的です。学びを継続できる環境を整えることで担当者の理解が深まり、組織全体の業務改善を後押しします。
法令遵守と情報管理の徹底
人事労務では、個人情報や給与データ、健康情報などを扱うため、情報管理と法令遵守は徹底すべき事項です。管理が不十分であれば、信用失墜や法的責任といった深刻なリスクを招きます。システムのセキュリティ強化やアクセス権限の見直しを常に行い、改正される法令に合わせて運用ルールを更新することが重要です。研修や定期的な監査を通じて運用を強化することで、安心して効率化を進められる環境を築けます。
人事労務効率化は段階的な取り組みが成果を生む
人事労務は業務の幅が広く、担当者の負担が蓄積しやすい分野ですが、段階を踏んで改善を進めれば効率化を着実に進展させることができます。業務の見える化やデジタル化、外部委託やシステム導入などを組み合わせれば、安定した体制づくりにも役立ちます。
まずは現状を整理し、効果の出やすい領域から取り組むことが成果を積み重ねるうえで有効です。自社に合った方法を選び、無理のないペースで進めることで、効率化は自然に定着していくでしょう。


