人事管理と労務管理の違いとは?業務内容や課題と対策を解説
公開日 2025/11/14
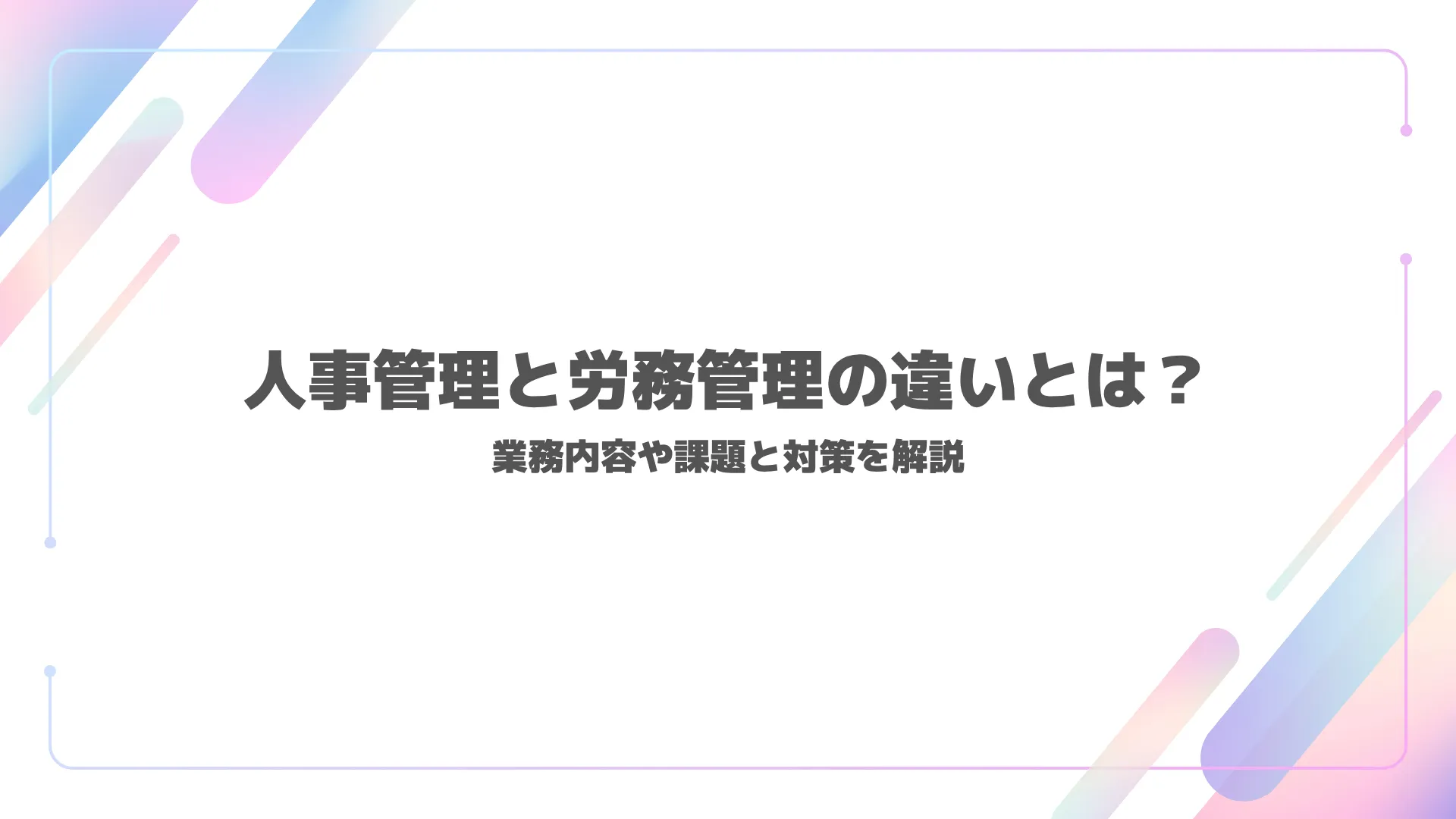
人事管理と労務管理は、どちらも組織に欠かせない業務です。しかし役割があいまいになると、担当者が混乱し、採用や勤怠管理といった日常業務に支障をきたすこともあります。本記事では、人事と労務の違いを整理したうえで、それぞれの業務内容や課題、対応策までをわかりやすく解説します。
目次
人事管理と労務管理の違いとは?
人事管理は「人材そのもの」を活かす仕事であり、労務管理は「働く環境」を支える仕事です。前者は採用・育成・評価を通じて人材を成長させ、後者は勤怠や給与、福利厚生を通じて職場環境を整えます。以下では、それぞれの業務内容や役割を詳しく見ていきます。
参考:人事労務とは?仕事内容や向いている人の特徴・課題と解決策を解説
人事管理とは「人材」にフォーカスした仕事
人事管理は、採用から育成、評価まで、人材をどう活かすかを考える仕事です。まず採用活動で自社に合う人を迎え、教育や研修でスキルを伸ばします。そのうえで適切な部署に配置し、評価制度やキャリアパスを構築して社員が成長しやすい環境をつくります。単に人員を補うだけでなく、働く意欲を高めたり離職を防いだりする役割も担います。短期的な成果だけでなく、中長期を見据えて人材を育てる姿勢が求められます。
労務管理とは「働く環境」を整える仕事
労務管理は、従業員が安心して働けるよう環境を維持する仕事です。勤怠や労働時間の管理、給与計算、社会保険や福利厚生の手続きなど、日常的な事務を正確に進めることが基本です。加えて、法改正への対応や安全衛生の確保、ハラスメント防止といった取り組みも含まれます。処理のミスは従業員の生活や会社の信用に影響するため、丁寧さとスピードの両立が欠かせません。近年はリモートワークや多様な雇用形態に対応するため、柔軟な制度設計やシステム導入による効率化も進められています。
人事管理と労務管理の業務内容の違いを比較
人事管理と労務管理は、どちらも従業員を対象とした業務ですが、取り組む視点が異なります。人事は人の成長や能力活用を扱い、労務は就業条件や職場体制に焦点を当てるのが大きな違いです。
以下では、目的や対象、求められるスキルの項目から違いを整理しました。
| 項目 | 人事管理 | 労務管理 |
|---|---|---|
| 目的 | 採用・育成・配置による 組織力向上 |
労働条件や環境整備による 安全・公平な就業維持 |
| 対象 | 能力・適性・キャリア形成 | 勤務状況・労働時間・福利厚生 |
| 必要なスキル | 面接・評価・教育の知識、 戦略的な視点 |
労働法令の理解、 正確な事務処理、リスク対応力 |
このように、人事管理は人材の活用を通じて組織の力を伸ばす役割を担い、労務管理は職場環境を守ることで安心して働ける状態を支えています。
ここから先は、それぞれの業務内容をさらに詳しく見ていきましょう。
人事管理の主な業務内容
人事管理は、人材を採用し、育成し、評価・配置することで組織の成長を支える業務です。主な内容は次のとおりです。
- 採用・人材確保:事業計画に基づいて人材を募集し、面接や選考を通じて適任者を採用します。
- 人材育成・教育:新入社員研修やスキルアップ研修を実施し、知識や能力を高めます。
- 人事評価・配置:成果や適性に基づいて評価を行い、社員が最も力を発揮できる部署や職務に配置します。
採用・育成・評価・配置を体系的に進めることで、人材の能力が引き出され、組織全体の成長が促されます。
労務管理の主な業務内容
労務管理は、従業員が安心して働けるよう労働条件を支援する業務です。主な内容は以下のとおりです。
- 勤怠・労働時間管理:出退勤や残業時間を正確に把握し、法令に沿った勤務体制を維持します。
- 給与・賞与計算:勤務実績や制度に基づき給与や賞与を計算し、誤りなく支給します。
- 社会保険・福利厚生手続き:健康保険や年金の手続きを行い、必要な制度を利用できるよう環境を用意します。
- 職場環境管理:安全衛生の確保やハラスメント防止に取り組み、快適で安心できる職場を守ります。
勤怠や給与、制度運用を行うことで、働きやすさが保たれ、企業への信頼も高まります。
人事管理と労務管理でよくある5つの課題と対策
人事や労務の担当業務は範囲が広く、思わぬ形で課題が表面化することがあります。対応を誤れば組織全体の力を弱める要因となるため、早めの対処が欠かせません。
ここでは、多くの企業で見られる5つの課題とその解決策を紹介します。
課題1. 業務が多く人手が足りない
問題点:採用市場の競争が激化し、必要な人材を確保することが難しくなっています。経験不足やスキルの不一致によるミスマッチ採用が起きると、短期離職や再採用コストの増加を招き、現場の負担も増します。特に中小企業においては採用担当者が他業務を兼任する場合も多く、十分な戦略を立てる時間を確保できないことがあります。
対策:自社の文化や働きやすさをSNSや採用サイトで積極的に発信し、採用ブランディングを進めましょう。求人票には業務内容や評価基準を明確に記載し、候補者が働くイメージを持ちやすくする工夫が必要です。昇進やスキルアップの機会を制度化し、既存社員の定着を図ることが人材不足解消の近道になります。
課題2. 従業員のエンゲージメント低下
問題点:従業員が会社や仕事への関心を失うと、生産性が低下し離職率も上昇します。背景には評価制度の不透明さやキャリア形成の不明確さ、上司や同僚との交流不足などが挙げられます。在宅勤務などが多い環境では、社員同士のつながりが希薄になりやすい傾向があります。
対策:定期的な1on1面談や匿名アンケートを実施し、従業員の声を拾い上げましょう。そのうえで、評価に成果や努力を反映させ、キャリアパスを示すことで意欲の向上を図れます。社内イベントやオンライン交流を積極的に取り入れ、部署や役職を超えたコミュニケーションの場を設けることも有効です。
課題3. 法令遵守(コンプライアンス)の対応が間に合わない
問題点:労働基準法や社会保険制度は頻繁に改正されます。情報収集が遅れると罰則や訴訟リスクを抱えることになり、企業の信用にも影響します。専任の法務部門を持たない企業では、制度改定や社内規定の見直しが後回しになりがちです。
対策:社労士や弁護士と連携し、最新情報を定期的に入手できる仕組みを持ちましょう。人事労務システムを導入すれば、給与や勤怠を法令基準に沿って処理できるようになります。管理職向けに法令遵守の研修を実施し、現場レベルで意識を根付かせることも重要です。
課題4. リモートワークでの管理が困難
問題点:在宅勤務やフレックスタイムの普及で、勤務状況や進捗を把握しづらくなっています。成果の評価が不公平になりやすく、不満を招く恐れがあります。また、オンライン環境では情報漏えいやセキュリティリスクも高まります。
対策:勤怠や業務進捗をリアルタイムで共有できるツールを導入し、業務の可視化を行います。評価制度は勤務時間ではなく成果を基準とし、場所にとらわれない仕組みが求められます。セキュリティ面ではアクセス権限の管理や通信の暗号化を徹底し、安全な業務環境を提供するのも大切です。
課題5. 情報の管理と活用不足
問題点:従業員情報や業務データが各部署に分散すると、確認や共有に時間がかかり意思決定が遅れます。過去のデータを活用できないまま同じ課題を繰り返す恐れもあります。
対策:データを一元的に扱えるシステムを導入し、社内全体で共有できる仕組みを導入することが有効です。蓄積した情報を分析すれば、採用計画や人員配置、教育施策の改善に役立ちます。また、データは定期的に点検し、常に最新の状態を維持することが大切です。
人事管理・労務管理にシステム・ツールを導入する3つのメリット
人事管理や労務管理は、日々の処理を正確に行いながら、迅速な判断を求められる領域です。残業時間の上限管理や有給休暇取得の促進など、働き方改革に対応するためには、煩雑な業務をいかに効率化するかが課題となります。システムやツールを導入すれば、手間のかかる作業を自動化し、担当者の負担を減らしながら正確さとスピードを両立した運用が可能になります。
ここでは、導入によって得られる3つのメリットを紹介します。
属人化の解消
従来は紙ベースや個人のパソコンに情報を保存することが多く、担当者の不在や退職時に引き継ぎが滞るリスクがありました。システムを利用すればデータを一元管理でき、必要なときに誰でも参照できる状態を保てます。その結果、ヒューマンエラーの抑制につながり、担当者に依存しない安定した運用が実現します。人員変更があっても業務を継続でき、組織全体の運営が円滑になります。
従業員データの見える化
勤怠記録や給与情報、評価データなどを部門ごとに管理していると、情報を探すだけで時間を要します。システムを導入すれば、複数のデータを一元化し、リアルタイムで把握できる環境を作れます。特にリモートワークにおいては、場所を選ばず最新データを共有できることが大きな強みになります。管理層は必要な情報をすぐに確認できるため、迅速で的確な判断を下せるようになります。
コストと時間の削減
勤怠集計や給与計算を手作業で行う場合、多くの時間と人員を必要とします。システムにより入力や計算を自動化すれば処理時間を大幅に短縮でき、誤入力や計算ミスの修正作業も減少します。人件費や運用コストを抑えつつ、浮いたリソースを戦略的な業務や社員教育など、付加価値の高い取り組みに振り向けられます。
人事管理・労務管理で活用するシステム・ツールの種類
人事管理・労務管理に活用されるシステムは、大きく「人事・給与系」と「人材マネジメント系」に分けられます。前者は勤怠や給与計算など日常業務の正確性と効率化を目的とし、後者は採用や評価など人材活用の高度化を支援します。以下では、それぞれの特性と活用例を紹介します。
人事・給与系
人事・給与系システムには、勤怠管理、労務管理、給与計算といった日常業務を支えるツールが含まれます。
- 勤怠管理システム:出退勤時間や休暇取得状況を自動で記録し、労働時間の把握や残業時間の集計を容易にします。
- 労務管理システム:社会保険手続きや雇用契約書の管理など、法令遵守が求められる業務を正確に処理します。
- 給与計算システム:勤怠データや各種手当をもとに給与を自動計算し、誤りや作業時間の削減に役立ちます。
こうしたシステムを活用することで、日常業務の正確性を保ちながら、人事部門の作業負担を抑えられます。
人材マネジメント系
人材マネジメント系システムは、人材の採用から評価・育成まで、企業の人材戦略を幅広く支援します。
- 採用管理システム:求人の掲載から応募者情報の一元管理、面接日程の調整までを効率化します。
- 人事評価システム:評価基準の統一や進捗管理を行い、公平で透明性のある評価運用を可能にします。
導入することで、人材の発掘から定着までを一貫して把握でき、成長戦略に関する人事施策を進めやすくなります。
参考:人事労務システムのおすすめ15選|確認ポイントや注意点も解説
人事管理・労務管理システム導入の注意点
システムを導入する際は、自社の課題や目的を明確にしておくことが大切です。方向性が定まらないまま進めてしまうと、「使いにくい」「必要な機能が不足している」といった不満が生じやすくなります。導入前に業務フローと必要機能を洗い出し、関係部門の認識をそろえておくことが成功の条件となります。
また、法改正への対応や個人情報保護など、セキュリティ面の確認も欠かせません。無料トライアルやデモを利用し、操作性やサポート体制を検証したうえで費用対効果を見極めると安心です。
人事管理と労務管理は役割こそ異なりますが、いずれも組織を円滑に運営するために重要な領域です。導入段階から双方の視点を取り入れることで、機能選定や運用設計の精度が高まり、導入効果を引き出しやすくなります。
人事管理と労務管理は役割も手法も異なるが、目指す方向は同じ
人事管理は採用・育成・評価を通じて組織を強め、労務管理は労働条件や制度を整えることで働きやすさを守ります。方法は異なりますが、目的は従業員の力を最大限に引き出すことです。両者が役割を理解し合い、協力して運用することで、安定と成長を同時にかなえられます。
制度やシステムはあくまで支援のための手段であり、組織を動かす主役は人です。人事と労務が同じ方向を見据え、誰もが安心して力を発揮できる環境を築くことが、企業の長期的な成長を支える土台となります。


