社内ITのヘルプデスクの自動化で問い合わせ削減|手順やポイントを解説
公開日 2025/10/03
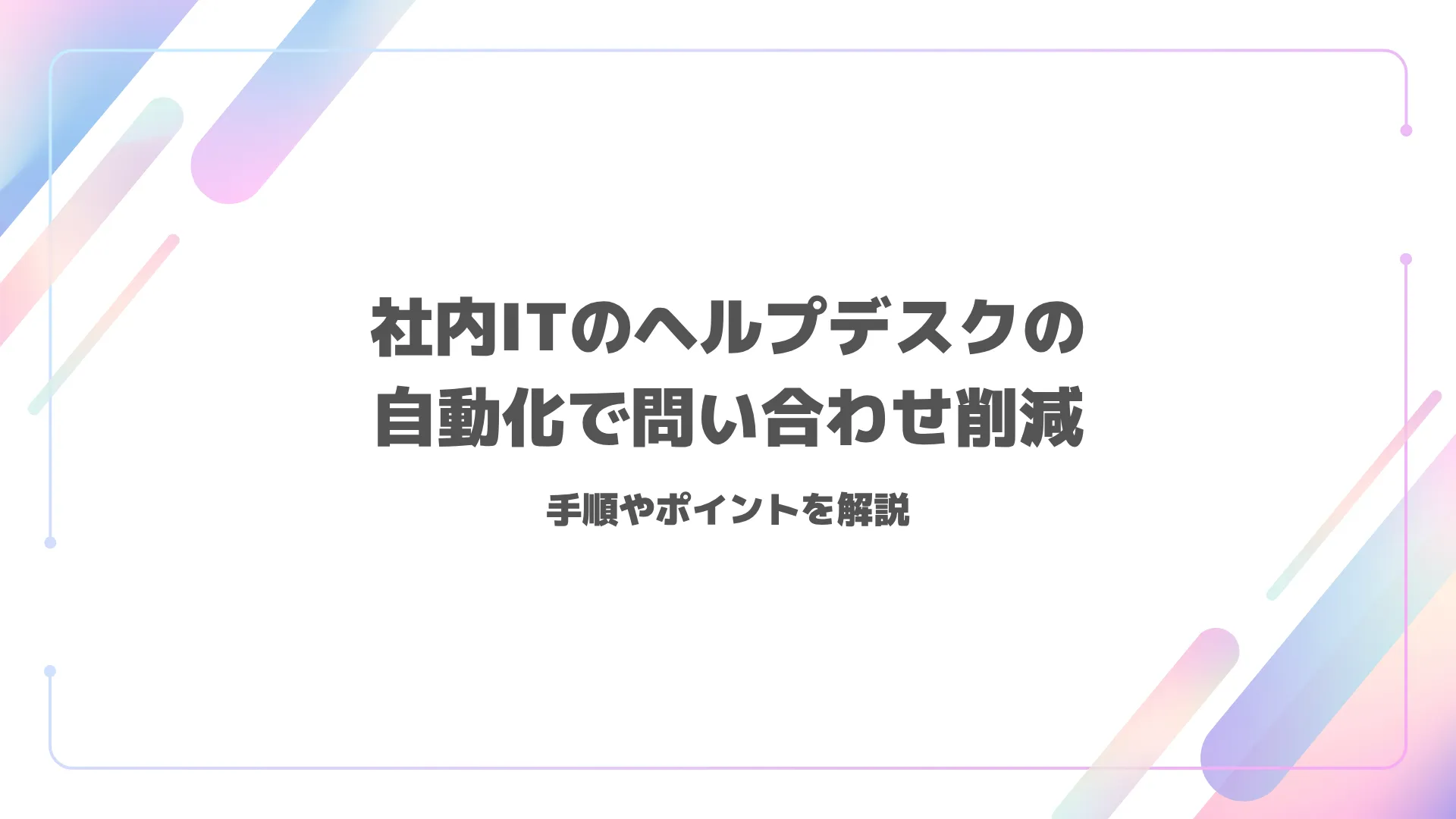
社内ITのヘルプデスクは、日々の問い合わせ対応が増える一方で、慢性的な人手不足や対応の属人化といった課題を抱えています。同じ質問が繰り返される、即時対応が求められる場面が多いといった状況では、従業員の負担が大きくなり、本来の業務に集中しづらくなることも少なくありません。
こうした課題を解決する手段として注目されているのが、社内ヘルプデスクの自動化です。
本記事では、自動化によるメリットや具体的な手順、運用時のポイントをわかりやすく解説します。おすすめツールも紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
目次
社内ITのヘルプデスクが抱えている課題
社内ITのヘルプデスクでは、問い合わせが集中したり、トラブル対応が複雑化したりと、多くの企業が共通して抱える悩みも少なくありません。
ここでは特に多くの企業で見られる課題を整理し、解説していきます。
同じ内容の問い合わせが何度も来る
多くの企業では、従業員が同じポイントでつまずくことが多く、結果として似た内容の問い合わせが繰り返し寄せられるという課題があります。パスワードの再設定方法や特定ソフトの操作方法など、基本的な質問はFAQに掲載していても、存在が周知されていなかったり、探しにくい構成だったりすると活用されません。
その結果、担当者は同じ説明を何度も行うことになり、対応負荷が増大します。こうした状況はコア業務の時間を圧迫し、効率低下を招く大きな要因となります。
問い合わせの量が増加傾向にある
企業のIT化が進む中で、新しい業務ツールやシステム、機能拡張の導入は年々増加しています。それに従って、従業員は使い方や設定方法、トラブル解消など多岐にわたる疑問を抱くようになり、社内ITヘルプデスクへの問い合わせ件数も増加しています。
特に導入初期は操作に不慣れな従業員が多く、質問が集中しやすいため、対応に追われがちです。結果として、ヘルプデスク担当者の負担は増し、本来の改善活動や予防策の検討に割ける時間が限られてしまいます。
慢性的な人手不足
社内ITヘルプデスクは売上に直結しにくい間接部門であるため、人材配分が後回しになりやすい傾向があります。その結果、専任担当者が確保できず、他業務との兼務で回しているケースも少なくありません。
慢性的な人手不足は、問い合わせ対応に追われる日常を生み、業務改善や効率化への取り組みが進まない要因となります。さらに負担の集中は担当者のモチベーション低下や離職リスクを高め、サービス品質の維持を難しくします。
即時対応を求められる場面が多い
社内ITヘルプデスクには、「システムにログインできない」「エラーで作業が進まない」など、業務の継続に直結する緊急度の高い問い合わせが頻繁に寄せられます。これらは即時対応が求められるため、担当者は進行中の業務を中断し、優先的に処理しなければなりません。
その結果、予定していた作業が後ろ倒しになり、業務時間の延長や残業の常態化を招くケースもあります。突発対応が続くことで、担当者の精神的負担や疲労感も蓄積しやすくなります。
属人化が進行している
社内ITヘルプデスクでは、担当者ごとのスキルや経験の差によって、回答の質やスピードにばらつきが生じることがあります。ノウハウが個人に依存したまま共有されない状態が続くと、特定の担当者が休職・退職した際に業務が滞り、対応が追いつかなくなるリスクが高まります。
さらに、ヘルプデスクが機能不全に陥れば、他部署の業務にも遅延や混乱を招きかねません。知識の共有体制を整え、属人化を防ぐことが安定運用の鍵となります。
参考:ヘルプデスクとは?役割や仕事内容からメリット・デメリットまで解説
社内ITのヘルプデスクを自動化することで改善が図れる
前章で触れたように、慢性的な人手不足や属人化など、社内ITヘルプデスクには多くの課題が存在しています。こうした課題を解決するには、チャットボットによる問い合わせ対応の自動化が有効です。
チャットボットを活用して、よくある質問や基本的なトラブルシューティングを自動化することで、担当者は複雑な案件や改善業務など、より付加価値の高い仕事に集中できます。
チャットボットには大きく分けて「AIチャットボット」と「シナリオボット」の2種類あります。
AIチャットボットは質問内容に応じて柔軟に回答し、会話を通じてナレッジを蓄積することが可能です。一方、シナリオボットはあらかじめ設定された手順や選択肢に沿って案内するため、パスワード再設定や申請手順など定型的な対応に適しています。
導入時は、問い合わせの種類や頻度に応じて両者を使い分けることで、属人化防止と効率化の双方を実現できます。
参考:AIチャットボットの種類を解説!自社に合うサービスの選び方も紹介
社内ITのヘルプデスクを自動化するメリット
社内ITヘルプデスクの自動化には、従業員の負担軽減や回答スピードの向上、さらにデータの蓄積・分析による業務改善など、多くのメリットがあります。
ここでは、その中でも特に重要な5つのメリットを解説します。
社内ITの従業員の負担を軽減できる
マニュアルに記載されているような定型的な質問は、チャットボットやFAQシステムなどの自動化ツールに任せることで、社内IT担当者の負担を大幅に軽減できます。
たとえばパスワードの再設定方法やアプリのインストール手順といった繰り返し発生する問い合わせを自動処理すれば、担当者は急を要するトラブルや複雑な案件への対応に集中可能です。結果として、業務効率が向上し、同時に担当者のストレスや残業リスクも軽減されます。
参考:FAQを最適化するAIチャットボット「IZANAI Powered by OpenAI」
返答のスピードが上がる
チャットボットなどの自動化ツールを導入すれば、よくある質問に即座に回答が提示され、利用者は待たされることなく問題を解決可能です。さらに、定型的な問い合わせが自動処理されることで、担当者が対応すべき件数自体も減少します。
その結果、人が対応する必要のある案件でも、順番待ちが短くなり、回答までのスピードが向上します。これにより、従業員の業務停滞を防ぎ、全体の生産性と満足度を高めることが可能です。
24時間365日対応可能
社内ITヘルプデスクを自動化するツールは、24時間365日稼働できるため、営業時間外や休日でも問い合わせに即時対応できる点も大きなメリットです。本社が休みの際でも、支店や店舗からのトラブルや操作方法の質問に自動で返答できるため、従業員は自分のタイミングで問題を解決可能です。
また、全国の拠点や複数部門からの問い合わせにも均一な対応が可能で、利便性の向上にも有効です。これにより、従業員満足度の向上と業務の円滑化が期待できます。
データの蓄積・分析ができる
社内ITヘルプデスクを自動化するツールは、問い合わせ内容や対応履歴を蓄積し、分析できる機能を備えています。これにより、どの質問が多いか、どの回答が解決率や満足度に課題があるかを把握可能です。
蓄積したデータをもとにマニュアルやFAQを更新したり、チャットボットや対応フローの改善を行ったりすることで、より効率的で精度の高いヘルプデスク運営を実現できます。継続的な分析は、問い合わせ削減や従業員満足度向上にもつながります。
人に聞きにくいことも質問しやすい
他部署の担当者に直接聞きにくい内容でも気軽に質問できる環境が整うという点も、社内ITヘルプデスクを自動化するメリットです。「こんなことで質問して迷惑かも」と悩む必要がなくなるため、不明点をそのままにせず解消しながら業務を進めやすくなります。
チャットボットなら質問の仕方を深く考える必要もなく、心理的ハードルを下げつつ、効率的な情報取得が可能です。従業員のストレス軽減と業務のスムーズな遂行の両立に寄与します。
社内ITのヘルプデスクを自動化する手順
社内ITのヘルプデスク自動化について解説しましたが、実際に導入するにはどのように進めればよいのでしょうか。ここでは、取り組みを具体的に進める際の手順を、7つのステップに分けて解説します。
1.導入目的や達成目標を具体的に設定する
自動化ツールの導入を成功させるには、まず目的や達成目標を明確にすることが重要です。ゴールが曖昧なままでは、必要な機能や最適なツールを選びにくくなります。
たとえば「社内問い合わせ対応時間を月○時間削減する」「定型質問の○%を自動化する」といった具体的な数値目標を設定すると、選定基準や導入後の評価軸が明確になります。
明確な目標は、運用改善の指針にもなり、導入効果を最大化するためには欠かせません。
2.自動化の方針を決める
自動化を進める際は、まずどの業務を対象にするのかを明確にし、それに必要な機能を洗い出します。例えばFAQ検索、チケット管理、外部システム連携など、目的に直結する機能を選定することが重要です。
チャットボットを導入する場合は、利用者がアクセスしやすい設置場所も事前に検討しましょう。社内ポータル、Slack、Teamsなど、どの社内ツールが適しているかを早い段階で検討しておくと、導入後の活用促進につながります。
3.ツールの運用体制を整える
自動化ツールは導入して終わりではなく、継続的な改善と管理が欠かせません。FAQの更新や回答精度の向上、利用状況の分析を定期的に行うためにも、あらかじめ運用担当者を決め、体制を整えておくことが重要です。
担当者は、効果測定や不具合対応、ユーザーからのフィードバック収集なども担います。役割と責任範囲を明確にすることで、ツールの性能を安定して発揮させながら、利用者の満足度と業務効率を長期的に高める運営体制を築けます。
4.導入するツールを選ぶ
ツール選定では、求める機能の有無や操作のしやすさ、サポート体制、費用対効果などを総合的に比較検討しましょう。導入後の使い勝手や業務との相性を見極めるため、可能であれば無料トライアルやデモ版を活用することをおすすめします。
実際の利用シーンを想定してテストすることで、社内に最適なツールを確実に選び、導入後の運用負担や無駄なコストを避けられます。
5.FAQ・シナリオを作る
次に、FAQやシナリオ作成を行います。このステップでは、過去の問い合わせ履歴や既存マニュアルなどから、回答の根拠となるデータを集めます。そのうえで、ユーザーが直感的に理解できるよう、質問から回答までの流れを整理したシナリオを作成しましょう。
情報は正確さだけでなく、読みやすさや用語の統一も重視することが大切です。ツール利用者が迷わず問題解決できる環境を整えられます。
参考:FAQを最適化するAIチャットボット「IZANAI Powered by OpenAI」
6.テスト運用を実施する
本格運用の前には必ずテスト運用を行い、実際の利用環境で課題を洗い出す必要があります。従業員に試用してもらい、操作性や回答の分かりやすさ、解決までの流れを確認しましょう。
フィードバックを基に、不要な機能の削減や不足している機能の追加、文章表現の改善などを行うことが大切です。こうした調整を重ねることで、リリース時には安定した品質と高い利用満足度を確保できます。
7.最終確認をして本格運用開始
全ての改善や機能調整が完了したら、最終確認を行い本格運用へ移行します。AI搭載ツールの場合は、運用前に十分な学習データを用いてAIの回答精度を高め、誤答や不適切な応答がないかも確認します。
初期段階での品質が高いほど、利用者の信頼を得やすく、定着もスムーズです。準備を整えたうえで安定稼働を目指しましょう。
社内ITのヘルプデスクを自動化するときのポイント
社内ITヘルプデスクを自動化するにあたっては、いくつか押さえておくべき重要なポイントがあります。運用を軌道に乗せるためには、単にツールを導入するだけでなく、継続的な改善や利用者目線での工夫が欠かせません。
- PDCAサイクルを回す
- ツールが回答する範囲を明確にしておく
- 優先順位が高いものから取りかかる
- 理解しやすい表現を心掛ける
- 導入するツールの操作性を確認する
ここでは、以下の5つのポイントについて解説します。
PDCAサイクルを回す
PDCAサイクルは、業務改善や品質管理の基本的なフレームワークです。「Plan(計画)」「Do(実行)」「Check(評価)」「Action(改善)」の頭文字から成り、各文字は以下の内容を意味します。
- Plan(計画):改善の目標を定め、達成のための計画を立てる段階。
- Do(実行):計画に基づいて実際に取り組みを実行する段階。
- Check(評価):実行した内容を評価・分析し、計画通りに成果が出ているかを確認する段階。
- Action(改善):評価結果を踏まえ、問題点を改善したり次の計画に反映させる段階。
ヘルプデスクの自動化も、一度導入すれば終わりではありません。古い情報や不具合をそのままにしないために、このサイクルを回すことが重要です。
定期的に効果を検証し、FAQやシナリオを最新化することで、利用者にとって信頼できる仕組みを維持できます。
ツールが回答する範囲を明確にしておく
自動化ツールを活用する際は、回答できる範囲と人間が対応すべき範囲を事前に切り分けておく必要があります。たとえば、パスワードリセットやソフトのインストール手順はツールに任せ、例外的なトラブルや判断が必要な案件は担当者へ回すといった基準を定めます。
役割分担を明確にしておくことで、利用者が「どこに問い合わせれば良いのか」と迷うことを防ぎ、スムーズな解決につながります。
優先順位が高いものから取りかかる
社内ヘルプデスクの自動化を進める際は、優先度の高い項目から取りかかることが重要です。具体的には、頻繁に問い合わせがある質問や、トラブル時に備えてあらかじめ用意しておいた方が良い項目を優先的に整備します。
こうすることで、問い合わせ対応の負担を早期に軽減でき、担当者はより重要で複雑な業務に集中できます。効率的な自動化を実現するためにも、まずは効果が高い部分から準備を始めましょう。
理解しやすい表現を心掛ける
社内ヘルプデスクの自動化で作成するFAQやチャットボットの回答では、従業員のIT知識やスキルの差を意識して、誰でも理解できる表現を使うことが大切です。
専門用語や略語は避け、必要に応じて画面のスクリーンショットや図解を添えることで、視覚的に理解しやすくなります。普段ITに関わらない人でも迷わず操作できるように整えることで、問い合わせの自己解決率をより一層高めることができます。
導入するツールの操作性を確認する
導入するツールの操作性を重視することも、ヘルプデスクを自動化する際には欠かせないポイントです。ユーザーが知りたい情報をスムーズに検索でき、運営側が簡単に内容を更新できる設計のツールを選ぶことで、日常的な利用が促進されます。
逆に使い勝手が悪いツールだと、従業員が活用を避け、結局問い合わせが増えてヘルプデスクの負担が増す恐れがあります。操作性の確認は、導入前に必ず行うべきポイントです。
社内ITのヘルプデスクを自動化した事例
SOMPOシステムズでは、社内問い合わせの多さや電話・メール対応の手間が課題でした。そこで2019年8月にユーザーローカル社のチャットボットを導入。社内公募で「テルミーちゃん」と名付け、まずはPCやアカウント取得などの定型的な問い合わせに対応できるようにするなど、スモールスタートで取り組みを実施しました。
チャットボットをキャラクター化することにより、社員からの愛着を獲得しつつ、月1回の定例会でQ&Aの追加や改善を続け、回答できる領域を少しずつ広げていきました。
導入から約4年で、システム関連の問い合わせ数は50%削減され、平均返答率は90%以上。利用者数も右肩上がりで、月間利用件数3,000件超を維持するという成果を上げています。
今後もキャラクターの成長とともに、利用者数のさらなる増加や、回答精度の向上、会話シナリオのバリエーションの増加を目指しているそうです。また、社内システムやアプリとのAPI連携を図り、社内問い合わせのさらなる効率化や利便性向上を図るとしています。
社内ITのヘルプデスクの業務を自動化するのにおすすめのツール
社内ITのヘルプデスク業務を自動化し、業務効率を飛躍的に高めるおすすめのツールを紹介します。
各ツールの概要や特徴を以下の表にまとめました。
| 概要 | 主な特徴 | |
|---|---|---|
| IZANAI(イザナイ) | AIを活用したチャットボット。社内ナレッジ共有・FAQ検索が可能。従業員の疑問を自動解決し、問い合わせ削減をサポート。 | 自然言語検索で曖昧な表現にも対応ナレッジの自動整理運用サポートあり |
| ActiBook(アクティブック) | 電子ブック形式で社内マニュアルや資料を管理・配信できるツール。情報共有を効率化。 | マニュアル・資料を電子ブック化検索・閲覧が簡単閲覧履歴管理可能 |
| Helpfeel AI(ヘルプフィール エーアイ) | AIによる問い合わせ前の自己解決を促進するナレッジ管理・検索ツール。 | 検索ノーヒット率0%を目指す高精度検索曖昧な言葉やスペルミスに対応問い合わせログ分析で改善 |
| SupportChatbot(サポートチャットボット) | AI搭載のチャットボットで問い合わせを自動対応するクラウドサービス。 | 自由入力の曖昧な質問にも対応Q&Aの管理画面が直感的テンプレート・運用サポートあり |
| Freshdesk(フレッシュデスク) | ヘルプデスク・カスタマーサポート業務の効率化を支援するデジタルツール。 | マルチチャネルでの一元管理案件の自動振り分けチャットボット・FAQ作成可能運用データ分析 |
IZANAI(イザナイ)

IZANAIは、生成AIを活用したチャットボットで、社内外のFAQ対応を自動化できるツールです。社内資料やWebサイトを登録するだけで設定でき、複雑な準備は不要。ユーザーの曖昧な質問にもAIが適切な回答を導き出すため、従業員が欲しい情報にすぐアクセスできます。
これにより、ヘルプデスク担当者の負担を軽減し、問い合わせ対応の効率化を実現します。人事・総務やカスタマーサポートなどの問い合わせが多い部門に特に効果的で、業務全体のスピードと精度を向上させることが可能です。
2週間の無料トライアルが用意されているため、まずはお試し感覚で利用してみると良いでしょう。
参考:FAQを最適化するAIチャットボット「IZANAI Powered by OpenAI」
ActiBook(アクティブック)

ActiBookは、PDFやOfficeファイルをアップロードするだけで手軽に電子ブック化できるツールです。動画にも対応しており、マニュアルや手順書、社内規程などをデジタル化して配布できます。アクセス制限をかけて社員限定の資料サイトを構築したり、閲覧ログを分析して利用状況を把握できる点も特徴です。
社内ITヘルプデスクでは、問い合わせの多い操作マニュアルやトラブル対応手順を電子ブック化して公開することで、自己解決を促し、対応件数の削減につながります。さらに、閲覧状況のログ分析で問い合わせ傾向を把握し、継続的な改善や精度向上なども期待できます。
Helpfeel AI(ヘルプフィール エーアイ)

引用元:Helpfeel AI(ヘルプフィール エーアイ) 公式サイト
Helpfeel AI(ヘルプフィール エーアイ)は、AIと独自の検索技術を活用した社内ナレッジ管理・検索ツールです。従業員が問い合わせ前に自己解決できる環境を提供します。
曖昧な表現やスペルミスにも対応し、社内規程やITサポート、マニュアルなど幅広い情報を瞬時に検索可能です。パスワードリセットやWi-Fi設定、勤怠申請や経費精算など日常的な問い合わせをAIが即時回答し、ヘルプデスクの負担を大幅に軽減できます。
また、検索ログをもとにFAQ作成や改善も効率化でき、社員の自己解決率向上と業務効率化を同時に実現できるツールです。
参考:Helpfeel AI(ヘルプフィール エーアイ) 公式サイト
SupportChatbot(サポートチャットボット)

引用元:SupportChatbot(サポートチャットボット) 公式サイト
SupportChatbot(サポートチャットボット)は、AIを活用して顧客や社員からの問い合わせを自動化するクラウドサービスです。言語処理に特化したAIが曖昧な表現や表記ゆれにも対応し、最適な回答を瞬時に提示します。
管理画面は直感的に操作できるデザインで、専門知識がなくてもQ&Aの修正や運用が可能です。テキストマイニングによる分析機能で利用状況や改善点も一目で把握できるといった魅力もあります。
導入することで、情報システムや総務、人事、経理、営業支援などの定型的な問い合わせを効率化。特にカスタマーサポートではメールや電話の簡易対応を減らして、業務負担を大幅に軽減できるツールです。
参考:SupportChatbot(サポートチャットボット) 公式サイト
Freshdesk(フレッシュデスク)

Freshdesk(フレッシュデスク)は、社内ITヘルプデスク業務を効率化するクラウド型ツールで、問い合わせの管理から対応までを一元化できます。メールやチャット、電話など複数チャネルをまとめて管理できるオムニチャネル機能や、案件の優先度・担当者に応じた自動割り振り、進捗状況の可視化により、対応漏れや負担集中を防ぐことが可能です。
さらに、FAQ作成やチャットボットの自作、運用データの解析、多言語対応も可能で、従業員の自己解決率を高めつつヘルプデスク業務を大幅に軽減できます。オリジナルアプリの組み合わせで自社向けの運用を最適化できる点も強みです。
14日間の無料トライアルが用意されているため、事前に使用感を確かめたい方におすすめです。
ツールを活用して、社内ITのヘルプデスクを効率的に自動化しよう
社内ITのヘルプデスクは、従業員が安心して業務を進められるよう支える重要な役割を担います。しかし、問い合わせの集中や対応の属人化、情報の検索に手間がかかるなど、様々な課題が存在しています。
チャットボットを導入すれば、従業員から寄せられるよくある質問や基本的なトラブルの対応の自動化が可能です。これにより、ヘルプデスク担当者の負担を大幅に軽減し、より専門的で付加価値の高い業務に集中する時間を確保できます。さらに、従業員はいつでも自己解決できるため、問題が迅速に解決し、業務効率も向上します。
今回ご紹介したツールのなかには、無料プランが利用できるものもあるので、まずは無料プランで、使い心地や自社の業務に合うかなどを試してみましょう。


