ヘルプデスクの業務改善ガイド|課題分析からツール選定のポイントまで解説
公開日 2025/11/14
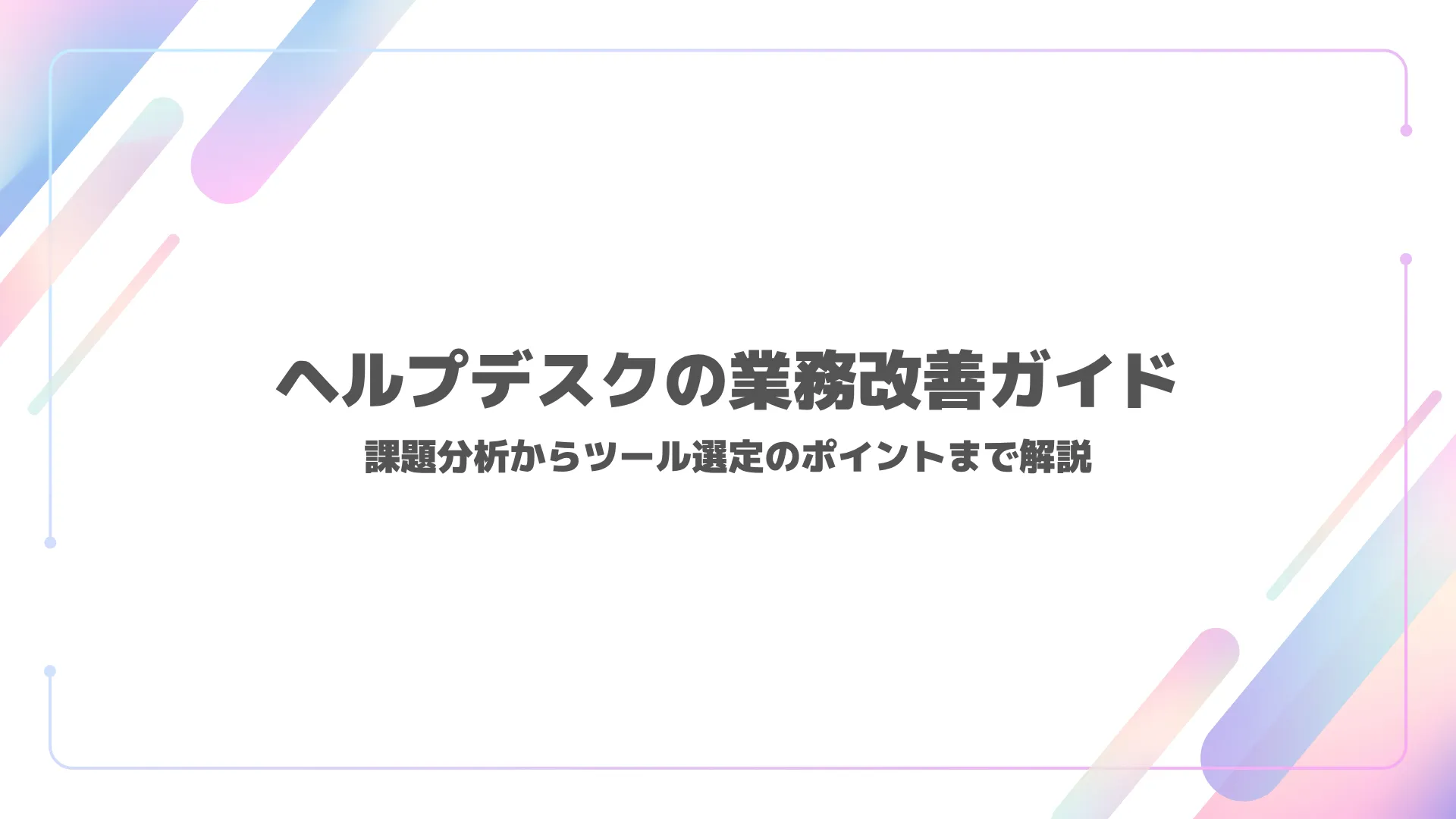
ヘルプデスクの業務改善は、問い合わせ件数の増加や人材不足によって、多くの企業で取り組むべき課題となっています。社内外から寄せられる問い合わせへの対応は、利用者の満足度向上につながる一方で、ヘルプデスク担当者への負担が大きくなりやすいのが現状です。
「問い合わせが多すぎて業務が回らない」「担当者しか知らない情報が多く、ナレッジの共有が進まない」などの悩みから、業務改善の必要性を感じている企業も多いのではないでしょうか。
本記事では、ヘルプデスク業務でよくある課題や具体的な改善策などを、事例とともにご紹介します。
目次
ヘルプデスク業務の課題とは?
まずは、多くの現場で見られる代表的な3つの課題を見ていきましょう。
参考:ヘルプデスクとは?役割や仕事内容からメリット・デメリットまで解説
問い合わせ件数が増加し担当者が疲弊する
まず課題として挙げられるのが、問い合わせ件数が多すぎて、担当者の業務負荷が過度に高まってしまうケースです。ヘルプデスクには、重要な問い合わせだけでなく、利用者自身で解決できる内容や、定型的な質問も多く寄せられ、担当者の業務負担ばかりが増えてしまいがちです。
その結果、本来優先すべき問い合わせへの回答が遅れ、サービス全体の品質低下につながる恐れがあります。さらに負担が続くと、担当者のモチベーション低下や離職リスクを招きかねません。
このような事態を防ぐには、早い段階で業務の効率化や仕組みづくりが必要です。
ナレッジの属人化・情報共有ができていない
担当者ごとに知識や対応方法が異なり、問い合わせ内容が属人化してしまうのもよくある課題です。情報が共有されていないと、同じ内容を何度も確認する手間が発生したり、担当者によって回答の質がばらついたりすることがあります。その結果、知識が蓄積されず、対応のスピードや品質に影響が出てしまいます。
改善を進めるには、ナレッジを共有するための仕組みを整え、誰でも一定水準で対応できる体制を構築することが大切です。
業務時間外対応の負荷やコストが増加する
問い合わせやトラブル対応は、時間を問わず発生します。そのため、夜間や休日の対応が多くなると、担当者の負担や人件費が増えてしまいます。24時間対応を前提とした体制づくりも求められるため、管理面でも課題が生じます。
また、夜間対応しない場合でも、時間外の問い合わせを翌日にまとめて処理しようとすると、通常業務に割く時間が削られ、結果として対応の遅れにつながってしまいます。
このような状況が続けば、顧客満足度の低下を招くリスクが高まります。業務改善に取り組む際は、時間外対応を減らす仕組みを整えることが重要です。
ヘルプデスク業務改善を成功に導く4つのステップ
ヘルプデスクの改善は、段階を踏みながら整理していくことで、効率的かつ着実に成果を出せます。ここでは、実践しやすい4つのステップをご紹介します。
ステップ1:現状分析と課題の可視化
最初に取り組むプロセスは、現状を正しく把握することです。問い合わせ件数や対応内容、処理にかかる時間を記録し、どこに問題があるのかを客観的に確認しましょう。課題を洗い出し、具体的にまとめることで優先度の高い改善ポイントが見えてきます。
たとえば、「自己解決できる質問が多いのか」「繰り返し聞かれている問い合わせは何か」といった視点で分析すると効果的です。はじめに状況を可視化しておくと、次の施策を計画しやすくなり、改善効果の測定もスムーズに進みます。
ステップ2:問い合わせ削減のための環境整備
問い合わせの数を減らすには、利用者自らが疑問を解決できる仕組みを整えることが重要です。FAQページを充実させたり、マニュアルを整理したりすることで、自己解決しやすい環境をつくれます。特に「よくある質問」や「定型的な内容」を優先して公開すると効果が高まります。
さらに、情報を一元的に提供できるようにすると、利用者は迷わずに必要な答えにたどり着けます。こうした仕組みは、効率化を進めるだけでなく、利用者満足度の向上にもつながります。
ステップ3:対応業務の効率化と標準化
次の段階では、日々の対応を効率的に進める仕組みづくりを意識しましょう。「回答テンプレート」を用意しておけば、よくある質問に迅速かつ正確に対応でき、担当者が毎回文章を考える手間を減らせます。
また、「ナレッジ共有ツール」を導入すれば、解決方法をチーム全体で共有できるようになります。対応時間の短縮につながり、担当者ごとの対応品質を一定に保つことも可能です。効率化と標準化を同時に進めれば、利用者も安定したサポートを受けられるようになります。
ステップ4:継続的改善とパフォーマンス測定
業務改善は一度で終わらせず、効果を確認しながら続けることが大切です。施策を実施した後は、定期的に成果を測定し、数値やデータをもとに評価しましょう。そこから新しい課題を発見し、次の改善へとつなげていく流れをつくることが大切です。
問い合わせ件数の推移や対応時間の短縮度合いなど、わかりやすい指標を使えば担当者も進捗も把握しやすくなります。改善と見直しのサイクルを習慣化することで、ヘルプデスク業務は着実に成長していくはずです。
ヘルプデスクの業務改善をするための5つの方法
ヘルプデスクの改善は、ひとつの対策だけでなく、複数の仕組みやツールを組み合わせることで、効率化と品質向上が可能になります。ここでは、実践しやすい5つの改善方法をご紹介します。
FAQシステムを導入する
業務改善の手段として有効なのが「FAQシステム」の導入です。よくある問い合わせを公開しておけば、利用者自身で問題を解決できるようになります。その結果、簡単な質問が減り、全体の問い合わせ件数も抑えられます。
さらに、FAQを検索しやすく整備しておけば、新人教育にも役立ちます。チーム内で知識を共有しやすくなり、対応のばらつきも防げるでしょう。定期的に更新し続けることで、利用者は常に最新情報にアクセスできます。
参考:AIチャットボットでFAQを最適化「IZANAI Powered by OpenAI」
問い合わせ回答テンプレートを作成する
対応のスピードと正確さを高めるには、「回答テンプレート」の活用が効果的です。ひんぱんに寄せられる質問をテンプレート化すれば、担当者のスキルに左右されず、安定した対応が可能になります。
電話対応では「トークスクリプト」、メールやチャットでは「返信用の定型文」を準備するとよいでしょう。過去の問い合わせや現場担当者の意見を参考にし、利用頻度の高いものから優先的に整備するとスムーズです。作業負担を減らすだけでなく、利用者を待たせる時間も短縮できます。
ナレッジ共有ツールを活用する
担当者の経験や勘に頼った対応だけでは、効率化に限界があります。そこで役立つのが「ナレッジ共有ツール」です。過去の問い合わせや解決方法を蓄積し、誰でも迅速に対応できるようになります。属人化を防ぐことができ、対応品質も一定に保てます。
また、よくある質問を社内FAQとして公開すれば、社員からの問い合わせも減らせます。ポータルサイトにマニュアルと一緒に掲載しておけば、社員が自ら検索して解決できるようになります。導入が容易でコストも抑えやすいため、ヘルプデスク全体の負担を軽くするうえで有効な手段です。
チャットボットを導入する
定型的な問い合わせ対応を効率化する手段として、「チャットボット」の導入があります。自動で会話を行うプログラムで、AIを搭載したタイプならあいまいな質問にも対応できます。ユーザーの質問に即時回答でき、24時間対応可能な点が大きな強みです。チャットボットが定型業務を担うことで、担当者はより複雑で専門性の高い問い合わせに集中できます。
最近では、社内資料やWebサイトを登録するだけで設定できるAIチャットボットも増えています。面倒なシナリオ作成が不要で、導入しやすいのが特長です。さらに、やり取りのデータを分析できるため、FAQの改善にもつながり、問い合わせ数の削減と生産性の向上に貢献します。
問い合わせ管理システムを導入する
対応の品質とスピードを高めるには、「問い合わせ管理システム」の導入が効果的です。電話・メール・SNSなど、複数の窓口から寄せられる問い合わせを一元管理し、対応漏れや重複を防げます。案件ごとの進捗を画面上で確認できるので、担当者が急に休んでもスムーズな引き継ぎが可能です。
さらに、件数の推移や問い合わせの種類を分析する機能もあり、業務課題の改善に役立ちます。チーム全体の状況を見える化できるので、ヘルプデスク業務を計画的に最適化していけるでしょう。
参考:AIチャットボットで社内外の問い合わせを効率化|IZANAI(イザナイ)
ヘルプデスク業務改善ツール選定のポイント3選
効率よくヘルプデスクの改善を進めるには、適切なツールの導入が必要です。ここでは、選定時に押さえておきたい3つのポイントをご紹介します。
ポイント1:導入目的と解決したい課題が明確か
新しいツールを検討する際は、「なぜ導入するのか」を明確にすることからはじめましょう。いま直面している課題を整理し、どの問題を解決したいのかを具体的に定義します。「問い合わせ件数を減らす」「対応スピードを上げる」「品質を安定させる」など、目標をはっきりさせてチーム全体で共有すると効果的です。
まずは、現場にヒアリングを行い、業務内容を細かく洗い出します。問題点を可視化できれば、必要な機能も判断しやすくなり、自社に最適なツールを選ぶための基準をつくれます。
ポイント2:現場の担当者が直感的に使えるか
どんなに機能が充実していても、操作が難しければ社内に定着しません。現場担当者が直感的に使え、研修に大きなコストをかけずに導入できるかを確認しましょう。
具体的には、「管理画面が見やすいか」「ひと目で状況を把握できるか」「日常的な操作が迷わず行えるか」といった点をチェックします。
多くのツールには、無料トライアルが用意されています。導入前に担当者に操作してもらい、感覚的に扱いやすいかを確かめておくと安心です。もし操作が複雑すぎれば、かえって業務負担が増える可能性があるため注意が必要です。
ポイント3:導入後のサポート体制は充実しているか
ツール提供元のサポート体制が充実しているかどうかも、選定時の重要な判断材料となります。ツール導入後の運用支援やトラブル対応、機能追加の相談など、どのようなサポートを受けられるか事前に確認しましょう。
公式サイトでサポート内容や対応時間を確認するだけでなく、既存ユーザーの口コミや事例を参考にするのも有効です。継続的に改善を続けるためには、ツール提供元との信頼関係と安心できるサポート環境が大切です。
関連記事:ヘルプデスクツールおすすめ10選|導入メリットや選び方も解説
その問い合わせ、AIが答えます|IZANAI(イザナイ)

毎日の問い合わせ業務に時間を取られていませんか?AIチャットボット「IZANAI(イザナイ)」は、FAQやマニュアルの情報をもとに、自動で高精度に回答する生成AIチャットボットです。ノーコードで誰でもすぐに導入でき、カスタマーサポートの定型対応を大幅に削減。
人が対応すべき「本当に重要な問い合わせ」に、もっと集中できる環境を作りましょう。
IZANAI(イザナイ)の主な特徴
- 社内資料やWebページを登録するだけで回答が可能
- PDF・Excel・WebサイトのURLなど、複数ソースを同時に学習
- FAQ整備が不十分でも、曖昧な質問に対応
- 面倒なシナリオ設計が不要
- 2週間の無料トライアル可能
参考:FAQを最適化するAIチャットボット|IZANAI Powered by OpenAI
ヘルプデスク業務改善の成功事例
ここでは、実際の企業がどのように業務改善を進め、成果を上げたのかをご紹介します。
株式会社レオパレス21|チャットボット導入で200時間の業務時間削減

賃貸事業や開発事業を展開する株式会社レオパレス21様では、ヘルプデスク業務の効率化を目的にシナリオ型チャットボット「IZANAI」を導入しました。コロナ禍で夜間の問い合わせが急増し、24時間の有人対応に限界を感じたことが大きなきっかけになったといいます。
同社は、多言語対応やメンテナンス性を重視してツールを選定。その結果、月間200時間の業務削減を実現しました。入居者からのよくある質問に自動で回答できるようになり、担当者は複雑な案件に集中できる体制が整ったそうです。
また、来店予約や物件案内にも活用され、顧客が自分のペースで行動を進められる仕組みを提供。業務効率と顧客体験の両面で効果を発揮しています。
参考:IZANAI導入により、200時間の業務時間削減!コスパよし、操作性よし、100点満点のツールです。|株式会社レオパレス21様
株式会社北豊島園自動車学校|AIチャットボットで問い合わせ件数50%以上削減

株式会社北豊島園自動車学校様は、AIチャットボットの導入で問い合わせ対応を大きく改善しました。導入前は、入校希望者や在校生から月300件近い電話が寄せられ、事務スタッフの負担増と接客品質の低下が課題となっていました。
そこで、費用対効果と直感的な操作性を評価し「IZANAI Powered by OpenAI」を採用。導入後は、電話問い合わせを50%以上削減できました。教習に関するよくある質問や手続きに、24時間対応できるようになり、顧客満足度と業務効率を同時に向上。さらに、月25時間の業務削減にもつながり、スタッフは対面での応対に専念できるようになりました。
参考:月300件の問い合わせを半分に!AIチャットボットで実現した接客に専念できる環境づくり|株式会社北豊島園自動車学校様
ヘルプデスクの改善で効率化と顧客体験の向上を目指そう!
ヘルプデスク業務の改善は、単に業務負担を軽減するだけでなく、顧客体験の向上や担当者のモチベーション維持にもつながります。まずは現状を正しく把握し、課題を可視化することからはじめましょう。
そのうえで、FAQやナレッジ共有ツール、チャットボットといった仕組みを導入すれば、問い合わせ件数の削減や対応の標準化を進められます。気軽にツールを試してみたい方は、「IZANAI(イザナイ)」の無料トライアルをご利用ください。問い合わせ対応を自動化し、サポート業務の効率化を実感してみてください。


